MENU


434件 181~200件を表示
-

2022.11.09 税務ニュース
本当のところは税務調査は怖くない?質問検査権は何かを理解しよう!
本当の税務調査が怖くない理由 強権的な税務調査。このような言葉を聞いたことがあると思いますが、税務調査は国家権力を背景に、高圧的な国税調査官が、皆様の命の次に大事なお金を奪っていくものです。税務調査にはこのようなイメージが大変強いため、税務調査を大変怖がっておられる方が多いという印象があります。 私のクライアントで、非常に気難しい方がいらっしゃいました。その社長、仕入れ先などの取引先はもちろん、税理士に対する要求も相当に大きく、不手際があれば即怒号をあびせる方でしたので、月次試算表の報告などの際は、税理士である私も非常に緊張するような方でした。このような方でさえ、「ウチの会社の税務調査は、本当に大丈夫なんですかね?」と、非常に心配しながら毎月の巡回の際は必ず聞く始末で、如何に納税者にとって税務調査が怖いものなのか、痛感させられました。 しかしながら、税務調査を法律的に考えると、税務調査は全く怖いものではないことが分かります。というのも、税務調査の主導権は税務署にはないとされているからです。誰にあるかと言えば、私たち納税者にあるのです。なぜなら、税務調査は納税者の承諾を前提とし...
-

2022.10.25 税務ニュース
事業承継の際には税負担を軽減できる?特例事業承継税制について
中小企業は日本の企業数の約99%、従業員数の約69%を占めており、地域経済を支える基盤として重要な役割を担っています「(出典)中小企業庁「中小企業・小規模事業者の数(2016年6月時点)」。一方で、中小企業の経営者のうち65歳以上の経営者が全体の4割を占め、中小企業の経営者の引退年齢が67歳~70歳と言われていることを鑑みると、今後5年から10年で中小企業の約半数が世代交代の時期に差し掛かるとみられています。日本経済の基盤である中小企業がこれまで培ってきた経営資源を次世代に承継していくことは喫緊の課題であり、事業承継は社会的な問題といえます。 1. 事業承継とは 事業承継とは文字通り「事業」そのものを「承継」する取組であり、会社の経営権を後継者に引き継ぐことです。事業承継で引き継ぐものとしては、「人」「資産」「知的資産」の三つの要素があります。「人」とは経営にあたる後継者を指し、「資産」とは自社の株式、事業用資産、資金等、「知的資産」とは目に見えない(形がない)資産で、経営理念、人脈や顧客との信頼関係、チームワークや組織力、ブランドや人材力などがそれにあたります。 出典:中...
-

2022.10.21 税務ニュース
電子インボイスは義務化される?電子インボイスと消費税インボイス制度の関係と今後の課題について解説。
2023年10月からスタートする消費税インボイス制度への移行が迫る中、電子インボイス(デジタルインボイス)への関心が高まっています。 本コラムでは、事業者のバックオフィス業務の効率化や生産性の向上を図る観点から普及が進められている電子インボイスのしくみや今後の課題について、やさしく解説します。 電子インボイス導入のきっかけ 電子インボイス導入のきっかけはコロナ禍といわれています。 新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大により、リモートワーク環境での請求業務への対応が課題になりました。これを契機にデジタル化(Digitalization)の必要性が認識され、官民連携のもと電子インボイス導入に向けての取組みがはじまりました。 2020年7月、会計・業務システムベンダーなどの民間が中心となり電子インボイス推進協議会(EIPA:E-Invoice Promotion Association、現「デジタルインボイス推進協議会」)が設立されました。2021年9月のデジタル庁の発足を経て、標準化された電子インボイスの普及を図るフェーズに至っています。現在は、2023年10月に開...
-

2022.10.20 税務ニュース
節電ポイントやマイナポイントには税金がかかる?ポイントと税金の関係について解説。
ポイントをもらったり使ったりした場合、税金がかかるのでしょうか? 本コラムでは、企業ポイントと税金の関係について、やさしく解説します。 ポイントと税金の関係は「値引き」かどうかで判断 近年の電力不足問題の深刻化を受けて「節電ポイント」の導入が進められています。 電力需要の逼迫が懸念されるため、各家庭に節電を促すのが目的です。電力会社が開催する節電キャンペーンや省エネプログラムに参加し、その内容に応じて節電ポイントが付与されます。 政府が実施する「ポイント政策」は、ほかにマイナポイントや消費税の増税に伴うキャッシュレス決済のポイント還元などが記憶に新しいところです。 この「ポイント」には税金がかかるのでしょうか? その判断の要点は「値引き」かどうかです。 この点について、国税庁は、個人が商品を購入するときに付与されるポイントで、「通常の商取引における値引き」と同様の行為が行われたものと考えられる場合には、所得税の課税対象にならないものとして取り扱うと説明しています。 マイナポイントや節電ポイントは「通常の商取引における値引き」とは同視できないため、課税対象になるのです。 ...
-

2022.10.11 税務ニュース
収益事業課税とは?NPOに対する課税の仕組みを解説
NPO法人に対して法人税がどのように課税されるのかは誤解も多く、分かりにくい部分です。例えば、一切課税されない、利益が出る事業に対しては課税されるといったような誤った認識を見聞きすることも少なくありません。そのため、本来は確定申告が必要であるにも関わらず申告をしていなかった例や、法人税が課税されない事業も含めて申告をしていたという例もあります。 今回は、NPO法人に対しての課税の仕組みについて解説します。 NPO法人への課税の考え方 NPO法人の法人税の納税義務は株式会社などの普通法人と異なり、法人税法上の収益事業に対してのみ課税されます。収益事業とは、①限定列挙された34業種であること、②継続して行われるものであること、③事業場を設けて行われるものであること、の3つの要件を満たすものです。つまり、34業種に該当する収益があったとしても、それが単発のイベント等であり継続しないものであれば収益事業には該当しないということです。 この背景にあるのは、イコールフッティング論といわれるものであり、これは営利法人と競合する事業については競争条件の公平等を図るべきという考え方です。その...
-

2022.10.07 税務ニュース
災害を被ったら農家の税金はどうなる?救済策を解説(その2)
前回に引き続き、今回も農家が被災したときの税金対策をお伝えします。今回は「納める税金を抑える方法」です。 事業での救済策①事業用資産に被災したときの損失計上と繰越・繰戻 農機具や農作物が被災し、損害が生じたら、損失部分は必要経費に計上できます。他の所得と損益通算をしても残る赤字は、翌年以後に繰り越したりできます。 ■計上する損失額 災害によって生じた事業用資産や棚卸資産の損失金額です。具体的には次のようなものとなります。 ■滅失した農機具などの固定資産 災害で滅失した日時点で「仮に譲渡したら」を前提として計算した取得費 ■収穫した稲や野菜、果実などの棚卸資産 被災して廃棄するしかなくなったもの…被災直前に「もしも出荷していたら」を前提に計算した金額。毎年の棚卸で用いている方法で評価して計算する(総平均法、先入先出法など) 売れるけど価値が下がったもの…「1の出荷前提で計算した金額-被災直後の農作物の評価額」 ■未収穫の農作物 「農作物の種苗費、肥料代、人件費その他経費などの合計額-収穫できたときの農作物の価額の合計額」 ■土砂などの障害物の除去費用 ...
-

2022.10.03 税務ニュース
あと1年で開始のインボイス…「持続化補助金」「IT導入補助金」を活用しよう
インボイスの開始まで1年を切りました。制度に対応するにはお金がかかります。「免税事業者から課税事業者になると、納税負担が増える」だけではありません。請求書や領収書の様式を変えなくてはならないのです。この2つの変化に対応すべく、2つの補助金制度にインボイス枠が設けられました。 インボイスで変わるのは「仕入税額控除」 「インボイス、インボイス」と言いますが、始まると何が大変になるのでしょうか。実はインボイスが始まると、いろいろとコストが増えるのです。コストが増える原因は「仕入税額控除」にあります。 仕入税額控除は条件つき 仕入税額控除とは、納める消費税を計算するときの「支払消費税を差し引く」ことをいいます。次の図の黄色の部分です。この仕入税額控除に、インボイスが大きく影響します。 仕入税額控除は、何もしないでできるわけではありません。次の2つを守らないといけないのです。 帳簿と請求書等(請求書や領収書など)を保存すること 1の帳簿と請求書等には税法に定めた一定事項が書かれていること 帳簿に書かれていても請求書等が捨てられていたら、仕入税額控除はできません。請求...
-

2022.09.27 税務ニュース
扶養の範囲内で稼働したい配達員、103万円の壁はあるのか?
はじめに 配達員をされている方には、親や配偶者などの扶養から外れない様に調整しつつ稼働されているケースがあります。パートやアルバイトであれば、いわゆる「103万円の壁」という言葉が浸透しているお陰で、103万円まで稼いで良いと知っている訳ですが、配達員の場合、「103万円とはどの金額なのか」「そもそも配達員でも103万円は関係あるのか」という疑問が生じてきます。このため、「扶養から外れたくないが配達報酬はいくらまで上げて良いのか」という相談を受けることがあります。 そこで、本稿では、これらの疑問を解決し、扶養の範囲内とはいくらの売上高なのかを探って行きたいと思います。なお、説明を複雑にしないため、配達員は70歳未満で配達報酬以外の収入はないものとして進めて行きます。 そもそも103万円の壁って何? まず、103万円の壁の成り立ちを説明します。 所得税に関して扶養に入るということは、生計をメインで支える親や配偶者などが扶養控除や配偶者控除の適用を受けること意味します。そして、これら適用を受けるには、扶養される側の所得が48万円以下でなければなりません。 ここで、所得は「収入-...
-
![クリエイターと税金[第1回]:人も税も中身が肝心?クリエイターが独立前に稼ぐ「お金の性質の違い」について解説](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-514.jpg)
2022.09.15 おんすけと学ぶ税務情報
クリエイターと税金[第1回]:人も税も中身が肝心?クリエイターが独立前に稼ぐ「お金の性質の違い」について解説
フリーランス・クリエイターが知っておきたいお金と税金のしくみ クリエイターが独立しようとすると、さまざまな疑問や悩みがでてきます。 本コラムでは、これから独立しようと考えている駆け出しクリエイターが知っておきたいお金と税金のしくみを、独立前・開業準備・開業1年後などのステップごとに、やさしく解説します。 第1回では、「独立前」にスポットを当てて、稼いだ「お金の性質」の違いについて考えてみましょう。 クリエイターが稼いだ「お金の性質」とは? 多様化するクリエイターの収入源 SNSなどのプラットフォームの発展により、個人が自分の作品を広める機会が増えました。今まで消費者の立場だけだった人でも、誰もがクリエイティブ領域に飛び込み、コンテンツの生産者・販売者になれるチャンスがあります。 クリエイティブ領域で利用されるプラットフォームは、YouTubeやInstagramなどのSNSをはじめとして、Shopify、NFTなど多岐にわたります。クリエイターはこれらのツールを活用して、デザイン・動画・音声・文字などの「コンテンツ」の提供、広告掲載、オリジ...
-

2022.09.13 税務ニュース
事業承継成功に向けて解決すべき「問題」とは?税理士が徹底解説!
「資産承継」と「経営承継」 “事業承継問題の解消が喫緊の課題である!” 各種メディアでよく出てくるフレーズです。インターネットで“事業承継”で検索すると、実に様々な情報が大量に表示されます。 ところで、事業承継の問題は誰に相談するとよいのでしょうか? 行政機関? 金融機関? 顧問税理士? M&A仲介会社? コンサルタント? 事業承継のケースによっても相談相手は異なってくるでしょう。日常的に接触機会の多い専門である税理士が、どういう立ち位置でこの事業承継にかかわってくるのかについて後ほどご紹介していきます。 では、少し具体的に事業承継の問題について考えてみましょう。 事業承継は大きく分けて、「資産承継」と「経営承継」に分けられます。この二つを承継してはじめて「事業承継」といいます。 「資産承継」は文字通り資産としての会社や事業を承継するという意味です。こちらは主に“お金”が問題になります。つまり、資産価値としての会社をいくらで買うとか、売った側の税金がいくらになるかというような話です。お金の問題は解決するのが比較的容易です。なぜなら、金額の多寡で判断が決まるからです。提示...
-

2022.09.07 税務ニュース
クリエイターの本名がファンにバレる?委託販売のインボイス発行方法3パターンとその活用可能性を解説
クリエイターが自分の作品を販売する方法はさまざまです。 本コラムでは、クリエイターにとって馴染み深い「委託販売」を取り上げ、インボイス発行方法の特例について、やさしく解説します。 特に「クリエイターの匿名性を守る」という面から、「媒介者交付特例」の活用可能性を考えてみましょう。 多様化するクリエイター作品の販売方法 クリエイターにとって作品の販売方法はさまざま クリエイターが自分の作品を販売する「方法・場所」はさまざまです。 ハンドメイド作品やアート・イラスト作品の場合、例えば、イベント販売、インターネット販売、委託販売などの販売方法があります。 委託販売のしくみ このうち「委託販売」とは、「業務を委託する事業者が媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行う課税資産の譲渡等」をいいます。つまり、クリエイターの作品の販売を代行してもらうことです。 販売を依頼する側(この場合はクリエイター)を「委託者」、販売を代行する側(この場合は販売代行業者)を「受託者」といいます。 委託販売のビジネスのしくみを利用すれば、委託者側では商品の所有権を保有したまま商品の販売を委託することが...
-

2022.09.05 税務ニュース
相続税対策はいらない?相続税がかかるかどうかのしくみを解説
「相続税対策が必要だ」__相続特集の雑誌で目にする言葉です。しかし、相続税対策がいらないこともあります。すべての財産が基礎控除額以下のときです。今回、相続税がかかるしくみと相続税のカギの一つである基礎控除額を解説します。 相続税がかかるかどうかを決める2つのカギ 相続が生じても、相続税がかからないこともあります。それは、課税価格の合計額が基礎控除額以下となるときです。「課税価格の合計額≦基礎控除額」のときは、相続税の申告も納税もいりません。 課税価格の合計額と基礎控除額の内容は、それぞれ次の通りです。 課税価格の合計額 課税価格とは、相続人や受遺者(遺言で亡くなった人から財産をもらった人)が亡くなった人から受け取った財産の正味の金額のことです。 ただし、現預金や不動産といったプラスの財産から借金や未払費用などのマイナスの財産を引いたものだけではありません。相続税法で課税するとされたものも、課税価格に含まれます。 課税価格は、遺産をもらった人ごとに、次の流れで計算します。 【引用元】No.4152 相続税の計算(国税庁) この課税価格をすべて合計したもの...
-

2022.08.29 税務ニュース
フードデリバリーUberEatsなどの配達員の確定申告-本気で動き出す前に!
はじめに 突然ですが、見知らぬ土地を旅行しようと言うときに、地図やガイドブックなどが無いとどうなるでしょうか。「自分がどこにいるのか」も「どこへ行くべきか」も「どうやって移動すべきか」も分からず途方に暮れてしまうかと思われます。これは確定申告についても同じです。 では、確定申告の最終目的地はどこでしょうか。確定申告の経験が少ない方からは、「所得を計算して、所得税を算出する」との回答がとても多いです。しかし、これは半分だけ正解です。正確には、その上で「申告期限までに納める税金、または、還付される税金を算出する」が最終目的地となります。 とは言え、「所得の計算とそこから所得税を算出すること」は、確定申告における最重要ランドマークです。そこで、本稿では、このランドマークの前と後に分けて確定申告書上のどこで何を計算するのかという視点で解説します。また、本稿の位置づけとして、確定申告の詳細な解説を理解する為の大枠の知識を説明する様に努めます。 確定申告の作業工程 唐突にランドマークを設定してその前と後という話をしましたが、まずは、確定申告の作業工程をまとめておきます...
-

2022.08.24 税務ニュース
【インボイス制度】登録されているか確認する方法&公表サイトではどんな情報が公開される?
1.はじめに~インボイス制度の概要~ 2023年(令和5年)10月1日から始まる適格請求書等保存方式、通称インボイス制度。 インボイスを発行するためには、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」になる必要があります。そして、適格請求書発行事業者の登録は消費税の課税事業者しかできません。つまり、インボイスを発行するためには次の2つの条件を満たす必要があります。 ①消費税の課税事業者であること ②税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すること 2.登録申請の流れ 登録申請の流れを簡単に説明すると①から④のような流れになります。 ①登録申請書を提出(電子申告又は郵送) ②税務署による審査 ③税務署側で登録と登録簿への登載 ④税務署から申請者へ通知…この通知に登録番号などが記載されています。 ※1出典:国税庁「消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます」 3.「適格請求書発行事業者」に登録されているか確認する方法 実は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、適格請求書発行事業者として登録された事業者の登録情報...
-

2022.08.15 税務ニュース
クレジットカードにはメリットがたくさん!自動仕訳で業務の効率化を目指してみませんか?
事業経営者には、ある程度共通している「やりたくないこと」と「やりたいこと」があります。例えば、次のような「やりたくないこと」は、多くの方が納得するのではないでしょうか。 お金を払いたくない お金の記録をつけたくない 会計ソフトの入力をしたくない やりたくない理由はシンプルです。これら経理や会計と呼ばれる作業が、事業の目的である「やりたいこと」に対して直接的に貢献しないように思える活動だからです。 逆に経営者が「やりたいこと」も見てみましょう。 お客さんが喜ぶ 社員が喜ぶ 儲かる これは分かりやすいと思います。事業者によってその理念は多様ですが、概ねこのようなものであると思います。今回は、これらの「やりたいこと」を実現し、「やりたくないこと」を回避するためにクレジットカードが有効だ、ということを説明していきます。 1. お金を払いたくない お金を払うことを支出と言います。クレジットカードを使うと、支出を減らすことができます。現金を使った取引と比較してみましょう。当然ですが、現金で商品を買うと、その場で商品を受け取り、同時に...
-

2022.08.10 税務ニュース
固定資産税の節税策?住宅街の土地に栗の木が生えているワケ
郊外の住宅街で栗の木しか植えられていない畑を目にすることがあります。少量の栗の販売だけで生活が成り立つとは思えません。なぜこのような土地があるのでしょうか。理由の一つは、固定資産税にあるようです。 固定資産税とは何か 固定資産税は、土地や建物、償却資産と呼ばれる事業用資産に課される税金です。都道府県や市区町村が課税します。納めるのはその年の1月1日において固定資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人です。税額は、原則、次の式で計算します。 固定資産税=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率) 農地の固定資産税は4区分で課税 農地も土地なので固定資産税がかかります。ただし、農地法で利用が制限されている分、収益性は宅地より劣ります。そのため、農地の固定資産税は宅地よりも低く設定されます。 ただ、農地と言っても様々です。農業向きなところもあれば、宅地向きなところもあります。固定資産税の課税にあたっては、農地は「一般農地」「生産緑地」「一般市街化区域農地」「特定市街化区域農地」に分けた上で計算します。 【引用元】農地の保有に対する税金(固定資...
-

2022.08.08 税務ニュース
「判決」「裁決」「判例」。違いをお教えします!
はじめに 私たち税理士に対する相談事や税務調査の際の折衝におきまして拠り所とするものが「税法」です。しかし法律というものは「税法」に限らず、取り扱いを明示しているものではなく、基本的な考え方を示すにとどまっております。これを補完するために「施行令」や「施行規則」というものも準備されておりますがこちらも法の保管という位置づけに過ぎません。 「判決」「裁決」「判例」 一方でこれらの法の下、行動をし、結論付けられた結果があります。これらが「判決」「裁決」「判例」です。いずれも具体的ケースにおいてどの様に法が解釈され適用されたかということが詳細に示されており、実務上大きな拠り所となります。近年「裁決」の出たタワマン節税をはじめ、これらの具体事例が今後の税務判断に影響を与えるのです。今回は「判決」「裁決」「判例」のそれぞれの正しい理解とそれぞれの違いをお伝えしていきます。 「判決」は裁判所が下した判断の結果 「判決」は皆様も新聞やニュース、ドラマなどでも耳にしたことがあるのではないでしょうか。こちらは「裁判所が下した判断の結果」を指します。ですので「東京地裁で認容」や「最高裁で棄却」などと...
-

2022.08.03 税務ニュース
居住用不動産の相続・譲渡に備える!過度な税負担を避けるための特例
ご自身が居住されている不動産について、過度な税負担が生じないよう多くの特例が存在します。私が確定申告をした際、特例が受けられなかったケースがありましたので、ご紹介します。 事例 父が居住用不動産(土地・建物)所有、子は別のところに居住用不動産を所有 父が亡くなったとき、父・母が居住していた土地・建物を「子が相続」 その後、母が介護施設に入るため、居住していた土地・建物を売却 ➡売却した土地建物の所有者は子であり、自己が居住する土地建物ではないため、居住用不動産の譲渡所得の特例を受けることができませんでした。 解説 不動産を名義変更する場合、登記が必要になるため、登録免許税や司法書士への報酬等が生じます。また、相続以外で不動産を取得した場合、不動産取得税の負担が生じます。従って、何度も名義変更をしないようにする方が、登記費用等の負担が減るため、相続の際に先に次の世代が取得するケースもあります。今回は以下のようになりました。 ① 父から相続した時点では、母が居住している不動産の売却予定がなかったので、登記費用等の負担を抑えようと考えた ② ...
-

2022.08.01 税務ニュース
【前編】相続問題に備えるために家族信託を活用しよう!
世界でもトップクラスの超高齢社会であり、その高齢者に資産が偏在する日本。ますます高齢化が進むなかで、認知症患者数も増え続けています。内閣府が平成29年に発表した「高齢社会白書」によると、2012年の認知症患者数は約460万人(高齢者人口の15%相当の割合)だったものが、2025年には700万人前後(高齢者の5人に1人くらい)になるという推計があります。その後も罹患者数は上昇していくでしょう。 一方で、遺産分割をめぐる争いも増加しており、家裁における遺産分割事件(家事調停・審判)数も近年では1万5千件を超えています。遺言書の作成により、ある程度「争族」を防止できるかもしれませんが、遺留分侵害額請求の訴訟が発生するリスクもあって、遺言書が万能なツールになるとは限りません。 そこで今回は、平成18年に改正された信託法による「家族信託」なる制度とそれに伴う税金のはなしについて、複数回に分けてご案内したいと思います。 そもそも信託とは? 信託とは、財産を預け(預かり)、預かった人は責任を持って預けた人のためにその財産を管理・運用・処分することをいいます。この時、その管理等によって...
-
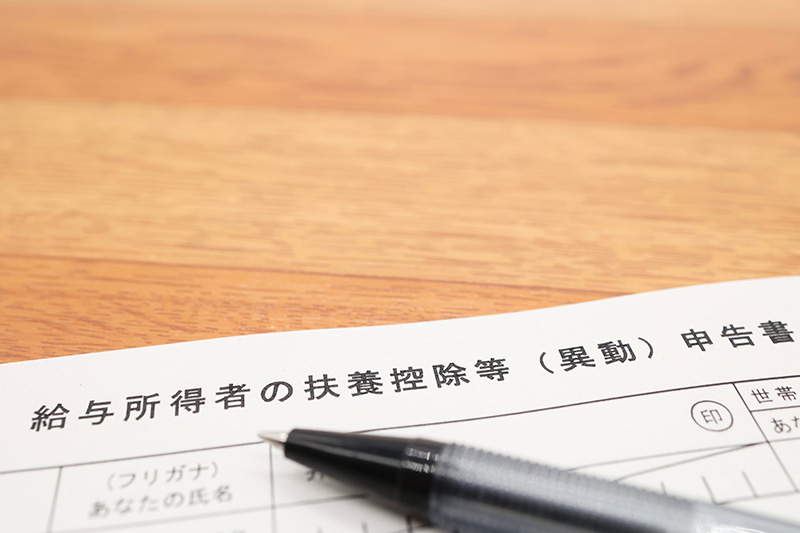
2022.07.29 税務ニュース
【2022年 年末調整】年末調整って何?経理初心者が知っておきたい基本をざっくり解説
11月になると、多くの企業や会計事務所がソワソワし始めます。経理になったばかりの方だと不思議に思うかもしれません。ソワソワの理由は「年末調整」です。 年末調整とは何でしょうか。なぜ会社が行うのでしょうか。今回は、経理1年目の方に向け、年末調整の基本をざっくり解説します。 年末調整とは何か 年末調整とは、給料や賞与から預かった所得税の合計額と、1年間の給与全体にかかる本来の所得税額とを比べ、その差額を精算する手続きをいいます。 会社の役員や従業員が受け取る役員報酬や給与・賞与は、決まった金額そのままを受け取るのではありません。社会保険料や所得税、住民税が源泉徴収(天引き)されています。支給されるのは、源泉徴収後の残額です。 源泉徴収される所得税は、扶養している家族の数と課税される給与額の額の2つだけで決めた概算額です。1年ベースで見た所得税を考えると、少し多めに徴収されています。 一方、1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる所得税は「年の途中で扶養する家族の数に変更があった」「住宅ローンを支払っている」「本人や家族が障害者である」といった事情を考慮した上で計算...









 トップ
トップ



![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)

