MENU


 PICKUP
PICKUP
税務ニュース
【2025年度(令和7年度)税制改正(その1)】103万円の壁の引き上げは123万円に!いつから?大学生のバイト「103万円→150万円」の控除も解説
昨年12月20日に2025年度(令和7年度)税制改正大綱が公表されました。もっとも注目されたのは「103万円の壁の引き上げ」です。どうなったのでしょうか。いつから始まるのでしょうか。今回は、103万円の壁の引き上げと大学生のバイトの壁の引き上げを中心に解説します。 2025年度(令和7年度)税制改正①「103万円の壁」が「123万円の壁」に 個人向けの税制改正の1つ目は「103万円の壁の引き上げ」です。 103万円の壁とは、パート・バイトといった給与所得者の非課税枠を言います。「給与所得控除の下限55万円+基礎控除額48万円=給与年収の非課税の上限103万円」という内容です。 多くのパート・バイトはこの103万円の壁を気にするため、年末になると「働き控え」という現象が起きていました。そのため、企業は人手不足に悩み、家計は物価高が改善されないという状況に陥っていたのです。 そこで、与党から政策協力を求められた国民民主党が「103万円の壁を引き上げるべきだ」と提案しました。議論が重ねられた結果、今回の税制改正で103万円の壁が引き上げとなったの...

社会保険ワンポイントコラム
職場の離職率低下につながる効果が!治療と仕事の両立支援について
治療と仕事の両立についての社会的背景 近年、医療の進歩により、がんのように以前は不治とされていた病気でも生存率が向上し、長期にわたって仕事との両立が可能になりつつあります。病気になったらすぐに離職しなければならないという状況から、治療を行いながら仕事を続けられる社会的環境へと変化しています。 しかし、疾病や障害を抱える従業員を支援するための社内体制が整っていない場合、従業員は仕事を続けたくても離職を選択せざるを得ません。これは企業にとっても人材の大きな損失といえるでしょう。 両立支援の内容 治療と仕事の両立支援の内容ですが、具体的には次のような柔軟な働き方ができる制度を設けた上で、私傷病の治療や療養を目的とした利用ができるようにします。 時差出勤制度 短時間勤務制度 時間単位の休暇制度・半日休暇制度 フレックスタイム制度 在宅勤務(テレワーク)制度 休職制度 両立支援に取り組むことの効果 労働政策研究・研修機構(JILPT)の「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)2024年3月」によれば、上記のよう...

55件 1~20件を表示
-

2025.01.29 中小企業おすすめ情報
リファラル採用とは?注目されている理由や成功のポイント
採用市場がますます激化する中、企業は優秀な人材を確保するために新たな採用手法を模索しています。その中で注目されているのが「リファラル採用」です。 これは社員自身の人脈を活用して候補者を紹介し、効率的かつ効果的に採用を進める方法です。企業文化への適応力が高く、採用後の定着率向上が期待できるこの手法は、今後の採用戦略における重要な柱として位置づけられています。 本記事では、リファラル採用の基本から成功のポイント、注意点まで詳しく解説します。 リファラル採用とは リファラル採用は、企業の社員が自分の知人や友人を候補者として紹介し、その紹介を通じて採用活動を行う手法です。 社員が企業文化や業務内容を理解した上で適切な人材を推薦するため、採用の質が向上することが期待できます。リファラル採用の定義や注目されている理由について詳しく見ていきましょう。 リファラル採用の定義と概要 リファラル採用は、従業員が自分の知人や友人を採用候補として紹介し、条件が合えば採用する方法です。 英語の "referral"(推薦や紹介)が語源です。社員自身が推薦者として責任を持つため、候補者と企業のミス...
-

2024.12.02 中小企業おすすめ情報
郵便料金の値上げに負けない!電子請求書でコスト削減
2024年10月1日より、郵便料金の見直しが行われました。これによって、コストが増加する会社も多いでしょう。一方、これまで電子化に踏み切れなかった会社が請求書の電子化に踏み出すチャンスとも言えます。そこで、本記事では郵便料金の値上げの概要とその影響、解決策として請求書を電子化する方法とそのポイントについて説明します。 郵便料金の改定の概要とその影響 2024年10月1日に実施された郵便料金の改定によって、全体的に値上げの傾向となりました。例えば、定形郵便物の料金は25gまでは84円でしたが、50gの区分と統合され、110円とされました。はがきは63円から85円へと、34.9%の大幅値上げがされました。一方、速達や書留、レターパックなど利用頻度の高いサービスは15%の値上げに抑制され、ゆうパック、ゆうパケット、ゆうめーるなどの荷物配送サービスは値上げ対象外とされています。 出典:2024年10月1日(火)から郵便料金が変わりました。 - 日本郵便 この改定によって大きな影響を受けるのが、大量の郵便物を発送する会社です。例えば、月に定形郵便物を1万通程度送る会社は約300万円の...
-

2024.09.06 中小企業おすすめ情報
これから変わる?職場における今後の定期健康診断の方向性
職場の健康診断における現行の診断項目が適当かどうかについては様々な意見があり、2023年に発足した厚生労働省の「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会(以下 検討会)」でまさに議論が進んでいる最中です。いろんなステークホルダーが絡むためにまだどこに着地するかははっきりしていないのですが、会議録から読み取れる今後の方向について、私見を含めまとめてみます。なお、検討会の議事録は厚生労働省のサイトに掲載されています。 国民の健康を支える職場の健康診断 職場で行われる健康診断は、「一般健診」と「特殊健診」に大きく区別されます。 一人でも労働者を雇用している事業主には労働者に「一般健診」を受けさせる義務があり、労働者は受ける義務があります。オフィスワーカーが年に1回(夜勤などがある人は半年に1回)受けているのはこの「一般健診」です。これに加えて、例えば有害な薬剤に接する人や、放射線に関わる業務に携わっている人などはその作業に応じた「特殊健診」を受ける義務があります。 市町村で実施している住民に対する健診は義務ではない一方、多くの人々が労働者の義務として健診を受け...
-

2024.07.02 中小企業おすすめ情報
中小企業のセキュリティ対策とは?現状・サイバー攻撃の種類も解説
デジタル化が進む現代において、情報漏えいやシステムダウンなどの脅威は増加の一途をたどっています。サイバー攻撃やデータ漏洩といったリスクは、企業の信頼性や事業継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。そのため、適切なセキュリティ対策とデータ保護戦略を構築することが不可欠です。 本記事では、中小企業が実践すべき具体的なオンラインセキュリティ対策と、データ保護のための戦略について詳しく解説します。 中小企業のオンラインセキュリティの重要性 中小企業にとって、オンラインセキュリティは事業継続のために欠かせないものです。サイバー攻撃の増加に伴い、セキュリティ対策が不十分な企業は深刻な被害を受けるリスクがあります。 たとえば、ランサムウェアによる攻撃を受けた場合、業務システムが暗号化され、全てのデータにアクセスできなくなります。これにより、業務が停止し、身代金を支払わざるを得ない状況に陥ることがあります。この結果、多額の経済的損失を被り、顧客の信頼を失う可能性があるでしょう。 また、フィッシング攻撃によって従業員の認証情報が盗まれた場合、不正アクセスにより顧客データや企業の機密情報が...
-

2024.06.28 中小企業おすすめ情報
悪天候の日の出社の基準は? 休業手当は必要?
台風や大雨などで天気が荒れる日は、できるだけ外出は控えるべきですが、仕事の都合上無理をしてでも出社が必要になる時もあるでしょう。しかし、悪天候の屋外を出歩くと事故で怪我をする恐れがあるため、企業が従業員に無理を強いてよいのかという疑問も出てきます。悪天候時の出社について、企業はどのように対応するべきでしょうか? 悪天候時の出社ルールは企業が決める 警報が発令されるレベルの大型台風や大雪の日に、出社するべきかどうかの判断で悩む人は少なくありません。 天候が荒れると予報されていても、実際にどのような天気になるかは当日になってみないとわからないものです。天気予報で散々大雨への注意を促していたのに、当日になってみると小雨程度しか雨が降らなかった、といった経験は誰しもがあるのではないでしょうか。しかし、警報発令中に会社で仕事していると、だんだん天気が荒れていき、従業員が帰宅難民になってしまうパターンもあるので油断は禁物です。 悪天候の日に出社するべきかについての規定は、法律にはありません。そのため、企業ごとに独自の基準で出社の要・不要を決定します。 判断の基準は、従業員の安全を考慮...
-
![アフターコロナの経営[シリーズ第6回]コロナ融資は繰り上げ返済すべきか?](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-173.jpg)
2024.06.19 中小企業おすすめ情報
アフターコロナの経営[シリーズ第6回]コロナ融資は繰り上げ返済すべきか?
このシリーズでは「アフターコロナの経営」というテーマで、この時代を生きる経営者が持っておきたい視点、知っておきたい情報を取り上げています。前回(第5回)のコラムでは、アフターコロナもまだまだ資金調達を必要とする事業者が多いことを受け、「自社はあとどれくらい借りられるのか」を考えるときの目安を解説しました。今回のコラムでは、それとは逆に資金が充足している、つまりコロナ禍のダメージから回復した事業者からの「コロナ融資は繰り上げ返済すべきか」という声を取り上げます。 コロナ禍のダメージから回復した事業者も多い 新型コロナウイルスの流行は、経営へのインパクトにおいて間違いなく戦後日本経済トップクラスの出来事でした。しかしアフターコロナの今、コロナ前の調子を取り戻した事業者も増えています。実際、経済動向をあらわす様々な指標はコロナ前の水準に戻ってきています。 多めに借りることもできたコロナ融資 2020年、一時的な措置として始まった様々なコロナ融資は、いずれもコロナ禍の影響を受けた事業者を対象にしたもので、利子負担が軽い、平時に比べると審査のハードルが低い、等の特徴がありました。「コ...
-

2024.06.14 中小企業おすすめ情報
パナソニック創業者が採用面接で聴いた質問とは?
誰もが知っているパナソニックという会社。この会社の創業者が松下幸之助さんです。筆者が就職する40年前は、松下電器産業という社名でした。当時は大阪府の門真市が拠点でした。松下翁は、会社経営にとどまらず、1946年には「Peace and Happiness through Prosperity」のスローガンを掲げてPHP研究所を創設したり、未来のリーダーを育成するため1979年に松下政経塾を設立されたりしました。特に、松下政経塾からは野田佳彦元首相をはじめとする国会議員や県知事など多くの政治家などを輩出しています。 松下翁は1894年(明治27年)和歌山県で生まれ、尋常小学校を4年生で中退して大阪の火鉢店や自転車店で丁稚奉公に出ています。その後、大阪電燈(現在の関西電力)に勤務。1918年(大正7年)23歳のときに松下電器器具製作所を創業されています。その後は、紆余曲折はあったにせよ、日本の経済成長と軌を一にして「天下の松下電器」へと成長させました。その松下翁の口癖は「成功したのは運が良かったから」「3つがなかったお陰」。3つとは「学歴がなかった」「家が貧しかった(落ちぶれた)...
-
![アフターコロナの経営[シリーズ第5回]我が社はどれくらい借りられる?目安を知ろう](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-186.jpg)
2024.05.27 中小企業おすすめ情報
アフターコロナの経営[シリーズ第5回]我が社はどれくらい借りられる?目安を知ろう
このシリーズでは「アフターコロナの経営」というテーマで、この時代を生きる経営者が持っておきたい視点、知っておきたい情報を取り上げています。前回(第4回)のコラムでは、コロナ融資の返済に苦しむ事業者が多い現状を受け、返済が苦しいときの対応に関する基礎知識を取り上げました。今回のコラムでは、アフターコロナもまだまだ資金調達を必要とする事業者が多いことを受け、「自社はあとどれくらい借りられるのか」を考えるときの目安を解説します。 アフターコロナも資金需要は尽きない コロナ禍で大きなダメージを受けた事業者の多くが、徐々にお客様を取り戻して回復に向かっているのではないでしょうか。完全回復までの道のりで頼りの綱となるのは、やはり「手元資金」です。例えばコロナ禍で従業員が離れてしまった場合は、人材の採用・教育・定着に取り組む資金が必要です。施設設備の修繕やバリューアップが必要なケースもあるでしょう。アフターコロナに世の中に浸透したデジタルツールを導入するケースもあるでしょう。 コロナ禍の局面では主に「赤字の補填」という意味でコロナ融資が必要でしたが、アフターコロナに立ち直ろうとする局面では...
-

2024.05.22 中小企業おすすめ情報
備えあれば患いなし?災害発生時に企業が取るべき対応について
近年、パンデミックや紛争、そして大地震等の自然災害等により、企業の危機管理や事業継続の在り方が問われるような事態が続発しています。災害等が発生した場合、通常通り業務を実施することが困難になります。企業としてはどのように備えておけば良いのでしょうか。 1. BCP策定について 介護事業所では、3年の経過措置期間が終わり2024年4月より「BCP」の策定が完全義務化されました。「BCP」とは、「Business Continuity Plan」、「事業継続計画」と訳され、中小企業庁のホームページでは、「BCP(事業継続計画)とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと」と説明されています。 各種サービス提供が途絶えてしまうと、サポートを必要とする高齢者や障害者等へ大きな影響を与えてしまいますので、介護事業所にて義務化されましたが、近年の状況からすると、全ての企業におい...
-

2024.05.20 中小企業おすすめ情報
中小企業が狙われているサイバー攻撃ってなに?~平均被害金額2,386万円から企業を守るために~
サイバー攻撃における被害の実態 特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)の「サイバー攻撃被害組織アンケート調査」により、ランサムウェア平均被害額は2,386 万円と発表されました。 国内のサイバー攻撃の被害組織で実際に生じたコストを調査するために、2017年1月から2022年6月までの5年半に報道のあった国内で発生したサイバー攻撃情報を収集し、被害組織の情報を調査し約1,300組織をリストアップし、アンケート調査を行ったものです。 また、ランサムウェア感染組織へのアンケート結果によると、データを復旧できた組織は50%で、全てバックアップデータからの復旧とのことで、アンケートに回答したランサムウェア被害組織すべてが「身代金は支払っていない」と回答しています。 警察庁の「令和5年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」では、2023年上半期に警察庁に報告のあった「企業・団体等におけるランサムウェア被害」の件数は103件に上り、そのうち約6割を中小企業が占めています。 被害種別 平均被害金額 サイバー攻撃の種別構成 ランサムウェア感染被害...
-
![アフターコロナの経営[シリーズ第4回]コロナ融資の返済が苦しいときの対応](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-200.jpg)
2024.05.01 中小企業おすすめ情報
アフターコロナの経営[シリーズ第4回]コロナ融資の返済が苦しいときの対応
このシリーズでは「アフターコロナの経営」というテーマで、この時代を生きる経営者が持っておきたい視点、知っておきたい情報を取り上げています。前回(第3回)のコラムでは、延長を重ねてきたコロナ融資が終了することを受け、今後のために知っておきたい融資の基礎知識を取り上げました。今回のコラムでは、コロナ融資の返済に苦しむ事業者が多い現状を受け、返済が苦しいときの対応に関する基礎知識を取り上げます。 コロナ融資の返済は順調ですか コロナ融資では、多くの場合、据え置き期間(元本の返済開始を猶予してもらえる期間)を設定することができました。この据え置き期間は最長5年とされており、3年程度で設定した事業者が多いようでしたので、コロナ禍が始まった2020年から2021年に融資を受けて、2023年から2024年にかけて元本の返済がスタートする・・・というケースが多いと思います。ちょうど本記事の執筆時点(2024年4月)の今がまさにその時期ですが、みなさん問題なく元本返済をスタートできているでしょうか。 コロナ融資で調達したお金をコロナ禍の赤字補填に充てたとしたら、これから始まる返済の原資は、当然...
-

2024.04.22 中小企業おすすめ情報
退職した人のパソコンのバックアップと安全な破棄・流用方法
春は新入社員が入社したり、逆に退職する人も多いでしょう。そこで問題になるのが、退職した人のパソコンです。パソコンやスマホ、タブレットなど会社支給の物は、会社の資産なので、個人で設定していたIDやパスワードを引き継がなくてはなりません。また会社経費で購入したアプリ、最近では月額や年額で契約するアプリなどもあるため、ソフトウェアのIDとパスワードの引継ぎも重要になります。 また長年使っていたパソコンは型が古く使えないものは、機密情報などを完全に消去してからでなければ廃棄できません。実はこの消去をしていないパソコンが非常に多く、中古ショップで部品取り用に買ってみたら顧客データのようなものが丸見えだったなんてことがあります(これは筆者が体験した実話です)。 ここでは退職した人のパソコンの引継ぎから、安全に破棄、もしくは流用するためのノウハウを説明します。 WindowsにログインできるIDとパスワードを必ず残してもらう! 退職した人のパソコンでまずすべきことは、WindowsやiOSにログインできるようIDとパスワードを引き継ぐことです。通常はログイン時にIDとパスワードを利用して...
-
![アフターコロナの経営[シリーズ第3回]ついに終了を迎えるコロナ融資。知っておきたい融資の基本](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-214.jpg)
2024.04.01 中小企業おすすめ情報
アフターコロナの経営[シリーズ第3回]ついに終了を迎えるコロナ融資。知っておきたい融資の基本
このシリーズでは「アフターコロナの経営」というテーマで、この時代を生きる経営者が持っておきたい視点、知っておきたい情報を取り上げています。前回(第2回)のコラムでは、アフターコロナの人手不足への対応策をお示ししました。今回のコラムでは、これまで延長を重ねてきたコロナ融資がいよいよ終了することを受け、今後のために知っておきたい融資の基礎知識を取り上げます。 平時より簡単に借りられたコロナ融資 コロナ融資は新型コロナウイルス感染症の影響が本格化した2020年から始まりました。と、言っても、「コロナ融資」という名前の融資メニューがあるわけではありません。公的機関がコロナへの対応として創設した様々な融資制度を総称して「コロナ融資」と呼ばれています。主なコロナ融資には以下のものがあります。 日本政策金融公庫(政府系金融機関)の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」 信用保証制度(注1)を用いた民間金融機関の融資(平時からある制度ですが、コロナの影響を受けた事業者向けに保証をより強化するもの) (注1)信用保証制度・・・事業者が民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が...
-
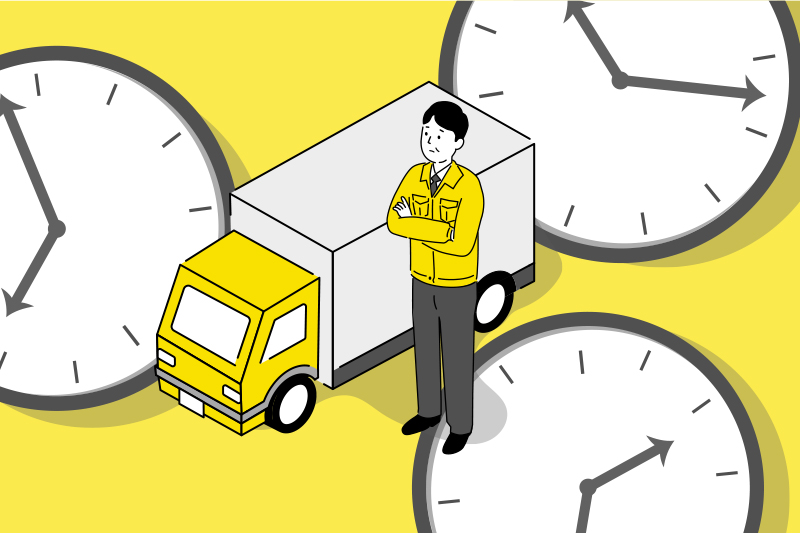
2024.03.22 中小企業おすすめ情報
2024年問題とは?物流・建設・医療の各業界の影響と解決策を解説
2022年頃から「2024年問題で各業界が大変なことになる」と騒がれるようになりました。特に影響が大きいとされているのが、物流・建設・医療の業界です。今の日本の産業では人手が足りていないと言われている中、2024年問題で深刻な問題が出るのではないかと言われています。 この記事では、2024年問題の内容と、物流・建設・医療の各業界への影響、解決策についてお伝えします。 1.2024年問題とは何か?背景も確認 2024年問題とは、2024年4月から時間外労働が規制されることで生じる問題を言います。2024年問題の背景と内容を以下、確認していきましょう。 1-1.2024年問題の背景 2024年問題の背景には、働き方改革関連法の成立があります。「職場環境を改善して、魅力的な職場づくりをしよう。そして人手不足を解消しよう」という号令の下、さまざまな法改正が行われました。 その1つが労働基準法の改正です。これにより、次のように時間外労働に上限が設けられることとなりました。大企業では2019年4月から、中小企業は2020年4月から適用されています。 引用元:働き方改革関...
-

2024.03.15 中小企業おすすめ情報
オフィスの電気代を抑える方法は? 有効な対応策を解説
現代人の日常生活は、ありとあらゆる場面で電化製品の恩恵を受けています。当然職場で仕事をする時にも電力は不可欠な存在です。しかし、近年では燃料価格の高騰によって、電気代が悩みの種になっている企業は少なくありません。 この記事では職場の電気代を削減する方法について解説します。無駄を減らしたり、業者を見直したりといった方法で、電気代の負担を軽減できる場合もあるので、対策方法を探している人は参考にしてみてください。 オフィスの電気料金の相場 オフィスではパソコン・電話・コピー機などのOA機器をはじめ、休憩時間に利用するための電子レンジやポットなどさまざまな電化製品が使用されています。ほとんどのオフィスは、一般的な家庭よりもスペースが広いため、照明や空調を広範囲に対応させなければならず、その分電気代が高額になりがちです。 オフィスの電気代は、10坪の広さで1ヶ月あたり約2万円、30坪で約4万円、70坪の場合は約7万円が相場とされています。月々支払っている金額が相場と大きく異なる場合は、一度電気の利用状況を見直しましょう。 ただし、「部屋の陽当たりが悪くて寒いため、暖房の設定温度を高...
-
![アフターコロナの経営[シリーズ第2回]補助金も新設!アフターコロナの人手不足対策](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-229.jpg)
2024.03.04 中小企業おすすめ情報
アフターコロナの経営[シリーズ第2回]補助金も新設!アフターコロナの人手不足対策
新型コロナウイルスの流行は、経営へのインパクトにおいて間違いなく戦後日本経済トップクラスの出来事でした。アフターコロナの今、様々な場面でコロナ前の風景が戻ってきました。経営者は、苦しかったコロナ禍を忘れて今まで通りの経営を続ければよいのでしょうか。 このシリーズでは「アフターコロナの経営」というテーマで、この時代を生きる経営者が持っておきたい視点、知っておきたい情報を取り上げています。前回(第1回)のコラムでは、コロナ禍を過ぎて元通りになったかに見える世の中も決して元通りではない、という視点をお示ししました。今回のコラムでは、アフターコロナの人手不足に関して知っておきたいことを取り上げます。 人流の極端な変化が招く、アフターコロナの人手不足 長かったコロナ禍を過ぎて、2023年は賑わいを取り戻した年でした。日本では2020年4月の緊急事態宣言が決定打となって全国の街から人が消え、その状態が3年近く続いた後、徐々に人流が戻ってきたところです。 日本人の動きも大きく変動しましたが、インバウンドは特に激しく変動しました。コロナ前、政府は東京2020オリンピック・パラリンピックに向...
-
![アフターコロナの経営[シリーズ第1回]コロナで変わった世の中に対応しよう](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-248.jpg)
2024.02.02 中小企業おすすめ情報
アフターコロナの経営[シリーズ第1回]コロナで変わった世の中に対応しよう
新型コロナウイルスは世界中の企業経営に影響を及ぼしました。日本では2020年から政府が実施した行動制限や営業自粛要請で「売上がゼロになる」というまさかの事態に至った事業者も少なくありません。 コロナ禍は、経営へのインパクトにおいて間違いなく戦後日本経済トップクラスの出来事です。アフターコロナの今、経済動向をあらわす様々な指標がコロナ前の水準に戻ってきましたが、経営者は、苦しかったコロナ禍を忘れて今まで通りの経営を続けてよいのでしょうか? このシリーズでは「アフターコロナの経営」というテーマで、この時代を生きる経営者が持っておきたい視点を取り上げてまいります。 コロナ禍が変えたことの筆頭「消費者の衛生観念」 アフターコロナの街に賑わいが戻った後も、なかなか「これで元通り」とはいかないことがいくつかあります。その筆頭が「消費者の衛生観念」です。コロナ禍の最中に政府が発した「3つの密を避けましょう」「ソーシャルディスタンス」という呼びかけは、人々の脳裏に強烈に刷り込まれました。「人ごみ」「不特定多数の人が触れる物」「他人やスタッフとの交流や触れ合い」を避ける意識はコロナ前とは比べ...
-

2024.01.19 中小企業おすすめ情報
最近話題のリスキリングとは?
はじめに 最近リスキリングという言葉をよく耳にするようになりました。日本の雇用制度の変革や人生100年時代における働き方の多様化など、社会的な背景からもリスキリング、学び直しといったキーワードの注目度が高まっています。 2023年6月、政府において「経済財政運営と改革の基本方針2023(骨太の方針)」というものが閣議決定されました。具体的には、「①リスキリングによる能力向上支援」、「②個々の企業の実態に応じた職務給の導入」、「③成長分野への労働移動の円滑化」の3つを柱とする政府の新しい改革の方向性を示すもので、この取り組みを「三位一体の労働市場改革」といいます。 三位一体の労働市場改革の考え方については、一人ひとりが自らのキャリアを選択する時代となってきた中、「職務ごとに要求されるスキルを明らかにすることで、労働者が自らの意思でリスキリングを行い、職務を選択できる制度に移行していくこと」が重要だとしたうえで、「内部労働市場と外部労働市場をシームレスにつなげ、労働者が自らの選択によって労働移動できるようにすることが急務」としています。 ポイントは、「労働者が自らの意思で」の部...
-

2023.12.18 中小企業おすすめ情報
スポーツジムの法人会員になるメリットは? 選ぶときのポイントも解説
従業員の定着や採用活動における企業のアピールのために、福利厚生の充実を図る企業は多くあります。福利厚生にはたくさんの種類がありますが、従業員の健康づくりを促進するために、スポーツジムの法人会員を検討してみてはいかがでしょうか。 今回の記事では、スポーツジムの法人会員になるメリットについて紹介していきます。 スポーツジムの法人会員になれば『健康経営』促進につながる 「学生の頃はよく運動していたけど、大人になってからはほとんど体を動かさなくなった」 社会人にはこんな人が多いのではないでしょうか? 年齢を重ねていくと、日常のさまざまな場面で身体の衰えを実感することが増えるものです。年齢による体力の衰えは仕方のないものですが、何も対応しないままでいると、状況はどんどん悪くなる一方になっていくでしょう。そこで、体力と健康な体を維持するためにも、大人になってからも運動を習慣づけることが大切になるのです。 体を動かすのであれば、自宅で筋トレや公園でスポーツ、家の近所をジョギングする、といった方法ももちろん効果的でしょう。そのほかに、スポーツジムの利用も独自のメリットを持つのでオススメで...
-

2023.11.08 中小企業おすすめ情報
採用計画を立てる前に覚えておこう! 秋採用の傾向と注意点とは?
少子化の進行によって労働人口が減少しつつある日本。加えて、かつては当たり前のものとして考えられていた終身雇用制度の時代が終わり、多くの人が転職をするようになった現代では、必要な人員を確保するために採用活動の重要性が高まっています。 企業が優秀な人材を獲得できるかどうかは“縁”に左右される要素が大きいものの、採用時期によって応募者の傾向に違いが見られる点も見逃せません。 今回の記事では、秋に実施する採用活動、いわゆる「秋採用」の傾向について解説していきます。 秋頃に実施する採用活動が『秋採用』 秋採用とは、名前が示す通り秋の時期に行われる採用活動です。企業によって多少の違いはありながらも、一般的には9月から11月にかけての期間が対象となります。 採用活動は時期によって市場に出回る人材の傾向に違いが出るものです。各時期の傾向を踏まえた上で採用活動を進めれば、企業の希望に合った人材を獲得できる可能性が高まります。また、一口に秋採用と言っても新卒の学生と転職を希望する社会人では、採用活動の傾向に大きな違いがあります。それぞれどのような特徴を持つか見ていきましょう。 新卒を対象とす...









 トップ
トップ



![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)

