MENU


55件 21~40件を表示
-
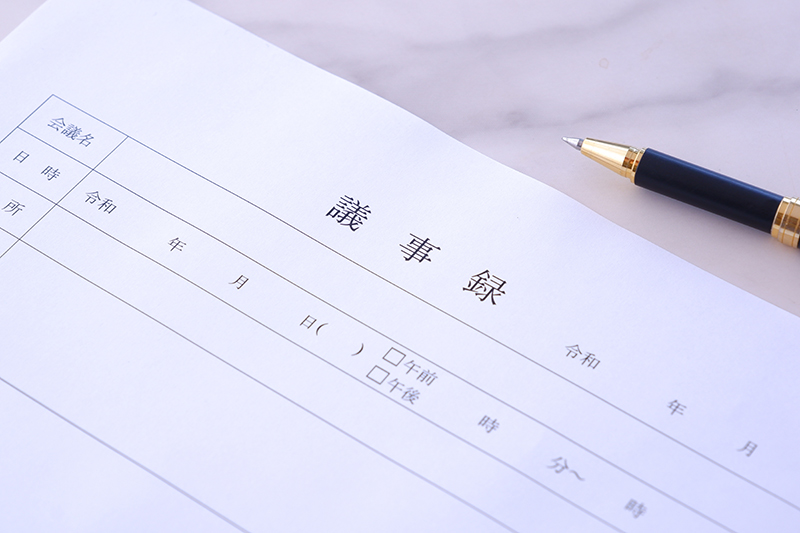
2023.10.06 中小企業おすすめ情報
コロナでここが変わった!~会社の議事録に印鑑を捺さなくなる?
はんこが押せないから、決済ができない! コロナ禍が始まったときに問題になったのは、「はんこが押せないから、決済ができない!」と言うものでした。会社の方針を決める決済は、すべてはんこが必要で、はんこを捺すためには、会社に行かなければならない。これは会社に限ったことではありません。町内会の回覧板も、学校の連絡帳も、みんなはんこに頼っていたんです。 考えてみれば、こんなに不確かな制度は無いように思います。はんこなど、珍しい名字でも、はんこ屋に行って、簡単に作れます。まして、珍しい名字でなければ、文房具屋でも、100円ショップでもはんこは売っています。「これは私のはんこで間違いありません」と証明できることができるでしょうか? 電子署名の出番 コロナ禍になり、急速にデジタル化が進みました。今やコロナに関わらず、テレワークが無くなれば、退職も考えるほどの影響を与えています。 はんこ制度も以前のように簡単に捺印ができなくなり、代わりに「電子署名」「電子証明書」という名前が聞かれるようになりました。電子署名についての法律が制定されたのは、平成12年、今から20年以上も前です。その...
-

2023.08.28 中小企業おすすめ情報
法改正から3年を迎えた賃金請求権時効延長の現実的影響
はじめに 2023年4月1日で労働基準法の重要な法改正から3年を迎えました。賃金請求権の消滅時効期間の延長です。従来、賃金請求権の消滅時効期間2年でしたが、2020年4月1日の労働基準法改正により、賃金請求権の消滅時効期間が3年(当分の間の措置であり、将来的には5年)に延長されました。つまり、今日現在において賃金未払いがあった場合、きっちり過去3年間遡って請求される可能性があるということです。 「うちの会社には賃金未払いなどないはず!」と自負されている会社様も多いと思います。 この“賃金未払い”には、給与計算誤りによるものや残業代不足なども含まれます。意図せずして潜在的に賃金未払いが起きてしまっていることも往々にしてありますので、今一度自社の給与計算方針に誤りがないか、再確認していただけたらと思います。 給与計算の基本①「就業規則通りに運用されているか?」 最近、就業規則(給与規程を含みます)の重要度が非常に高まっているのを感じます。労務の分野では、キャリアアップ助成金など多くの助成金がありますが、就業規則が規定している通りにきちんと運用されているか、という点をかなり厳格...
-

2023.08.24 中小企業おすすめ情報
夏場の健康被害に要注意! 職場で実践するべき暑さ対策とは?
最高気温が30度後半をマークすることも珍しくない、近年の暑い日本の夏。「猛暑」と呼ばれる厳しい気温で体調を崩してしまう人が増えるこの季節には、従業員を健康被害から守るための暑さ対策が欠かせません。 今回は、職場で取り入れるべき暑さ対策を働くシーン別に解説していきます。 職場の暑さが原因で生じるデメリット 過酷な夏場の暑さは、従業員の働きぶりに悪影響を与えかねないので、しっかりと対策を打たなければなりません。最も注意するべきなのが熱中症です。熱中症とは、気温や湿度が高い環境によって体温調整に不調をきたすことで発生する病気です。 初期症状では、主にめまいや立ちくらみなどが起こり、さらに進行すると体のだるさや頭痛、吐き気といった症状が出ます。重症になると、意識障害や真っすぐ歩けなくなってしまうほどの状態になるケースもあり、最悪の場合は死亡してしまうことも。 毎年、6月から9月にかけて熱中症で緊急搬送される人は数万人出ています。高齢者だけでなく、子供や若い世代の人が熱中症になることも珍しくないので、誰にでも起こり得るものと認識して対策していきましょう。 熱中症以外にも、暑さの影...
-

2023.08.21 中小企業おすすめ情報
いまさら聞けない賞与(ボーナス)の基本。支給の目的とは?
例年6月末〜7月にかけては、多くのサラリーマンが待ちに待ったボーナスシーズン。月々の給与と比べてどれくらいの金額が支給されるか、気になっていた方も多かったのではないでしょうか。ボーナスは「賞与」とも呼ばれ、企業の経営方針や業績などにより金額が大きく左右される賃金です。ここではどのような目的で支給されるのかなど、ビジネスマンとして押さえておきたい賞与の基本について解説します。 支給要件は就業規則に明記が必要 賞与とは月々の給与とは別に支払われる一時金のことです。多くの企業では、主に夏と冬の年2回にわたり支給されています。 法律により企業に支給義務がある月給に対し、賞与はあくまで企業が任意で行う賃金払いです。そのため、支給時期や回数には法律の定めがなく、企業によっては支払いそのものがない場合もあります。 賞与を支給する場合、企業はその要件を就業規則に明記する必要があります。一例として、次のような記載が考えられるでしょう。 第●条 賞与 1.正社員については賞与を支給する。但しその勤務成績、および会社の業績等を考慮して減額または不支給とすることがある。 2.賞与の支給日は...
-

2023.07.18 中小企業おすすめ情報
お店の営業目標の立て方(後編)-生きた目標を立てて行動に移そう-
このコラムでは、前編と後編の2回にわたって営業目標の立て方を解説しています。 前編では、売上目標の立て方を解説しました。売上目標を明確にしたら次にすべきことは、日々の具体的なアクションにつながる集客目標を立てることです。後編の今回は、売上目標を集客目標に換算するやり方を解説します。 売上目標だけでは、具体的なアクションにつながらない 例えば、あなたのお店の売上目標が月300万円だとします。先月の売上は250万円で、目標にあと50万円届かなかったとしましょう。「今月は先月よりも頑張らなくちゃ」ということになりますが、売上をあと50万円増やすために具体的に何をどれくらい頑張ればよいのか、店長であるあなたは、スタッフに説明できますか? 例えば、あと何枚チラシを配ればよいでしょうか。客単価が何円になればよいでしょうか。 「あと50万円」という売上目標だけでは漠然としていて、そのような具体的な行動につながらないのです。 成長するお店は、集客目標を立てている 「あと50万円」の道しるべになるのが、集客目標(客数と客単価の目標)です。お店の日々の努力の成果が直接あらわれるのは、客数と客単...
-

2023.06.15 中小企業おすすめ情報
お店の営業目標の立て方(前編)-根拠のある売上目標の作り方を解説-
飲食店や小売店などのお店を経営しておられる皆様、日々の営業目標は立てていますか? 営業目標として「平日は1日10万円、土日は1日20万円が売上目標だ」といった売上目標を掲げる例がよく見られます。しかしその売上目標に明確な根拠があるケースは、あまり多くないようです。また、売上目標を具体的な集客目標(客数の目標)に落とし込めている方も、多くないようです。 このコラムでは、前編と後編の2回にわたって、お店の営業目標の立て方を解説します。前編の今回は、根拠のある売上目標の作り方を解説します。 売上目標を立てるために、まず「儲け(利益)」の目標を立てる 売上がどんなに大きくても、赤字では頑張った甲斐がありませんよね。その商売がうまくいったかどうかは、売上ではなく儲け(利益)で判断するものです。したがって、営業目標を考えるときにはまず「自分はこのお店で毎月どれくらいの儲けを出したいのか?」を考えることが出発点となります。つまり、材料の仕入れや、家賃、人件費、広告費、水道光熱費・・・、といった費用を全部払ったあとに残る利益が、毎月どれくらいあれば最低限良しとするのか。それ...
-
![[どうする?フリーランスの報酬]自分の売り値の決め方](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-386.jpg)
2023.05.18 中小企業おすすめ情報
[どうする?フリーランスの報酬]自分の売り値の決め方
独立して何年たっても、クライアントから「見積書をください」と言われたときには悩むものではないでしょうか。自分のスキルを売るフリーランスにとって、「報酬をどうやって決めるか」は永遠の関心事です。「あらかじめ自分の価格表を用意しておけばよい」というのはよく言われることです。しかし、その価格表をどう作るか。それが問題なのですよね。 「相場金額」が明確でない仕事は特に見積もりにくい 相場金額が明確な仕事であれば、世間一般の相場金額を基準にして見積を作ることができます。 しかし、相場金額が明確でない仕事もあります。例えば特殊な分野のデザインや執筆、クライアントの要望にオーダーメイドで対応する調査分析やコンサルティングなどが挙げられます。ホームページ制作などは比較的「相場金額が明確な仕事」と思われがちですが、ユニークなデザインや機能を備える場合や、企画段階から請け負う場合などは、世間一般の相場金額とは一概に比較できません。このように相場金額が明確でない仕事の場合、金額を見積もるのは難しいものです。 これまでの仕事の報酬を時給換算(日給換算)してみよう 相場が明確でない仕事の場合、その報酬...
-

2023.05.11 中小企業おすすめ情報
企業型DC(企業型確定拠出年金)とは?メリット・デメリット・注意点を解説
企業型DC(企業型確定拠出年金)は、従業員のモチベーションアップや退職後の生活のサポートなどを目的に企業が導入する制度です。個人型確定拠出年金「iDeCo」との違いや導入のメリットなどが気になる方は多いのではないでしょうか。 今回は、企業型DC(企業型確定拠出年金)の仕組みや特徴からメリット・デメリット、注意点まで詳しく解説します。 企業型DC(企業型確定拠出年金)とは 企業型DC(企業型確定拠出年金)とは、企業が掛金を毎月積み立ててて、従業員が運用する制度です。制度を導入した企業の従業員が自動的に加入するケースと、従業員が選択できるケース(選択型企業DC)があります。 企業型DCの加入要件は、「国民年金の第2号被保険者」で、なおかつ「労使合意に基づき確定拠出年金制度を実施する企業に従事している」ことです。 企業型DC(企業型確定拠出年金)の仕組み 企業型DC(企業型確定拠出年金)は、企業が拠出した掛金をもとに、従業員が自ら金融商品を選択したり資産配分を決めたりして運用します。そして、60歳以降の定年に退職一時金もしくは退職年金の形式で受け取ります。積み立てた資産は原則60...
-

2023.04.25 中小企業おすすめ情報
新卒従業員必見、給与明細で押さえておきたいポイントとは?
4月も終わりに近づき、待ちに待った給料日を迎える新社会人も多いことでしょう。給与の支給とともに配布されるのが給与明細。しかし、いざ明細を見てみても「何が記載されているかわからない」なんて人もいるかと思います。ここでは新卒従業員向けに、給与明細の簡単な見方を解説していきましょう。 実際に受け取れる手取りは「差引支給額」でわかる 給与明細とは一般的に、次のような資料を指します。原則として給与支給時期になると、勤務先から配布。これを見れば、受け取る給与がどのような流れで算出されているか、ある程度確認することが可能です。 まず注目すべきは、右下にて記載の「差引支給額」。これが実際に給与の振込口座に入金されるなどして従業員が使うことのできる、いわゆる「手取り」を示しています。 手取りは毎月の家計に直結する金額なので、「差引支給額だけを見てあとは気にしない」という方も多いかと思います。 しかし、どのようにして差引支給額が算出されるか、理解するのも重要といえます。なぜなら手取りは、税金などを天引きして算出される金額であり、ここからは本来の収入がわからないからです。それでは、手取りは...
-

2023.04.20 中小企業おすすめ情報
ユーザー目線を忘れない!「売れる」新商品の価格の決め方(応用編)
新しい商品を売り出すとき、価格をどうやって決めていますか? このコラムでは、基本編と応用編の2回にわたって価格の決め方を解説しています。 前回の基本編では、市場に受け入れられる、つまり「売れる」価格設定の進め方をご紹介しました。今回は応用編として、価格設定において知っておきたいことを2つ取り上げます。 知っておきたいこと1:価格は随時見直すもの 価格は「一度設定したら変えられない」というものではありません。「価格は随時、柔軟に見直すもの」という認識を持っておきましょう。価格を見直すきっかけになり得ることとして、次の2つが挙げられます。 ① 類似商品の動向(価格と機能) ② 自社商品の原価の動向 この2つのことは、毎月のルーチン業務に組み込むなどして、その商品を扱っている限りずっとチェックし続けたいものです。 <価格を見直すきっかけになること①:類似商品の動向(価格と機能)> 類似商品の価格動向は常にチェックしましょう。例えば、後発の会社が安くて良いものを発売したことなどをきっかけに、低価格競争が起きることがあります。また、ある商品の値下げに各社が追随することがあります。そのよ...
-

2023.04.12 中小企業おすすめ情報
従業員数50人以上の会社の”人事労務担当者”が知っておくべき5つのポイント
はじめに 従業員規模が拡大するにつれ、企業として対応すべき労務管理上の義務が新たに発生します。人数規模による企業の義務は、幾度となく法改正を繰り返して基準も変化しており、実務対応に頭を悩ませている人事労務担当者も多いのではないでしょうか。 本記事では、従業員数が50人以上になった場合に発生する5つの義務について、人事労務担当者が知っておくべきポイントを解説していきます。 そもそも従業員数50人とは? 従業員数50人には、フルタイムの常勤社員のみならず、パートタイマーも含むものとされています。また、労働安全衛生法令では、事業場を場所的観念によって考えます。つまり、営業所や工場、施設等、拠点を複数持つ企業においては、会社全体で50人の判定をするのではなく、拠点ごとに50人の判定をする必要があります。 (1)産業医の選任 従業員の健康管理を適切に行う為に「産業医」を選任しなければならないことになっています。「産業医」は、医師の中でも特別な研修を受けた者が有する認定資格であり、医師であれば誰でもよいわけではありません。この「産業医」探しになかなか苦労することがありま...
-

2023.03.31 中小企業おすすめ情報
フリーランス保護新法と中小企業への影響について解説!
現在、フリーランス保護新法を制定すべく議論が進められています。フリーランス保護新法が施行されるとフリーランスへ発注する中小企業へも大きな影響が及ぶ可能性があります。 この記事ではフリーランス保護新法とはどういった法律なのか、中小企業へどういった影響があるのかをご説明します。フリーランスへ外注する機会のある場合にはぜひ参考にしてみてください。 1.フリーランス保護新法が制定される背景事情 フリーランス保護新法は、発注企業に対して立場の弱くなりがちなフリーランスの立場を守るための法律です。まだ制定されていませんが、今後速やかに制定につなげられるよう、政府で議論が進められています。 フリーランス保護新法が制定される背景となった事情は以下のとおりです。 現在、働き方の多様化などの需要によってフリーランスの人口が増えています。ただフリーーランスには労働基準法などの労働者保護法令が適用されません。発注者が企業であるのに対し受注者であるフリーランスは個人であり、どうしても立場が弱くなってしまいがちです。報酬を減額されたり支払い遅延が生じたりするケースも少なくありません。また...
-

2023.03.24 中小企業おすすめ情報
中小企業のWeb集客の方法は?相談先の選び方も解説
Web集客を始めようと考えている方の中には、次のような悩みを抱える方が多いのではないでしょうか。 どのような方法があるのかわからない そもそも自社に向いているのかがわからない どこに依頼すればいいのかわからない そこで今回は、中小企業のWeb集客の方法・種類から相談先の選び方まで詳しく解説します。 そもそもWeb集客とは Web集客とは、インターネットを活用した集客方法のことです。最初に思い浮かべるのがWeb広告や自社ブログ、メールマガジンなどではないでしょうか。Web広告にもさまざまな種類があるほか、MEOやSNS集客といった方法もあります。 Web集客は一見多くの人に宣伝できて高い効果が見込めるように思えるかもしれませんが、戦略を立てて実行しなければコストを無駄に消費することになりかねません。 まずは、Web集客の手法を理解して、自社に合った方法を模索したうえでプロに相談することが大切です。 Web集客の手法 それでは、Web集客の手法について詳しくみていきましょう。 オウンドメディア オウンドメディアとは、企業が自ら所有するメディア...
-

2023.03.23 中小企業おすすめ情報
ネット炎上!~そのときあなたの会社はどうする?
会社でブログを開設していたり、社員が個人的にSNSやブログなどで会社の様子を書いていることがあります。その記事が炎上したら、会社はどのような対応をできるでしょうか。 令和4年にプロバイダ制限責任法が改正になったことは、話題になりました。今回はその内容をご紹介します。 1.事前対応について 会社の社員が、個人的にSNSやブログを書いている場合に、会社はどのくらい介入できるでしょうか。 まずは、会社の就業規則の一環として、SNSガイドラインなどを作成することが考えられます。社員の中には、どこまでSNSで公表して良いものか、わからない方もいるでしょう。社員の意識としては、「このくらいは大丈夫だろう」と思っても、実際は大事に発展する場合もあります。たとえば、取引先の会社の近くで撮った写真や、プライベートで取引先の方と一緒にいた写真をアップされることで、写り込みによる競合他社への情報流出や、取引先からのクレームにつながることもあります。 このような事態を防ぐため、会社が社員のSNSに注意を払わなくてはなりません。 社内でSNSに対する共通の認識を統一する意味でも、ガイドラインを設...
-

2023.03.22 中小企業おすすめ情報
ユーザー目線を忘れない!「売れる」新商品の価格の決め方(基本編)
新しい商品を売り出すとき、価格をどうやって決めていますか? 一番よくある決め方は、その商品の仕入れや製造などにかかる「コスト」に「儲け」を乗せる決め方ではないでしょうか。 販売価格 = コスト(原価や管理費など) + 利益 この決め方は、計算方法がシンプルで分かりやすいため、よく見られます。しかし、これにはデメリットがあります。このような方法で設定した価格には、売り手側の都合しか反映されていないので、競合商品の価格と釣り合いが取れていなかったり、顧客の求める価格からずれてしまっていたりして、市場に受け入れられない価格になる場合がある、というデメリットです。 このコラムでは、基本編と応用編の2回にわたって価格の決め方を解説します。基本編の今回は、市場に受け入れられる、つまり「売れる」価格設定の進め方を解説します。 (ご注意)ここでは、すでに他社の類似商品が世の中に出回っている一般的な商材を前提に解説しています。また、革新的な生産方法・調達方法などによって“品質を維持したまま価格破壊を実現する”といった特殊事例は除外し、一般的な新商品の価格設定のケースを前提に解説しています。 価...
-

2023.03.02 中小企業おすすめ情報
大企業と取引したい!プレゼンコンペに勝つコツ(後編)
大企業や行政機関などの大きな組織が物品・サービスを調達するとき、既存の取引先に限らず、新しい取引先候補に対しても提案や見積を募ることがあります。このような入札(総合評価方式)やプレゼンコンペに参加するチャンスを得たら、ぜひ受注を狙いたいですね。 このコラムの前編では、大きな組織の調達の特徴や、入札(総合評価方式)やプレゼンコンペに勝つコツの概要(評価項目に丁寧に対応すること)を解説しました。後編の今回は、より理解を深めていただくために発注者側の視点を具体的に例示して解説します。 (ご注意)取引先の選定方法や評価項目は、発注者側がそれぞれ自由に設定するものですので、ここで解説する内容はあくまでも一般論としてご参考程度にお読みください。 発注者側が取引先を選ぶ視点(例)の全体像 このコラムの前編で取り上げた通り、大きな組織が入札(総合評価方式)やプレゼンコンペによって取引先を選ぶ際は、各社からの提案内容に、あらかじめ用意された評価項目・評価基準に則って点数をつけるやり方が一般的です。 評価項目は、その調達案件の商品・サービスの特性、調達の背景などを踏まえて事前に用...
-

2023.02.24 中小企業おすすめ情報
経営者が知っておきたい相続の基礎知識|争続を防ぐためのポイントも解説
多額の資産を持つ経営者は、会社や個人の財産の相続について基礎知識を習得しておくことが大切です。法律で定められた「法定相続人」が複数人いる場合、遺言状を作成しないと「争続」が起きてしまう可能性があります。争続とは、遺産の分配についてトラブルになり、遺族同士の関係が悪くなることです。 そこで本記事では、経営者が知っておきたい相続の基礎知識と争続を防ぐためのポイントについて紹介します。 そもそも相続とは 相続とは、被相続人(亡くなった方)の資産や負債を相続人(相続を受ける方)に引き継ぐことです。相続人は法律で定められており、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが該当します。ただし、遺言書で指定することで、家族以外の人物に遺産を引き継がせることも可能です。 相続の方法 遺言書を作成していない状況で亡くなり、なおかつ法定相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議を行います。両方のケースについて詳しくみていきましょう。 遺族で遺産分割協議を行う 遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産の分配や負債の扱いなどについて取り決め、遺産分割協議書に全員の署名と押印をして役所へ提出します。1人でも署名・押...
-

2023.02.07 中小企業おすすめ情報
インボイスは見送っていい? 対応すべき? 基本を学んで賢く対応しよう
10月から仕入れ税額控除を受けるためにインボイスが必要になる インボイス制度が2023年10月1日からスタートします。インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことで、仕入税額控除の要件としてインボイス(適格請求書)の保存が必要になるのが特徴です。中小企業や個人事業主がこのインボイスに対応するかどうかが今話題になっています。会社員は基本的に意識する必要はないのですが、副業をしている人にはやはり関わってきます。 インボイスのことを理解するには、まずざっくりと消費税の仕組みを把握しておく必要があります。例えば、ビジネスで100万円を売り上げた場合、顧客から消費税10万円を預かります。「預かった」と言うのは、消費税は国に納めるからです。顧客から預かった消費税を代わりに納税する必要があるのです。 しかし、100万円を売り上げるために、30万円の仕入れをしている場合、この30万円の消費税3万円は仕入れ先に支払っています。そのため、全体で納税すべき10万円から3万円を控除できます。この仕組みを仕入税額控除と言います。 これまでは、帳簿の保存のみで控除を受けられていたのですが、10月以...
-

2023.01.27 中小企業おすすめ情報
大企業と取引したい!プレゼンコンペに勝つコツ(前編)
大企業や行政機関などの大きな組織が物品・サービスを調達するとき、既存の取引先に限らず、新しい取引先候補に対しても提案や見積を募ることがあります。このような入札(総合評価方式)やプレゼンコンペに参加するチャンスを得たら、ぜひ受注を狙いたいですね。 大きな組織の調達活動には、大きな組織ならではの特徴があります。受注を狙うにあたっては、その特徴を理解したうえで臨みましょう。 大きな組織における調達の特徴 ~誰もが納得できる取引先選定~ 大きな組織から仕事を受注するには「担当者のお気に入りになればOK」というわけにはいきません。大きな組織では普通、誰かひとりの一存で大きいお金を動かすことが出来ないからです。「なぜその会社に発注するのか」を、担当者が課長・部長・役員・社長にそれぞれ説明して決裁を仰ぐ、等といった承認プロセスが存在します。 また、大きな組織には、意思決定プロセスをブラックボックスにせず社内外の関係者に説明する責任があります。つまり、その会社を選んだ根拠を説明する必要があるのです。例えば大企業では、株主から「取引先をどのように決めているのか」と問われれば説明します。行政組...
-

2023.01.25 中小企業おすすめ情報
経理処理を効率化! 法人カードのメリットや導入時の注意点を解説
クレジットカードには個人の一般消費者向けに発行されているカード以外にも、企業や個人事業主が事業のために利用できる「法人カード」があります。ここでは経理事務の削減や資金繰りにも役に立つ法人カードの特徴を解説していきます。 事業の経費を支払うためのクレジットカード 法人カードとは企業などの法人や、個人事業主に対して発行されるクレジットカードです。基本的には、法人の代表者や個人事業主がクレジットカードの発行企業に申し込みを行い、カードの契約者となることで利用できます。 法人カードは、主に事業に関する経費を支払う目的で使用され、個人向けカードより利用限度額が大きい傾向があります。加えて特徴的なのが、契約した代表者だけではなく、従業員が利用するためのカードも複数枚発行できる点です。 また、個人向けのクレジットカードとは異なり、代金の引き落とし先として、法人が名義人となる銀行口座(法人口座)を指定することもできます。これにより、多数の従業員が複数枚の法人カードで支払いを行ったとしても、支払い元を1つの法人口座とすることが可能なのです。 経費精算や会計処理の手間を減らせる 企業などの法人...









 トップ
トップ



![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)

