MENU


434件 121~140件を表示
-

2023.06.23 税務ニュース
ちっとも簡易じゃないけど簡易課税
エルメス製スーツ、50%引きでもまだ高い インボイス制度が導入されることにより従来消費税の申告は不要であった方でも、次回の確定申告期には消費税も申告する見込というケースがとても多くなっています。準備の早い方であれば、いわゆる2割特例があるから心配は要らないと考えていらっしゃるかも知れません。 しかし、2割特例は、時限立法であり令和9年に行なう確定申告までしか採用できません(図1)。では、その後はどうなるのでしょうか。順当に行きますと、現行の消費税の計算方法や申告方法に従うことになり、いわば独り立ちさせられることになります。 現在、消費税の計算方法には、一般課税(原則)と簡易課税があります。なかなかどうして、一般の方でもインボイス制度導入騒ぎのお陰で、何となく2種類あることまではご存じであることも多いです。ただ、簡易課税という名称から、「ちゃちゃっと申告できる」と思われがちですが、簡易課税は一般課税よりはマシですが全然簡易ではありません。エルメス製のスーツが50%引きになってもまだ高くて買えないというのと似たような話です。まぁ、一般課税がどれだけ面倒臭いんだ...
-
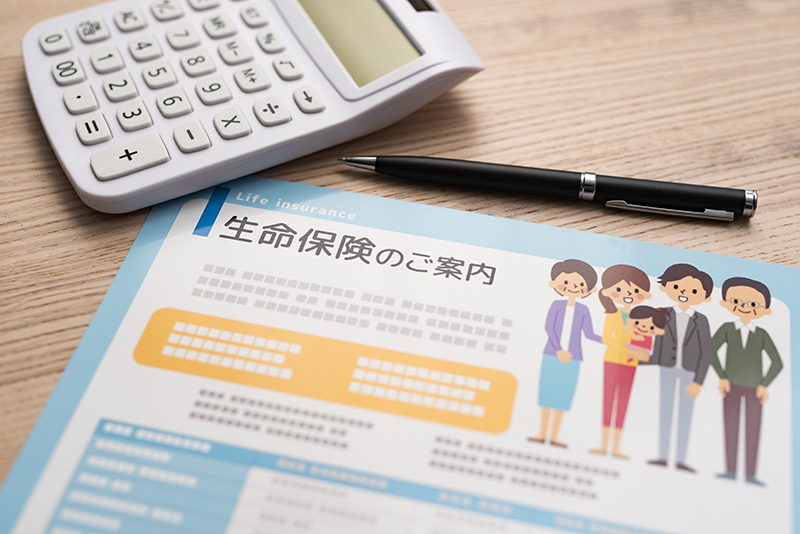
2023.06.16 税務ニュース
「生命保険」を積極的に活用して相続財産を守る!
2015(平成27)年、相続税の計算において基礎控除額の引き下げ・遺産取得金額2億円以上の相続税率引き上げなどの改正項目が施行されました。その結果、被相続人数(死亡者数)のうち相続税の申告をしなければならない人の割合(課税割合)は、改正前の2016(平成26)年分までは約4%(申告件数は約56千人)だったのが、2021(令和3年)分では9%以上(申告件数は約134千人)にまで推移し、実に2倍以上となっています。ちなみに2021(令和3)年分の被相続人1人あたり相続税の課税価格は13,835万円でした。 (国税庁「令和3年分 相続税の申告実績の概要」) このように相続税の課税水準は下がっており、「うちは相続税とは無縁」と高を括っていると、後に困った状況に追い込まれるケースが考えられます。たいていの場合、問題となるのは納税資金です。特に遺産のうちに不動産や換金価値の乏しい財産(自社株など)が多くを占める場合です。 (国税庁「令和3年分 相続税の申告実績の概要」) 早いうちから納税資金対策を! 将来的に相続税が課されるだろうと事前に想定できるのであれば、早いうちから手を打つ...
-

2023.06.14 税務ニュース
アフターコロナを乗り切るために、決算書+『説明資料』を作成しよう
コロナウイルスが5類に分類され、さぁこれからコロナ禍の損失を取り返そうという昨今でございますが、まだまだその爪痕は大きいのが実情ではないでしょうか? これから起業するにしても、体制を立て直すにしても、自社の状況を財務的(数値的に)に説明出来る事だけでなく、自社が今後更に良くなっていくよ!という期待感のあるメッセージを持って伝えられる説明資料が重要です。 事実、筆者が関与させて頂いている中小企業において、通常時は業種柄融資を受けにくいお客様や債務超過に陥っていた会社様が、今回ご紹介する説明資料の作成に取り組み、見事多額の融資を受ける事に成功して、コロナ禍においても大きく売り上げを伸ばす事が出来ました。 決算書だけではダメな理由 会社の財務状況を示す書類として、一般的には決算書の提出が求められます。 「単年度」の決算書を見ると、そこから分かる事は意外と少ない事に気づかされます。財務の数値というのは「比較」してみて初めて意味をもってくると考えられます。仮に黒字だったとしても、前期やコロナ前の「自社と比較」してどうなのか?「同業他社と比較」したらどうだろう?こういった比較概念を通...
-

2023.06.05 税務ニュース
いつから引かれる?どう計算する?個人住民税のしくみを解説
会社や個人に個人住民税の決定通知書が届く時期となりました。「6月から急激に手取りが減った。なんでだろう」「所得税より高い!」そう感じている人も多いのではないでしょうか。今回は、個人住民税のしくみを解説し、Q&Aで疑問にお答えします。 個人住民税とは?種類や納めるべき人、納付時期などを確認 最初に個人住民税の内容を確認しましょう。 住民税とは何か 住民税は、その地域に住所などを有する個人や法人に課される税金です。地域の行政サービスの費用としての性格を持ちます。法人に課する住民税が「法人住民税」、個人に課する住民税がこの記事でお伝えする「個人住民税」です。 住民税の種類 個人住民税は、都道府県民税と市町村民税があります。都道府県民税と市町村民税は次のように構成されています。 都道府県民税 均等割 所得割 利子割 配当割 株式等譲渡所得割 市町村民税 ※東京都の特別区(23区)を含む 均等割 所得割 個人住民税でよく出てくるのは「均等割」「所得割」です。均等割と所得割の内容は、次のようになっています。 種類 内...
-

2023.06.02 税務ニュース
【消費税の確定申告】第2回:「収入=課税」とは限らない?消費税がかかる取引の見分け方(その1)
第1回 「本則課税」「簡易課税」ってどんな計算をするの?基本を解説 第2回 「収入=課税」とは限らない?消費税がかかる取引の見分け方(その1) インボイスに登録して課税事業者になった人が来年悩むのは「消費税の確定申告」かと思います。消費税の計算は所得税と大きく異なるからです。今回は、消費税の計算の第一歩として必要な「消費税のかかる取引の見分け方」の1つ目をお伝えします。 消費税がかかる取引の見分けが大事な理由 「消費税の計算って、所得税や住民税とあまり変わらないんじゃない?」。 インボイスに登録して免税事業者から課税事業者になる方の中には、このように感じている方もいるかもしれません。しかし消費税のしくみは所得税・住民税と大きく異なります。 消費税がかかるのは「収入」「経費」の一部にすぎない 所得税・住民税の課税ベースは基本的に「収入-経費」で計算します。一方、消費税はそう単純ではありません。収入・経費について「どれに消費税がかかるか」を見分ける必要があります。なぜかと言うと、すべての収入と経費に消費税がかかっているわけではないからです。 「売り上げたら消費税がかかる」 「...
-
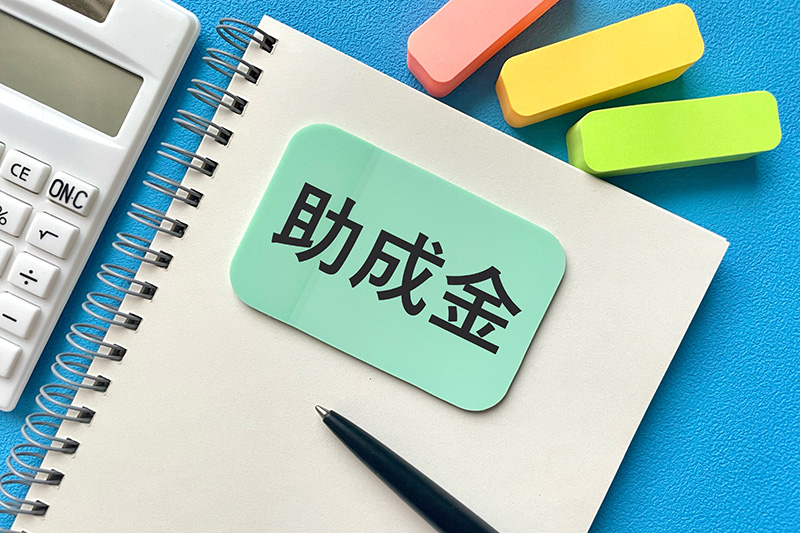
2023.05.31 税務ニュース
NPO法人が補助金や助成金を受給する際に気を付けたいポイント
NPO法人の資金調達方法の一つに補助金や助成金があります。受益者負担が成り立ちにくい領域で事業活動を行っているNPO法人にとっては、補助金や助成金が重要な財源となっている場合も少なくありません。そこで今回は、NPO法人が補助金等を受ける際の注意点などについて解説したいと思います。 補助金や助成金と法人税の取り扱い 補助金や助成金は事業活動から得られる収入ではないため、原則として収益事業には該当せず法人税は課税されません。ただし、収益事業の収入または経費を補填するために交付を受ける場合についても益金として認識します。 例えば、特定の事業を実施するために補助率を定めて経費の一定割合を支給するという補助金等があります。このような場合は、実施する事業が収益事業に該当する場合には法人税の課税対象となります。一方で、実施する事業が収益事業に該当しないのであれば、補助金に対しても課税はありません。 また、固定資産の取得や改良のために支給される補助金等は、その固定資産が収益事業に使われるものであっても益金不算入となり課税されません。この場合、収益事業の減価償却費は助成金等を控除しない実際の...
-

2023.05.29 税務ニュース
ネットビジネスの申告漏れに監視の目。副業YouTuberも知っておきたい税金のペナルティ。
インフルエンサーやYouTuberによる相次ぐ申告漏れのニュースが話題になっています。投げ銭や動画配信による収入があるにもかかわらず、申告しなかったり、期限に間に合わなかったりすると、ペナルティが課されてしまいます。 相次ぐネットビジネスの申告漏れに監視の目 2023年3月、美容系インフルエンサーの女性9人が税務調査を受け、6年間で合計約3億円の申告漏れを指摘されました。追徴税額は、合計で約8,500万円にのぼるとみられます。Instagramや動画投稿サイトの商品紹介で得た収入の一部を申告していなかったのです。 また、同じ月にYouTuberの事案も報じられました。投げ銭など約3,600万円のもうけが無申告であったため、約700万円を追徴課税されたのです。「申告が必要とは知らなかった」という主張でしたが、調査により他のYouTuberが投稿した税務調査対策の動画を観ていたことが発覚しました。意図的な無申告と認定され、重いペナルティが課されました。 このように、インフルエンサーやYouTuberとして活動している配信者が、国税局の税務調査を受け、申告漏れを指摘されるケースが...
-

2023.05.24 税務ニュース
取り敢えずの「期限内申告」という税理士法違反
「自主修正」をすれば大丈夫? 税務調査の結果、申告もれが見つかると、追徴される税額に上乗せで加算税というペナルティが課税されます。この加算税を削減する方法として、本稿でも取り上げた「自主修正」があります。税務調査が入る前に、ご自身で申告内容を見直して、誤りがあれば自主的に当初提出した申告書の内容を修正する申告が自主修正ですが、自主修正を行えば、税務署に手間をかけていないこともありますので、税務調査の予告がなされる前に行えば加算税が全額免除され、予告がなされた後でも一部減額されます。 このため、自主修正は非常に有用な制度であり、税務調査の予告があってからでも申告内容を見直して活用するべきものですが、さらに賢い使い方として、「取り敢えずの期限内申告」という申告を奨励する自称税務調査の専門家がいます。取り敢えずの期限内申告とは、適当な数字でもいいので、申告期限内に申告だけ行うことを意味します。 このような申告を奨励する理由として、申告期限に遅れた申告に対しては、税務調査が実施されるか否かに関係なく原則として「無申告加算税」という加算税が課されたり、場合によっては青色申告という税制上...
-

2023.05.23 税務ニュース
課税事業者はインボイスで何に気をつけるべき?免税事業者とのかかわりも解説
「インボイス制度で課税事業者が悩むことはない。登録すればいいだけだ」__そう思われがちです。しかし課税事業者にも2つ心配があります。1つはインボイスに登録した後の手続き、もう1つは免税事業者との取引の考え方です。 課税事業者がインボイスに登録した後の注意点 課税事業者がインボイス制度でうっかりしやすいのは「課税売上高が1000万円以下になったとき」です。次の3つは注意した方がいいでしょう。 1.1000万円以下になっただけでは免税になれない 今年の10月以降、課税売上高が1000万円以下になったときの扱いが変わります。従来と違い、自動的に免税事業者にはなれません。基準期間の課税売上高が1000万円を下回っても消費税の申告と納税は必要です。 理由は「インボイスの発行事業者に登録したままだから」です。インボイスの発行事業者の前提は「課税事業者であること」です。そのため「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しない限り、免税事業者に戻れません。 個人事業主の場合 ※この他、特定期間の課税売上高または給与等支払額が1000万円以下かどうかでも判定 2.100...
-

2023.05.22 税務ニュース
フリーランスがインボイスで損をしないために、今やるべきこと
(1)インボイスが始まると、なぜ、免税事業者は損なのか インボイス制度は、これまで消費税に縁のなかった免税事業者にもっとも影響を与えると言われます。確かにインボイス制度が、フリーランスにとって不利な改正なのは、否定できません。しかし税理士に依頼せず、自分で確定申告しているフリーランスも多く、ほとんどの方が消費税の仕組みには詳しくないと思われます。 そこでフリーランスの視点に立って、インボイス制度の基本といまフリーランスがやるべき事をお伝えします。 日本では、医療費など法律で定められた一部の取引を除いて、ほぼ全ての取引(=課税取引)に消費税が課税されます。消費税は、消費税を払った消費者ではなく、受け取った人(=納税義務者)が、申告し納税するのが特徴です。納税義務者は、受け取った消費税の全額ではなく、自分が支払った消費税を差し引いて納税します。払った消費税を差し引くことを仕入税額控除といいます。インボイスとは、自分が消費税を支払ったことを証明する書類なのです。 インボイス制度が始まる前は、商品を仕入れたり、交通費などの費用を払ったときは、領収書や請求書に記載がなくても、支払った...
-

2023.05.19 税務ニュース
【消費税の確定申告】第1回:「本則課税」「簡易課税」ってどんな計算をするの?基本を解説
2023年10月のインボイス制度以後、心配なのは消費税の確定申告です。9月末まで免税事業者の方は、どう計算したらいいのかに戸惑うかもしれません。今回から消費税の確定申告の知識を少しずつお伝えします。第1回目は消費税の納税額の計算方法です。 第1回 「本則課税」「簡易課税」ってどんな計算をするの?基本を解説 第2回 「収入=課税」とは限らない?消費税がかかる取引の見分け方(その1) 消費税の計算方法は本来「本則課税」「簡易課税」の2つ インボイスで注目されているのは「2割特例」という消費税の計算方法です。インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった事業者向けの制度で、預かった消費税の2割を納めればいいとされています。 【参考】インボイス「2割特例」とは?どれくらい節税できる?注意点も解説 ただ、これは2023年度税制改正で初めて設けられた特例です。2026年9月30日の日を含む課税期間までしか使えませんし、使える事業者もかなり限られています。一時的な措置に過ぎません。 本来、消費税の計算方法は「本則課税」「簡易課税」の2つです。本則課税はどの事業者でも使えます。一...
-

2023.05.16 税務ニュース
副業、フリーランスのための確定申告の賢いやり方
税理士ではなくとも個人の確定申告の申告期限である3月15日は、なんとなく気が重くなる日として認識されているでしょう。現実的にはサラリーマンが確定申告する場面としては医療費控除と住宅ローン控除一年目などのケースが多く、確定申告する人は限られた人というイメージです。 しかし、最近は自社の社員について副業を認める会社も増えており、副業の収入をどのように申告するのかが問題になることもあります。また、そもそも会社を辞めてフリーランスとして自由な立場で働く人も増えており、そのような立場の人であれば3月15日はとてつもなくプレッシャーがかかる日ともいえるでしょう。 なぜなら、いうまでもなくそれらの人々は申告期限までに申告書を所轄税務署に提出し、納税を行わなければならないためです。今回の記事はこうした副業、フリーランスのための確定申告の賢いやり方についてご紹介していきます。 帳簿の整備こそが最大の節税? 副業やフリーランスの方が税務申告を行う上で、最初に意識していただきたいのは「帳簿をしっかりとつけ、取引を確実に記録する」ということです。「帳簿をつければ節税できるの?」という疑問の声も聞こ...
-

2023.05.10 税務ニュース
あなたの会社での経費精算の方法、インボイス対応している?
令和5年10月1日からインボイス制度がいよいよ開始されます。事業者の皆様においては、適格請求書発行事業者の登録申請、請求書等の発行業務、受領したインボイスの取り扱い、インボイス制度への対応を着々と進めていること思われます。 インボイス制度が始まると、事業者が仕入税額控除を受けるにはインボイスの保存が必要になります。そして、それは経費精算の場においても同様です。従業員から経費精算の申請があった際には、支払金額や目的だけでなく、その領収証等がインボイスの要件を充たしているものかを確認する必要があります。 仕入税額控除の要件 インボイス制度開始以後において、仕入税額控除を受けるには、「一定の事項」が記載されたインボイスの保存が要件となります。 「一定の事項」は下記の通りです。 ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 ② 課税資産の譲渡等を行った年月日 ③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨) ④ 税率ごとに区分した課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額の合計額及び適用...
-

2023.05.02 税務ニュース
「投げ銭」はファンからの贈り物?「投げ銭」に関する税金の取扱いを解説。
ネット配信者が多額の「投げ銭」を得るケースが急増する一方で、「投げ銭」を含む動画配信収入を申告しない配信者に税務調査が入るケースが相次いでいます。YouTubeのスーパーチャット(スパチャ)に代表されるオンラインの「投げ銭」を得た場合には、税金の種類などを状況・目的により判断しますが、基本的には申告が必要です。 「投げ銭」とは? コロナ禍の影響でライブ活動ができないアーティストなどが、ネット上でライブ配信を行い、多額のオンライン「投げ銭」を得るケースが増えています。 オンライン「投げ銭」とは、映像・音楽・記事・イラストなど、アーティストやクリエイターがネット上で公開しているコンテンツに対して、視聴者やファンがオンラインで送金することをいいます。「投げ銭」というと、街頭やステージで活動するアーティストに対する「おひねり」をイメージする人も多いかもしれませんが、ネット上で活動するYouTuberやイラストレーターなどに対しても行われています。 また、「投げ銭」は金銭だけでなく、プラットフォームサービス内で流通する独自のポイントやアイテムで行われる場合もあります。暗号資産に関する...
-

2023.04.28 税務ニュース
<経費精算カフェ店長が解説>経費についてスッキリ解説!
みなさま、こんにちは。税理士の脇田です。2022年9月から、月末の2日間だけ「経費精算カフェ」店長をしております。2023年の3月には、スペシャル版「確定申告カフェ」を開催し、1月2月の経費精算カフェと合わせて満員御礼でした。 今回は、「経費精算カフェ」「確定申告カフェ」で多かった質問を中心に、経費について解説していきます! 「経費精算カフェ」ってなに? 経費精算カフェとは、高円寺にあるカフェで、毎月、月末の2日間(1日4時間)だけオープンします。 事前予約が必要で、ルールは3つ。 「経費精算」を目的とした方しか入店できません 入店時に店長に「経費精算」の目標を宣言します たてた「目標」が終わるまで退店できません。 ※経費精算とは、経費を帳簿につけたり、領収書の整理をしたりすること。 経費精算カフェでは、ScanSnap(スキャナー)利用可能、ホットドリンク飲み放題、全席電源コンセント/USB高速充電器つき、Wi-Fiも入り、マウスや電源アダプター無料レンタル…などなどサービスが充実しています。 なにより、自宅で一人でやるより、他の...
-

2023.04.26 税務ニュース
これからの会計事務所に求められる顧客管理の方法とは?
はじめに 会計事務所の顧客である中小企業の経営は厳しい状態です。後継者不足や経済状況の悪化などは彼らの経営をより困難にし、会計事務所にとっても顧客数を減らし、顧問報酬を低下させることに繫がります。さらに、企業数の減少は会計事務所同士の競争激化をも引き起こします。 つまり、会計事務所は、今後一層厳しくなる社会環境の中で、生存と発展のために悪戦苦闘しなければならないことになります。そのような状況下で、各事務所は様々な戦略を立案・実行することになると思いますが、どのような計画においても重要になる経営管理の代表格が、今回取り上げる「顧客管理」です。 顧客管理とは、自社が管理するすべての情報を”顧客” という軸で収集・保存・活用するすべてのプロセスを指します。顧客管理の対象となる情報は、顧客の住所や代表者名といったものだけでなく、「どんな接点で面識を持ち、どういう提案のもと見積書を提示し、どんな契約を締結したのか、そして、どのような業務の予定があり、または実行し、請求・決済に至っているのか」という一連のものです。 これらの顧客管理によって得られる情報は、「顧客が何を望んでいて、何で困...
-

2023.04.24 税務ニュース
税務調査にもいろいろな種類が!反面調査・現物確認調査・無予告調査
税務調査にはいろいろと種類があります。一般的に考えられている税務調査は、予め税務調査の日程の通知があり、その通知をされた納税者に対し、納税者の経理資料などをチェックするものと思われますが、税務署が行う税務調査はこれだけではありません。 税務調査先の取引先を調査する「反面調査」 まず、反面調査と言われる調査があります。これは、本丸である税務調査先の取引先を調査するものを言います。税務調査先である納税者の取引をチェックしている時、現金で数千万の支出をしているなど、怪しい経費が見つかったとします。この経費は本当に税務上認められる経費なのか、税務調査先を調べてもよくわからない場合、事実関係を確認するためにその取引先を税務調査する権限が税務署には与えられています。 取引先を調査すれば、事実関係の確認がスムーズにできます。税務調査は脱税などを防止するために行われるものですから、このような権限が国税調査官には与えられているのです。税務調査においては、調査先が活用している銀行を調査することもありますが、これも反面調査の権限で行われています。 反面、取引先を調査されると迷惑がかかるため、何と...
-

2023.04.21 税務ニュース
【最新消費税】インボイス制度で注目!消費税の簡易課税とは?2割特例との関係、注意点を解説
個人事業主の方は確定申告が終わりほっと一息、3月決算の方はこれから決算と申告ですね。日常業務もありますが、本年10月からはいよいよ適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。これに伴い、新規開業や新設法人など従来の制度では免税事業者であった事業者の方々も、インボイスを発行するために課税事業者になるケースも多いようです。そうしたインボイス制度を機に課税事業者になる免税事業者向けに、令和5年度税制改正で特例措置が設けられました。 そこで、簡易課税と特例措置を中心に最新の消費税のポイントを解説します。選択する方法により、消費税の納税額が大きく変わることもあるため、慎重な検討を行いましょう。 (1)納付する消費税の計算方法 納める消費税は、課税売上げに係る消費税額(売上税額)から課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額)を差し引いて計算します。売上税額から課税仕入れ等に係る消費税額を差し引くことを仕入税額控除といい、2023(令和5)年10月1日のインボイス制度開始以後は、原則課税により消費税の計算を行う場合、原則としてインボイスの保存がなければ仕入税額控除ができなくなります(※...
-

2023.04.18 税務ニュース
役員給与の扱いは?「定期同額給与」について正しく理解する
中小企業のオーナー様は株主であると同時に、その会社の代表取締役として就任されるケースがほとんどではないでしょうか。その際に、会社から代表取締役個人に対して支払われる給与が役員給与(役員報酬)です。役員給与は従業員に対して支払われる給与とは異なるものとして、税法上の規定が設けられております。今回はその中でも多く扱われる「定期同額給与」についてお伝えさせていただきます。 役員給与は原則損金不算入 役員給与については法人税法第34条の定めにより、原則損金不算入として扱うこととされております。会社法施行前は原則損金算入であったものが原則損金不算入と改正されたことは、大変影響の大きい改正でした。まずは、役員給与は原則損金不算入であるということを正しく把握しておきましょう。 別段の定めにより3形態に限り損金算入できる それでは役員給与を損金算入していないかというと、ほとんどの企業においては損金算入されていると思います。これは誤りではなく、限定された3形態に限り法人税法では損金算入を認めております。それが「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3形態です。今回はこの中の「定期同...
-

2023.04.17 税務ニュース
令和5年度税制改正でどう変わる?贈与と生前対策①
愛とお金 愛を形に残すことはとても難しいです。 日本人の性格上、愛を言葉に表すことも苦手な人が多いのではないでしょうか? 愛を表現する形は色々ありますが、税理士という職業柄、愛をお金で表す場面に遭遇することはしばしばあります。代表的なものとしては、「奥様に愛の証として指輪を贈る」、というものがあります。大変無粋な話ですが、税理士的な目線から見ると、この指輪に贈与税が課税されるのか、が気になってしまうところです。世の中には様々な職業の人がいますが、お金に関する職業に就いている人はどうしても貨幣価値に換算して物事を考える癖がついてしまっているものです。 貨幣価値に置き換えると、物事の大小は客観的な“数字”に置きかえて考えることができ、理解しやすい面はあります。もちろん、金額の大小だけで物事のすべてを判断できると考えている人はいないと思いますが、金額に換算すると単純化することができるのも事実です。 110万円という壁 話を戻しましょう。 「指輪に贈与税がかかるのか」という問いです。問いに対する回答は、ほとんどが“いいえ”ですが、理論上、まれに“はい”というケースが...









 トップ
トップ



![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)

