MENU


434件 21~40件を表示
-
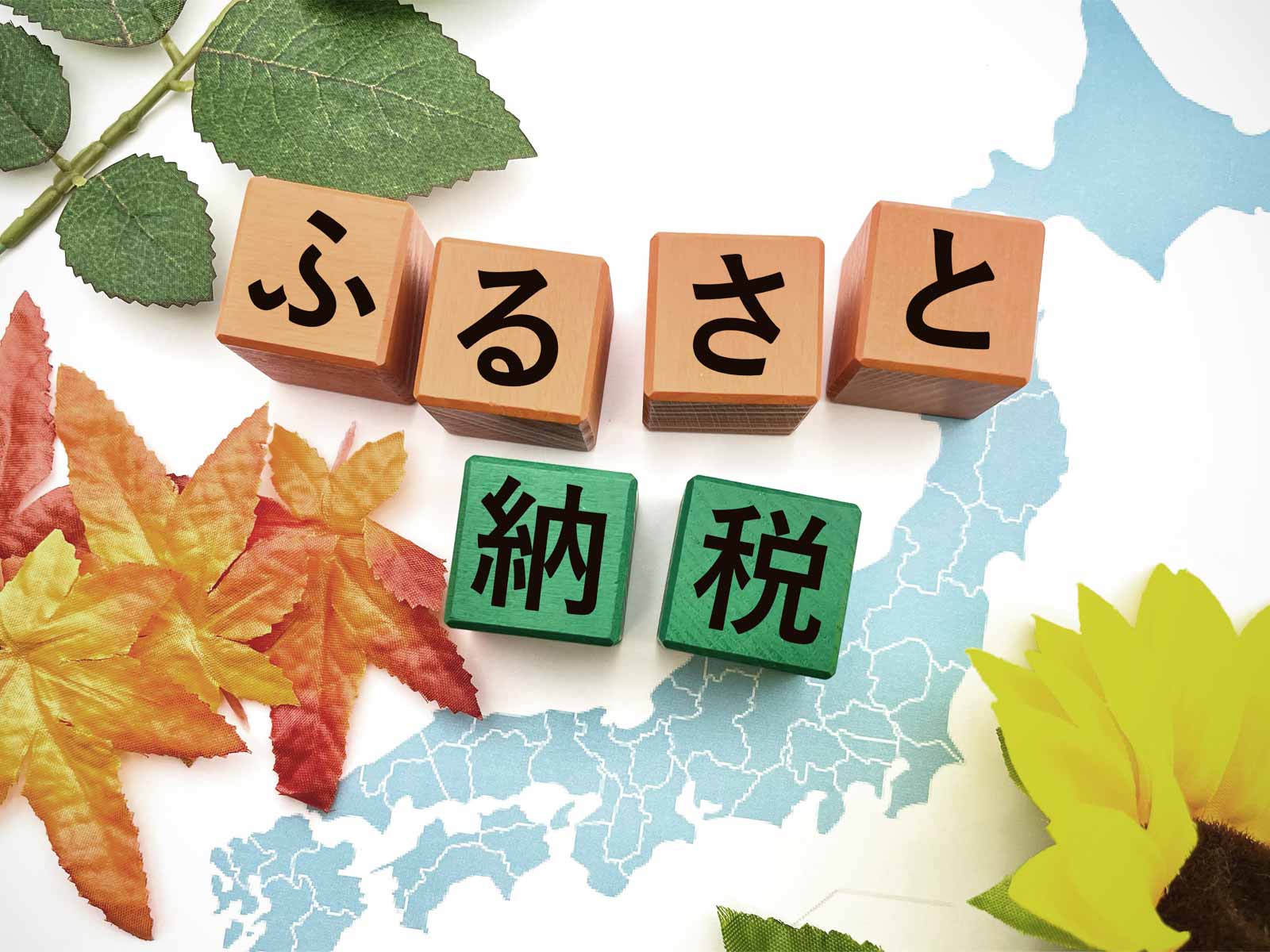
2024.09.26 税務ニュース
ふるさと納税を活用してNPO法人が収入を多角化する方法
近年、ふるさと納税に対する関心が高まっており、年々寄付額が増加しています。2015年度では受入件数が726万件で受入額が1652億円だったものが、2023年度には受入件数が5894万件で受入額が1兆1175億円となり初めて1兆円を突破しました。(図表1) 図表1:ふるさと納税の受入額及び受入件数 (出展:総務省自治税務局市町村税課「ふるさと納税に関する現況調査結果」より筆者作成) ふるさと納税の拡大により、ふるさと納税が重要な財源の一つになっている自治体もあります。また、ふるさと納税の返礼品に採用されることで、大きく売り上げを伸ばす事業者も存在します。NPO法人が取り扱う商品やサービスでもふるさと納税の返礼品に採用されている例もあり、収入増加の一つの選択肢として検討する価値があるでしょう。 ふるさと納税の新たな動きと具体例 最近のふるさと納税の動向として、無形の返礼品の増加が挙げられます。例えば、新潟県湯沢町はフジロックフェスティバルの入場券を返礼品の一つにしています。このようにイベント等の入場券を返礼品にすることで、地域に人を呼び込み、食事や宿泊などへの波及効果などが期待さ...
-
![個人事業主も活用したいクラウドファンディングのしくみと税金[第3回]:購入型クラウドファンディングに係る税金②](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-134.jpg)
2024.09.24 税務ニュース
個人事業主も活用したいクラウドファンディングのしくみと税金[第3回]:購入型クラウドファンディングに係る税金②
近年、フリーランスや個人事業主も活用できる資金調達手段として注目されているクラウドファンディング。何回かの連載で、フリーランスや個人事業主が知っておきたいクラウドファンディングのしくみと税金について解説します。第3回では、購入型クラウドファンディングを実施するうえで知っておきたい節税対策や必要経費にスポットをあててみましょう。 購入型クラウドファンディングに係る税金 購入型クラウドファンディングで集めた資金に対しては、資金調達者が事業者であれば事業所得、それ以外の場合には雑所得として、所得税および住民税が課税されます。 購入型クラウドファンディングにおいては、「資金調達者を支援する」というかたちをとっているため「支援」や「応援」といった言葉が使われていますが、その実態は事業者が行う通常の売買取引と同じです。資金調達者はリターンという名目で商品やサービスを提供し、資金提供者は支援金という名目でその対価を支払っているにすぎません。そのため、資金調達者が事業を営んでいる場合、資金調達者が資金提供者から受け取った資金は、事業所得として所得税および住民税の課税対象となるのです。 なお...
-

2024.09.17 税務ニュース
法人成りとは?個人事業主が自分で手続きするときの流れを解説②税務・労務の届出・申請
登場人物 よっちゃん(以下「よ」):まゆこの夫。行政書士。仕事はできるが税金はくわしくない。特技は料理と釣り。夢は釣り三昧の日々。 まゆこ(以下「ま」):税理士・税務ライター。「こむずかしい税金をいかに分かりやすく表現するか」ばかり考えている。趣味は、よっちゃんのごはんを食べること。 「そろそろ法人成りしたい」。そんな風に感じるタイミングが個人事業主に訪れることがあります。個人事業主として行ってきた業務を法人に移す「法人成り」はどんな手続きが必要なのでしょうか。2回にわたって解説します。2回目の今回は税務・労務の手続きと注意点です。 登記したら税務・労務の手続きが必要…なぜ? よ「個人の事業を法人化したら、税務や労務の手続きも必要になるよね」 ま「そうなの」 よ「あらためて考えると面倒くさいよね。会社作って終わったら、そこで終わりにしてほしい」 ま「そうねぇ。でも会社も人間と同じく、経済活動をすればいろいろ社会的な責任が生じるから必要なのよ」 よ「?」 ま「ちょっと聞くけど、会社の経済活動にはどんなものがあると思う?」 よ「こんな感じかなぁ」 ま「こう...
-

2024.09.11 税務ニュース
【インボイス】登録したけどやめたい…どうしたらいい?個人事業主向けに手続きと注意点を解説
「インボイス、登録したけど消費税が重いから止めたい」そんな声を聞くようになりました。インボイス登録をやめるとき、どんな手続きをいつまでにしたらいいのでしょうか。今回は、手続きと注意点を個人事業主向けに解説します。 インボイスが必要な事業主、なくてもいい事業主 「インボイスに登録してたけれど、なくても困らない」と感じた事業主がいるかと思います。事実、インボイス登録が必要かどうかは、取引先次第です。次のように分かれます。 BtoBで大企業相手 デザイナーやライターなど、大企業から受注する事業主の多くは、インボイス登録をした方が無難です。大企業は原則課税で消費税の納税額を計算しています。原則課税だと、インボイスがないと仕入税額控除できません。つまり仮払いした消費税相当額分、損をするのです。 引用元:【インボイス制度】領収書はどう書くべき?手書きもOK?個人の飲食店・小売店に解説 昨年10月前後、得意先の大企業から登録をお願いされるケースが多数ありました。「登録しないなら10%分、取引額を下げてほしい」と交渉された人もいたかと思われます。 BtoBで中小規模の事業者相手 ビジネス客...
-

2024.08.13 税務ニュース
消費税にも関わる!土地と建物の譲渡対価の按分
一括譲渡した土地と建物の区分 実務上、所有する不動産について、土地と建物を一括で譲渡することはよくありますが、その契約書に土地と建物の譲渡金額の内訳が明記されていない場合、税務上は適正に土地と建物の取得価額に区分する必要があるとされています。なぜなら、建物には消費税が課税される反面、土地には課税されませんし、購入する側からすれば建物の取得価額は減価償却という形で経費にすることができる反面、土地は経費にすることができないなど、土地と建物で税務処理が大きく異なるからです。 原則として固定資産税評価額で按分 税務上は時価課税の原則がありますので、このようなケースは、土地と建物の時価を算定した上で、その時価の比で按分するのが原則です。時価と言っても、不動産鑑定士が評価した金額や相続税評価額を割り返した金額などいろいろな時価が考えられます。しかし、この土地と建物の一括譲渡に関しては、過去の判例上は固定資産税評価額で按分するのが妥当とされるケースが多いです。 この理由は、固定資産税評価額は地方公共団体が公開するもので信頼性が高いだけでなく、同一の地方公共団体が公表するものですので算定根拠が...
-

2024.08.09 税務ニュース
賃上げ促進税制とは?2024年度(令和6年度)版の全体像と中小企業向け繰越控除、注意点を解説
2024年度(令和6年度)税制改正で賃上げ促進税制が変わりました。「2024年度版賃上げ促進税制」です。新年度版は控除額などが拡充されましたが、注意すべき点もあります。2024年度版賃上げ促進税制の全体像と中小企業向け特典の繰越控除、注意点を解説します。 賃上げ促進税制とは何か?経緯を確認 賃上げ促進税制とは、企業が従業員の給与等の額を増加した場合に、増加額の一部を法人税額や所得税額から差し引く制度です。従業員の給与の増加額の一部を企業所得の課税額から控除するしくみは、2013年4月から始まりました。 「所得拡大促進税制」「人材確保等促進税制」と名を変えて、現在に至っています。 当初は「要件が厳しすぎて使いづらい」と言われていましたが、徐々に条件が緩和。税額控除割合の引き上げなどで賃上げのインセンティブも高まりました。その結果、現在、多くの企業が活用しています。 しかしそれでも「赤字企業は活用できない」などの欠点がありました。2024年度版賃上げ促進税制は、こういった点も配慮されたものとなっています。 2024年度(令和6年度)賃上げ促進税制の全体像 ここで2024年度版賃...
-
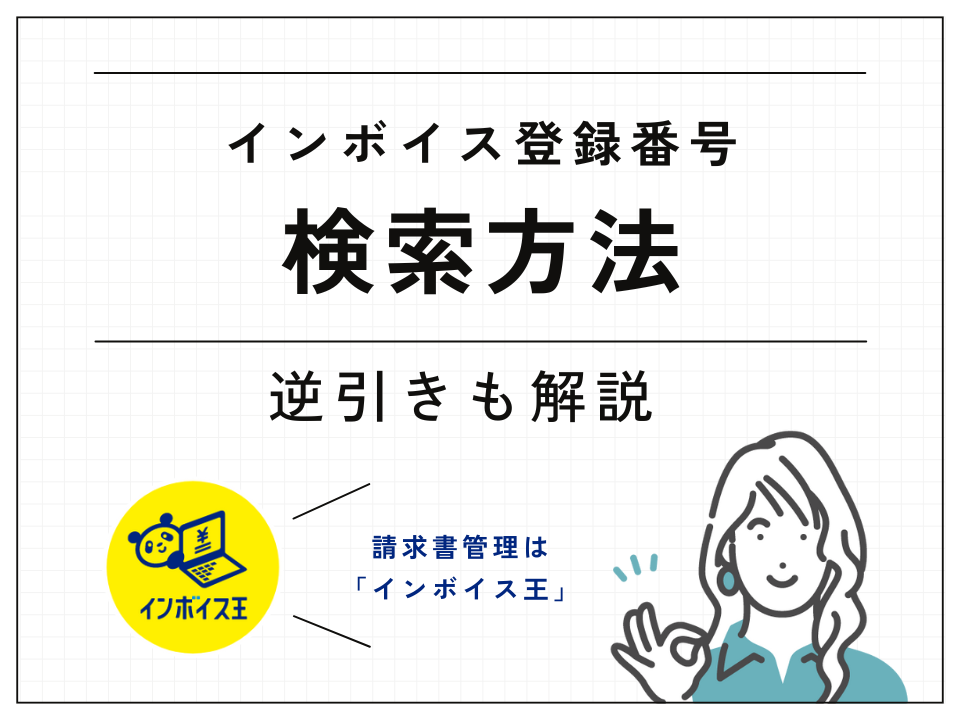
2024.08.08 税務ニュース
インボイス制度の登録番号を検索&確認する方法を解説|逆引きも
今回は、インボイス登録番号の確認方法を解説します。 インボイス制度の概要も含めて分かりやすく解説しているので、本制度についてよく分からないという人にもおすすめの記事です。 ソリマチ株式会社が手掛ける請求書発行サービス「インボイス王」も紹介しているので、ぜひご覧ください! インボイス制度の登録番号を効率的に管理するなら「インボイス王」 ソリマチ株式会社が提供する「インボイス王」は、インボイス制度に対応した請求書(適格請求書)をかんたんに発行・受領できるツールです。 インボイス王でできること ・請求書月10枚までの発行であれば無料で利用可能! ・年間5,500円で適格請求書が無制限で作成可能! ・項目が自動で取り込まれるOCR機能対応 ・取引先の情報は検索して簡単に登録・管理! ・ソリマチ製品「会計王」との連携で自動仕分化 インボイス王は取引先の登録番号もラクラク管理ができます。 一度登録した取引先の法人番号はインボイス王で確認ができ、法人ごとにまとめて請求書の管理も簡単です。。 また「インボイス王」は、月10枚までならインボイス制度対応の請求...
-

2024.07.30 税務ニュース
相続税対策の前に…贈与税のしくみと生前贈与のメリット・デメリット、考えるときのポイントを確認
「年110万円以下で贈与をすれば、贈与税がかからずに相続税対策ができる」という一言をよく目にします。確かに生前贈与は将来の相続税を減らす効果がありますが、贈与税を正しく知らないとかえって損をするかもしれません。今回は、生前贈与を考えている方向けに、現在の贈与税のしくみと生前贈与のメリット・デメリット、生前贈与を考えるときのポイントをお伝えします。 贈与税の制度には2つある 現在、贈与税の制度は2つあります。いずれも「毎年1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額がいくらか」で申告・納税の要不要を考えていくのが基本スタイルです。 暦年課税制度 「1年間にもらった財産の合計額はいくらなのか」で贈与税の額が決まる制度です。財産をもらった側が申告・納税をしなくてはなりません。相続時精算課税選択届出書を提出していなければ、暦年課税制度で計算することになります。ただし、申告・納税が必要となるのは1年間にもらった財産の額が110万円を超えてからです。 なお、財産をあげた側・もらった側の年齢や関係によって、税額計算で使う税率や控除額が変わります。 特例贈与財産 一部の親子間、...
-

2024.07.29 税務ニュース
インボイス制度導入後のNPO法人の動向は?
2023年10月1日から適格請求書保存方式(インボイス制度)がスタートし、適格請求書発行事業者の登録を行ったNPO法人も多いと思います。しかし、経理の現場では混乱も少なくなく、スムーズな船出とは言えない状況です。今回はインボイス登録を行なった団体と行わなかった団体の事例をそれぞれ紹介し、現場にどのような影響があり、今後検討が必要であろうと思われる事項について解説します。 インボイス登録を行なった事業者 まず、就労継続支援B型作業所を運営するNPO法人がインボイス登録を実施した事例をご紹介します。このNPO法人では、一般企業からの軽作業などを請け負っており、取引先との間において消費税負担の問題が生じることとなりました。このNPO法人では、取引先との協議などを経てインボイス登録することとなりました。インボイス制度導入前から作業の単価に変動はないためNPO法人の負担が増えますが、想定される税負担を試算し、納税資金を確保できるよう準備しています。 インボイス登録を行わなかった事業者 障害福祉サービスを行うNPO法人でもインボイス登録をしていないケースがあります。この団体は自立訓練を中心...
-
![子どもと話したいお金と税金のはなし[第4回]:環境と税金のはなし。森林環境税を知っていますか?](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-157.jpg)
2024.07.26 おんすけと学ぶ税務情報
子どもと話したいお金と税金のはなし[第4回]:環境と税金のはなし。森林環境税を知っていますか?
大人になるために避けてとおれない、けれど難しいお金や税金のこと。本コラムでは、経営者や経理担当者のみなさんがお子さんとお話をするきっかけになるように、お金と税金のトピックについて、身近な事例を取り上げて解説します。 森林環境税という新しい税を知っていますか? 実はすでに、令和6年度から1人1,000円が住民税に上乗せされるかたちで徴収されています。 第4回では、この森林環境税を中心に、環境と税金の関係にスポットを当ててみましょう。 森林環境税を知っていますか? 令和6年度から森林環境税という新しい税がスタートしているのを知っていますか? 森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課される国税です。国内の森林整備などを目的に、住民税に上乗せされる形で徴収されます。 近年、地球温暖化、大気汚染、水質保全などの環境問題が話題にあがりますが、この対策の一つとして世界的に議論が重ねられているのが「環境税」という税金です。 前述の森林環境税は、名前からすると「環境税」の一種のようにもみえますが、森林環境税とはいったいどのような税金なのでしょう? 環...
-

2024.07.24 税務ニュース
【しっかり理解!ふるさと納税】確定申告とワンストップ特例の違い、実際トクした税金の確認方法
1.ふるさと納税とは? ふるさと納税は、納税という名称ですが実際は都道府県や市区町村への「寄附」です。 ご自身の選んだ自治体に寄附をすると、原則として確定申告(※)をすることで、所得税、住民税から一定額までの控除を受けることができます。 ※条件に該当する場合は、後述のふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できます。 2.ふるさと納税ではいくらトクする? ふるさと納税をした場合、上限の範囲内であれば、寄付した額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます。上限額は、収入や家族構成等に応じて異なります。 例えば、年収700万円の会社員(給与収入のみ)で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分28,000円が所得税と住民税から控除されます。 (試算例と図は、総務省ウェブサイト「ふるさと納税ポータルサイト」より) このケースでは30,000円のふるさと納税によって 28,000円の税金が安くなる ふるさと納税の返礼品をもらえる ことになります。つまり、上限の範囲内の寄附であれ...
-

2024.07.22 税務ニュース
【定額減税】調整給付とは?給付の条件や計算のしくみ、注意点を解説
定額減税の話題で注目されているのが「調整給付」です。給与や年金の源泉徴収税額などから減税しきれないときにもらえるお金のことを言います。どのように計算するのでしょうか。今回は、調整給付の条件や注意点も解説します。 調整給付とは 調整給付とは、定額減税をしてもしきれなかった人に対する給付金です。定額減税とは、所得税・住民税から一定額を控除する制度のことを言います。2024年度(令和6年度)税制改正で設けられました。 【参考】「定額減税」って何?2024年6月からの源泉徴収と年末調整はどうすべき?① 定額減税される金額は、次の通りです。 所得税は2024年分の所得税から、住民税は2024年度分の住民税の所得割額から控除されます。控除されるタイミングは、次のようになっています。 1回目の源泉徴収や予定納税で減税しきれなければ、2回目以降の支給時の源泉徴収や予定納税で減税されます。 引用元:公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税|日本年金機構 それでも年内の所得税や年度内の住民税所得割額から定額減税分を控除しきれないことがあります。所得額が少なく、課税額が低いケース...
-

2024.07.18 税務ニュース
仮装・隠蔽と税務調査における7年遡及
税務調査が行われ、誤りや不正が見つかるとほとんどの場合修正申告をすることになります。反対に、誤りや不正がなければ是認、軽微であれば指導に留められ、修正申告は必要ありません。 修正申告をして新たに納めるべき税金が発生すれば、その本税だけでなく、過少申告加算税や重加算税といった罰金のような税が賦課され、利息として延滞税も発生します。 税務調査による本税の増加が単なる誤りであれば過少申告加算税、仮装・隠蔽に基づくものであれば重加算税の対象となり、税務調査を担当する税務職員は重加算税をより重視しているため、調査中は必至に不正を発見しようとします。 ここでの「不正」とはほとんどの場合「仮装・隠蔽」と同義です。実務上もその違いはほとんど意識されません。 仮装・隠蔽とは その前に、仮装・隠蔽について書かれた国税通則法68条を見てみましょう。 第六十八条 「(前略)納税者が・・・事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは・・・過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重...
-

2024.07.10 税務ニュース
【免税店(輸出物品販売場)とは?消費税が免税になる条件と手続き、不正のパターンを解説】
免税店(輸出物品販売場)での不正のニュースが増えています。そもそも免税店とは何でしょうか。なぜ外国人の消費税が免税されるのでしょうか。不正防止に向けた2024年度(令和6年度)税制改正についても解説します。 免税店(輸出物品販売場)とは何か 免税店とは、外国人旅行者など非居住者に対して商品を販売する際、消費税を免除して売ることのできる店舗のことです。消費税法では「輸出物品販売場」と言います。「Tax Free」「免税」を掲げるお店だと、外国人旅行者は消費税0円で商品を買えるのです。 なぜ免税になるのか なぜ外国人旅行者等が購入すると消費税が免税になるのでしょうか。それは最終消費地が国外だからです。 日本の消費税は「最終的に日本で消費されるモノ・サービス」にかかります。国外で消費されるものは「輸出免税」とされ、消費税が免除されるのです。 【消費税の確定申告】第3回:「収入=課税」とは限らない?消費税がかかる取引の見分け方(その2) 外国人旅行客が買った物も同じです。日本国内ではなく最終的に国外で消費されることが前提なので、日本国内での消費税は免除されるのです。 輸出...
-

2024.06.21 税務ニュース
役員退職金と税務調査
役員退職金と税務調査 税務調査において、問題になる項目のひとつに役員退職金があります。役員退職金は適正額の範囲内という制限はあるものの、その金額はかなり大きく計算されるため、他の費用にして大きな金額が経費として認められます。このため、役員退職金は法人税の節税で非常に重要になる訳ですが、税務署もその分厳しく内容をチェックします。 役員退職金については、その適正額と、退職の事実があるか、この2点が問題になります。 役員退職金の適正額 経費と認められる役員退職金の適正額は、平均功績倍率法という方法で計算されることが通例です。これは、①退職時の最終の役員報酬月額、②勤続年数、③その役員の役職に応じた平均功績倍率、の3つを乗じた金額を適正額とする方法です。例えば、平均功績倍率が概ね3.0とされる代表取締役が退職した場合、その勤続年数が20年で最終報酬月額が100万なら、6000万(=100万×20年×3.0)と算定されます。 この方法で誤解が大きいのは、役員賞与を支給している場合の取扱いです。例えば、退職する事業年度の役員の月額報酬が5万、賞与が1200万とした場合、一か月あたりの支給...
-

2024.06.18 税務ニュース
IT導入補助金とは?2024年度の特徴、流れ、用語の意義を解説
ここ最近、IT導入補助金の話題をよく目にします。コロナを境に急増したリモートワーク、インボイス制度や改正電子帳簿保存法の開始に伴い、新たにIT機器の導入を検討する事業主が増えていることが背景にあるようです。そして、制度も年々少しずつ変わってきています。今回、2024年におけるIT導入補助金の制度概要についてお伝えします。 IT導入補助金とは何か IT導入補助金とは、業務効率化やDX(デジタルトランスフォーメーション)につながるITツールの導入を支援するための補助金です。経済産業省が主体となって、中小企業や小規模事業者の生産性の向上を目的に毎年公募されています。2017年からスタートし、2024年で8回目となりました。 新型コロナウイルス感染症がまん延した時期は、テレワーク環境整備などのための特別枠が設けられました。最近は、2023年10月開始のインボイス制度対応の枠などがあります。 「融資と違って返済の必要がない」「同一年度内は何度でも応募できる」といった利点から、毎年多数の企業が応募しています。 2024年度IT導入補助金の特徴 2024年度のIT導入補助金には、次のよう...
-

2024.06.17 税務ニュース
【インボイス】古物商特例の誤解2選!古物商の免許があればメルカリでも仕入税額控除できる?買取でインボイスはNG?
2023年10月からインボイス制度が始まりました。これに伴い「古物商の免許さえあればオンラインのフリマ(フリーマーケット)でも仮払した消費税相当額を控除できる」「インボイスがあると仕入税額控除はできない」という誤解があるようです。今回は、この2つの誤解を、古物商特例の内容と照らし合わせながら解いていきます。 古物商特例とは何か 古物商特例とは、インボイス制度下での仕入税額控除の特例の一つです。 インボイス制度が始まった今、本則課税(原則課税・一般課税)の課税事業者は、インボイス(適格請求書)が必要です。インボイスがないと、「仕入税額控除」という「仮払した消費税相当額を納税額の計算上、差し引く」ことができません。 しかし現実には、インボイスをもらうことが難しい事業を営む課税事業者もいます。次のような業種です。 古物商 質屋 中古の住宅や車の販売 こういった業種の仕入先の多くは個人であるため、インボイスをもらうことは不可能です。結果、仕入税額控除を受けられず、他の業種に比べて不利になります。彼らが不利にならないようにするには、インボイスがなくても控除できるよ...
-

2024.06.10 税務ニュース
事業主に記帳や申告の知識はどこまで必要か
はじめに 近年、副業も含めると、かなり多くの方が事業を始めていらっしゃいます。開業を志す方は、営業の方法や収入を増やす方法については十分に検討され、ある程度の道筋を想定していらっしゃる一方で、経理や確定申告の準備は不十分であることが多いです。 そこで、本稿では、帳簿の作成や確定申告に関する知識を「どの程度持っていれば良いか」および「どんな方法で得れば良いか」についてご紹介いたします。 帳簿作成の目的 帳簿作成の目的について考えてみます。表向きには、財政状態の推移および残高の把握、経営成績の把握ということになっています。しかし、小規模な個人事業主の場合には、主に確定申告を見据えて帳簿を作成しているのが現実と言えるでしょう。もちろん、将来的に事業が大きくなって財政状態や経営成績の把握が重要となるフェーズが訪れる可能性もありますが、開業当初は取り敢えず税務上の要請に応えられれば、最低限の目的は達成できると考えられます。 税務上の要請とは 税務上の要請とは、本来は守備範囲の広い表現ですが、開業にあたっては適正な納税額の計算と、税制の優遇措置を受ける条件と割り切ってしまえます。税制優遇は...
-

2024.06.05 税務ニュース
漫画家・作曲家は確定申告のアフターケアが大事!予定納税の注意点と対策方法について解説。
確定申告が終わってひと安心。しかし、所得税の納税は確定申告時の年1回だけとは限りません。一定の税額が発生している場合には、年の途中に「予定納税」の義務が生じることがあるのです。 特に、漫画家・作曲家などのクリエイターが平均課税制度を利用した場合は要注意。本コラムでは、所得税の予定納税の注意点と対策方法について解説します。 所得税の予定納税とは? 予定納税とは、税金の前払いルールのことです。予定納税の対象者は、年の途中に所得税の前払いをしなければなりません。 予定納税をするかどうか、そして予定納税の時期や金額は、自分で自由に決めることはできません。予定納税の義務がある人には、おおむね6月15日頃までに税務署から通知が届きます。また、予定納税の時期は7月と11月、予定納税の金額は前年の所得税の3分の2(7月と11月にそれぞれ3分の1ずつ)と税金のルールで決められています。 予定納税の義務がある場合、納付期限を過ぎると延滞税という追加の負担が発生してしまうため注意しましょう。 予定納税の対象となる人は? 予定納税の対象者かどうかは、前年の確定申告の納税額で判定します。 具体的に...
-

2024.06.03 税務ニュース
お酒の転売、シロウトがやると違法になる?法務・税務のリスクを解説②税務編
前回に引き続き、今回もお酒の転売に関する注意点です。今回は税務面についてお伝えします。 登場人物 よっちゃん(以下「よ」):まゆこの夫。行政書士。仕事はできるが税金はくわしくない。特技は料理と釣り。夢は釣り三昧の日々。 まゆこ(以下「ま」):税理士・税務ライター。「こむずかしい税金をいかに分かりやすく表現するか」ばかり考えている。趣味は、よっちゃんのごはんを食べること。 酒の繰り返し転売には税金がかかる ま「気になって調べたけど、前からお酒の転売は問題になっているのね」 よ「どれどれ…えっ!主婦も?」 ま「テーマは無免許販売による酒税法違反だけど…たぶん他の税金も納めていないんじゃないかしら」 【参考】酒類の無免許ネット転売が横行…大阪国税局、主婦や法人などに計188万円の納付通告 ま「『家にある不用品をたまに売る』程度だったら問題ないのよ。生活用動産の譲渡は所得税も住民税も非課税。消費税だってかからない。お酒は生活用動産とは言い難いけど、金額なんてたかが知れているから問題にならない。当然、酒販売の免許もなければ義務も果たさない」 よ「繰り返し転売だとどう...









 トップ
トップ



![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)

