MENU


 PICKUP
PICKUP
税務ニュース
【2025年度(令和7年度)税制改正(その1)】103万円の壁の引き上げは123万円に!いつから?大学生のバイト「103万円→150万円」の控除も解説
昨年12月20日に2025年度(令和7年度)税制改正大綱が公表されました。もっとも注目されたのは「103万円の壁の引き上げ」です。どうなったのでしょうか。いつから始まるのでしょうか。今回は、103万円の壁の引き上げと大学生のバイトの壁の引き上げを中心に解説します。 2025年度(令和7年度)税制改正①「103万円の壁」が「123万円の壁」に 個人向けの税制改正の1つ目は「103万円の壁の引き上げ」です。 103万円の壁とは、パート・バイトといった給与所得者の非課税枠を言います。「給与所得控除の下限55万円+基礎控除額48万円=給与年収の非課税の上限103万円」という内容です。 多くのパート・バイトはこの103万円の壁を気にするため、年末になると「働き控え」という現象が起きていました。そのため、企業は人手不足に悩み、家計は物価高が改善されないという状況に陥っていたのです。 そこで、与党から政策協力を求められた国民民主党が「103万円の壁を引き上げるべきだ」と提案しました。議論が重ねられた結果、今回の税制改正で103万円の壁が引き上げとなったの...

社会保険ワンポイントコラム
職場の離職率低下につながる効果が!治療と仕事の両立支援について
治療と仕事の両立についての社会的背景 近年、医療の進歩により、がんのように以前は不治とされていた病気でも生存率が向上し、長期にわたって仕事との両立が可能になりつつあります。病気になったらすぐに離職しなければならないという状況から、治療を行いながら仕事を続けられる社会的環境へと変化しています。 しかし、疾病や障害を抱える従業員を支援するための社内体制が整っていない場合、従業員は仕事を続けたくても離職を選択せざるを得ません。これは企業にとっても人材の大きな損失といえるでしょう。 両立支援の内容 治療と仕事の両立支援の内容ですが、具体的には次のような柔軟な働き方ができる制度を設けた上で、私傷病の治療や療養を目的とした利用ができるようにします。 時差出勤制度 短時間勤務制度 時間単位の休暇制度・半日休暇制度 フレックスタイム制度 在宅勤務(テレワーク)制度 休職制度 両立支援に取り組むことの効果 労働政策研究・研修機構(JILPT)の「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)2024年3月」によれば、上記のよう...

99件 1~20件を表示
-

2025.01.22 税務ニュース
【定額減税】2025年度(令和7年度)の給与支払報告書の摘要欄3つの意味は?注意点も解説
年明け1月は年末調整を受けて各市町村に給与支払報告書を送ることになります。ここで注意したいのが摘要欄の記載事項です。今回は定額減税についても書かなくてはなりません。この記事では、定額減税について摘要欄に記載すべき3つの事項と注意点を解説します。 2025年度(令和7年度)の給与支払報告書には定額減税も記載 年末調整が終わると、給与所得の源泉徴収票を含めた法定調書と給与支払報告書を作成し、提出しなくてはなりません。今回提出する書類の提出期限や提出先は、それぞれ次のようになっています。 書類名 目的 提出先 提出期限 令和6年分(2024年分)法定調書(給与所得の源泉徴収票を含む) 支払を受けた者の確定申告等の内容が正しいかどうかの裏付けのため 事業主の事業所所在地を管轄する税務署 2025年1月31日 令和7年度分(2025年度分)給与支払報告書 令和7年度(2025年度)の個人住民税の計算のため 給与等を受け取った役員・従業員それぞれの住所地の市町村 特に注意したいのが給与支払報告書です。書かれているのは2024年1月1日から12月31日までの給与所得です。...
-
![個人事業主も活用したいクラウドファンディングのしくみと税金[第5回]:寄付型クラウドファンディングと税金](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-97.jpg)
2024.12.20 起業応援・創業ガイド
個人事業主も活用したいクラウドファンディングのしくみと税金[第5回]:寄付型クラウドファンディングと税金
近年、フリーランスや個人事業主も活用できる資金調達手段として注目されているクラウドファンディング。何回かの連載で、フリーランスや個人事業主が知っておきたいクラウドファンディングのしくみと税金について解説します。第5回では個人が実施する寄付型クラウドファンディングにスポットをあててみましょう。 寄付型クラウドファンディングと税金 寄付型クラウドファンディングは、被災地や社会的弱者の支援など、社会貢献性の高いプロジェクトに利用されることが多い資金調達方法です。寄付型クラウドファンディングは、東日本大震災をきっかけに日本国内での普及が進みました。 寄付型クラウドファンディングの特徴は、支援者がクラウドファンディング実施者の社会貢献活動に対して資金を提供し、見返りを求めないというものです。したがって、寄付型クラウドファンディングにおいて、支援者が受け取るリターンの多くは、「お礼の手紙」「定期的な活動報告」「イベントへの参加」「プロジェクトのノベルティ」などとなっています。 寄付型クラウドファンディングには、寄付(寄附)に関する税金のルールが適用されます。しかし、寄付型クラウドファン...
-

2024.12.13 税務ニュース
【消費税】還付されるはずが納税に!?事業主なら注意したい消費税の届出と対策を紹介
消費税の届出はいろいろありますが、一度提出するとほぼ永久に有効です。そのため、届出書を提出したことを忘れてしまうと数年後、思わぬ課税になることも。今回は消費税の届出で注意すべきものと対策をご紹介します。 消費税の主な届出書3選 消費税の主な届出には次の3つがあります。 課税事業者選択届出書 「基準期間の課税売上高が1000万円以下」といった理由で本来消費税が免税となる事業主が、あえて課税事業者になるときに提出する届出書です。たいていは「支払った消費税額>売上分の消費税額」となったがため、消費税の還付が見込めるときに提出します。 届出書は、課税事業者になりたい課税期間の初日の前日までに提出することが必要です。ただし開業したばかりならば、開業した課税期間の末日までに提出すれば、提出した課税期間から課税事業者となります。 参考:消費税課税事業者選択届出書|国税庁 簡易課税制度選択届出書 基準期間の課税売上高が5000万円以下の課税事業者がシンプルに消費税の納税額を計算しようとするときに提出する届出書です。 本来、納める消費税は「売上分の消費税額-支払った消費税」で計算すべきもので...
-

2024.12.11 税務ニュース
【ふるさと納税】ワンストップ特例が無効になるケースとは?サラリーマンや年金生活者の確定申告での注意点も解説
年末になり、ふるさと納税が気になる季節になりました。サラリーマンや年金生活者の方はワンストップ特例を検討しているかと思います。ワンストップ特例は確定申告がいらなくなる点が魅力ですが、うっかりすると住民税で節税できなくなることも。今回は、ワンストップ特例が無効になるケースと確定申告での注意点をお伝えします。 ワンストップ特例とは何か ワンストップ特例とは、手続きさえすれば自動的に翌年6月からの住民税から「寄付した金額-2000円」が控除されるしくみを言います。 ふるさと納税で節税したい場合、本来は確定申告をしなくてはなりません。しかし、寄付先の自治体にワンストップ特例の手続きをすれば、確定申告をしなくても「寄付額-2000円」が、寄付をした翌年6月からの住民税から差し引かれるのです。 引用元:ふるさと納税トピックス一覧|制度改正について(2015年4月1日)|総務省 ただし、ワンストップ特例を使える人や要件が決まっています。次の通りです。 対象者 給与所得者や年金受給者のうち、確定申告をする必要のない人に限られます。 要件 1年間のふるさと納税の寄付先が5つの自治体以下であ...
-

2024.10.10 税務ニュース
【災害の税務】自分で期限を延長できる?個別延長の申請手続きと注意点を解説
台風や大雨の被害を受けたとき、事業者によっては「申告や申請が期限に間に合わない」と悩むこともあるでしょう。国税庁が期限を延長してくれればいいのですが、いつも延長されるわけではありません。こんなとき、自分で期限延長の手続きをすることも可能です。今回は、個別延長の申請手続きと注意点を解説します。 災害シーズンに多い申告・申請・納税の手続 台風や大雨が頻発する夏から秋でも、税務手続は必要です。国税ならば、主に次のようなものがあります。 手続 個人 法人 申告・納税 ・所得税の予定納税(第1期分) ・消費税の中間申告・納税(年3回・12回) ・源泉所得税(原則は毎月10日) ・給与等の源泉所得税(納期の特例は7月10日) ・個人事業税(8月末) ・個人住民税(普通徴収は8月末、10月末、給与の特別徴収は毎月10日) ・法人税・法人住民税・法人事業税の確定申告 ・消費税の確定申告 ・消費税の中間申告・納税(年1回・3回・12回) ・個人住民税(給与の特別徴収は毎月10日) ・法人住民税・法人事業税の中間納付 ・源泉所得税(原則は毎月10日) ・給与等の源泉所得税(納期の特例は7...
-

2024.09.30 税務ニュース
【定額減税】定額減税で年末調整はどう変わる?定額減税に伴う年末調整の注意点を税理士が解説
1. 定額減税と令和6年分年末調整 2024年6月以降支給の給与から開始した定額減税。毎月の給与や賞与で所得税の減税額の計算を行ってきましたが、年末に実施する令和6年分年末調整も通常年とは異なる取扱いがあるため留意が必要です。 本記事では、定額減税により令和6年分の年末調整がどのように変わるか概要とポイントを解説します。早めに確認して、令和6年分の年末調整に備えていきましょう! ≪月次減税と年調減税のイメージ図≫ 図解:国税庁『給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた』 2. 年調減税事務の手順 年末調整時に行う定額減税に係る事務を年調減税事務と言います。令和6年分年末調整の際は、年末調整時点の定額減税額を計算し精算を行う必要があります。 年調減税事務は次の流れで行います。 ≪年調減税事務の流れ≫ (1)対象者の確認 ↓ (2)年調減税額の計算 ↓ (3)年調減税額の控除 (1)対象者の確認 年調減税事務の対象となる人を確認します。 年末調整の対象者が、原則として年調所得税額(※1)から年調減税額を控除する対象になります。 ただし、年末調整の対象者のうち、...
-
![個人事業主も活用したいクラウドファンディングのしくみと税金[第3回]:購入型クラウドファンディングに係る税金②](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-134.jpg)
2024.09.24 税務ニュース
個人事業主も活用したいクラウドファンディングのしくみと税金[第3回]:購入型クラウドファンディングに係る税金②
近年、フリーランスや個人事業主も活用できる資金調達手段として注目されているクラウドファンディング。何回かの連載で、フリーランスや個人事業主が知っておきたいクラウドファンディングのしくみと税金について解説します。第3回では、購入型クラウドファンディングを実施するうえで知っておきたい節税対策や必要経費にスポットをあててみましょう。 購入型クラウドファンディングに係る税金 購入型クラウドファンディングで集めた資金に対しては、資金調達者が事業者であれば事業所得、それ以外の場合には雑所得として、所得税および住民税が課税されます。 購入型クラウドファンディングにおいては、「資金調達者を支援する」というかたちをとっているため「支援」や「応援」といった言葉が使われていますが、その実態は事業者が行う通常の売買取引と同じです。資金調達者はリターンという名目で商品やサービスを提供し、資金提供者は支援金という名目でその対価を支払っているにすぎません。そのため、資金調達者が事業を営んでいる場合、資金調達者が資金提供者から受け取った資金は、事業所得として所得税および住民税の課税対象となるのです。 なお...
-

2024.06.03 税務ニュース
お酒の転売、シロウトがやると違法になる?法務・税務のリスクを解説②税務編
前回に引き続き、今回もお酒の転売に関する注意点です。今回は税務面についてお伝えします。 登場人物 よっちゃん(以下「よ」):まゆこの夫。行政書士。仕事はできるが税金はくわしくない。特技は料理と釣り。夢は釣り三昧の日々。 まゆこ(以下「ま」):税理士・税務ライター。「こむずかしい税金をいかに分かりやすく表現するか」ばかり考えている。趣味は、よっちゃんのごはんを食べること。 酒の繰り返し転売には税金がかかる ま「気になって調べたけど、前からお酒の転売は問題になっているのね」 よ「どれどれ…えっ!主婦も?」 ま「テーマは無免許販売による酒税法違反だけど…たぶん他の税金も納めていないんじゃないかしら」 【参考】酒類の無免許ネット転売が横行…大阪国税局、主婦や法人などに計188万円の納付通告 ま「『家にある不用品をたまに売る』程度だったら問題ないのよ。生活用動産の譲渡は所得税も住民税も非課税。消費税だってかからない。お酒は生活用動産とは言い難いけど、金額なんてたかが知れているから問題にならない。当然、酒販売の免許もなければ義務も果たさない」 よ「繰り返し転売だとどう...
-

2024.05.14 農家おすすめ情報
スマート農業による特別償却制度の創設 令和6年度税制改正
はじめに スマート農業に関して特別償却制度が令和6年度税制改正により新設された。スマート農業技術等を活用した生産性の高い食料供給体制の確立に向けた税制上の所要措置について解説する。農業者はぜひ本稿を読んで参考にしていただきたい。記事の記載にあたり財務省及び農林水産省の公表資料をもとにわかりやすく説明している部分は、著者の個人的な見解も含むことをあらかじめお断りしておく。 背景 今後20年間で、現在の基幹的農業従事者の大宗を占める70歳以上の年齢層がリタイアした後、農業者数は現在から大きく減少することが見込まれる。従来の生産方式等を前提とした農業生産では農業の持続性を確保できない懸念が生じている。 基幹的農業従事者数と平均年齢 ここがポイント!今後20年間で、基幹的農業従事者は現在(2023年)の116万人から30 万人にまで減少することが見込まれる。 用語解説基幹的農業従事者とは、ふだん仕事として主に自営農業に従事している人。 スマート農業とは、ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用する農業のこと。 参考:スマート農業(水田作)スマート農業導入により農作業のハードルが下がり、...
-

2024.05.09 税務ニュース
【定額減税】住民税は大丈夫?早めに確認したい4つのポイント
6月からの定額減税は所得税だけでなく住民税もあります。住民税は所得税と違い、2023年分の所得や家族状況が基準です。年末調整や確定申告の内容によっては、住民税の定額減税が受けられなかったり、予想外の事態になったりするかもしれません。今回は、住民税の定額減税で確認したい4つのポイントをお伝えします。 登場人物 よっちゃん(以下「よ」):まゆこの夫。行政書士。仕事はできるが税金はくわしくない。特技は料理と釣り。夢は釣り三昧の日々。 まゆこ(以下「ま」):税理士・税務ライター。「こむずかしい税金をいかに分かりやすく表現するか」ばかり考えている。趣味は、よっちゃんのごはんを食べること。 定額減税、所得税は「2024年分」住民税は「2023年分」を基準に計算 よ「なんで住民税が大事なの?市町村が計算するから関係ないじゃん」 ま「…住民税の定額減税がいつの分の所得を基準に計算するか、知ってる?」 よ「住民税の定額減税も所得税と同じで2024年6月に始まるから…2024年分の所得じゃないの?」 ま「ハズレ。住民税の定額減税は2023年分の所得...
-

2024.05.08 税務ニュース
交際費等から除かれる飲食費が「1万円まで」に!損金算入の要件と中小企業への影響を解説
2024年度税制改正で交際費課税が変わりました。目玉の1つは「交際費から除外する飲食費の上限が1人あたり5000円から1万円へ」です。具体的な改正内容はどのようなものでしょうか。また、中小企業にどのように影響するのでしょうか。今回は、改正のポイントを確認し、今後について考察します。 2024年税制改正で交際費等課税のポイント2つを確認 2024年度税制改正では交際費等の損金計上の扱いが拡充されました。昨今の物価高への対応と中小企業の経済活動の促進が目的です。具体的には、次の2点となります。 1.交際費等から除外される飲食費の上限額が「5000円→1万円」に 法人が支出する交際費は原則、損金の額(法人税法上の経費の額)に算入できないとされています。しかし特例的に、法人の規模ごとに一定額を損金の額に算入することが認められています。 現在の交際費等の損金算入限度額は、次の通りです。 期末資本金等の額 交際費等の損金算入限度額 1億円以下 次のいずれかの金額 年800万円が上限 接待飲食費×50%が上限 1億円超100億円以下 接待飲食費×50%が上限 ...
-

2024.04.30 税務ニュース
【【能登半島地震】2023年分所得税の前倒し適用、雑損控除だけじゃない?注意点も解説】
能登半島地震で被災した場合、税負担を軽くする制度を2023年分で適用することができます。今回は、前倒し適用ができる所得税の制度を3つご紹介します。 能登半島地震による損失は2023年分の所得税から適用できる 2024年1月1日の能登半島地震で建物や車などが被災しました。「家が倒壊して住めない」「修繕にお金がかかる」といったところもあったようです。 ここで真っ先に考えるのが「雑損控除などで納税負担を軽くすること」ですが、本来、すぐに雑損控除を受けることはできません。なぜかというと雑損控除などの基因となる損害が生じたのは2024年になってからだからです。2024年分で雑損控除を受けるなら、2025年になるのを待つしかありません。 しかし、2024年になって早々に被災した人たちに「所得控除を1年待て」というのは酷なもの。被災者の中には、生活や事業の資金がなくなって「今すぐ申告して還付を受けたい」という人もいるかもしれません。 そういった人たちの負担を少しでも軽くすべく、雑損控除などを1年前倒しして適用できる法律が立案されました。次の2つの法案が2024年2月21日に国会で成...
-
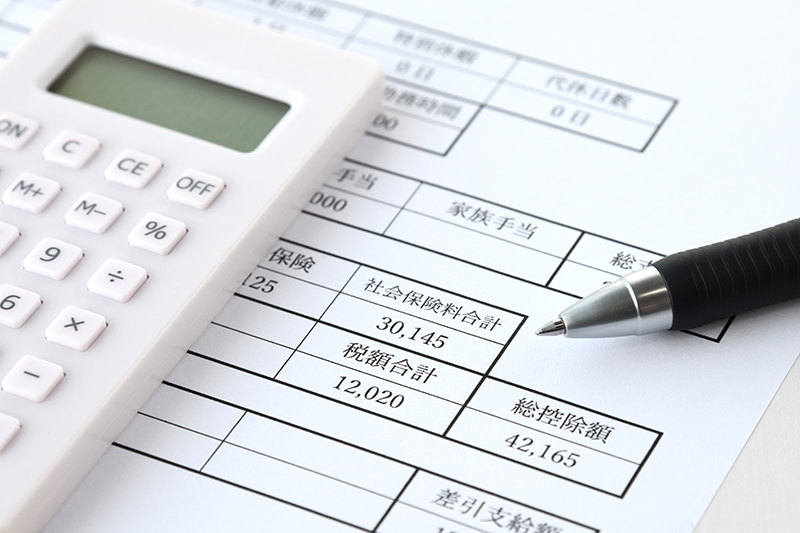
2024.03.20 社会保険ワンポイントコラム
「4・5・6月の残業を減らすと社会保険料が少なくなる」は本当か
もうすぐ4月。この時期になると必ず耳にするフレーズに、「4・5・6月の残業を減らすと社会保険料が少なくなる」というものがある。しかしながら、これは必ずしも事実とは言い切れない面があることをご存じだろうか。今回は「4・5・6月の残業を減らすと社会保険料が少なくなる」の意味を考察してみよう。 春の「3カ月間の平均給与額」が1年間の社会保険料額を決める 厚生年金や健康保険の保険料額は、給与額に基づいて定められた標準報酬月額に保険料率を乗じて決定される。ただし、標準報酬月額は実際に支給されている給与額との差異が大きくなり過ぎないよう、年に1回、定時決定と呼ばれる見直し作業を行うことが義務付けられている。 定時決定では「4・5・6月に支給された給与の平均額」を基に新しい標準報酬月額を決定し、その年の9月から1年間は新しい標準報酬月額に基づいて社会保険料を計算することになる。そのため、「4・5・6月の残業を減らせば残業代が少なくなる分、支給される給与額も減り、1年間の社会保険料負担が減少する」と考えがちである。 しかしながら、「4・5・6月の残業を減らす」ことは、必ずしも「4・5・6月に支...
-

2024.02.26 税務ニュース
ほとんどの人ができない所得税の正しい計算。累進課税とは
元国税職員さんきゅう倉田です。好きな税務調査は「任意調査」です。 2023年4月に東京大学に入学し、2月からは春休みを満喫しています。春休みにやることといえば、「確定申告」ですね。経費を入力し、売上を入力し、所得を計算し、社会保険料などを控除して、所得税率をかけて、所得税を計算する。 少し前までは紙の確定申告書に手書きで行っていました。ぼくが税務署で確定申告の応援業務を行っていたときは、所得税の税率表を首から下げて納税者のみなさんの補助として計算をしていましたが、今ではパソコンやスマホでの申告が主流です。 確定申告期間に税務署や確定申告の会場に行っても、紙で確定申告書を作成することはなく、パソコンが割り当てられネットワーク上で送信、控えはプリンタで出力します。面倒な計算もないので、とても楽になりました。税の三原則の中に「簡素」があります。税制度は無駄や余計なものを省いたものである必要があり、納税や申告の方法も同様です。確定申告の簡素化・単純化は納税者の納税を促すことは間違いありません。 確定申告が簡単になること、そして源泉徴収や年末調整によって個人が税金の計算をしなくて...
-

2024.02.23 税務ニュース
相続時精算課税制度の再確認(制度の概要と改正内容)
令和5年度の税制改正により、相続時精算課税制度の見直しが行われました。相続時精算課税制度は平成15年に創設されたものですが、一度選択すると撤回することができず、また必ずしも有利になる訳ではないため、制度を選択するには慎重な判断が必要で、あまり活用されていませんでした。 改正により、相続対策として使いやすくなりましたので、相続時精算課税制度のおさらいとその活用方法をお伝えいたします。 暦年課税贈与と相続時精算課税制度の概要 贈与税の計算方法は、「暦年課税贈与」が原則となります。暦年課税贈与の場合、年間110万円の基礎控除額があるため、贈与でもらった財産の額が110万円を超えなければ申告不要、超えた場合は超えた額に応じた贈与税率を乗じて贈与税を算出します。また、相続税の計算上「生前贈与加算」の規定があり、相続開始前7年以内(令和6年1月1日以降の贈与の場合)の贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。 それに対し、相続時精算課税制度は、選択した場合に適用がある特例制度です。特別控除額2,500万円がありますので、贈与税の負担なく次世代に大きく財産を移転することが可能です。...
-

2024.02.15 税務ニュース
「定額減税」って何?2024年6月からの源泉徴収と年末調整はどうすべき?①
昨年12月14日、2024年度(令和6年度)税制改正大綱が発表されました。もっとも注目されたのは「定額減税」です。6月以降、給与や賞与からの源泉徴収が大変になると言われています。なぜでしょうか。2回にわたって解説します。1回目は定額減税の内容の確認です。 登場人物 よっちゃん(以下「よ」):まゆこの夫。行政書士。仕事はできるが税金はくわしくない。特技は料理と釣り。夢は釣り三昧の日々。 まゆこ(以下「ま」):税理士・税務ライター。「こむずかしい税金をいかに分かりやすく表現するか」ばかり考えている。趣味は、よっちゃんのごはんを食べること。 定額減税って何? よ「定額減税って何なの?」 ま「1人あたり所得税3万円と住民税1万円が控除されるという制度よ」 よ「所得から?」 ま「税額から。本来かかる所得税が5万円で住民税が3万円なら、所得税は2万円に、住民税は1万円になるってわけ」 よ「へー。それは1人あたりの控除額なの?」 ま「そうね。ただ、扶養家族がいるなら、その家族分も『所得税3万円、住民税1万円』が税額からさしひかれるの」 ...
-

2024.02.12 税務ニュース
社長が毎年タダ同然で高級車を乗り換える節税スキーム!
近年、ビッグモーターの件などで中古車市場が話題になりました。 中古車の値動きについては、 半導体・部品不足が解消されてきたことによる、新車の納期の短縮 ロシアへの中古車の輸出規制が、より厳格化されたこと 不祥事による中古車販売会社に対する不信感 などがあり、値が下がる要因のほうが多いです。 一般的に輸入車はリセールバリューが低くなる傾向にあります。そんな中でも、ポルシェやメルセデスベンツのGクラスなどは、リセールバリューが高い人気車です。外車を乗り換える経営者の方も多いですが、実は、その車の中古車価格の1割くらいしかお金を払っていないかもしれません。今回は、中古車の1割ほどの価格で高級車を毎年乗り換える節税スキームを解説していきます。 減価償却ってなに? まずは減価償却がどういうものかを解説します。 減価償却は、該当する固定資産の購入費用を、何年かに渡って分割して経費にする会計処理です。原則として10万円以上の資産が対象です。物によって何年で経費に出来るか、細かく法律で決められています。この年数を法定耐用年数と言います。 減価償却には、定額法と...
-

2024.01.12 税務ニュース
美術品やアート作品で節税?絵画や彫刻などの減価償却について解説。
美術品やアート作品の購入が節税対策につながることはあまり知られていません。実は2015年から美術品等に関する税金のルールが大きく変わっているのです。本コラムでは、美術品やアート作品の購入が会社の税金に与える影響と注意点について解説します。 大きく変わった美術品の税金ルール 長期間にわたって使用する高額な資産を購入した場合、その購入価額の全額を購入時点の事業経費とせずに、法令で定められた耐用年数にわたって事業の経費にしていきます。これを「減価償却」といいます。一方で、時の経過により価値が減少しない資産は「減価償却」の対象になりません。つまり、税金の計算に影響を及ぼさないのです。 さて、高額な資産といっても、絵画や彫刻などの美術品やアート作品についてはどのように考えたらよいのでしょうか?多くの人が鑑賞したからといって美術品等の価値が損なわれるわけではありません。また、美術品等の価値が時間の経過によって減少するともいえず、加えて、美術品等の評価は嗜好や作品の人気の動向などにより一様ではありません。客観的な基準が求められる税金のルールとしては、悩ましい問題だといえるでしょう。 この...
-

2024.01.08 税務ニュース
今からでも間に合う「電子帳簿保存法」対策
(1)ついに義務化された電子帳簿保存法 2年間、猶予されていた「電子取引における電子保存の義務化」が、ついに令和6年1月1日から再スタートしました。中小企業や個人事業主の中には、まだ対応できていない、何をどうすればいいのかさっぱり分からない、という人も多いのではないでしょうか。でも大丈夫。これから対策すれば、十分間に合います。 電子保存の義務化には、会社のバックヤードを効率化するという副次的な効果があります。法律で決まったことだからと、いやいや対応するのではなく、経理のDX化を進めるチャンスととらえて、前向きに取り組んではいかがでしょうか。 本記事では、今さら聞けない電子帳簿保存法の基本的なルールと、電子データ保存に向けて何から始めればよいかについてご説明したいと思います。 (2)電子帳簿保存法の超入門 電子帳簿保存法の改正で何が変わる? 会社や個人事業主等が保存しなければならない書類には、取引を記録した帳簿や、取引に関連して作成した書類、取引先から受け取った書類などがあります。以前は、これらの書類は紙で保存しなければなりませんでした。たとえばカード会社のサイトからダウンロー...
-

2024.01.05 税務ニュース
【令和6年能登半島地震】雑損控除、災害減免法?災害時の税務対策を順番に解説
今年1月1日、能登半島で震度7の地震が起きました。被災地では混乱が続き、復興には時間がかかると見られます。ここで気になるのが税金です。1月は源泉所得税の納付のほか、法定調書や給与支払報告書の提出、償却資産の申告があります。しかし落ち着いて税務をこなす余裕はありません。そこで今回は、災害という緊急事態が生じたときの税務対策を、時間の流れとともに解説します。 「雑損控除」「災害減免法の軽減免除」は後回しの理由 災害時の税務対策で最初に思いつくのは「災害減免法による所得税の軽減免除」「雑損控除」かと思います。 【参考記事】災害が起きたら役員・従業員の税金はどうなる?救済策を確認しよう(1) しかし実際は、すぐに活用しません。今回の能登半島地震なら、来年考えます。 なぜかというと、2024年1月1日に起きた災害で影響を受けるのは2024年分の所得税や2025年度の個人住民税だからです。2024年分の所得と税額を計算して申告するのは2025年3月15日期限の確定申告となります。つまり、実際に計算するのは来年になるわけです。 このほか、目の前に迫った申告や納付、申請や届出の期限...









 トップ
トップ



![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)

