MENU


 PICKUP
PICKUP
税務ニュース
【2025年度(令和7年度)税制改正(その1)】103万円の壁の引き上げは123万円に!いつから?大学生のバイト「103万円→150万円」の控除も解説
昨年12月20日に2025年度(令和7年度)税制改正大綱が公表されました。もっとも注目されたのは「103万円の壁の引き上げ」です。どうなったのでしょうか。いつから始まるのでしょうか。今回は、103万円の壁の引き上げと大学生のバイトの壁の引き上げを中心に解説します。 2025年度(令和7年度)税制改正①「103万円の壁」が「123万円の壁」に 個人向けの税制改正の1つ目は「103万円の壁の引き上げ」です。 103万円の壁とは、パート・バイトといった給与所得者の非課税枠を言います。「給与所得控除の下限55万円+基礎控除額48万円=給与年収の非課税の上限103万円」という内容です。 多くのパート・バイトはこの103万円の壁を気にするため、年末になると「働き控え」という現象が起きていました。そのため、企業は人手不足に悩み、家計は物価高が改善されないという状況に陥っていたのです。 そこで、与党から政策協力を求められた国民民主党が「103万円の壁を引き上げるべきだ」と提案しました。議論が重ねられた結果、今回の税制改正で103万円の壁が引き上げとなったの...

社会保険ワンポイントコラム
職場の離職率低下につながる効果が!治療と仕事の両立支援について
治療と仕事の両立についての社会的背景 近年、医療の進歩により、がんのように以前は不治とされていた病気でも生存率が向上し、長期にわたって仕事との両立が可能になりつつあります。病気になったらすぐに離職しなければならないという状況から、治療を行いながら仕事を続けられる社会的環境へと変化しています。 しかし、疾病や障害を抱える従業員を支援するための社内体制が整っていない場合、従業員は仕事を続けたくても離職を選択せざるを得ません。これは企業にとっても人材の大きな損失といえるでしょう。 両立支援の内容 治療と仕事の両立支援の内容ですが、具体的には次のような柔軟な働き方ができる制度を設けた上で、私傷病の治療や療養を目的とした利用ができるようにします。 時差出勤制度 短時間勤務制度 時間単位の休暇制度・半日休暇制度 フレックスタイム制度 在宅勤務(テレワーク)制度 休職制度 両立支援に取り組むことの効果 労働政策研究・研修機構(JILPT)の「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)2024年3月」によれば、上記のよう...

21件 1~20件を表示
-
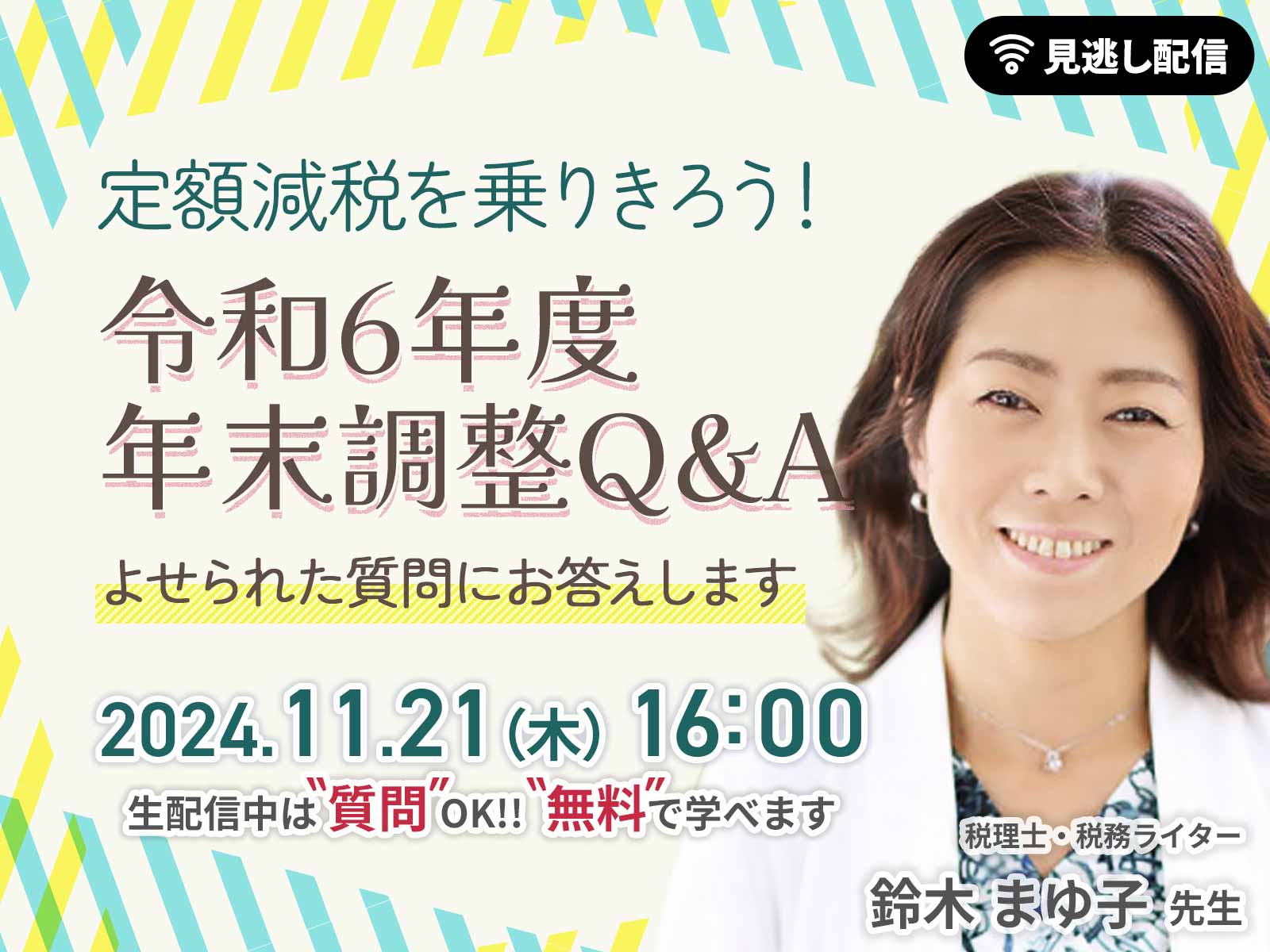
2024.11.28 見逃し配信
【見逃し配信】定額減税を乗りきろう!令和6年度 年末調整 Q&A ~よせられた質問にお答えします~
2024年11月21日(木)、ソリマチ株式会社は税理士・税務ライター 鈴木まゆ子 先生をお招きし、「定額減税を乗りきろう!令和6年度 年末調整 Q&A~よせられた質問にお答えします~」と題した無料のオンラインセミナーを開催いたしました。 セミナーレポート 定額減税は、納税者本人とその配偶者や扶養親族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が控除される制度です。年末調整においても、定額減税における所得税控除が生じるケースが多く、扶養人数の変更などにも注意が必要です。 今回のセミナーでは、税理士・税務ライターの鈴木まゆ子先生をお招きし、令和6年の年末調整の注意点について解説いただきました。また事前にお寄せいただいた年末調整についての質問にも、セミナー内で回答・解説しています。 年末調整は毎年変更点が生じるものですが、今年は定額減税の影響で、より複雑になることが予想されます。ぜひ今回のセミナーを参考にしていただければ幸いです。 [template id="4604"]
-

2024.11.20 税務ニュース
【年末調整】定額減税で変わる源泉徴収票&控除済み及び控除されていない定額減税額の確認方法
さて、今年も年末調整の時期がやってまいりました。 令和6年の年末調整は、定額減税により年末調整のしかたが例年とは大きく変わります。 年末調整時に行う定額減税を年調減税と言い、令和6年分の年末調整の際は、年末調整時点の定額減税額を計算し精算を行う必要があります。 また、定額減税の実施により「給与所得の源泉徴収票」(源泉徴収票)の記載について、例年とは異なる点があります。本記事では、「令和6年分給与所得の源泉徴収票」の書き方&見方について「定額減税」に関する部分をわかりやすく解説します。 1. 定額減税と源泉徴収票の記載 (1)源泉徴収票へ定額減税に関する事項の記載が必要な人は? 年末調整対象者の「給与所得の源泉徴収票」には、定額減税に関する記載が必要です。 年末調整の対象者 → 源泉徴収票に定額減税に関する記載が必要 年末調整の対象ではない方 → 源泉徴収票に定額減税に関する記載は不要 (2)源泉徴収票には定額減税に関するどのような記載が必要? 年末調整対象者の源泉徴収票の「(摘要)」欄に一定の定額減税に関する事項を記載します。 (摘要)欄は、源泉徴収票の真...
-

2024.11.13 税務ニュース
【2024年(令和6年)年末調整】定額減税は申告書のどこを見るべき?注意点も解説
2024年(令和6年)の年末調整では、例年の控除項目に加え、定額減税も計算します。年末調整の申告書の中に定額減税の項目も設けられているようですが、中には対処できないことも。今回は「年末調整の申告書のどこで定額減税を確認すべきか」をお伝えし、年末調整ならではの注意点にも触れます。 年末調整での定額減税をおさらい 定額減税は、6月以降の月次源泉だけでなく、今回の年末調整でも行います。年末調整で減税される所得税の金額は次の通りです。 同一生計配偶者や扶養親族の要件は次の通りです。いずれも本年最後の給与支給の時点で当てはまるかどうかを判断します。 定額減税、2024年の年末調整の申告書のどこに書くのか 2024年の年末調整で使う用紙 今回の年末調整で役員・従業員に書いてもらう書類は、以下の通りです。 書類名 目的 扱う控除・減税 対象者 令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 年末調整に基づいた源泉徴収を行うため 扶養控除 障害者控除 勤労学生控除 ひとり親控除 寡婦控除 ...
-

2024.09.30 税務ニュース
【定額減税】定額減税で年末調整はどう変わる?定額減税に伴う年末調整の注意点を税理士が解説
1. 定額減税と令和6年分年末調整 2024年6月以降支給の給与から開始した定額減税。毎月の給与や賞与で所得税の減税額の計算を行ってきましたが、年末に実施する令和6年分年末調整も通常年とは異なる取扱いがあるため留意が必要です。 本記事では、定額減税により令和6年分の年末調整がどのように変わるか概要とポイントを解説します。早めに確認して、令和6年分の年末調整に備えていきましょう! ≪月次減税と年調減税のイメージ図≫ 図解:国税庁『給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた』 2. 年調減税事務の手順 年末調整時に行う定額減税に係る事務を年調減税事務と言います。令和6年分年末調整の際は、年末調整時点の定額減税額を計算し精算を行う必要があります。 年調減税事務は次の流れで行います。 ≪年調減税事務の流れ≫ (1)対象者の確認 ↓ (2)年調減税額の計算 ↓ (3)年調減税額の控除 (1)対象者の確認 年調減税事務の対象となる人を確認します。 年末調整の対象者が、原則として年調所得税額(※1)から年調減税額を控除する対象になります。 ただし、年末調整の対象者のうち、...
-

2024.02.28 税務ニュース
「定額減税」って何?2024年6月からの源泉徴収と年末調整はどうすべき?②
前回に引き続いて「定額減税」のお話です。定額減税が始まるのは、今年の6月からです。大変なのは現場で給与計算を行う担当者でしょう。なぜなら月次の源泉徴収で定額減税をしないといけないから。今回は、給与計算での定額減税の流れや注意点を解説します。 登場人物 よっちゃん(以下「よ」):まゆこの夫。行政書士。仕事はできるが税金はくわしくない。特技は料理と釣り。夢は釣り三昧の日々。 まゆこ(以下「ま」):税理士・税務ライター。「こむずかしい税金をいかに分かりやすく表現するか」ばかり考えている。趣味は、よっちゃんのごはんを食べること。 給与計算は「6月からの源泉徴収」に注意 よ「定額減税で6月からの給与計算がめんどくさい…ってどういうこと?」 ま「覚えている?所得税の定額減税は『給与・賞与からの源泉徴収』『公的年金等からの源泉徴収』『予定納税』で行うって」 ま「それぞれ、誰が定額減税をやる?」 よ「給与・賞与は基本、会社。公的年金等は年金機構とか…。予定納税は税務署から通知書が届くよね」 ま「つまり?」 よ「給与所得での定額減税は...
-

2024.02.15 税務ニュース
「定額減税」って何?2024年6月からの源泉徴収と年末調整はどうすべき?①
昨年12月14日、2024年度(令和6年度)税制改正大綱が発表されました。もっとも注目されたのは「定額減税」です。6月以降、給与や賞与からの源泉徴収が大変になると言われています。なぜでしょうか。2回にわたって解説します。1回目は定額減税の内容の確認です。 登場人物 よっちゃん(以下「よ」):まゆこの夫。行政書士。仕事はできるが税金はくわしくない。特技は料理と釣り。夢は釣り三昧の日々。 まゆこ(以下「ま」):税理士・税務ライター。「こむずかしい税金をいかに分かりやすく表現するか」ばかり考えている。趣味は、よっちゃんのごはんを食べること。 定額減税って何? よ「定額減税って何なの?」 ま「1人あたり所得税3万円と住民税1万円が控除されるという制度よ」 よ「所得から?」 ま「税額から。本来かかる所得税が5万円で住民税が3万円なら、所得税は2万円に、住民税は1万円になるってわけ」 よ「へー。それは1人あたりの控除額なの?」 ま「そうね。ただ、扶養家族がいるなら、その家族分も『所得税3万円、住民税1万円』が税額からさしひかれるの」 ...
-

2023.12.02 社会保険ワンポイントコラム
「国民年金の控除証明書が届いていたんですけど、どうしたらいいですか?」と問われたら、何と答えればよい
例年11月に入ると、日本年金機構から『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が発行される。この証明書は国民年金の書類だが、厚生年金に加入中でも届くことがある。そのため、従業員が社会保険事務担当者に「国民年金の控除証明書が届いていたが、どうしたらいいか」などと問い合わせることもあるようだ。そこで今回は、企業に勤務中でも国民年金の控除証明書が届くケース、年末調整終了後の証明書の利用方法などを整理してみよう。 国民年金の控除証明書は会社員にも届くことがある 国民年金保険料の控除証明書は、1年間に納めた国民年金の保険料額を公的に証明する書類である。令和5年度の場合は、令和5年1月1日から同年10月2日までの間に国民年金保険料を1カ月でも納付した実績がある人に対し、11月初旬に日本年金機構から送付されている。 そのため、現在は会社員であり厚生年金に加入中であっても、令和5年1月1日から同年10月2日までの間に以下に該当するケースなどでは、国民年金保険料の控除証明書が届くことになる。 令和5年1月1日から同年10月2日までの間に… 会社勤めをしていなかった期間がある。 過...
-

2023.11.29 税務ニュース
【2023年年末調整】今さら聞けない年末調整の申告書…誰がどの書類を出すべき?
年末調整では、さまざまな申告書を会社に提出します。種類が多いため、誰がどの書類を出したらいいのかで悩むことも。今回は、年末調整をこれから行う会社員やバイト・パートの方に向けて年末調整で提出すべき書類をお伝えします。 年末調整で必要な申告書には何があるか 年末調整で会社に提出する申告書は、次のようになっています。 会社が役員や従業員に配布して記入してもらう申告書 役員や従業員が税務署から入手して提出する申告書 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 参照:令和5年分(2023年分)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁 年末調整を受けるのに必ず提出しなくてはならない書類です。この申告書に書かれている内容は年末調整だけでなく、給与や賞与から源泉徴収する税額の計算の基となります。具体的には、次の所得控除の情報を確認します。 配偶者(特別)控除 扶養控除 障害者控除 ひとり親控除 寡婦控除 勤労学生控除 年末調整では、その年分の扶養控除等(異動)申告書が必要です。ただ実際には、翌年分も一緒に提出するケースが多いかと思います。なぜかというと会社は...
-

2023.11.21 税務ニュース
目指せ、e-年調! 年末調整の電子化に取り組もう
今年もいよいよ年末調整シーズンに突入しています。年に1度の事務とはいえ、忙しい年末に負担がかかる作業です。ほとんどの方が、できる限り手間や時間をかけたくないと思うはずです。 年末調整の電子化とは、これまで紙ベースで進めていた年末調整の手続をすべてデータでの手続に代えることです。従業員は各種証明書の取り寄せや各種申告書の作成をパソコンやスマホで簡単にできます。会社などの事業主は従業員と電子データのやりとりで一連の手続が完結するので、従来の紙書面のやりとりでは面倒だった作業が飛躍的に効率化します。 年末調整電子化のメリット 従業員 手書きでの書類作成が不要に! 複雑な控除額の計算はソフトにおまかせ! テレワーク中など社外からも書類(データ)の提出できる! マイナポータルによる証明書類をまとめて入手できる! 事業主 紙の各種申告書様式の配布や回収が不要に! 回収様式の控除額や添付書類のチェック作業が削減! 給与システムへの手入力が省略される! 紙の申告書様式や添付書類の保管(場所)が不要に! ※データで年末調整手続...
-

2023.11.16 税務ニュース
【2023年年末調整】今回から扶養控除が厳格化…なぜ?国外扶養親族の新たな条件と必要書類を確認
2023年分の年末調整における最大の変更点は「扶養控除にできる国外扶養親族の条件の厳格化」です。どう厳しくなったのでしょうか。この記事では、国外扶養親族の扶養控除の変更点とその背景についてお伝えします。 2023年分から国外扶養親族の扶養控除の条件が変わる 国外扶養親族とは、国外に住む配偶者以外の扶養親族のことです。扶養親族は、基本的に年末時点で次の条件に当てはまる人をいいます。 配偶者以外の6親等内親族または3親等内姻族など 年間の合計所得金額が48万円以下 納税者本人と生計を一にしている 青色事業専従者として給与をもらっておらず、かつ白色事業専従者でもない 2022年分まで、国外の扶養親族で扶養控除をするときの条件は国内扶養親族と同じでした。証明書類の提示や提出が求められるとしても、です。しかし2023年分から、次のように扶養控除の条件が変わります。 引用元:令和5年分年末調整のしかた|国税庁 具体的な内容は次の通りです。 30歳以上70歳未満は原則「扶養控除NG」 扶養親族がその年の12月31日時点で30歳以上70歳未満だと扶養控除にはできませ...
-

2023.10.04 税務ニュース
2023年分の年末調整の変更点と事務スケジュール
2023年分の年末調整計算事務に係る制度改正は、4点あります。今回はその変更ポイントを確認しつつ、年1回の事務を適切かつスムーズに進めていただくために、今後のスケジューリングについておさらいしていきましょう。 2023(令和5)年分の年末調整に関わる変更ポイント (1) 住宅ローン控除の適用期限・控除率・控除期間・要件の見直し (2) 国外居住親族に係る扶養控除要件の見直し (3) 扶養控除等申告書 住民税に関する事項の記載項目を追加 (4) 個人住民税特別徴収税額通知が本人宛に電子化選択可能 (1) 住宅ローン控除 変更ポイント① 適用期限・控除率・控除期間 この変更は2022(令和4)年度税制改正を受けて適用されるものです。住宅ローン控除適用初年分は確定申告によらなければならないため、年末調整には2年目となる今年の分から影響します。 2022(令和4)年から2025(令和7)年までの間に入居した場合、下記のとおりに変更されています。 住宅の区分 居住の用に供した年 控除期間 各年の控除額の計算(控除限度額) 認定長期優良住宅 令和4年・令和5年 13年 年末残...
-

2022.11.30 税務ニュース
11月16日開催 みんなの経営応セミナー『今さら聞けない…令和4年の年末調整『ココだけ』ポイント解説!』Q&Aまとめ
2022年11月16日、「みんなの経営応援セミナー」で令和4年の年末調整についてお話をさせていただきました。その中で、答えきれなかったご質問について、この場を借りてお返事させていただきます。 Q1.新型コロナウイルス感染症で休業して、従業員に休業手当を支給していました。この手当は給与に含めて年末調整をする必要があるのでしょうか。 A 質問の文章を見る限り、年末調整が必要だと思われます。 休業手当は「どういう事情で支給したのか」により課税か否かが分かれます。 労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」:課税(給与所得) 労働基準法第76条の規定に基づく「休業補償」:非課税 1は、「コロナ禍による営業自粛」など、使用者の都合で休業したときに支払われるものです。労働基準法第26条により、平均賃金の6割以上の手当てを支払わなければならないとされています。このとき支給した休業手当は給与所得です。そのため、年末調整の対象となります。 一方2は、業務のときに従業員が負傷などをして仕事ができないときに支払われるものです。こちらは非課税となりますので、年末調整の対象ではあり...
-

2022.11.22 税務ニュース
【2022年年末調整】年末調整で扱う12の所得控除を一気に確認!注意点も解説
年末調整で扱う所得控除は数が多く、全部で12あります。今回は、この12の所得控除の内容や条件を確認しましょう。 社会保険料控除 社会保険料を支払ったときの所得控除です。控除できる金額は、その年に支払った金額すべてです。控除額は、本人が年間に支払った全額です。なお、生計同一配偶者や扶養親族など家族が本来負担すべきものも、扶養する本人が支払ったのなら控除できます。 小規模企業共済等掛金控除 iDeCoや企業版DCの掛金、会社役員などが加入する小規模企業共済の掛金などを支払ったときの所得控除です。その年に支払った金額すべてを控除できます。ただし、社会保険料と違い、本人分しか控除できません。妻の分を実質的に負担したとしても控除できません。 生命保険料控除 生命保険料、介護医療保険料または個人年金保険料を支払った人に適用される所得控除です。 控除額 控除額は、その年に支払った金額をベースに計算します。ただ、社会保険料や小規模企業共済等掛金控除と違い、支払額すべてが差し引けるわけではありません。上限額があります。 【引用元】No.1140 生命保険料控除(国税庁) また...
-

2022.11.11 見逃し配信
《セミナー動画》今さら聞けない…令和4年の年末調整『ココだけ』ポイント解説!
11月16日(水)の『みんなの経営応援セミナー』では、税理士で税務ライターの鈴木まゆ子先生をお招きし、令和4年の年末調整の『ココだけ』ポイントをお話しいただきました。令和4年の変更点や、年末調整の流れ、書類のチェックポイントについて実務の視点からわかりやすく解説いただきました。ぜひご覧ください。 ■11/16(水) 今さら聞けない…令和4年の年末調整『ココだけ』ポイント解説! 放送日:2022年11月16日(水)15:00~(1時間・予定)生放送 講師:税理士・税務ライター 鈴木 まゆ子 先生 講師の鈴木まゆ子先生は、『みんなの経営応援通信』にも多数ご執筆いただいております。ぜひこちらも併せてご覧ください。 視聴はこちらから。 ・セミナーテキストはこちら(PDFダウンロード) セミナー内容 ■年末調整とは?2022年の変更点も確認 ■年末調整の流れ・対象者・書類 ■年末調整で扱う控除/扱わない控除 ■年末調整の「ココだけ」チェックポイント ■その他の注意点 過去の番組 70以上の番組を見逃し配信!録画も無料でご覧いただけます。 https://revis...
-

2022.11.10 税務ニュース
【2022年年末調整】年末調整と確定申告、両方やるのはどんな人?
会社員の多くは年末調整で完結します。しかし、人によっては確定申告も行わなくてはなりません。どのようなときでしょうか。年末調整と確定申告の違いを確認しつつ、両方やるパターンを見ていきましょう。 年末調整と確定申告はどう違うのか そもそも、年末調整と確定申告はどう違うのでしょうか。最初に確認しましょう。 年末調整 年末調整は、「給与から天引きした所得税の精算手続き」です。給与や賞与からは、所得税が天引き(源泉徴収)されています。この源泉所得税は、本来かかる税額よりやや多めに設定されています。また、生命保険料控除や地震保険料控除などは考慮されていません。 このため、年末に1年間の正しい課税所得額を計算し、天引きした所得税と精算する手続きをします。この手続きが年末調整です。 【参考】【2022年 年末調整】年末調整って何?経理初心者が知っておきたい基本をざっくり解説 確定申告 確定申告は、1年間のすべての所得額、控除額から正しい所得税の額を計算し、申告する手続きです。通常、翌年3月15日が期限となっています。このとき、年末調整と同じく、源泉徴収された所得税や先払いした所...
-
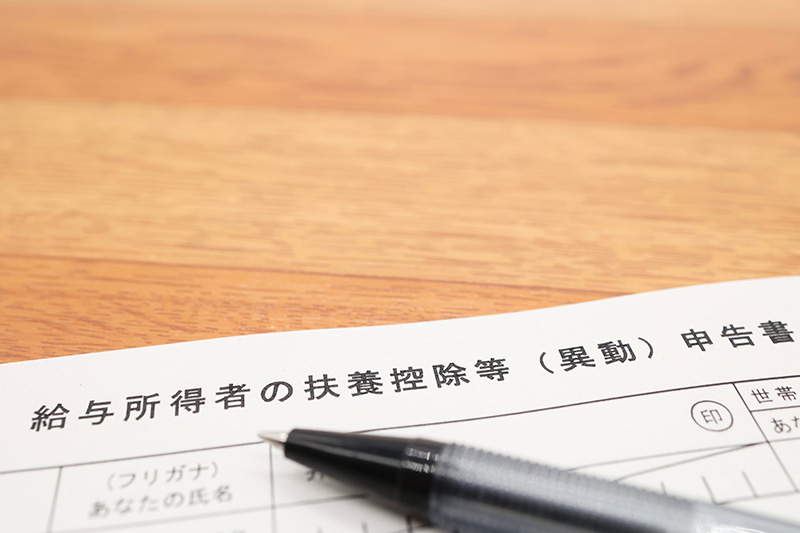
2022.07.29 税務ニュース
【2022年 年末調整】年末調整って何?経理初心者が知っておきたい基本をざっくり解説
11月になると、多くの企業や会計事務所がソワソワし始めます。経理になったばかりの方だと不思議に思うかもしれません。ソワソワの理由は「年末調整」です。 年末調整とは何でしょうか。なぜ会社が行うのでしょうか。今回は、経理1年目の方に向け、年末調整の基本をざっくり解説します。 年末調整とは何か 年末調整とは、給料や賞与から預かった所得税の合計額と、1年間の給与全体にかかる本来の所得税額とを比べ、その差額を精算する手続きをいいます。 会社の役員や従業員が受け取る役員報酬や給与・賞与は、決まった金額そのままを受け取るのではありません。社会保険料や所得税、住民税が源泉徴収(天引き)されています。支給されるのは、源泉徴収後の残額です。 源泉徴収される所得税は、扶養している家族の数と課税される給与額の額の2つだけで決めた概算額です。1年ベースで見た所得税を考えると、少し多めに徴収されています。 一方、1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる所得税は「年の途中で扶養する家族の数に変更があった」「住宅ローンを支払っている」「本人や家族が障害者である」といった事情を考慮した上で計算...
-

2022.04.26 税務ニュース
JA「建物更生共済」の保険料は年末調整で控除できる?所得税の扱いを確認しよう
地方の方が加入している損害保険で多いのが、JA(農業協同組合)が扱っている「建物更生共済(たてこう)」です。この共済は、一般的な損害保険とかなり違います。そのため、税法上の扱いも複雑です。今回は、加入している方に向け、年末調整や確定申告における建物更生共済の掛金の扱いを解説します。 建物更生共済とは何か 建物更生共済とは、JAが扱っている共済制度です。火災や台風、地震といった自然災害で建物や動産が損害を受けたときに備える損害保険ですが、他の民間企業の損害保険と異なり、次のような特徴があります。 すべてが掛け捨てとはならない 多くの損害保険は掛け捨て型ですが、建物更生共済は「一部掛け捨て、一部積立型」となっています。また、「建物更生共済むてきプラス『建物』」のように、全額積立 となっている商品もあります。そのため、共済金の受取は、火災などの共済事故が発生した時だけではありません。共済満期時に、満期共済金・満期時割戻金・据置割戻金が受け取れます。 「積立」のある損害保険だから課税がややこしい 積立部分があるため、税法上も他の民間の損害保険と同じようには扱えません。満期を迎えたら、一...
-

2021.11.15 税務ニュース
事業主・経理担当者必見!令和3年(2021年)の年末調整手続のチェックポイントを確認しましょう。
いよいよ年末調整の時期が近づきました。12月の調整計算に向け、すでに準備を始めている事業者の方々も多いと思います。すでに国税庁から2021年(令和3年)分の年調ソフト(Ver.2.0.0)もリリースされました。本年分については調整計算上の大きな変更点はありませんが、昨年から煩雑化した計算項目に対して、事業主は引き続き正確かつ効率的に調整を行うことが要求されています。 2021年(令和3年)分の変更点 年末調整申告書等(※)への押印義務が廃止されました! 年末調整申告書等(※)の電子化について税務署への承認申請が不要になりました! e-Taxによる申請等のイメージデータによる送信が可能になりました! ※「年末調整申告書等」とは、「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除申告書」、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」ならびに翌年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいいます(以下、同様)。 1. 様式の変更 (国税庁サイトより一部抜粋) 押印義務の廃止により、年末調整申告書等につ...
-
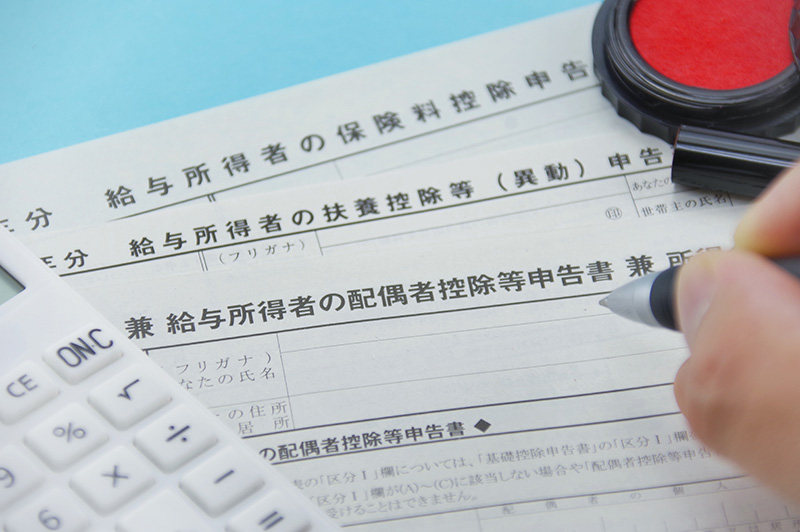
2021.09.30 税務ニュース
事業主×従業員 年末調整でやるべきことを両目線から解説します!
年末調整といえば、寒くなり始める頃から事務を進めるイメージです。しかしながらすでにご案内のとおりで、事業主(勤務先)および従業員双方にとってますます煩雑化した計算事務への対応に加え、手続を適切かつスムーズに進めるための電子化ツールの運用もあり、初冬あたりから準備を始めても早すぎるということはありません。2021年10月にも国税庁から令和3年度版「年調ソフト」が無償でリリースされますので、事務の電子化を含めて事業主・従業員ともに混乱することがないよう、ぜひともこの時期から地ならしをしていきましょう。 <年末調整手続の従来型と電子化型の違い> 手続の内容 従来型 電子化型 事業主 (勤務先) 控除額等のチェック 検算必要 検算不要 給与システムへの取込み 手書き書類より手入力 電子データをインポート 従業員 年末調整申告書類の作成 必要事項を手書き 自動入力(または手入力) 控除額等の計算 手計算 自動計算 (出所:国税庁「年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するFAQ」より一部抜粋) 年末調整の対象となる従業員の範...
-

2021.07.30 税務ニュース
2021年分の年末調整を適切に、スムーズに進めよう。-電子化による事務の効率化にレッツトライ!-
2020年分から大きく変わった年末調整計算事務。たくさんの変更点とその煩雑さの影響で、事務や計算の手続に戸惑い、混乱した事業者も多かったようです。2021年分以降、適切かつスムーズに進めていただくために、変更点と必要な手続きを早いうちからおさらいし、進捗管理をしつつ、電子化による事務の効率化にも取り組んでいきましょう。 年末調整の変更ポイントをおさらい 給与所得控除額の引き下げ・基礎控除額の見直し・所得金額調整控除の導入・ひとり親控除の新設・年末調整関係申告書様式の変更と追加など、詳しくは「2020年分 年末調整の変更ポイント」を参照してください。 必要な申告書の確認と手続の電子化 2020年分より年末調整関係申告書の種類が増えたことにより、従業員側の申告書作成・提出、事業主(勤務先)側の申告書収集・内容確認に、手間と時間がかかります。そのため事業主(勤務先)は、従業員に対して早いうちから要領の周知が必要です。また、年末調整は年の瀬の忙しい時期に行われることから、電子化を推進することで従業員と事業主(勤務先)双方の負担軽減につながります。 年末調整申告書の種類 控除の...









 トップ
トップ



![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)

