MENU


152件 61~80件を表示
-

2023.02.20 税務ニュース
あなたの知らない領収書の世界(インボイス編)
税理士は知っているけれども、一般の人には知られていない領収書をテーマにした「あなたの知らない領収書の世界」。読者の皆様のおかげで回数を重ねることができ、今回も取り上げていただくことになりました。読者の皆様には、大変、感謝しております。 さて、今回の領収書の世界は、インボイス制度が導入された後の世界についてです。しかし、インボイスの世界は、私たち税理士にとっても未知の世界です。そういう意味では、“だれも知らないインボイスの世界”ともいえるのです。 インボイス制度の簡単な内容 インボイス制度につきましては、新聞報道やネット上の記事でかなり詳しく取り上げられており、ここでは簡単な内容を見ていきます。インボイス制度は、令和5年10月1日より実際の取り扱いが始まります。今までの領収書、請求書と取り扱いが異なる部分がいくつかありますがそれは消費税の取り扱いに限られます。つまり、そのほかの取り扱いについては、従来のそれとは異ならないということを理解しておくとよいでしょう。 例えば、品物の料金を支払った際にもらった領収書は、インボイス発行事業者かどうかは関係なく、その代金を支払った証拠には...
-

2023.02.16 税務ニュース
【2023年度税制改正大綱】インボイスに緩和措置?「2割特例」「適格返還請求書」などを解説
2022年12月16日、2023年度税制改正大綱が発表されました。今回、個人事業主の注目を集めたのが「インボイス(適格請求書)」です。大綱発表前に報道された緩和措置が反映される形となりました。今回は、インボイス制度にかかわる改正を3つ、お伝えします。 インボイス制度の改正①:「2割特例」で負担が緩和 1つ目は、「2割特例」です。インボイス制度の開始とともに免税事業者から課税事業者になる事業者のために設けられました。 課税事業者になったときの消費税の計算方法は2つあります。1つは「本則課税」、もう1つは「簡易課税」です。 課税方式 納税額の計算方法 事業者の条件 証憑(仕入についての領収書等)の保存 還付の可能性 本則課税 実際に売上にかかった消費税から実際に支払った消費税を差し引く なし 必要 あり 簡易課税 「売上にかかった消費税-(売上にかかった消費税×みなし仕入率)」で計算 基準期間の課税売上高が5000万円以下 不要 なし 売上の少ない小規模事業者だと、簡易課税を選ぶことが多いです。「手間がかからなくてラク」という印象を持たれやすいからかもしれ...
-

2023.02.10 税務ニュース
【インボイスと家賃】もう準備はOK?口座振替、口座振込の家賃の場合はどう対応する?
2023年10月から始まる適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度。事業者の皆さまは、制度の理解から適格請求書発行事業者の登録申請、インボイス対応の請求書(領収書)の様式作成等の準備を着々と進められていることでしょう。取引先から登録番号を尋ねられるケースもありますね。 さて、今回はインボイス制度への対応の中で見落としがちなあるケースについてです。 インボイス制度への対応と言えば請求書の様式変更は既に対応済みもしくはこれから対応を予定されていると思いますが、実は口座振替や口座振込により事務所や店舗の家賃等を支払っている場合は留意が必要です。どのような点が問題となるのか、そして具体的にどのように対応するかについて本記事では解説していきます。 本記事が役立つ方 口座振替や口座振込により事務所や店舗の家賃の支払いをしている法人、個人事業主 口座振替や口座振込により事務所や店舗の家賃を受け取っている不動産事業者 不動産賃貸管理会社 など 1.インボイス制度の概要 まず、消費税の基本的な仕組みについてです。消費税は原則として売上げに係る消費税額から仕入れや経費に係る...
-

2023.02.07 中小企業おすすめ情報
インボイスは見送っていい? 対応すべき? 基本を学んで賢く対応しよう
10月から仕入れ税額控除を受けるためにインボイスが必要になる インボイス制度が2023年10月1日からスタートします。インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことで、仕入税額控除の要件としてインボイス(適格請求書)の保存が必要になるのが特徴です。中小企業や個人事業主がこのインボイスに対応するかどうかが今話題になっています。会社員は基本的に意識する必要はないのですが、副業をしている人にはやはり関わってきます。 インボイスのことを理解するには、まずざっくりと消費税の仕組みを把握しておく必要があります。例えば、ビジネスで100万円を売り上げた場合、顧客から消費税10万円を預かります。「預かった」と言うのは、消費税は国に納めるからです。顧客から預かった消費税を代わりに納税する必要があるのです。 しかし、100万円を売り上げるために、30万円の仕入れをしている場合、この30万円の消費税3万円は仕入れ先に支払っています。そのため、全体で納税すべき10万円から3万円を控除できます。この仕組みを仕入税額控除と言います。 これまでは、帳簿の保存のみで控除を受けられていたのですが、10月以...
-

2023.01.30 税務ニュース
小規模事業者の税負担が「売上税額の20%」に。インボイス制度に2つの負担軽減措置。
2022年12月16日、2023年度(令和5年度)与党税制改正大綱が公表されました。そのなかでも事業者にとって気になるのは、インボイス制度に関するトピックではないでしょうか? 本コラムでは、与党税制改正大綱で盛り込まれた小規模事業者を対象とするインボイス制度の2つの負担軽減措置について、やさしく解説します。 インボイス制度に2つの負担軽減措置 業界団体などから反対声明が発表され、フリーランス団体が反対運動を行うなど、漫画、アニメ、声優などのエンターテインメント業界で特に反響が大きかったインボイス制度。インボイス制度の導入により影響を受けるのは、企業から仕事を請け負うクリエイターなど、主に個人事業主・フリーランス・スモールビジネスなどの小規模事業者といわれています。 インボイス制度は予定どおり2023年10月1日からスタートしますが、新しい制度への移行にあたって混乱が生じないように、以下の2つの負担軽減措置が設けられる予定です。 ① インボイス発行事業者となる免税事業者に対する納税額の負担軽減措置(2割特例) ② 中小事業者に対する事務負担軽減(少額特例) 消費税の税負担が「...
-

2023.01.25 中小企業おすすめ情報
経理処理を効率化! 法人カードのメリットや導入時の注意点を解説
クレジットカードには個人の一般消費者向けに発行されているカード以外にも、企業や個人事業主が事業のために利用できる「法人カード」があります。ここでは経理事務の削減や資金繰りにも役に立つ法人カードの特徴を解説していきます。 事業の経費を支払うためのクレジットカード 法人カードとは企業などの法人や、個人事業主に対して発行されるクレジットカードです。基本的には、法人の代表者や個人事業主がクレジットカードの発行企業に申し込みを行い、カードの契約者となることで利用できます。 法人カードは、主に事業に関する経費を支払う目的で使用され、個人向けカードより利用限度額が大きい傾向があります。加えて特徴的なのが、契約した代表者だけではなく、従業員が利用するためのカードも複数枚発行できる点です。 また、個人向けのクレジットカードとは異なり、代金の引き落とし先として、法人が名義人となる銀行口座(法人口座)を指定することもできます。これにより、多数の従業員が複数枚の法人カードで支払いを行ったとしても、支払い元を1つの法人口座とすることが可能なのです。 経費精算や会計処理の手間を減らせる 企業などの法人...
-

2023.01.23 税務ニュース
給与のデジタル払いと税金のスマホアプリ納付が解禁。メリットとデメリットについて解説。
「給与のデジタル払い」が2023年4月に解禁されます。今までは給与を銀行振込で受け取るのが一般的でしたが、今後はどのような点に注意すべきでしょうか。 コラムでは、キャッシュレス化に伴って広がる選択肢とその課題について、2022年12月1日からスタートした「税金のスマホアプリ納付」とあわせて、やさしく解説します。 「給与のデジタル払い」ってなんですか? 「給与のデジタル払い(デジタルペイロール)」とは、給与をスマートフォンの決済アプリや電子マネーを利用して支払うことをいいます。銀行口座を介さずに、給与を資金移動業者が管理するキャッシュレス決済口座へデジタル情報として送金します。キャッシュレス決済口座の代表的なものには、PayPay、LINE Pay、楽天Pay、PayPalなどがあります。 給与は、通貨(現金)払いが「原則」です。 給与の支払方法には、「賃金支払いの5原則」と呼ばれる法律のルールがあり、給与を支払う側はこの原則を守る義務があります。労働基準法第24条では、賃金は、①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上の頻度で、⑤一定期日を定めて支払わなければならな...
-

2023.01.19 税務ニュース
税金、似た用語多過ぎ問題-インボイス編
入り乱れる用語 どうにも税金にまつわる用語には、似た用語が多く分かり難いです。試しに、消費税制について、正確性に全振りして分かり易さを完全放棄した文章で説明してみます。読み難すぎて、むしろ面白い文章になりました。 「令和5年10月1日よりインボイス制度がスタートします。これ以後、売り手である適格請求書発行事業者には適格請求書の発行義務が法律に規定され、買い手は適格請求書等を保存しなければ仕入税額控除が出来なくなります。仕入税額控除は、従来、請求書等保存方式が採用されていたところ、軽減税率の導入により区分記載請求書等保存方式へと変更され、インボイス制度開始以後は、適格請求書等保存方式となります。」 この、知っている人にしか通じない文章の中に、請求書という言葉が4種類登場しています。そして、面倒なことに4種類とも少しずつ意味が違います。現実問題としては、用語が多少交錯していてもやるべきことだけ押さえておけば困ることはないです。とは言え、よく分からない単語を使い続けるのも気持ちの良いものでもないので、今回はインボイス制度にまつわる用語を整理し、何故巷をこれだけ大騒ぎさせているのか改めて...
-

2022.12.20 社会保険ワンポイントコラム
はじめての給与計算ソフト導入 押さえておくべきポイントは?
はじめに 今日はソリマチ給料王の認定インストラクター「SOI(Sorimachi Official Instructor)」である私が、はじめて自社で給与計算を行うお客様に対し日頃行っているサポートの流れに沿って、給与計算ソフト導入の際の押さえておくべきポイントについてご説明します。 給与計算ってどうやってやるの? 給与計算のやり方にもいろいろあります。やり方は大きく以下の3つです。 ① 手書きで行う。 ② Excelで行う。 ③ 給与計算ソフトを導入する。 ① 手書きで行う これが最も安価でお金をかけない方法です。それこそ100円ショップで売っているような複写式の給与明細書に手書きで記入する方法です。パソコンの知識も必要ありません。従業員が時給のアルバイト数名程度しかいないようなケースではこのやり方も有効です。給与から天引きするのは所得税と、あっても雇用保険料(週20時間以上の勤務の場合)ぐらいですので、給与計算も比較的シンプルです。 ただし、社会保険に入り始めると途端に給与計算が複雑化します。個人事業でアルバイト従業員が1名~4名程度の小規模事業者向きです。 ② Excel...
-

2022.12.14 税務ニュース
クリニックが今取り組むべきDXとは?収益プロセスと人件費プロセスの重要性
新型コロナ・ウイルス感染症のパンデミック以降、我が国のクリニック(無床診療所)は、コロナ対策が徹底されたことで季節性感染症や風邪の発生が例年に比べて大幅に減少したことが響いたり、学校の休校や部活動の自粛でスポーツでのケガによる受診が減ったほか、外出自粛の影響で交通事故などによる外傷の受診も減少しています。結果的に、帝国データバンクが示しているように、実に8割のクリニックがコロナ前に比べて減収しているようです。 また、従来から問題視されている通り、2021年2月5日の医療制度改革関連法案の決定による2025年からの後期高齢者の医療費窓口負担の増加に端を発し、全世代の患者さんの医療費負担の増加→家計負担の増加→受診控え→クリニックの減収という予測される負のスパイラル(いわゆる2025年問題)への対応が急がれています。 今回はそのような環境変化において、クリニックがどのようにDXを試みるべきか、検討していきたいと思います。 クリニックの基本的なビジネス はじめに、クリニックの基本的なビジネスプロセスについて整理をしておきます。クリニックは、診療科や医薬処方の有無などの個別差はある...
-

2022.12.12 IT・ガジェット情報
【家電ライターが解説】月に1週間以上は出張にでる筆者がオススメ!ビジネスに便利なデジタルツール厳選5点!
筆者は地方の工場に呼ばれて取材記事を書いたり、地方局に行ってテレビ番組に出させてもらったりしています。そのため多いときでは3週間連続、少なくても月のうち1週間は出張という生活をしています。また原稿はたいてい急かされるので、移動中の電車内やホテルなどで執筆して、写真や映像も添えて編集部にデータを送っています。 そこで筆者の出張用バッグに入っている厳選した5つのツールをご紹介します。 先方のテレビやプロジェクタが映らないのは日常!それを回避するモバイルプロジェクタ 営業職をはじめ先方にプレゼンをする機会が多い方に断然オススメなのがモバイルプロジェクタです。ノートパソコンを見せながらのプレゼンは、昨今のアクリル板や密を避ける環境で難しくなっています。かと言ってプレゼン資料を印刷して配布してしまうと、先方は紙ばかり見てしまい、自分に注目して大事なことを言おうとしても俯いたままなんてよくあります。 また営業職の多くの方が体験しているように、先方のテレビやプロジェクターを借りると、映像が写らなかったり、音がでなかったりというのは日常茶飯事(笑い)。これではプレゼンする前から先方を飽きさ...
-

2022.12.08 税務ニュース
インボイス制度に対応した領収証の書き方・記載例~小売業、飲食店業など領収証でインボイス制度に対応する方法~
2023年(令和5年)10月1日から始まるインボイス制度。インボイス制度は「適格請求書等保存方式」と言い、インボイスは別名「適格請求書」と言います。その名称から、インボイス=請求書という印象が強く、小売業や飲食店業など普段請求書ではなく、領収証を発行している事業者の中には、「請求書でないとインボイスに対応できない?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。 本記事では、普段請求書ではなく領収証を発行されている事業者の方、請求書ではなく領収証を受け取る課税事業者の方へ向けて、インボイス制度開始後におけるインボイス制度対応の領収証について解説していきます。 1.インボイスとは何か?手書き領収証でもインボイスとして認められるか? インボイスとは、前述の通り「適格請求書」のことです。では、「適格請求書」とは何でしょうか。国税庁では、適格請求書を次のように定義しています。 適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。そして、請求書や納...
-

2022.12.05 IT・ガジェット情報
2025年以降、DX化を推進しない企業が生き残っていくのは難しい時代になる
日本企業のDXが進まないと、2025年以降は毎年12兆円の経済損失が生じる 経済産業省は2018年に「DX(デジタルトランスフォーメーション)レポート」を発表し、これまでの非効率なビジネスのやりかたを続けた場合、2025年以降に毎年最大12兆円の経済損失が生じると予測しました。これを「2025年の崖」と呼び、経営者の中でも「DX」という言葉がバズりました。 経済産業省は企業が自己診断できる「DX推進指標」を2019年に策定したところ、日本のDXは諸外国と比べ想定以上に遅れていることがわかりました。その後コロナ禍に突入し、テレワークやビデオ会議などが普及しIT化が進んだように見えたのですが、2020年の自己診断でも9割以上の企業がDXに未着手でした。 [caption id="attachment_11017" align="aligncenter" width="1372"] DX推進指標自己診断結果。グラフは「DXレポート2」より[/caption] 2020年に経済産業省が発表した「デジタルガバナンス・コード2.0」ではDX化を推進するため、経営者に求め...
-

2022.11.11 税務ニュース
準備は早ければ早いほどよい!今の時期から令和4年分「確定申告」の準備をしよう!
今年も残すところあとわずか。“今年分の確定申告はまだ先のこと”と考えていると、忙しい年末年始を過ごしているとあっという間に時が過ぎ、結局は間際に準備に取り掛かるという慌ただしい事態を招いてしまいます。差し迫った状況では適正な申告もおぼつかなくなるため、早い時期から改正項目をチェックし、計算に必要な知識・データ・書類を整えるようにしましょう。 準備は早ければ早いほどよい! 個人事業主や一定の条件に当てはまる方に義務がある所得税の確定申告。そして義務はなくても所得税の還付が受けられるため申告したほうがよい還付申告。特にお勤めの方は、勤務先が「年末調整」を行ってくれるので原則的には確定申告不要ですが、副業所得があるなど確定申告をしなければならないケースもあります。 確定申告の期間は周知のとおりで2月16日から3月15日です。納税が必要な場合も原則3月15日までに納めます。一見すると作業時間にゆとりがあるように感じるかもしれませんが、実際には申告に必要な書類を事前に取得・管理しておく必要があるため、準備はできる限り早い時期から始めるほうがいいでしょう。 必要書類は申告内容によってさ...
-

2022.10.28 社会保険ワンポイントコラム
2022年10月から社会保険の給付金受け取りが簡単に!?「公金受取口座登録制度」とは
公金受取口座登録制度という仕組みをご存じだろうか。2022年10月からはこの制度を利用し、健康保険の傷病手当金や雇用保険の育児休業給付金などの受け取りが可能になっている。そこで今回は、公金受取口座登録制度を利用した社会保険の給付金受け取りについて見てみよう。 公金受取口座の利用で給付金の申請が簡便に 公金受取口座登録制度とは公的な給付金などの受け取りに使用する目的で、自身の預金口座をマイナンバーと一緒にデジタル庁に事前登録する制度である。登録した口座を公金受取口座と呼び、給付金申請時に同口座への振り込みを指定することで、申請書への預金口座の記載や預金通帳のコピーの添付などが不要になる。そのため、従前よりも申請手続きが簡便になり、迅速な支払いを受けられるとされている。 公金受取口座での給付金の受け取りは、2022年10月以降、準備が整った団体から順次開始することとされていた。そのため、労災保険、雇用保険及び健保組合が運営する健康保険の給付については2022年10月11日から、厚生年金保険の給付ついては2022年10月31日から公金受取口座での受け取りが可能になっている。 ただ...
-
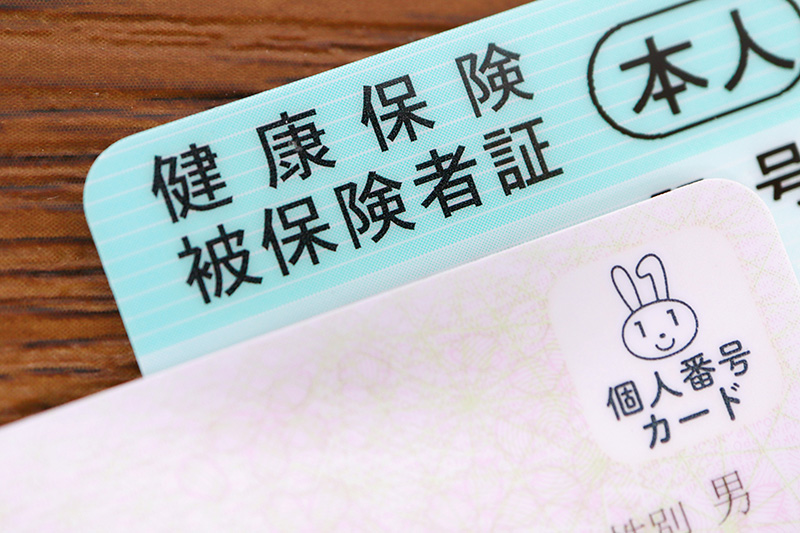
2022.10.26 社会保険ワンポイントコラム
2024年秋、健康保険証がマイナンバーカードに!知っておきたいメリット・デメリット
河野デジタル相は10月13日、記者会見にて「現在の健康保険証を廃止し、マイナカードと一体化した『マイナ保険証』を原則とする」という政府の方針を発表しました。2024年秋以降、病院での診療や薬局での薬の購入は原則、健康保険証と一体化したマイナンバーカードで行われることになります。現行の健康保険証は使えなくなるのです。 マイナンバーカード一体化の背景 健康保険証とマイナンバーカードの一体化を言い換えると「マイナンバーカード所持の義務化」です。日本は国民皆保険制度を採用しており、健康保険への加入は義務付けられています。加入の事実を示すのが健康保険証なのですが、「健康保険証=マイナンバーカード」になれば、健康保険に加入している人全員、マイナンバーカードを持つ必要が生じるのです。 なぜ政府は、このような方針を打ち出したのでしょうか。背景には次の2つがあります。 ポイント事業をしても取得率が50%未満 1つ目の理由は「マイナンバーカードがなかなか普及しないから」です。2016年1月にマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がスタート、同時にマイナンバーカードの交付が始まりました。6年超が...
-

2022.10.21 税務ニュース
電子インボイスは義務化される?電子インボイスと消費税インボイス制度の関係と今後の課題について解説。
2023年10月からスタートする消費税インボイス制度への移行が迫る中、電子インボイス(デジタルインボイス)への関心が高まっています。 本コラムでは、事業者のバックオフィス業務の効率化や生産性の向上を図る観点から普及が進められている電子インボイスのしくみや今後の課題について、やさしく解説します。 電子インボイス導入のきっかけ 電子インボイス導入のきっかけはコロナ禍といわれています。 新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大により、リモートワーク環境での請求業務への対応が課題になりました。これを契機にデジタル化(Digitalization)の必要性が認識され、官民連携のもと電子インボイス導入に向けての取組みがはじまりました。 2020年7月、会計・業務システムベンダーなどの民間が中心となり電子インボイス推進協議会(EIPA:E-Invoice Promotion Association、現「デジタルインボイス推進協議会」)が設立されました。2021年9月のデジタル庁の発足を経て、標準化された電子インボイスの普及を図るフェーズに至っています。現在は、2023年10月に開...
-

2022.10.20 税務ニュース
節電ポイントやマイナポイントには税金がかかる?ポイントと税金の関係について解説。
ポイントをもらったり使ったりした場合、税金がかかるのでしょうか? 本コラムでは、企業ポイントと税金の関係について、やさしく解説します。 ポイントと税金の関係は「値引き」かどうかで判断 近年の電力不足問題の深刻化を受けて「節電ポイント」の導入が進められています。 電力需要の逼迫が懸念されるため、各家庭に節電を促すのが目的です。電力会社が開催する節電キャンペーンや省エネプログラムに参加し、その内容に応じて節電ポイントが付与されます。 政府が実施する「ポイント政策」は、ほかにマイナポイントや消費税の増税に伴うキャッシュレス決済のポイント還元などが記憶に新しいところです。 この「ポイント」には税金がかかるのでしょうか? その判断の要点は「値引き」かどうかです。 この点について、国税庁は、個人が商品を購入するときに付与されるポイントで、「通常の商取引における値引き」と同様の行為が行われたものと考えられる場合には、所得税の課税対象にならないものとして取り扱うと説明しています。 マイナポイントや節電ポイントは「通常の商取引における値引き」とは同視できないため、課税対象になるのです。 ...
-

2022.10.12 農家おすすめ情報
明解!農業者はじめ取引先事業者へ!消費税インボイス経過措置・独占禁止法等
消費税インボイス登録に関する経過措置の適用期間延長 2023年10月1日にスタートするインボイス制度、2022年4月に消費税法等の一部が改正された。今回、農業版消費税インボイス制度について、農業者側は法改正された部分及び取引する事業会社側は独占禁止法等について解説するのでぜひ参考にしていただきたい。これから消費税インボイスの準備を検討している方は以前の記事と合わせて確認してほしい。記事の記載にあたり国税庁及び財務省の公表資料をもとにわかりやすく説明している部分は、著者の個人的な見解も含むことをあらかじめお断りする。 インボイス発行事業者の登録については、農業者(免税事業者)が、2023年10月1日の属する課税期間中にインボイス発行事業者の登録を受けた場合は、登録を受けた日からインボイス発行事業者となることができる経過措置が設けられているが、当該経過措置の適用期間が延長され、2023年10月1日から2029年9月30日までの日の属する課税期間においても、登録を受けた日からインボイス発行事業者となることができることとなった。 経過措置とは 従来の法律から新しい法律に移行する際に、不...
-

2022.10.03 税務ニュース
あと1年で開始のインボイス…「持続化補助金」「IT導入補助金」を活用しよう
インボイスの開始まで1年を切りました。制度に対応するにはお金がかかります。「免税事業者から課税事業者になると、納税負担が増える」だけではありません。請求書や領収書の様式を変えなくてはならないのです。この2つの変化に対応すべく、2つの補助金制度にインボイス枠が設けられました。 インボイスで変わるのは「仕入税額控除」 「インボイス、インボイス」と言いますが、始まると何が大変になるのでしょうか。実はインボイスが始まると、いろいろとコストが増えるのです。コストが増える原因は「仕入税額控除」にあります。 仕入税額控除は条件つき 仕入税額控除とは、納める消費税を計算するときの「支払消費税を差し引く」ことをいいます。次の図の黄色の部分です。この仕入税額控除に、インボイスが大きく影響します。 仕入税額控除は、何もしないでできるわけではありません。次の2つを守らないといけないのです。 帳簿と請求書等(請求書や領収書など)を保存すること 1の帳簿と請求書等には税法に定めた一定事項が書かれていること 帳簿に書かれていても請求書等が捨てられていたら、仕入税額控除はできません。請求...









 トップ
トップ



![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)

