MENU


78件 61~78件を表示
-

2022.05.30 税務ニュース
小規模事業者がインボイス事業者に登録する際の申請書の書き方を解説
2023年10月から日本版インボイス制度がスタートすると、個人事業主/フリーランスなどの小規模な事業者であっても、インボイス事業者への登録が必要になるケースが出てきます。しかし、小規模な事業者の場合、税理士と顧問契約を結んでいない人も多く、登録申請書の書き方がわからないとお悩みの方もいるのではないでしょうか? 本コラムでは、現時点で免税事業者に該当する個人事業主/フリーランスの人向けに、インボイス事業者に登録するために必要な申請書の書き方を、具体例を使ってやさしく解説していきます。 インボイスとは インボイス(invoice)とは、一般的に、英語で「商品の明細が付いた請求書」を意味します。日本のインボイス制度では「適格請求書」という言葉が用いられています。 このインボイスは、8%や10%などの複数税率のもとで、請求書のどの明細にどれだけの消費税がかかっているかについて、インボイスを発行する側(売手)・インボイスを受け取る側(買手)・税務署の誰が見てもわかるようにする手段として導入されました。 インボイス事業者登録の申請が必要 インボイスを発行するためには、インボイス事業者(...
-

2022.05.18 税務ニュース
請求書から理解するインボイス制度—クリエイターなどの個人事業主・フリーランスへの影響は? —
1. インボイス制度理解のポイントは? インボイス制度が始まると、個人事業主やフリーランスで、今まで消費税が免税とされてきた人にも影響はあるのでしょうか? インボイス制度は「適格請求書等保存方式」といい、消費税に関する制度です。この制度を理解するポイントは「請求書」にあります。 取引先に対する請求書の発行は、個人事業主やフリーランスにとって欠かすことのできない業務のひとつですよね。身近な存在である請求書から、消費税の仕組みとインボイス制度による影響を紐解いてみましょう。 2. 請求書の基本的な形式をおさらい まず、一般的な請求書の記載項目についておさらいしましょう。以下の図表1の左側をご覧ください。もしあなたがフリーランスのクリエイターである場合には、図表1の右側のように、源泉所得税の金額も記載するケースが多いでしょう。 3. 消費税の免税事業者 次に、図表1の請求書の記載項目のうち、消費税に関する項目に着目してみましょう。個人事業主やフリーランスであっても、事業として継続的に売上があれば、原則として消費税を国に納めなければなりません。しかし、現行制度では消費税の免税事業者...
-

2022.04.25 税務ニュース
【NPO法人とインボイス制度】対応を考える上でのポイントを解説
ご存知の方も多いと思いますが、令和5(2023)年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」)がスタートします。インボイス制度の下では、適格請求書発行事業者として登録されていない取引先への支払いは仕入税額控除が認められません。(制度導入から6年間は経過措置あり) NPO法人は消費税の免税事業者も多いため、インボイス制度への対応に苦慮している法人も少なくないでしょう。今回はインボイス制度の概要と適格請求書発行事業者に登録をすべきかの判断材料を整理したいと思います。 特に注意すべきNPO法人 株式会社などの営利企業には税務署からの郵送物や顧問税理士などからインボイス制度について周知が進められているところです。ただ、NPO法人は収益事業課税のため、収益事業を行っておらず基準期間の課税売上高が1000万円以下の団体は法人税・消費税ともに確定申告義務がありません。このような団体は税務署や税理士との接点が少ないため、インボイス制度に関する情報もあまり入っていない可能性があります。 このような収益事業を行っていない小規模のNPO法人にも関わる制度改正ですので、情報...
-

2022.04.18 税務ニュース
インボイス制度で美容師の収入は変わるのか?~業務委託美容師と業務委託サロンの場合~
みなさま、こんにちは。税理士の脇田です。最近よく耳にする「インボイス制度」。来年の10月から始まります。インボイスって登録した方がいいのかしない方がいいのか、しないといけないものなのかしなくてもいいのか…?徹底解説していきます! 消費税の仕組み 消費税を負担するのは消費者ですが、実際に税務署に納付するのは事業者です。これを読んでいるあなたは、消費者でもあり、事業者でもあるので混乱するかもしれません。 例えば、あなたがスーパーで家庭の夕飯の買い物をしているときは「消費者」、事業のための文具を買うときには「事業者」の立場です。スーパーでの買い物では消費税を払い、その負担もします。つまり、払いっぱなしです。事業のために文具を買うときには消費税を払っても(「事業者なんで払いません!」と言うわけにはいかないのでいったん払う)、それを負担する必要はありません。その分の消費税はあとで返してもらえるのです。 一方、事業で売上げた時にもらう消費税は、あとで税務署に納めることになります。結論から言うと、原則はこのようになります。 事業者が納める消費税 ...
-

2022.03.11 農家おすすめ情報
農業者必見!消費税インボイス制度が農家にもたらす影響を徹底解説!
農業者必見!消費税インボイス制度とは? 農家の方は「インボイス」という言葉を頻繁に耳にするのでは?2019年10月の複数税率導入に次ぐ消費税の新しい制度(インボイス制度)が2023年10月にスタートする。農家の方は自分には関係ないと思っている方が多いようなので、本稿を読んで少しでも参考にしていただきたい。記事の記載にあたり国税庁及び農林水産省の公表資料をもとに農家の方にわかりやすく説明している部分は、著者の個人的な見解も含むことをあらかじめお断りする。 なぜ今、農業者の消費税インボイス制度が重要か? 2023年10月1日から消費税のインボイス制度が実施される。インボイス制度は全国の農業者に一番影響があると言われているのはなぜなのか?農林業センサスによると販売農家103万戸の約9割が売上1,000万円以下の免税事業者なのでインパクトが大きいことがわかる。これまで所得税の申告のみで済んだがインボイス導入で消費税の申告納税が必要になる農家が増えるのではないかと話題だ。 農業者のインボイス制度が実務に与える影響 複数税率の影響 2019年10月から複数税率導入(標準税率1...
-

2022.03.03 税務ニュース
【とにかく早いうちに登録申請書の提出を】備えあれば憂いなし!今から始める「インボイス制度」への対応
消費税の実務について、インボイス制度と呼ばれる「適格請求書等保存方式」が2023年(令和5年)10月からスタートします。当制度は必ず適格請求書発行事業者登録をすることが前提となっており、すでに事業者登録の申請が受け付けられています。 <インボイス制度 事前準備の留意点> とにかく早いうちに登録申請書の提出を! 売り手事業者としてインボイス交付に対応できる体制づくりを! 買い手事業者は継続的な取引先に事業者登録やインボイス交付方法などの事前確認を! 申請から登録までのイメージ 登録を申請できるのは、消費税の課税事業者のみです。ただし、免税事業者であっても登録を受けようとする課税期間において課税事業者となるときは、申請書を提出できます。 『適格請求書発行事業者の登録申請書』の提出はe-Taxの利用が推奨されていますが、郵送でも可能です。郵送の場合の宛先は、各国税局の「インボイス登録センター」となります。 付与される登録番号は、法人の場合は既存の「法人番号」、個人の場合は登録センターが定めた13桁の番号となり、必ずアルファベット“T”の文字が接頭さ...
-

2022.03.01 税務ニュース
副業収入が減る??事業者も会社員も必見!副業による「インボイス制度」の影響について詳しく解説!
副業解禁・副業推進のニュースが当たり前にみられる時代になりました。今回は、2023年10月から始まるインボイス制度が及ぼす副業をされている方への影響を解説していきます。 この記事を読むと以下が分かるようになります。 インボイス制度が始まると、副業に影響があるのか?売上が減少するかも・・と言われている理由 副業の方のインボイス制度への対策 インボイス制度の概要 https://revision.sorimachi.biz/taxnews/20210927_01 https://revision.sorimachi.biz/taxnews/20210811_01 2023年10月1日(令和5年10月1日)から「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が導入されます。今回は、副業の方に、インボイス制度がどのように影響があるのかを中心にお話しますので、制度の詳細については、大枠を説明させて頂きます。 インボイス制度とは「企業と企業(または個人)の取引における消費税額や適用税率を正確に把握することを目的とした制度」で、消費税の仕入税額控除を受ける際に「適格請求書(...
-

2022.02.06 税務ニュース
電子帳簿保存法とインボイスが変わった?個人事業主が注意すべき令和4年度税制改正3つを確認
昨年12月、与党税制調査会が令和4年度税制改正大綱を発表しました。会計業界がもっとも注目したのは「電子帳簿保存法」と「インボイス」です。また、簿外経費の扱いも厳しくなりました。今回は、この3つに焦点を当て、個人事業主向けに税制改正のポイントをお伝えします。 改正1:電子帳簿保存法は2年猶予に 令和3年度税制改正を受け、今年1月から新たな電子帳簿保存法が施行されました。改正前の電子帳簿保存法は「事前に税務署の承認が必要」など、厳しい条件だらけでした。しかし、今年から事前承認が不要になるなどで使いやすくなったのです。現在、会計ソフトのデータのままで総勘定元帳などの帳簿を保存しても、所得税や法人税でいう「帳簿等の保存」として認められます。 ただ、一つだけ面倒が増えました。「電子取引データの保存」です。メールでもらった請求書やウェブサイトからダウンロードした明細書は、紙ではなく電子データのまま保存しなくてはなりません。「取引年月日・取引金額・取引先名」で検索したら、すぐに出てくるようにしておく必要もあります。これを守らないと「帳簿等の保存」をしていると認められず、青色申告の承認が取り...
-

2022.01.21 みんなの経営応援通信編集部
【DXの基礎知識】これからどうなる!?インボイス制度、早わかり!
令和5年10月1日から導入されるインボイス制度について、どの程度ご存じでしょうか?まだまだ先の話と思っていませんか? 実は、インボイス制度に欠かせない「適格請求書発行事業者」登録の受付が、令和3年10月1日より開始されます。そろそろ準備を始めても良い頃合いなのです。 (2021年)令和3年 10月 適格請求書発行事業者の登録申請書受付開始 (2023年)令和5年 10月 インボイス制度開始 免税事業者からの仕入税額控除の特例(80%控除) (2026年)令和8年 10月 免税事業者からの仕入税額控除の特例(50%控除) 名前を聞いたことはあるけど、どういう制度なのかよくわからない、そもそも聞いたことがない、という方も、ご安心ください。インボイスとはいったい何か、導入されたら何が起こるのか、以下でわかりやすく解説していきます。 インボイスって何だろう? インボイスという単語は、英語で「請求書(invoice)」という意味です。つまり、「インボイス制度」は請求書に...
-
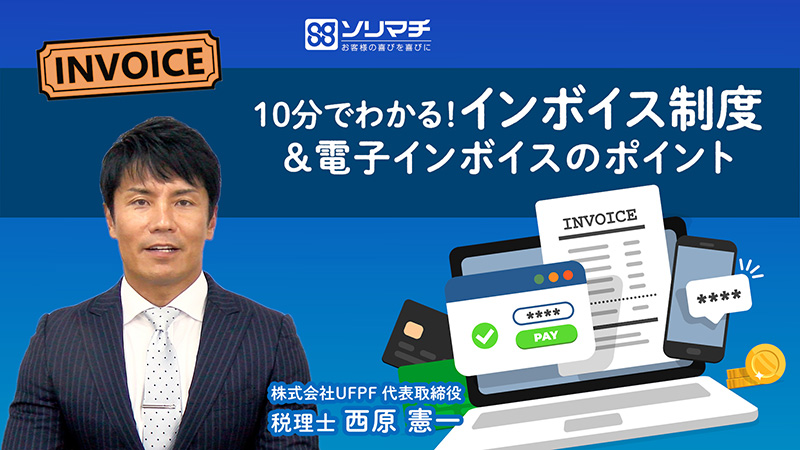
2021.11.04 見逃し配信
《解説動画》10分でわかる!インボイス制度&電子インボイスのポイント
インボイス制度とは何か? 具体的な対応方法は?登録事業者になるには? 人気税理士 西原 憲一 先生がインボイス制度をまるっと解説! [template id="4604"] [democracy id="152"]
-

2021.10.14 見逃し配信
《解説動画》知らなきゃヤバいことに!インボイス制度の導入と運用について丁寧に解説
今回は税理士の西原 憲一先生をお招きし、2021年10月1日に登録事業者の申請受付が始まったインボイス制度をテーマにお話いただきました。インボイス制度が導入されたらどうなるのか、導入に向けての準備や運用のポイント等を解説していただき、生放送中はたくさんの質問が寄せられました。ぜひこの機会にご覧ください。 《解説動画》知らなきゃヤバいことに!インボイス制度の導入と運用について丁寧に解説 放送日:2021年10月11日(月) 講 師:株式会社UFPF 代表取締役 税理士 西原 憲一 先生 ■インボイスの導入 ・消費税 申告計算の基本的なしくみ ・消費税の負担と納付 ・「インボイス」って? ・「インボイス制度」って? ・買い手が「インボイス」を保存しなければ? ・請求書 記載項目の制度別比較 ・「インボイス(適格請求書)」のイメージ ・「インボイス制度」の導入スケジュール ・申請から登録までの流れ ・免税事業者が登録事業者になるには? ■インボイス制度の運用 ・免税事業者が売り手となる場合 ・仕入税額控除の経過措置 ・「インボイス」発行義務の免除 ・運用面の素朴な...
-

2021.09.27 税務ニュース
2021年10月1日「インボイス制度」登録申請が始まります。いまいちど要点をチェックしましょう。
2021年10月1日から登録申請が始まる「インボイス制度」について『みんなの経営応援通信』ではさまざまな角度からお伝えしてきました。今回はこれまでの記事を一覧にまとめましたので是非ご確認ください。 令和5年10月1日からの適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応するためには予め適格請求書発行事業者になっておく必要があります。当該の事業者になるための登録申請受付が令和3年10月1日(金)より国税庁Webサイトにて開始されます。 インボイス制度コラム 免税事業者が気になるインボイス制度…簡易課税を選べば節税できる? インボイス発行のために課税事業者になる場合、「簡易課税制度」を選べば節税になるかもしれません。簡易課税制度とは何か、どうやって利用すればよいのか、などをお伝えします。 https://revision.sorimachi.biz/taxnews/20211010 〔免税事業者むけ〕10月1日に登録始まる「インボイス制度」なぜ必要?準備もわかりやすく解説 「インボイスでどうなるの?」「何を準備すべき?」そんな不安を持つ方に向けて、インボ...
-

2021.09.24 税務ニュース
免税事業者が気になるインボイス制度…簡易課税を選べば節税できる?
インボイス制度の登録申請が今年10月から始まります。多くの免税事業者の方は「どうしようか」と迷っていることでしょう。インボイスを発行するには消費税を納めなくてはならないからです。ただ、簡易課税を利用すれば少し節税できるかもしれません。 インボイスを発行するなら課税事業者にならないといけない 最初にインボイス制度の内容と条件を確認しましょう。 インボイスは「課税事業者であることの証明」 インボイス制度は「課税事業者であることを請求書や領収書で証明する制度」です。インボイスは英語で「明細付き請求書」を意味しますが、制度上は「必要事項が書かれた請求書や領収書、納品書など」を指します。税法では「適格請求書」と呼びます。 以前の記事に書いた通り、令和5年10月1日以降、請求書や領収書に必要事項すべてが書かれていないと、受け取った側は支払った分の消費税を預かり分の消費税から差し引けなくなるのです。 【引用元】適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために(国税庁) 注目すべきは①の「登録番号」です。今年の10月1日以降に申請すれば付与されますが、誰でももらえるわけではあり...
-

2021.08.09 税務ニュース
〔免税事業者むけ〕10月1日に登録始まる「インボイス制度」なぜ必要?準備もわかりやすく解説
インボイス制度の登録申請が今年の10月1日から始まります。本格的な開始は2年後に迫りました。「インボイスでどうなるの?」「何を準備すべき?」今回はそんな不安を持つ方に向けてイチから解説します。 インボイス制度の意味と目的 最初にインボイス制度の意味と目的を確認しましょう。 インボイス制度とは何か インボイス制度は正式名称を「適格請求書保存方式」といい、消費税の税率や税額が記載された請求書等を発行する制度です。インボイスは「適格請求書等」を意味します。消費税の詳細が書かれたインボイスは「仕入先が消費税を納めていることの証明書」となるわけです。 インボイス制度の目的は「益税問題の解消」 なぜ、インボイス制度が始まるのでしょうか。この制度の目的は、日本の消費税制度がこれまで抱えてきた「益税問題」の解消にあります。 平成元年4月1日に消費税が始まって以降、課税売上高が一定額以下の事業者は、申告・納税の義務が免除されてきました。免税点は創設当初3000万円でしたが、平成16年4月1日から現在まで1000万円となっています。 「免税事業者は、消費税抜きで売上請求するのか」というと、そう...
-

2021.08.01 みんなの経営応援通信編集部
インボイス制度に対応する上での困りごと第一位は?「インボイス制度アンケート集計結果」
インボイスへの本音を探ります! ソリマチでは、ユーザー様宛にメールマガジン「会計・実務情報通信」を定期配信しています。この「会計・実務情報通信」2021年6月14日号・2021年6月22日号にて、インボイスに関するアンケート調査を掲載し、延べ103名の方からご回答をいただきました。 以下では、その集計結果について、ご報告いたします。なお「複数回答可」とある設問は複数の選択肢を選択できる形式で、それ以外は一つの選択肢のみを選択する形式です。 「知っている」「少し知っている」という回答が全体の7割以上を占めました。ただし、「知らない」が2割弱ですから、未だに十分な周知が行き届いていない現状もあるようです。 こちらも「非常に関心がある」「関心がある」が8割弱を占めました。もともと、インボイスに関心を持っている方がこのアンケートに積極的に答えた、という側面もあるかもしれませんが、現時点で予想以上に多くの方が関心を抱いているようです。 この結果を見ると、回答者全体の52.43%が免税事業者ですから、「免税事業者だが、課税事業者になる」と回答したのは、免税事業者全体の(2...
-

2021.06.01 税務ニュース
「インボイス制度」のココが気になる!運用面について詳しく解説します
「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」のスタートまで、あと3年を切っています。前編では当制度のあらましについてご案内しました。法人・個人ともに事業者であれば必ず関わるもの。“知らなかった”では済まされない大切な実務の知識であることはご理解いただけたかと思います。今回は「インボイス制度」の気になる運用面についてご紹介させていただきます。 免税事業者が売り手となる取引があった場合はどうなる? 「インボイス制度」の導入後は、買い手が消費税計算において仕入税額控除(商製品やサービスの購入に係る消費税相当額を差し引くこと)をするために、売り手事業者の登録番号などが記載された「適格請求書」を保存しなければならないことを前編でご確認いただきました。 消費税の申告計算 ここで、基準期間の課税売上高が1,000万円未満であることなどの理由から消費税の申告・納税をしなくてもよい事業者のことを一般的に消費税の「免税事業者」と呼ばれますが、この免税事業者は、税務署に届出をすることにより課税事業者となる(つまり免税の要件を満たしていても消費税の申告・納税をする)ことを選択しない限り、適格請求書(...
-

2021.04.25 税務ニュース
インボイス制度とは? 今さら聞けない「インボイス制度」のあらまし
2019年(平成31年)10月から消費税率の引き上げと軽減税率が導入され、税率の区分経理を行わなければならなくなったことに伴い、消費税の仕入税額控除の要件が「帳簿・請求書等の保存方式」から「区分記載請求書等保存方式」に見直されたのは記憶に新しいところです。そして現行の「区分記載請求書等保存方式」は、いよいよ2023年(令和5年)10月から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)に移行される予定です。 個人・法人にかかわらず、事業者の皆様は来るべき新制度のスタートに向けて、今のうちから制度の内容を十分に理解し、しっかりと準備をしておかなければなりません。 各制度の適用時期(導入スケジュール)を確認しよう! インボイス制度の導入で、何が変わるのか? 「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」がスタートすると、ココが変わります。 請求書に記載すべき事項が変わる 登録を受けた事業者のみが「適格請求書」を交付できる 事業者登録には事前に税務署へ申請をしなければならない 登録を受けた事業者は、買い手に「適格請求書」を交付しなければならない 買い手が...
-

2020.08.18 税務ニュース
2023年10月より導入予定の「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」とは?
2019年10月1日より消費税率が10%へ引き上げられると共に、軽減税率制度が導入されました。8%と10%の複数税率制度となったため、事業者においては、複数税率に対応したレジやシステムの導入・改修、8%と10%に区分した請求書の発行に追われたことと思います。それから早1年が経とうとしていますが、この複数税率制度がさらに変わっていくことはご存知でしょうか。2023年10月1日より、適格請求書等保存方式、いわゆる「インボイス制度」が導入される予定となっています。 インボイスとは、もともと税率や税額を記載した明細書のことで、税額把握のために使われることから「税額票」とも呼ばれています。ヨーロッパ諸国においては、インボイスを用いた消費税計算を行っています。今後は、日本においてもこのインボイスに基づいて消費税を計算していくこととなります。なぜこのような制度が必要なのか、まず消費税の仕組みから確認し、この制度の導入によってどのような対応が必要なのか解説していきたいと思います。 1.消費税の仕組み まず、消費税の仕組みから確認していきます。消費税とは、商品・製品の販売やサービスの提供などの...









 トップ
トップ



![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)

