MENU


896件 61~80件を表示
-

2024.09.11 税務ニュース
【インボイス】登録したけどやめたい…どうしたらいい?個人事業主向けに手続きと注意点を解説
「インボイス、登録したけど消費税が重いから止めたい」そんな声を聞くようになりました。インボイス登録をやめるとき、どんな手続きをいつまでにしたらいいのでしょうか。今回は、手続きと注意点を個人事業主向けに解説します。 インボイスが必要な事業主、なくてもいい事業主 「インボイスに登録してたけれど、なくても困らない」と感じた事業主がいるかと思います。事実、インボイス登録が必要かどうかは、取引先次第です。次のように分かれます。 BtoBで大企業相手 デザイナーやライターなど、大企業から受注する事業主の多くは、インボイス登録をした方が無難です。大企業は原則課税で消費税の納税額を計算しています。原則課税だと、インボイスがないと仕入税額控除できません。つまり仮払いした消費税相当額分、損をするのです。 引用元:【インボイス制度】領収書はどう書くべき?手書きもOK?個人の飲食店・小売店に解説 昨年10月前後、得意先の大企業から登録をお願いされるケースが多数ありました。「登録しないなら10%分、取引額を下げてほしい」と交渉された人もいたかと思われます。 BtoBで中小規模の事業者相手 ビジネス客...
-

2024.09.09 みんなの経営応援通信編集部
サステナブルなエコ名刺&キャンピングレンタカー事業、北海道から世界を見つめる印刷会社の歩みとは
SDGsという単語が浸透し始めた現在、ビジネスにおいても環境保護や社会貢献という視点が重要性を増しています。消費者は製品の背後にあるストーリーにこそ価値を見出し、「モノからコトヘ」という価値観の転換が起こっています。 今回は、そんなSDGsの先駆けともいえる、サステナブルな事業を手掛ける企業にお話をお伺いしました。バナナの茎で作った紙を利用した「エコ名刺」事業を手掛ける丸吉日新堂印刷株式会社、およびキャンピングカーレンタル事業を営む北海道ノマドレンタカー株式会社の代表取締役・阿部 晋也様に、これまでの歩みを語っていただきました。 バナナの茎から「エコ名刺」ができるまで 丸吉日新堂印刷の歩み 丸吉日新堂印刷株式会社は40年以上の歴史があり、当初は手書きの複写伝票をメインに取り扱っていました。しかし、パソコンが普及して手書き伝票の需要が衰退したので、名刺通販を事業のメインに据えました。 ごく普通の名刺ではなくて付加価値をつけたサービスを提供したい、という想いから、初めはペットボトルの再生名刺を手掛けていました。しかし、再生用ペットボトルの海外流出などでメーカーが撤退し、事...
-

2024.09.06 中小企業おすすめ情報
これから変わる?職場における今後の定期健康診断の方向性
職場の健康診断における現行の診断項目が適当かどうかについては様々な意見があり、2023年に発足した厚生労働省の「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会(以下 検討会)」でまさに議論が進んでいる最中です。いろんなステークホルダーが絡むためにまだどこに着地するかははっきりしていないのですが、会議録から読み取れる今後の方向について、私見を含めまとめてみます。なお、検討会の議事録は厚生労働省のサイトに掲載されています。 国民の健康を支える職場の健康診断 職場で行われる健康診断は、「一般健診」と「特殊健診」に大きく区別されます。 一人でも労働者を雇用している事業主には労働者に「一般健診」を受けさせる義務があり、労働者は受ける義務があります。オフィスワーカーが年に1回(夜勤などがある人は半年に1回)受けているのはこの「一般健診」です。これに加えて、例えば有害な薬剤に接する人や、放射線に関わる業務に携わっている人などはその作業に応じた「特殊健診」を受ける義務があります。 市町村で実施している住民に対する健診は義務ではない一方、多くの人々が労働者の義務として健診を受け...
-

2024.09.05 見逃し配信
【見逃し配信】これって経費になる?人気税理士が教える節税と仕訳のコツ
2024年8月27日(火)、ソリマチ株式会社は脇田弥輝税理士事務所の税理士 脇田 弥輝(みき) 先生 をお招きし、「これって経費になる?人気税理士が教える節税と仕訳のコツ」と題した無料のオンラインセミナーを主催いたしました。 セミナーレポート 事業にかかった費用は「経費」として、売上から差し引いて所得税等の計算をすることができます。ですが、個人事業主として活動している場合、事業に関係する経費なのか、それとも経費ではないのか、判断が難しい出費が多々あります。 今回お招きした講師の脇田先生は、経費精算を行う人のための場所「経費精算カフェ」の店長も務めています。そこでお客様から寄せられる「これは経費になりますか?」という相談について、様々に答えています。 その実地のご経験を活かして、今回のセミナーでは「これは経費になる?ならない?」という具体例を多数挙げながら、「”経費”になるかどうかをどう判断するべきか」をわかりやすくご解説いただいています。 [template id="4604"]
-

2024.09.04 IT・ガジェット情報
【文具ライター推薦】文房具も環境にやさしいサステナブルなものを選ぼう
普段使うものだからこそ環境にやさしい商品を選んだり、捨てずに使い続けたりと、個人でもできる「サステナブルな取り組み」が重要視されています。文房具業界で環境へ配慮した「サステナブルな商品」に注目が集まっています。「サステナブルな商品」とは、持続可能な社会を実現するため生産から販売、破棄までのサイクルを通して、環境や経済などに配慮している商品のことです。そこで今回は、今注目の最新のサステナブルな文房具をご紹介します。 CO2排出量を48%削減できる「バイオチューブ搭載サラサクリップ」 [caption id="attachment_18398" align="aligncenter" width="1280"] バイオチューブ搭載サラサクリップと替え芯[/caption] 筆記メーカーのゼブラから、環境配慮したジェルボールペンの「バイオチューブ搭載サラサクリップ」が8月1日に発売しました。ペン本体、替芯、替芯のパッケージにまで環境配慮したジェルボールペンです。ゼブラは1997年からボールペンの本体に再生プラスチックを使用することで環境に配慮した商品作りを進めてきましたが、さらなる環...
-

2024.09.03 IT・ガジェット情報
スキャナで領収書をデジタル化すればスペース節約で固定資産税が軽減!?
「電子帳簿保存法」改正でデジタル化の理解も深まり、経理の予算が確保できた!という方も多いでしょう。おそらくその目玉となるのが、領収書のデジタル化です。関連会社から領収書をPDFで貰えれば、そのままパソコンのハードディスクに保存するだけです。しかもフィルダやファイルの命名規則さえ合わせれば、実際のファイルに保存するより明確で検索も簡単。 なによりメールで送れるので郵送時間がなく、誤記が見つかってもすぐに出し直しできます。まぁ、それで仕事が増えたとという方もいるかも知れませんが……。 しかし問題は「紙の領収書」です。少なくはなってきましたが、備品や消耗品の購入、タクシー代や飲食費、宿泊費や燃料代など、まだまだ紙が横行してます。 そんな紙の領収書を撲滅するのが「スキャナ」です。紙の領収書をコピー機の要領でスキャンすると、画像データやPDFとしてパソコンに保存できます。 しかしパソコンの販売店に行ったり、Webで検索してみると、いろいろな形のスキャナがあり、機能も異なりそうです。それぞれのスキャナはどんな業務に向いていて、領収書の整理に便利なスキャナはどれでしょうか? いろいろ...
-

2024.09.02 農家おすすめ情報
知っておくべき!相続土地国庫帰属制度による農地について
はじめに 農地を相続したものの、「遠方に住んでいて利用する予定がない」「周りに迷惑がかからないようにきちんと管理するのは経済的な負担が大きい」。そのような理由で相続した農地を手放したいとき、その農地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」という制度があるのはご存知だろうか。 2023年4月27日施行から1年経過、巷で話題になっているのでその内容について解説する。農地を相続したにもかかわらず耕作をしない等の問題を抱えている方はぜひ本稿を読んで参考にしていただきたい。記事の記載にあたり内閣府及び法務省の公表資料をもとにわかりやすく説明している部分は、著者の個人的な見解も含むことをあらかじめお断りしておく。 相続土地国庫帰属制度の背景 これまでは、相続財産に不要な農地があってもその農地だけを放棄することができず、不要な農地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかのどちらかしか方法がなかった。 農産物価格の低迷や農家の後継者不足などにより農地利用のニーズが低下している昨今、農地を相続したが農地を利用しないので手放したいと考える方が増加する傾向にある。これらが...
-

2024.08.29 農家おすすめ情報
少量多品目農家必見!酷暑での野菜の調整・発送テクニック!
猛暑に負けない!収穫から発送までの秘訣 近頃の猛烈な暑さは尋常ではありません。少量多品目農家にとって、酷暑は収穫から発送までの全てのプロセスに影響を及ぼす難敵です。特に、収穫したばかりの新鮮な野菜を最良の状態で客に届けるためには、どのような工夫が必要か頭を悩ませている農家も多いのではないでしょうか。今回は、タケイファームで実践している、野菜の調整・発送テクニックを紹介します。 タケイファームでは、栽培した野菜の95%をレストランへ翌日に届くように送っています。収穫当日の天気が雨予報になっているからといって前日に収穫することはありません。悪天候であれば収穫ができないため、先方に延期する旨を伝えます。あくまでも採れたてにこだわっているからです。シェフからは、「鮮度がすごくいい、武井さんの野菜だとすぐにわかる」と言われています。しかし、夏場はその状態を保つことは簡単ではありません。他の農家と差別化するためには、ひと手間もふた手間も必要ですが、逆を言えば、ライバルに差をつけるチャンスでもあるのです。 野菜の鮮度を保つ工夫 毎日の猛烈な暑さの中で、野菜の鮮度を落とさずに収穫するために次の...
-
![個人事業主も活用したいクラウドファンディングのしくみと税金[第2回]:購入型クラウドファンディングに係る税金①](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-146.jpg)
2024.08.23 起業応援・創業ガイド
個人事業主も活用したいクラウドファンディングのしくみと税金[第2回]:購入型クラウドファンディングに係る税金①
近年、フリーランスや個人事業主も活用できる資金調達手段として注目されているクラウドファンディング。何回かの連載で、フリーランスや個人事業主が知っておきたいクラウドファンディングのしくみと税金について解説します。第2回では購入型クラウドファンディングに係る税金について、所得税と住民税にスポットをあててみましょう。 購入型クラウドファンディングとは 「購入型クラウドファンディング」は、資金調達者が商品やサービスをリターンとして設定し資金提供を募る方法です。資金調達者は集めた資金を活用して商品・サービスを開発し、プロジェクトに賛同し支援金を支払った資金提供者は、クラウドファンディングの成立後、完成した商品・サービスをリターンとして受け取ります。 このように、「購入型クラウドファンディング」は、商品などの開発資金を大人数で提供し完成品を受け取ることから、実態としては共同購入に近い性質があります。 購入型クラウドファンディングのメリットとデメリット クラウドファンディングの本来の目的は資金調達ですが、クラウドファンディングによって得られるメリットはそれだけではありません。 まず、資金...
-
![経営相談の現場から[シリーズ第2回]安い報酬で働き詰めの現状を打破したい](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-147.jpg)
2024.08.19 起業応援・創業ガイド
経営相談の現場から[シリーズ第2回]安い報酬で働き詰めの現状を打破したい
筆者は経営コンサルタントとして、日々経営者の方々のお悩みを伺っています。このシリーズは「経営相談の現場から」というテーマで、中小企業経営者や個人事業主の方から実際にあったご相談内容を取り上げます。今回はフリーランスとして動画編集を手掛けるBさんから、今後の事業方針についてのご相談を頂きました。 毎日遅くまで作業して、月の売上は15万円・・・。 Bさん 「事業者が動画再生サイトにアップする動画の編集を請け負っています。編集技術は独学で身につけました。クライアントがご自身で撮影した動画を、私が編集します。目を引くサムネイルを作ったり、効果音やテロップを入れたり、テンポよく話が展開するようにシーンをつなぎ合わせたり、といったことをしています。」 筆 者 「動画を活用する事業者は増えていますよね。受注はどのように獲得していますか?」 Bさん 「クリエイターと発注者をつなぐマッチングサイトを利用しています。私のホームページに過去実績やサンプル動画を載せているので、それを見た方からSNSで依頼が来ることもあります。」 筆 者 「そうですか。受注は順調ですか?」 Bさん 「はい。有難...
-

2024.08.15 起業応援・創業ガイド
個人事業主の小規模企業共済とiDeCo~違いとメリット・注意点は?
1. 小規模企業共済とは?税務上の取扱い、メリットと注意点は? ①小規模企業共済の概要 小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための、積み立てによる退職金制度です。国の機関である中小機構が運営しています。2023年3月末現在の加入者数は約162万人、資産運用残高は約11兆1,313億円です。(出所:中小機構ウェブサイト) 加入者は、月々1,000円~70,000円までの間(500円単位)で掛金を納付します。そして、退職や廃業時に積み立て金額に応じた共済金を受け取ります。この共済金の受け取り方は、「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。 ②小規模企業共済の税務上の取扱い 掛金払い込み時:掛金の全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。 共済金および解約手当金の受け取り時:受け取る際の年齢や一括または分割などの受取方法などで税法上の取扱いが異なります。 (基本的な取扱い) 個人事業主が廃業した場合や会社等の解散または会社役員の退任により共済金を受け取る場合の基本的な取り扱いは次の通りです。 一時金受け取りを選択した場合は「退職所得」 分...
-

2024.08.13 税務ニュース
消費税にも関わる!土地と建物の譲渡対価の按分
一括譲渡した土地と建物の区分 実務上、所有する不動産について、土地と建物を一括で譲渡することはよくありますが、その契約書に土地と建物の譲渡金額の内訳が明記されていない場合、税務上は適正に土地と建物の取得価額に区分する必要があるとされています。なぜなら、建物には消費税が課税される反面、土地には課税されませんし、購入する側からすれば建物の取得価額は減価償却という形で経費にすることができる反面、土地は経費にすることができないなど、土地と建物で税務処理が大きく異なるからです。 原則として固定資産税評価額で按分 税務上は時価課税の原則がありますので、このようなケースは、土地と建物の時価を算定した上で、その時価の比で按分するのが原則です。時価と言っても、不動産鑑定士が評価した金額や相続税評価額を割り返した金額などいろいろな時価が考えられます。しかし、この土地と建物の一括譲渡に関しては、過去の判例上は固定資産税評価額で按分するのが妥当とされるケースが多いです。 この理由は、固定資産税評価額は地方公共団体が公開するもので信頼性が高いだけでなく、同一の地方公共団体が公表するものですので算定根拠が...
-

2024.08.09 税務ニュース
賃上げ促進税制とは?2024年度(令和6年度)版の全体像と中小企業向け繰越控除、注意点を解説
2024年度(令和6年度)税制改正で賃上げ促進税制が変わりました。「2024年度版賃上げ促進税制」です。新年度版は控除額などが拡充されましたが、注意すべき点もあります。2024年度版賃上げ促進税制の全体像と中小企業向け特典の繰越控除、注意点を解説します。 賃上げ促進税制とは何か?経緯を確認 賃上げ促進税制とは、企業が従業員の給与等の額を増加した場合に、増加額の一部を法人税額や所得税額から差し引く制度です。従業員の給与の増加額の一部を企業所得の課税額から控除するしくみは、2013年4月から始まりました。 「所得拡大促進税制」「人材確保等促進税制」と名を変えて、現在に至っています。 当初は「要件が厳しすぎて使いづらい」と言われていましたが、徐々に条件が緩和。税額控除割合の引き上げなどで賃上げのインセンティブも高まりました。その結果、現在、多くの企業が活用しています。 しかしそれでも「赤字企業は活用できない」などの欠点がありました。2024年度版賃上げ促進税制は、こういった点も配慮されたものとなっています。 2024年度(令和6年度)賃上げ促進税制の全体像 ここで2024年度版賃...
-
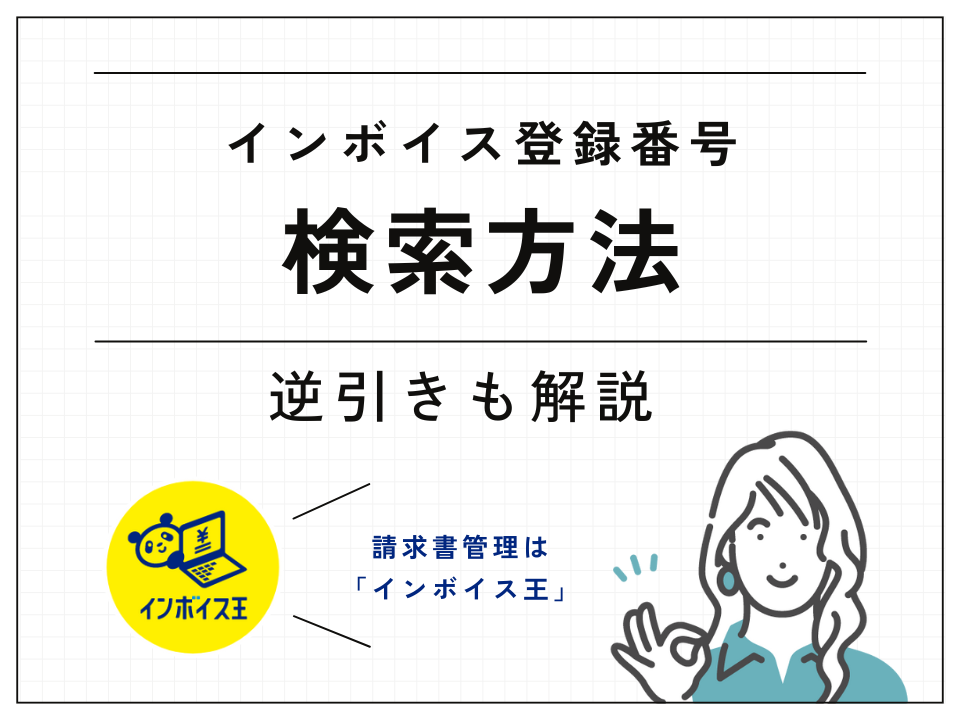
2024.08.08 税務ニュース
インボイス制度の登録番号を検索&確認する方法を解説|逆引きも
今回は、インボイス登録番号の確認方法を解説します。 インボイス制度の概要も含めて分かりやすく解説しているので、本制度についてよく分からないという人にもおすすめの記事です。 ソリマチ株式会社が手掛ける請求書発行サービス「インボイス王」も紹介しているので、ぜひご覧ください! インボイス制度の登録番号を効率的に管理するなら「インボイス王」 ソリマチ株式会社が提供する「インボイス王」は、インボイス制度に対応した請求書(適格請求書)をかんたんに発行・受領できるツールです。 インボイス王でできること ・請求書月10枚までの発行であれば無料で利用可能! ・年間5,500円で適格請求書が無制限で作成可能! ・項目が自動で取り込まれるOCR機能対応 ・取引先の情報は検索して簡単に登録・管理! ・ソリマチ製品「会計王」との連携で自動仕分化 インボイス王は取引先の登録番号もラクラク管理ができます。 一度登録した取引先の法人番号はインボイス王で確認ができ、法人ごとにまとめて請求書の管理も簡単です。。 また「インボイス王」は、月10枚までならインボイス制度対応の請求...
-

2024.08.07 起業応援・創業ガイド
手作り食品を売るのに必要な手続きは?無許可販売のペナルティも解説
「クッキーやパンを手作りするのが趣味」という主婦はめずらしくありません。中には趣味が高じて、作ったお菓子やパンを売ろうと考える人もいるでしょう。注意したいのが「食品を売るときの免許」です。何も手続せずに販売すると、思わぬ罰金を払うことになるかもしれません。今回は、手作り食品を売るときに必要な手続きと無許可で販売したときのペナルティを解説します。 食品販売には原則「営業許可」が必要…なぜ? お菓子やパンをはじめ、手作りした食品を売るのなら営業許可が必要です。なぜ必要なのでしょうか。それは、買った人の健康に影響を及ぼす可能性があるからです。 手作りした食べ物には、作る本人の状況や作るときの環境が影響します。もし作った本人が手を洗わずに食品を触っていたり、病気の状態で作っていたり、あるいは、作るときの台所が不衛生だったりすれば、作った食べ物に雑菌が入る可能性があります。食べて食中毒になるかもしれません。 そういったことが生じないよう、手作り食品の販売は許可制度となっています。事前に売りたい本人に「手作り食品を売りたいです。こういう状況で売ります」といった申請をさせ、管轄の保健所が...
-

2024.08.05 IT・ガジェット情報
ChatGPTやGemini、Claudeなど最新の生成AIを無料で使える「天秤AI」で業務効率改善&AIスキルアップを実現
生成AIの領域は今までにないほど進化が早く、2か月もあれば時代遅れになっていきます。従来のガジェットやソフトウェアの10倍くらい新陳代謝が激しいというイメージです。 2022年、「ChatGPT」が世界に衝撃を与えて生成AIの頂点にいました。2023年にも相次いで性能向上と機能強化をリリースし、独走状態に入ったかと思いきや、ライバルが急に頭角を現してきました。それが、Googleの「Gemini」とAnthropicの「Claude」です。どちらも、「ChatGPT」と同レベルの性能を備えるうえ、マルチモーダルやコード生成の機能を強化しており、もはや戦国時代です。 ChatGPTやGemini、Claudeなどの生成AIサービスは無料でも利用できるのですが、性能が低いAIモデルとなります。高性能なAIは有料プランを契約することで利用できます。とは言え、どのサービスを選べばよいのかわからない、という人もいるのではないでしょうか。そこでお勧めなのが、「天秤AI by GMO」です。 [caption id="attachment_18137" align="aligncent...
-

2024.08.02 社会保険ワンポイントコラム
2024年10月より従業員数51人以上の企業が対象へ!短時間勤務者の社会保険適用拡大のポイント
2016年10月から、社会保険の加入対象がパート・アルバイトなどの短時間労働者へも広がりました。2016年当初「従業員数501人以上」だった企業要件は、2022年10月からは「従業員数101人以上」へ、そして2024年10月からは「従業員数51人以上」へと拡大されます。新たに適用対象者となる方の手続き漏れがないよう、適用要件や準備の流れは正しく理解しておきたいものです。 そこで今回は、社会保険の適用拡大のポイントを解説します。 適用拡大の対象企業とは 2024年10月から適用拡大の新たな対象となる企業は、従業員数が51人以上100人以下の企業です。ここでいう従業員数とは、「フルタイムの従業員数」+「週の労働時間および月の所定労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数」の合計で、パート・アルバイトを含みます。つまり、現在の厚生年金保険の被保険者数と考えていただくと良いです。 従業員数は月によって増減があると思いますが、直近12か月のうち6か月以上で前述の基準を上回ると、対象企業と捉えられます。また、労務に関する手続きの中には、事業場(支店・支社)ごとに制度適用判断や人数のカウ...
-

2024.07.31 IT・ガジェット情報
中小企業が活用すべきクラウドサービスとは?現状や選び方を解説
中小企業にとって、効率的かつ柔軟な業務運営を実現するための鍵となるのがクラウドサービスです。しかし、クラウドサービスの種類は多岐にわたり、どのサービスが自社に最適かを見極めるのは容易ではありません。本記事では、中小企業がクラウドサービスを活用する際の現状や、その選び方について詳しく解説します。 中小企業のクラウドサービスの利用状況 中小企業のクラウドサービスの利用状況について、総務省の「令和3年 情報通信白書」と「令和3年通信利用動向調査の結果」によると、2020年時点で全体の68.7%がクラウドサービスを利用しています。しかし、この数字は企業の規模や資本金によって大きく異なります。 具体的には、資本金1千万円未満の企業ではクラウド利用率が44.2%にとどまっています。これは、中小企業がクラウドサービスの導入に慎重であることを示しています。資本金1千万円~3千万円未満の企業では利用率が58.2%とやや高くなりますが、それでも半数程度です。 一方で、資本金1億円~5億円の企業ではクラウド利用率が77.3%に達し、50億円以上の大企業では95.0%と非常に高い利用率を示していま...
-

2024.07.30 税務ニュース
相続税対策の前に…贈与税のしくみと生前贈与のメリット・デメリット、考えるときのポイントを確認
「年110万円以下で贈与をすれば、贈与税がかからずに相続税対策ができる」という一言をよく目にします。確かに生前贈与は将来の相続税を減らす効果がありますが、贈与税を正しく知らないとかえって損をするかもしれません。今回は、生前贈与を考えている方向けに、現在の贈与税のしくみと生前贈与のメリット・デメリット、生前贈与を考えるときのポイントをお伝えします。 贈与税の制度には2つある 現在、贈与税の制度は2つあります。いずれも「毎年1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額がいくらか」で申告・納税の要不要を考えていくのが基本スタイルです。 暦年課税制度 「1年間にもらった財産の合計額はいくらなのか」で贈与税の額が決まる制度です。財産をもらった側が申告・納税をしなくてはなりません。相続時精算課税選択届出書を提出していなければ、暦年課税制度で計算することになります。ただし、申告・納税が必要となるのは1年間にもらった財産の額が110万円を超えてからです。 なお、財産をあげた側・もらった側の年齢や関係によって、税額計算で使う税率や控除額が変わります。 特例贈与財産 一部の親子間、...
-

2024.07.29 税務ニュース
インボイス制度導入後のNPO法人の動向は?
2023年10月1日から適格請求書保存方式(インボイス制度)がスタートし、適格請求書発行事業者の登録を行ったNPO法人も多いと思います。しかし、経理の現場では混乱も少なくなく、スムーズな船出とは言えない状況です。今回はインボイス登録を行なった団体と行わなかった団体の事例をそれぞれ紹介し、現場にどのような影響があり、今後検討が必要であろうと思われる事項について解説します。 インボイス登録を行なった事業者 まず、就労継続支援B型作業所を運営するNPO法人がインボイス登録を実施した事例をご紹介します。このNPO法人では、一般企業からの軽作業などを請け負っており、取引先との間において消費税負担の問題が生じることとなりました。このNPO法人では、取引先との協議などを経てインボイス登録することとなりました。インボイス制度導入前から作業の単価に変動はないためNPO法人の負担が増えますが、想定される税負担を試算し、納税資金を確保できるよう準備しています。 インボイス登録を行わなかった事業者 障害福祉サービスを行うNPO法人でもインボイス登録をしていないケースがあります。この団体は自立訓練を中心...









 トップ
トップ



![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)

