MENU


896件 401~420件を表示
-

2022.12.12 IT・ガジェット情報
【家電ライターが解説】月に1週間以上は出張にでる筆者がオススメ!ビジネスに便利なデジタルツール厳選5点!
筆者は地方の工場に呼ばれて取材記事を書いたり、地方局に行ってテレビ番組に出させてもらったりしています。そのため多いときでは3週間連続、少なくても月のうち1週間は出張という生活をしています。また原稿はたいてい急かされるので、移動中の電車内やホテルなどで執筆して、写真や映像も添えて編集部にデータを送っています。 そこで筆者の出張用バッグに入っている厳選した5つのツールをご紹介します。 先方のテレビやプロジェクタが映らないのは日常!それを回避するモバイルプロジェクタ 営業職をはじめ先方にプレゼンをする機会が多い方に断然オススメなのがモバイルプロジェクタです。ノートパソコンを見せながらのプレゼンは、昨今のアクリル板や密を避ける環境で難しくなっています。かと言ってプレゼン資料を印刷して配布してしまうと、先方は紙ばかり見てしまい、自分に注目して大事なことを言おうとしても俯いたままなんてよくあります。 また営業職の多くの方が体験しているように、先方のテレビやプロジェクターを借りると、映像が写らなかったり、音がでなかったりというのは日常茶飯事(笑い)。これではプレゼンする前から先方を飽きさ...
-

2022.12.09 社会保険ワンポイントコラム
会社は新卒社員の「配属ガチャ」否定に屈してはならない
「配属ガチャ」とは何でしょうか? 「○○ガチャ」という言葉に不案内な方もおられると思うので、まずこの意味を簡単に説明しましょう。そもそも「ガチャ」というのは、カプセルトイまたはカプセルトイの販売機のことです。「ガチャポン」「ガチャガチャ」といったほうが馴染みのある方も多いかもしれません。「ガチャ」の特徴は、この自動販売機に入っている数多くの商品の中から何が出てくるかは、購入してみないと分からないことです。 ここから派生した使われ方として、親を選べない「親ガチャ」とか、子を選べない「子ガチャ」、遺伝子を選べない「遺伝ガチャ」などなど、個人の努力ではどうしようもないものが「○○ガチャ」という言葉で表現されているようです。 このように、「出てくるものがランダムで選べない」というのが「ガチャ」の大きな特徴です。「配属ガチャ」というのは、新卒社員が入社予定の会社の希望する勤務地や職種に配属されるかどうかを「ガチャ」になぞらえた言葉です。今の若者はなぜ配属先を気にするのか。そして会社はこのような若者にどう対応すべきなのかを考えてみましょう。 「配属ガチャ」はなぜ敬遠されるのでしょうか 昔...
-
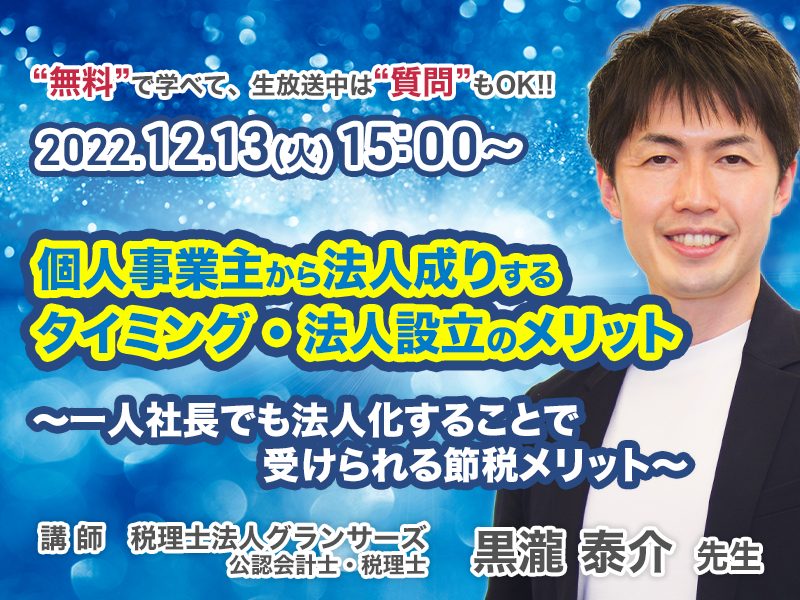
2022.12.09 見逃し配信
《セミナー動画》個人事業主から法人成りするタイミング・法人設立のメリット ~一人社長でも法人化することで受けられる節税メリット~
12月13日(火)の『みんなの経営応援セミナー』では、個人事業主から法人成りするタイミング・法人設立のメリットを税理士の黒瀧泰介先生に解説していただきました。 個人事業主と法人の違いや法人設立についてや株式会社と合同会社の違いやマイクロ法人について、わかりやすくお話しいただきました。ぜひご覧ください。 ■12/13(火) 個人事業主から法人成りするタイミング・法人設立のメリット ~一人社長でも法人化することで受けられる節税メリット~ 放送日:2022年12月13日(火)15:00~(1時間・予定)生放送 講師:税理士法人グランサーズ 共同代表 公認会計士・税理士 黒瀧 泰介先生 講師の黒瀧先生は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル』で節税でキャッシュを最大限残す方法や運用で効率よく増やしていく方法を配信されています。 視聴はこちらから。 ・セミナーテキストはこちら(PDFダウンロード) セミナー内容 ■個人事業主の悩み〜所得税・住民税が高すぎる ■法人設立のメリット・デメリット ■法人成りのタイミングはいつ? ■法人成りの手続きと注意点 ■株式会社と合同会...
-

2022.12.08 税務ニュース
インボイス制度に対応した領収証の書き方・記載例~小売業、飲食店業など領収証でインボイス制度に対応する方法~
2023年(令和5年)10月1日から始まるインボイス制度。インボイス制度は「適格請求書等保存方式」と言い、インボイスは別名「適格請求書」と言います。その名称から、インボイス=請求書という印象が強く、小売業や飲食店業など普段請求書ではなく、領収証を発行している事業者の中には、「請求書でないとインボイスに対応できない?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。 本記事では、普段請求書ではなく領収証を発行されている事業者の方、請求書ではなく領収証を受け取る課税事業者の方へ向けて、インボイス制度開始後におけるインボイス制度対応の領収証について解説していきます。 1.インボイスとは何か?手書き領収証でもインボイスとして認められるか? インボイスとは、前述の通り「適格請求書」のことです。では、「適格請求書」とは何でしょうか。国税庁では、適格請求書を次のように定義しています。 適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。そして、請求書や納...
-

2022.12.07 IT・ガジェット情報
<連載>フリーランスが知っておきたい、「ロジカルで美しい」プレゼン資料作成術 ―【シリーズ第7回】投影資料と配付資料の使い分け
独立すると、営業活動・ビジネスパートナー探し・資金調達などでご自身のビジネスをプレゼンする場面があります。人によってはセミナーに登壇して人前でプレゼンする機会もあることでしょう。 このシリーズでは、ロジカルで美しいプレゼン資料の作成技術を、全7回にわたって解説します。 第1回 プレゼンの骨格をロジカルに組み立てる 第2回 各ページの内容をロジカルに構成する 第3回 美しい資料で表現する 第4回 パワーポイントの使い方 ~時短ワザ~ 第5回 パワーポイントの使い方 ~図解入門~ 第6回 パワーポイントの使い方 ~アニメーションの活用法~ 第7回 投影資料と配付資料の使い分け ←今回はここ 前回の第6回では、画面に投影するプレゼン資料におけるアニメーション機能の活用法を取り上げました。最終回の今回は、投影資料と配付資料の使い分けの考え方を取り上げます。 投影資料と同じものを配付するのは、ベストではない 皆さんは、プレゼンで投影資料を使うとき、紙の配付資料も用意しますか?用意する場合、どのような資料を配付しますか? このことについては「こうするべき」という常識や統一見解はありませ...
-

2022.12.05 IT・ガジェット情報
2025年以降、DX化を推進しない企業が生き残っていくのは難しい時代になる
日本企業のDXが進まないと、2025年以降は毎年12兆円の経済損失が生じる 経済産業省は2018年に「DX(デジタルトランスフォーメーション)レポート」を発表し、これまでの非効率なビジネスのやりかたを続けた場合、2025年以降に毎年最大12兆円の経済損失が生じると予測しました。これを「2025年の崖」と呼び、経営者の中でも「DX」という言葉がバズりました。 経済産業省は企業が自己診断できる「DX推進指標」を2019年に策定したところ、日本のDXは諸外国と比べ想定以上に遅れていることがわかりました。その後コロナ禍に突入し、テレワークやビデオ会議などが普及しIT化が進んだように見えたのですが、2020年の自己診断でも9割以上の企業がDXに未着手でした。 [caption id="attachment_11017" align="aligncenter" width="1372"] DX推進指標自己診断結果。グラフは「DXレポート2」より[/caption] 2020年に経済産業省が発表した「デジタルガバナンス・コード2.0」ではDX化を推進するため、経営者に求め...
-

2022.12.01 社会保険ワンポイントコラム
管理職に昇格したら残業代不要?勘違いされやすい「管理監督者」を再確認
度々、「管理職には残業代が出ない」という言葉を耳にします。しかし、「管理職」とは誰のことを指すか正しく理解できているでしょうか。管理監督者の定義を勘違いしている会社も多くあり、その勘違いは未払残業代の観点からも実は大きなリスクです。 そろそろ来期の昇級・昇格を検討する時期を迎える会社もあることと思います。この機に「管理監督者」について再確認しましょう。 法律上の「管理監督者」とは誰か 労働基準法では、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」は同法の一部の適用が除外されています。これに該当する労働者を一般的に「管理監督者」と呼んでいます。「管理監督者」という単語から、「管理職」のことを指すと考える方も多いですが、実はそれは危険な間違いです。 設けられている役職の種類や各役職に与えられる権限は、会社によって当然異なります。そのため、管理監督者は役職名とは関係なく、実際にどのような役割・待遇だったかで判断されます。現在では、これまでの判例や行政通達などを通じて下記のような内容を総合的に見て判断するとされています。 経営上の判断事項において、経営者と一体的な...
-

2022.11.30 税務ニュース
11月16日開催 みんなの経営応セミナー『今さら聞けない…令和4年の年末調整『ココだけ』ポイント解説!』Q&Aまとめ
2022年11月16日、「みんなの経営応援セミナー」で令和4年の年末調整についてお話をさせていただきました。その中で、答えきれなかったご質問について、この場を借りてお返事させていただきます。 Q1.新型コロナウイルス感染症で休業して、従業員に休業手当を支給していました。この手当は給与に含めて年末調整をする必要があるのでしょうか。 A 質問の文章を見る限り、年末調整が必要だと思われます。 休業手当は「どういう事情で支給したのか」により課税か否かが分かれます。 労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」:課税(給与所得) 労働基準法第76条の規定に基づく「休業補償」:非課税 1は、「コロナ禍による営業自粛」など、使用者の都合で休業したときに支払われるものです。労働基準法第26条により、平均賃金の6割以上の手当てを支払わなければならないとされています。このとき支給した休業手当は給与所得です。そのため、年末調整の対象となります。 一方2は、業務のときに従業員が負傷などをして仕事ができないときに支払われるものです。こちらは非課税となりますので、年末調整の対象ではあり...
-

2022.11.28 税務ニュース
【後編】相続問題に備えるために家族信託を活用しよう!
【前編】では、信託の定義と信託を家族で運用する「家族信託」のキホンについてご案内しました。今回は家族信託の具体的な活用例のうち主なものをご紹介します。 不動産の家族信託 近年における相続税の申告事績の概要をみると、相続財産の金額構成比としては不動産(土地・家屋)が約40%と最も高い割合を示しています(令和2年分 国税庁報道発表資料)。ちなみに平成23年分は約52%でした。地価の下落により土地部分の割合が減少しているとはいえ、不動産の構成比は依然高いままです。したがって国内の相続問題を考えるうえでは、やはり所有する不動産の処分や承継などについて無視できないといえます。 1. 不動産の処分・価値の維持 所有不動産を処分する目的として、主に生活資金の確保、金融商品の購入・運用、新しい物件の確保(建て替え・買い換え・大規模修繕など)が考えられます。物件の売却・リフォームには契約の締結が必要とされますが、所有者の意思・判断能力が著しく低下した状況による契約は、法律上無効となるため売買取引が成立しません。しかし家族信託を活用すれば、信託契約による受託者が受益者のために信託された不動産の売却...
-

2022.11.25 IT・ガジェット情報
何を買う? iPhone 14 無印/Plus/Pro/Pro Maxのスペックを徹底比較!
iPhone 14はminiがなくなりPlusがラインナップ 2022年9月8日にiPhone 14シリーズが発表され、iPhone 14/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Maxは9月16日、iPhone 14 Plusは10月7日に発売されました。iPhone 12/13にラインナップしていた5.4インチディスプレイのminiモデルがなくなり、新たに大画面のiPhone 14 Plusがお目見えしています。iPhone 14シリーズ、買うべきか、見送るべきか。今回は、各モデルのスペックを細かく見ながら、どんなシチュエーションで活躍するのかを紹介します。 iPhone 14シリーズはiPhone 14とiPhone 14 Proの2カテゴリーに分けられ、iPhone 14には無印とPlusがあり、iPhone 14 ProはProとPro Maxがあります。iPhone 14 無印/PlusのチップセットはA15 Bionicチップです。iPhone 13 Proに載っていた5コアのタイプで、ニューラルエンジンは1秒間に15.8兆回の演算が可能です。下位...
-

2022.11.24 税務ニュース
実践型の生きたスキルが身につく!経理マインドを強化しよう!【前編】
経理マインドとは? 中小企業の経理の仕事には、太い柱が二本必要だと考えています。 一本目は専門的な知識の柱、二本目は社長に「今すぐ話したい!」と思われるための仕事力という柱です。 二本目の柱である経理の仕事力。これが経理マインドから培われるのだとすれば、それを強化するためにはどうするか? 中小企業の経理の目的のひとつに、社長の会社経営をよりスムーズに手助けすることがあります。ということは、経理担当者こそが会社の命運をかけた重要ポストであるともいえるでしょう。 経理マインドを鍛えることにより、簿記検定や税理士試験といった試験勉強では学ぶことのできない、実践型の生きたスキルが身についていきます。すでに中小企業の経理という職に就いている方が、実践型の生きたスキルを身につけると何が起こるのか?それは、今よりも視野が広がることであり、いまよりもはるかに多くの選択肢をもつことができることです。 私の考える経理マインドを、6つご紹介したいと思います。このお話は前半と後半に分け、前編で3つ、後編で3つ、をご紹介します。 【経理マインド1】経理担当者のマインドセット たくさんの仕事を覚え、...
-

2022.11.22 税務ニュース
【2022年年末調整】年末調整で扱う12の所得控除を一気に確認!注意点も解説
年末調整で扱う所得控除は数が多く、全部で12あります。今回は、この12の所得控除の内容や条件を確認しましょう。 社会保険料控除 社会保険料を支払ったときの所得控除です。控除できる金額は、その年に支払った金額すべてです。控除額は、本人が年間に支払った全額です。なお、生計同一配偶者や扶養親族など家族が本来負担すべきものも、扶養する本人が支払ったのなら控除できます。 小規模企業共済等掛金控除 iDeCoや企業版DCの掛金、会社役員などが加入する小規模企業共済の掛金などを支払ったときの所得控除です。その年に支払った金額すべてを控除できます。ただし、社会保険料と違い、本人分しか控除できません。妻の分を実質的に負担したとしても控除できません。 生命保険料控除 生命保険料、介護医療保険料または個人年金保険料を支払った人に適用される所得控除です。 控除額 控除額は、その年に支払った金額をベースに計算します。ただ、社会保険料や小規模企業共済等掛金控除と違い、支払額すべてが差し引けるわけではありません。上限額があります。 【引用元】No.1140 生命保険料控除(国税庁) また...
-

2022.11.21 IT・ガジェット情報
Google Analytics 4とは? 〜ユニバーサルアナリティクスとの違いとGA4の基礎基本〜
Webサイトのアクセス解析ツールとして多くのWeb担当者、マーケティング担当者に利用されているGoogle Analytics 。現在は2020年10月にリリースの最新バージョン、「GA4(Google Analytics 4 プロパティ)」が推奨プロパティとして展開され、既に利用できるようになっておりますが、旧バージョンとなるユニバーサルアナリティクスが2023年7月1日をもって終了となるのはご存じでしょうか。 現在でも、ユニバーサルアナリティクスを利用されている方は大変多いと思われますが、2023年7月1日のサポート終了後はデータが処理されなくなってしまいます。少なくとも6か月間はアクセス可能とのことですが、過去データの閲覧のみが可能で、その後のデータ収集及びアクセス解析は利用できません。今後はGA4のみの対応となり、提供元であるGoogleも早い段階でのGA4への移行を推奨しています。 多くの貴重な新機能が搭載されている一方で、これまでとは勝手が違うユーザーインターフェースとなることから、移行に対し二の足を踏んでいる方も多いことでしょう。 今回はGA4とユニバーサル...
-

2022.11.16 社会保険ワンポイントコラム
インフルエンザは今年こそ流行する!?その原因と対策について
2022年8月9日、日本感染症学会は今シーズンのインフルエンザに関する提言を出しました。今年はインフルエンザ、それもA香港型と言われる毒性が強いタイプが流行する危険が高く、下手をすると大流行するというものです。 そもそもインフルエンザとは ここでインフルエンザについて復習しておきましょう。インフルエンザは広い意味での風邪の一種で冬(12月~3月)に流行しインフルエンザウイルスがのどや鼻から体内に入ることで感染します。通常の風邪と違って、急に39度を超えるような非常に高い熱が出てつらいというのが特徴です。 また高齢者においてはインフルエンザが治った後に肺が「荒れて」おり、そのあとに別の菌が入って肺炎を起こして命に関わることが知られています。また小児においては稀にけいれん、意識障害などの症状を起こし命に関わることや後遺症が残ることが知られています。これはインフルエンザ脳症と言われるものです。 なぜ今年は流行する? さてなぜインフルエンザは今年流行する危険が高いと言われているのでしょう。いくつかの原因があります。第一にこの2年、新型コロナに対して世界中の人がマスクや対人距離をとる、...
-

2022.11.14 税務ニュース
フードデリバリー配達員、必要経費になるかならないか?
必要経費って何? 所得税の標的となる所得を計算するにあたり、配達報酬などの売上は所得を増加させ、必要経費は所得を減少させます。従って、必要経費が多いほど税金の負担は小さくなるため、納税者としては、必要経費をなるべく大きくしたいところです。しかし、何でも必要経費に算入されると税収がゼロになってしまうため、必要経費には一定のルールがあり、お金を払ったからといって闇雲に必要経費には出来ません。 フードデリバリー配達員などの個人事業主には、プライベート関連と業務関連の2種類の支出があります。これらのうち必要経費となるものは、業務関連の支出のみです。保温バックなどの配達用品や、配達に関わる交通費、駐車料金は、当然必要経費となります。他方、「事業に関わる支出は何でも必要経費になる」という噂話がありますが、必要経費のルールはそこまで緩くはありません。 事業に関わるってどういうこと? 実のところ、現状「事業と関わりがあるか否か」についての明確な基準を示すことは出来ません。その様な現状であっても、次の様に整理することは出来そうです。 必要経費になるもの それが無いと売上を得られない支出 ...
-

2022.11.11 見逃し配信
《セミナー動画》今さら聞けない…令和4年の年末調整『ココだけ』ポイント解説!
11月16日(水)の『みんなの経営応援セミナー』では、税理士で税務ライターの鈴木まゆ子先生をお招きし、令和4年の年末調整の『ココだけ』ポイントをお話しいただきました。令和4年の変更点や、年末調整の流れ、書類のチェックポイントについて実務の視点からわかりやすく解説いただきました。ぜひご覧ください。 ■11/16(水) 今さら聞けない…令和4年の年末調整『ココだけ』ポイント解説! 放送日:2022年11月16日(水)15:00~(1時間・予定)生放送 講師:税理士・税務ライター 鈴木 まゆ子 先生 講師の鈴木まゆ子先生は、『みんなの経営応援通信』にも多数ご執筆いただいております。ぜひこちらも併せてご覧ください。 視聴はこちらから。 ・セミナーテキストはこちら(PDFダウンロード) セミナー内容 ■年末調整とは?2022年の変更点も確認 ■年末調整の流れ・対象者・書類 ■年末調整で扱う控除/扱わない控除 ■年末調整の「ココだけ」チェックポイント ■その他の注意点 過去の番組 70以上の番組を見逃し配信!録画も無料でご覧いただけます。 https://revis...
-

2022.11.11 税務ニュース
準備は早ければ早いほどよい!今の時期から令和4年分「確定申告」の準備をしよう!
今年も残すところあとわずか。“今年分の確定申告はまだ先のこと”と考えていると、忙しい年末年始を過ごしているとあっという間に時が過ぎ、結局は間際に準備に取り掛かるという慌ただしい事態を招いてしまいます。差し迫った状況では適正な申告もおぼつかなくなるため、早い時期から改正項目をチェックし、計算に必要な知識・データ・書類を整えるようにしましょう。 準備は早ければ早いほどよい! 個人事業主や一定の条件に当てはまる方に義務がある所得税の確定申告。そして義務はなくても所得税の還付が受けられるため申告したほうがよい還付申告。特にお勤めの方は、勤務先が「年末調整」を行ってくれるので原則的には確定申告不要ですが、副業所得があるなど確定申告をしなければならないケースもあります。 確定申告の期間は周知のとおりで2月16日から3月15日です。納税が必要な場合も原則3月15日までに納めます。一見すると作業時間にゆとりがあるように感じるかもしれませんが、実際には申告に必要な書類を事前に取得・管理しておく必要があるため、準備はできる限り早い時期から始めるほうがいいでしょう。 必要書類は申告内容によってさ...
-

2022.11.10 税務ニュース
【2022年年末調整】年末調整と確定申告、両方やるのはどんな人?
会社員の多くは年末調整で完結します。しかし、人によっては確定申告も行わなくてはなりません。どのようなときでしょうか。年末調整と確定申告の違いを確認しつつ、両方やるパターンを見ていきましょう。 年末調整と確定申告はどう違うのか そもそも、年末調整と確定申告はどう違うのでしょうか。最初に確認しましょう。 年末調整 年末調整は、「給与から天引きした所得税の精算手続き」です。給与や賞与からは、所得税が天引き(源泉徴収)されています。この源泉所得税は、本来かかる税額よりやや多めに設定されています。また、生命保険料控除や地震保険料控除などは考慮されていません。 このため、年末に1年間の正しい課税所得額を計算し、天引きした所得税と精算する手続きをします。この手続きが年末調整です。 【参考】【2022年 年末調整】年末調整って何?経理初心者が知っておきたい基本をざっくり解説 確定申告 確定申告は、1年間のすべての所得額、控除額から正しい所得税の額を計算し、申告する手続きです。通常、翌年3月15日が期限となっています。このとき、年末調整と同じく、源泉徴収された所得税や先払いした所...
-
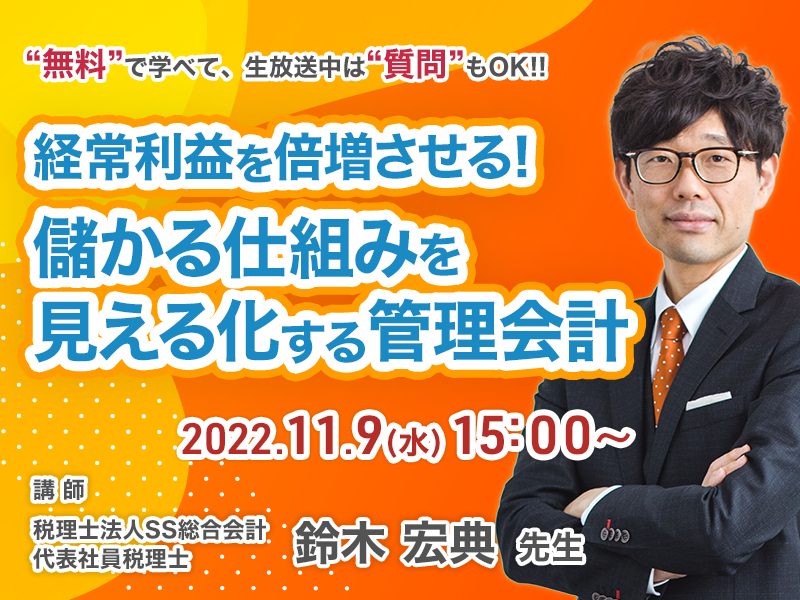
2022.11.10 見逃し配信
《セミナー動画》経常利益を倍増させる!儲かる仕組みを見える化する管理会計
11月9日(水)の『みんなの経営応援セミナー』では、税理士の鈴木 宏典先生をお招きし、「管理会計」をテーマにお話しいただきました。ストラック図を用いて、変動損益計算書から経常利益を倍増させる仕組みや、儲かる仕組みを見える化する方法を教えていただきました。ぜひご覧ください。 ■11/9(水) 経常利益を倍増させる!儲かる仕組みを見える化する管理会計 放送日:2022年11月9日(水)15:00~ 講師:税理士法人SS総合会計 代表社員税理士 鈴木 宏典 先生 視聴はこちらから。 ・セミナーテキストはこちら(PDFダウンロード) セミナー内容 ■儲けの仕組みが分かる会計…それは管理会計! ■ストラック図で見れば損益計算書も簡単にわかる! ■値上げの戦略か?増客の戦略か?どちらが有利? ■財務数字を見る視点「鳥の目」「虫の目」「魚の目」 ■部門別PLと連年比較財務諸表の重要性 過去の番組 70以上の番組を見逃し配信!録画も無料でご覧いただけます。 https://revision.sorimachi.biz/ouen-seminar/info/ &nbs...
-

2022.11.09 税務ニュース
本当のところは税務調査は怖くない?質問検査権は何かを理解しよう!
本当の税務調査が怖くない理由 強権的な税務調査。このような言葉を聞いたことがあると思いますが、税務調査は国家権力を背景に、高圧的な国税調査官が、皆様の命の次に大事なお金を奪っていくものです。税務調査にはこのようなイメージが大変強いため、税務調査を大変怖がっておられる方が多いという印象があります。 私のクライアントで、非常に気難しい方がいらっしゃいました。その社長、仕入れ先などの取引先はもちろん、税理士に対する要求も相当に大きく、不手際があれば即怒号をあびせる方でしたので、月次試算表の報告などの際は、税理士である私も非常に緊張するような方でした。このような方でさえ、「ウチの会社の税務調査は、本当に大丈夫なんですかね?」と、非常に心配しながら毎月の巡回の際は必ず聞く始末で、如何に納税者にとって税務調査が怖いものなのか、痛感させられました。 しかしながら、税務調査を法律的に考えると、税務調査は全く怖いものではないことが分かります。というのも、税務調査の主導権は税務署にはないとされているからです。誰にあるかと言えば、私たち納税者にあるのです。なぜなら、税務調査は納税者の承諾を前提とし...









 トップ
トップ





