MENU


43件 21~40件を表示
-

2023.06.02 税務ニュース
【消費税の確定申告】第2回:「収入=課税」とは限らない?消費税がかかる取引の見分け方(その1)
第1回 「本則課税」「簡易課税」ってどんな計算をするの?基本を解説 第2回 「収入=課税」とは限らない?消費税がかかる取引の見分け方(その1) インボイスに登録して課税事業者になった人が来年悩むのは「消費税の確定申告」かと思います。消費税の計算は所得税と大きく異なるからです。今回は、消費税の計算の第一歩として必要な「消費税のかかる取引の見分け方」の1つ目をお伝えします。 消費税がかかる取引の見分けが大事な理由 「消費税の計算って、所得税や住民税とあまり変わらないんじゃない?」。 インボイスに登録して免税事業者から課税事業者になる方の中には、このように感じている方もいるかもしれません。しかし消費税のしくみは所得税・住民税と大きく異なります。 消費税がかかるのは「収入」「経費」の一部にすぎない 所得税・住民税の課税ベースは基本的に「収入-経費」で計算します。一方、消費税はそう単純ではありません。収入・経費について「どれに消費税がかかるか」を見分ける必要があります。なぜかと言うと、すべての収入と経費に消費税がかかっているわけではないからです。 「売り上げたら消費税がかかる」 「...
-

2023.05.29 税務ニュース
ネットビジネスの申告漏れに監視の目。副業YouTuberも知っておきたい税金のペナルティ。
インフルエンサーやYouTuberによる相次ぐ申告漏れのニュースが話題になっています。投げ銭や動画配信による収入があるにもかかわらず、申告しなかったり、期限に間に合わなかったりすると、ペナルティが課されてしまいます。 相次ぐネットビジネスの申告漏れに監視の目 2023年3月、美容系インフルエンサーの女性9人が税務調査を受け、6年間で合計約3億円の申告漏れを指摘されました。追徴税額は、合計で約8,500万円にのぼるとみられます。Instagramや動画投稿サイトの商品紹介で得た収入の一部を申告していなかったのです。 また、同じ月にYouTuberの事案も報じられました。投げ銭など約3,600万円のもうけが無申告であったため、約700万円を追徴課税されたのです。「申告が必要とは知らなかった」という主張でしたが、調査により他のYouTuberが投稿した税務調査対策の動画を観ていたことが発覚しました。意図的な無申告と認定され、重いペナルティが課されました。 このように、インフルエンサーやYouTuberとして活動している配信者が、国税局の税務調査を受け、申告漏れを指摘されるケースが...
-

2023.05.16 税務ニュース
副業、フリーランスのための確定申告の賢いやり方
税理士ではなくとも個人の確定申告の申告期限である3月15日は、なんとなく気が重くなる日として認識されているでしょう。現実的にはサラリーマンが確定申告する場面としては医療費控除と住宅ローン控除一年目などのケースが多く、確定申告する人は限られた人というイメージです。 しかし、最近は自社の社員について副業を認める会社も増えており、副業の収入をどのように申告するのかが問題になることもあります。また、そもそも会社を辞めてフリーランスとして自由な立場で働く人も増えており、そのような立場の人であれば3月15日はとてつもなくプレッシャーがかかる日ともいえるでしょう。 なぜなら、いうまでもなくそれらの人々は申告期限までに申告書を所轄税務署に提出し、納税を行わなければならないためです。今回の記事はこうした副業、フリーランスのための確定申告の賢いやり方についてご紹介していきます。 帳簿の整備こそが最大の節税? 副業やフリーランスの方が税務申告を行う上で、最初に意識していただきたいのは「帳簿をしっかりとつけ、取引を確実に記録する」ということです。「帳簿をつければ節税できるの?」という疑問の声も聞こ...
-
![クリエイターと税金[第3回]:青・白どっち?クリエイターが知っておきたい青色申告のメリット・デメリット。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-428.jpg)
2023.03.07 おんすけと学ぶ税務情報
クリエイターと税金[第3回]:青・白どっち?クリエイターが知っておきたい青色申告のメリット・デメリット。
フリーランス・クリエイターが知っておきたいお金と税金のしくみ 本コラムでは、これから独立しようと考えている駆け出しクリエイターが知っておきたいお金と税金のしくみを、独立前・開業準備・開業1年後などのステップごとに、やさしく解説します。 独立開業したクリエイターを待ち構えているのが、年に1度の確定申告。「確定申告するなら青色申告がお得」と聞いたことがあるのではないでしょうか? しかし、青色申告は良い面ばかりではありません。第3回では「開業1年後」にスポットを当てて、青色申告のメリット・デメリットを整理してみましょう。 青色申告と白色申告の基礎知識 青色申告と白色申告 確定申告には「青色」と「白色」の2種類があり、確定申告の際に提出する書類が違うことに加えて、受けることのできる控除額や特典などが異なります(下図)。通常の方法である「白色申告」と比較して、「青色申告」には税金の面でさまざまなメリットがあります。 また、同じ「青色申告」でも記帳や申告のしかたによって控除額が異なります(下図)。一定水準の記帳で記帳している場合には...
-

2023.02.28 税務ニュース
【2023年確定申告】ふるさと納税で申告すべきケースとは?申告のしかたと注意点も解説
ふるさと納税で確定申告する人は、2023年も多そうです。「ワンストップ特例をしたから大丈夫」と思っていても、申告しないと節税できないこともあります。申告のしかたも含めて解説します。 ふるさと納税で確定申告すべきケース ふるさと納税で確定申告すべきかどうかは、次の2パターンで判断します。 会社役員や正社員、パート・バイト、年金生活者 年末調整や2月に1回の年金支給で完結するような給与所得者や公的年金の生活者は、ワンストップ特例を使えれば確定申告は不要です。「寄附した金額-2000円」が翌年6月から徴収される住民税からさしひかれます。 ただし「ワンストップ特例が使えれば」の話です。特例を使えるのは次の条件すべてを満たした給与所得者・年金受給者です。「申請したから大丈夫」ではありません。 寄附先の自治体の数が5つ以下 年明けに確定申告をしない 引っ越しがあったことを寄附先に報告している 年明け1月10日(必着)までにワンストップ特例申請書を寄附先に送った つまり、次のどれかに当てはまる人は、確定申告しないと寄附した分の控除ができなくなります。 1.ワンストッ...
-

2023.02.14 税務ニュース
あなたの稼ぎは「事業所得」か「雑所得」か
令和4年8月事変 令和4年8月、「売上300万円以下の副業は原則として雑所得として扱う」という国税庁の指針が世間を騒がせた。これまで自らの副業を事業所得に相当すると考えて申告をしてきた事業主の多くが、税制優遇措置の無い雑所得として扱われると言うのであるから大問題である。当然、この指針に対して論拠の説明を求める声や反対意見が多く寄せられ、2ヶ月後の10月には幾分トーンダウンした指針が公表された。これにより、騒ぎは一応の落ち着きを見せ現在に至っている。 この指針は、「所得税法基本通達」と呼ばれるものである。通達とは、法律でもなければ、裁判所が示した法解釈でもない。だとすれば何か。有り体に言えば、上席の役人(国税庁長官)が作った下位の役人(税務署職員)のための業務マニュアルに相当する。 税務署職員用の業務マニュアルなので、本来、納税者を拘束するものではない。しかし、我が国の役人は大変優秀なので、税務署職員はこのマニュアルを完璧なまでに遵守する。結果、裁判も辞さない覚悟が無ければ、納税者の側も無視することは出来ない性質を持つことになる。たかがマニュアル、されどマニュアルである。 &...
-
![NFTアートと税金[第1回]:NFTアートを販売した場合の確定申告はどうする?NFTの基礎知識と課税関係の概要について解説。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-457.jpg)
2023.01.17 税務ニュース
NFTアートと税金[第1回]:NFTアートを販売した場合の確定申告はどうする?NFTの基礎知識と課税関係の概要について解説。
本コラムでは、 NFTアートと税金の関係について、やさしく解説します。第1回では、NFTの概要と確定申告の際の基本的な考え方を整理します。 なお、NFTについては、国税庁から必ずしも明確な見解が出ているわけではありません。そのため、筆者の私見を交えて解説しています。 そもそも「NFT」ってなんだろう? NFTはブロックチェーン上で発行されるトークン(Token)の一種です。トークンにはもともと「しるし」「象徴」という意味がありますが、ここではブロックチェーン技術を利用して発行された仮想通貨や認証のことを指します。 NFTは「Non-Fungible-Token(非代替性トークン)」の略であり、コピーが容易なデジタルデータに対して、その「非代替性(唯一性)」を担保するテクノロジーをいいます。イメージしやすい表現にするならば、「唯一性を保証する証明書付きのデジタルデータ」といえるでしょう。NFTはコピーそのものを防ぐ技術ではありませんが、デジタルデータにNFTが紐づいているかで、それがコピーであるか識別することができます。 ここで、「非代替性」という難しい言葉がでてきましたが...
-

2023.01.16 見逃し配信
《セミナー動画》はじめてでも大丈夫!フリーランスと個人事業主のための確定申告勉強会
1月23日(月)の「みんなの経営応援セミナー」では、確定申告をテーマに公認会計士・税理士の大野修平先生にご登壇いただきました。前半は確定申告の基礎について、後半はフリーランス・個人事業主、副業所得のある方、賃貸住宅などの不動産オーナー、株・FX・仮想通貨などの資産運用をしている方などケース別にポイントを解説していただきました。ぜひご覧ください。 ■1/23(月) はじめてでも大丈夫!フリーランスと個人事業主のための確定申告勉強会 2023年1月23日(月)15:00~ 講師:セブンセンス税理士法人 公認会計士・税理士 大野 修平 先生 視聴はこちらから。 ・セミナーテキストはこちら(PDFダウンロード) セミナー内容 ■確定申告の基本 ■個人事業主・フリーランスの確定申告 ■副業所得のあるサラリーマンの確定申告 ■賃貸不動産オーナーの確定申告 ■株取引のある方の確定申告 ■FX取引のある方の確定申告 ■仮想通貨取引のある方の確定申告 ■ふるさと納税をした方の確定申告 過去の番組 70以上の番組を見逃し配信!録画も無料でご覧いただけます。 htt...
-

2023.01.12 税務ニュース
こんなときにも!?な確定申告をピックアップして解説!
まもなく令和4年分の確定申告がスタートします。昨年までは確定申告をしていなくても、今年は確定申告をするべき、もしくは確定申告をしたほうがいいケースがあります。あるいは確定申告をしていたとしても、昨年までとは違った計算手続を含めなければならない場合も考えられます。そんな中でも特に留意すべき点のうち主なものをピックアップして解説します。 年間の給与収入が2,000万円を超える 1. 年末調整ができず、確定申告をしなければならない お勤めの方で年収2,000万円を超えると、勤め先で年末調整ができず、本人が確定申告しなければなりません。通常、他に所得がなければ確定申告により源泉徴収された税金が還付される場合がほとんどです。注意が必要なのは、令和2年分から「所得金額調整控除」という計算手続ができたことです。現役世代では「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」が関係しますが、要件に合う場合には、下記の計算式に基づいて調整控除額を求め、給与所得から差し引きましょう。 <所得金額調整控除の要件> 次のいずれかに当てはまる場合 本人が特別障害者 年齢23歳未満の扶養親族...
-
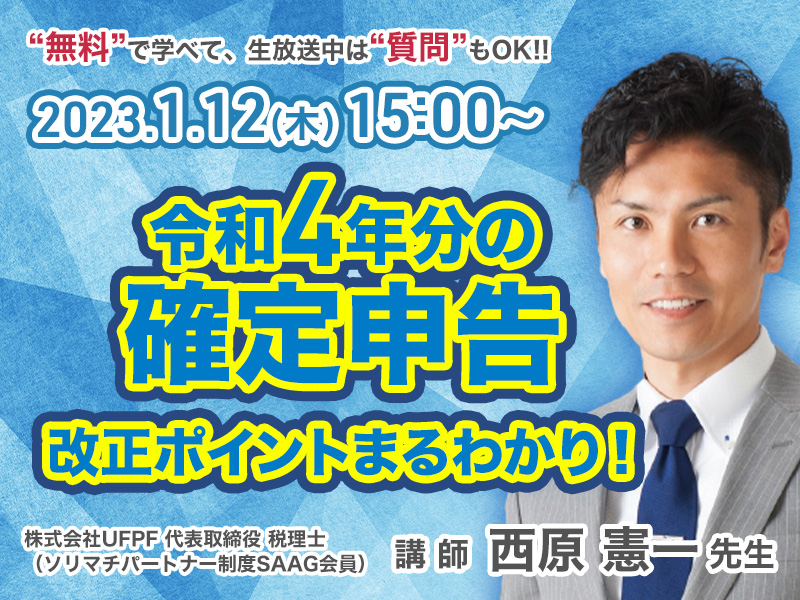
2023.01.05 見逃し配信
《セミナー動画》令和4年分の確定申告 改正ポイントまるわかり!
1月12日(木)の『みんなの経営応援セミナー』では、毎年確定申告をしている方向けに令和4年分の確定申告の改正ポイントを税理士の西原憲一先生に解説していただきしていただきました。 申告書の様式変更についてや雑所得の取り扱い、住宅ローン控除、退職所得控除などの変更について、わかりやすくお話しいただきました。ぜひご覧ください。 ■1/12(木) 令和4年分の確定申告 改正ポイントまるわかり! 2023年1月12日(木)15:00~ 講師:株式会社UFPF 代表取締役 税理士 西原 憲一 先生(ソリマチパートナー制度SAAG会員) 視聴はこちらから。 ・セミナーテキストはこちら(PDFダウンロード) セミナー内容 ■所得税等申告書の様式変更 ■業務に係る雑所得の取り扱い変更 ■住宅ローン減税の要件と控除率変更 ■退職所得控除の計算方法一部変更 過去の番組 70以上の番組を見逃し配信!録画も無料でご覧いただけます。 https://revision.sorimachi.biz/ouen-seminar/info/ 今後もソリマチでは、みんなの経営応援セミナーを通...
-
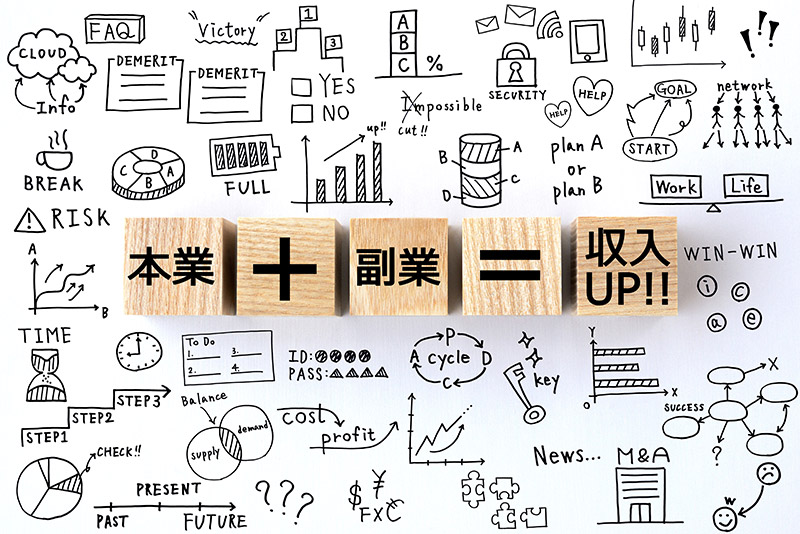
2023.01.03 起業応援・創業ガイド
副業で20万円以下は確定申告はしなくていい?
会社員で副業・兼業をしている方、これからしようかなと検討中の方は多いのではないでしょうか?副業・兼業で収入を得たら、知っておく必要がある確定申告について、しなければいけない場合、確定申告不要となる場合について詳しく解説しています。 ①会社員の副業と確定申告 国策を挙げて、副業が推進される時代です。副業解禁も進み、副業に本気で取り組む会社員の方も増えています。総務省による調査によれば、下記のように副業を希望する雇用者は年々増加傾向にあることが分かっています。 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」P22から引用 副業で収入を得たら、自分で1年間の税金を計算し、申告と納付を行う「確定申告」についても知っておく必要があります。会社員の方は、特殊なケースに該当しない限り、1年間の税金の精算として会社が行うおなじみの「年末調整」で税金の計算は完了しています。 でも、副業で収入を得た場合は、会社員が副業で得た合計額が、年間で20万円を超えた場合には、確定申告を行う必要があります。この20万円の判定は、副業が給料なのか、その他の事業所得や雑所得かによって異なります。 副業がパートアル...
-

2023.01.01 税務ニュース
【2023年確定申告】還付申告は1月1日からできるってホント?注意点も解説
年明け、還付申告を予定している人は多いでしょう。「申告は2月16日以降」と思っているかもしれません。実は、還付申告は年明け1月1日からできます。申告できる期間も長いのが特徴的ですが、うっかりすると損をすることも。今回は、還付申告の内容と注意点をお伝えします。 還付申告とは何か 還付申告とは、源泉徴収や予定納税で納め過ぎた税金の一部を還付してもらうための確定申告をいいます。 「国民自らが所得と税額を申告し、納税をする」というのが、日本の税金の原則です(申告納税制度)。しかし本当に国民全員が自ら申告すると、税務署の作業が膨大になり、徴税コストがかさみます。また、一度に多額の納税は、納税者自身にも負担です。 そこで、給与や年金、報酬などの支払から所得税を天引きしたり(源泉徴収)、ある程度所得のある人は税金の一部を前払いしてもらったり(予定納税)しています。ただし、先払いした所得税が本来かかるべき税額よりも多くなることがあります。確定申告をすれば、この払い過ぎた所得税が一部戻ってくるのです。 還付申告をできる人 還付申告できるのは「納め過ぎた所得税のある人」です。つ...
-

2022.11.11 税務ニュース
準備は早ければ早いほどよい!今の時期から令和4年分「確定申告」の準備をしよう!
今年も残すところあとわずか。“今年分の確定申告はまだ先のこと”と考えていると、忙しい年末年始を過ごしているとあっという間に時が過ぎ、結局は間際に準備に取り掛かるという慌ただしい事態を招いてしまいます。差し迫った状況では適正な申告もおぼつかなくなるため、早い時期から改正項目をチェックし、計算に必要な知識・データ・書類を整えるようにしましょう。 準備は早ければ早いほどよい! 個人事業主や一定の条件に当てはまる方に義務がある所得税の確定申告。そして義務はなくても所得税の還付が受けられるため申告したほうがよい還付申告。特にお勤めの方は、勤務先が「年末調整」を行ってくれるので原則的には確定申告不要ですが、副業所得があるなど確定申告をしなければならないケースもあります。 確定申告の期間は周知のとおりで2月16日から3月15日です。納税が必要な場合も原則3月15日までに納めます。一見すると作業時間にゆとりがあるように感じるかもしれませんが、実際には申告に必要な書類を事前に取得・管理しておく必要があるため、準備はできる限り早い時期から始めるほうがいいでしょう。 必要書類は申告内容によってさ...
-

2022.11.10 税務ニュース
【2022年年末調整】年末調整と確定申告、両方やるのはどんな人?
会社員の多くは年末調整で完結します。しかし、人によっては確定申告も行わなくてはなりません。どのようなときでしょうか。年末調整と確定申告の違いを確認しつつ、両方やるパターンを見ていきましょう。 年末調整と確定申告はどう違うのか そもそも、年末調整と確定申告はどう違うのでしょうか。最初に確認しましょう。 年末調整 年末調整は、「給与から天引きした所得税の精算手続き」です。給与や賞与からは、所得税が天引き(源泉徴収)されています。この源泉所得税は、本来かかる税額よりやや多めに設定されています。また、生命保険料控除や地震保険料控除などは考慮されていません。 このため、年末に1年間の正しい課税所得額を計算し、天引きした所得税と精算する手続きをします。この手続きが年末調整です。 【参考】【2022年 年末調整】年末調整って何?経理初心者が知っておきたい基本をざっくり解説 確定申告 確定申告は、1年間のすべての所得額、控除額から正しい所得税の額を計算し、申告する手続きです。通常、翌年3月15日が期限となっています。このとき、年末調整と同じく、源泉徴収された所得税や先払いした所...
-

2022.08.29 税務ニュース
フードデリバリーUberEatsなどの配達員の確定申告-本気で動き出す前に!
はじめに 突然ですが、見知らぬ土地を旅行しようと言うときに、地図やガイドブックなどが無いとどうなるでしょうか。「自分がどこにいるのか」も「どこへ行くべきか」も「どうやって移動すべきか」も分からず途方に暮れてしまうかと思われます。これは確定申告についても同じです。 では、確定申告の最終目的地はどこでしょうか。確定申告の経験が少ない方からは、「所得を計算して、所得税を算出する」との回答がとても多いです。しかし、これは半分だけ正解です。正確には、その上で「申告期限までに納める税金、または、還付される税金を算出する」が最終目的地となります。 とは言え、「所得の計算とそこから所得税を算出すること」は、確定申告における最重要ランドマークです。そこで、本稿では、このランドマークの前と後に分けて確定申告書上のどこで何を計算するのかという視点で解説します。また、本稿の位置づけとして、確定申告の詳細な解説を理解する為の大枠の知識を説明する様に努めます。 確定申告の作業工程 唐突にランドマークを設定してその前と後という話をしましたが、まずは、確定申告の作業工程をまとめておきます...
-

2022.06.01 税務ニュース
農業を副業にしたら確定申告は必要?申告不要なケースと注意点を解説
近年の就農ブームの影響からか、家庭菜園や一日農業バイトなどを副業にする話を耳にします。副業で収入を得たとき、気になるのが税金です。今回は、農業を副業にしたときの確定申告について解説します。 副業の農業の所得区分と所得計算の方法 副業の所得には、所得税と住民税がかかります。「所得税」「住民税の所得割」の税額計算は、おおよそ次の流れになります。 所得額の合計-所得控除の合計=課税所得金額 課税所得金額×税率(所得税は5~45%、住民税所得割は一律10%) 2から税額控除などを差し引き、最終的な納税額を算出 ※上記は総合課税での計算。実際は分離課税の対象となる所得が別途ある。また、住民税は、均等割もかかる。 ここで押さえたいのが「副業の農業の所得」です。所得は税法上、10種類に区分されます。そして、「どう稼いだか」で所得の種類と計算の仕方は変わるのです。 自分で育てて販売→雑所得または事業所得 家庭菜園などで自ら野菜や果物、花卉を育て、農協や個人に販売しているケースなら、「雑所得」あるいは「事業所得」に区分します。所得額はいずれも、次のように計算します。 雑所得...
-

2022.02.25 税務ニュース
「病院で払ったから医療費」ではない!医療費控除7つの基本を確認しよう
確定申告でもっとも多い質問が医療費控除です。多くの人になじみのある控除ですが、分かっていそうで分かっていないことも。今回、医療費控除で知っておきたい7つの基本を解説します。 1:「治療や療養に必要な分」だけが対象 病院で支払ったものなら何でも医療費になるわけではありません。原則、「治療または療養のための支出」「病状に見合った金額」が対象です。 【参考】医療費控除の対象になる医療費(国税庁) 言い換えると「治療ではないもの」「治療でもぜいたくすぎるもの」は対象外です。次のようなものは医療費になりません。 インフルエンザやコロナのワクチン→予防目的だからダメ 大人の歯列矯正→美容目的だからダメ(生活に支障があるがゆえの矯正は医療費控除になる) 健康診断や人間ドック、PCR検査→検査に過ぎないからダメ(ただし、この後、病気が発覚し、治療に進んだら医療費控除になる) サプリメント→健康増進目的だからダメ また、医療費をクレジットカード決済したときの支払利息や手数料は、医療費になりません。 2:実際に支払った金額が控除対象 「2021年12月に受けた手術の費用は2...
-
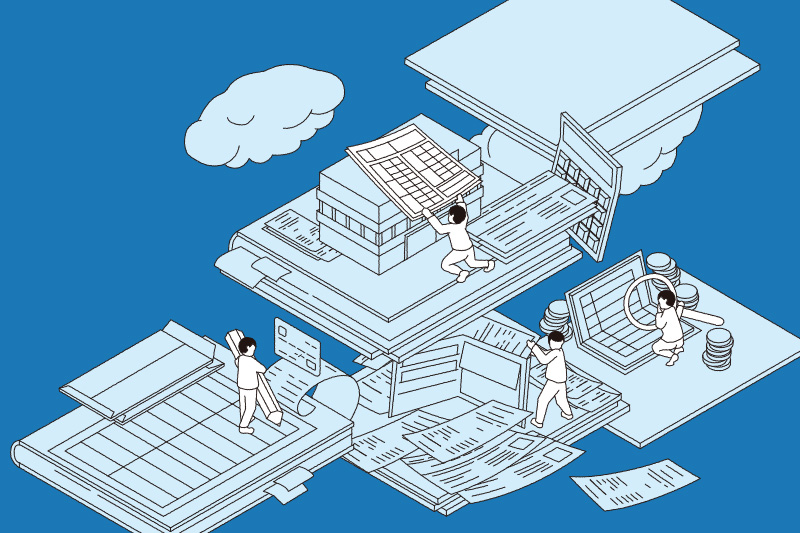
2022.02.22 見逃し配信
《解説動画》【令和3年分確定申告】みんなの青色申告21操作セミナー ~これを見れば今年の青色申告ができる!~
みんなの青色申告を使って、導入から令和3年分 青色申告・確定申告までイッキに解説!セミナーテキストを利用しながら、わかりやすく解説いたします。セミナーテキストは以下よりダウンロードお願いいたします。 講師:株式会社NCS 須戸 政之 様 オンラインセミナー会場 https://www.youtube.com/watch?v=cEuuBpfmds8 セミナーテキスト https://revision.sorimachi.biz/seminar/files/2022_aoiro21_seminar.pdf (約3MB) みんなの青色申告 “帳簿の作成までは終わったが、決算書作成の操作が知りたい” “消費税への対応方法は?” “確定申告書の作成はどうすれば良い?” “次年度への繰り越し方法は?” 本編2時間の長丁場ですが、動画セミナーなのでお客様が気になる部分から見ることができます!もちろん、コーヒー片手に全編見ていただいても嬉しい限りです! YouTube動画 目次 ■1. はじめに ■2. 決算処理の流れ ■3. 決算に向けて 3-1 残高確認をしましょう 3-2 費用...
-

2022.01.21 みんなの経営応援通信編集部
【DXの基礎知識】自宅で便利な確定申告!e-Taxのメリットと使い方
e-Taxって何だろう? e-Taxとは国税庁が運営する国税電子申告・納税システムの通称で、国税に関する申告や納税、申請・届出をインターネット経由で行うことができるシステムです。 2004年から運用を開始したe-Taxは、サービスや対象地域を拡大し、現在では様々な手続きに利用することができるようになっています。 ※e-Taxで可能な手続き一覧 e-Taxと一口に言っても形態は多種多様で、WEBサイト、PC用ソフト、スマートフォン用アプリなど、それぞれ使用できるデバイスや可能な手続きが異なっています。 ※e-Taxのソフト・コーナー(個人向け) ※e-Taxのソフト・コーナー(法人向け) e-Taxのメリット いつでもどこでも手続きOK 税務署に足を運ぶことなく、自宅や事務所から手続きを行うことができます。確定申告期間の税務署は非常に混雑していて、何時間も待つことも珍しくありませんので、e-Taxを利用することで移動時間・待ち時間を節約できます。 一定の添付書類の省略が可能 e-Tax経由で手続きをした場合、その記載内容を...
-

2022.01.18 税務ニュース
何もわからないフリーランスのための確定申告講座
あけましておめでとうございます。2021年も終わりいよいよ確定申告の時期が近づいてきました。 初めての確定申告はわからないことが多く、でも「何がわからないかもわからない」、だから質問もできない…そういう方も多いです。本稿では、確定申告によく出てくる『単語の説明』から、『どのようにして税金を計算するのか』までを、わかりやすく説明します。 (1)「売上」「収入」「所得」「利益」ってなに? 「ここに『所得』を書いてください」って言われて、何を書けばいいかすぐわかる人は少ないと思います。ざっくり言うとこうです。 売上=収入 お客様からいただくお金。 所得=利益 売上から経費を引いたもの。儲かった部分。 所得には色々な種類があるのですが、フリーランスのみなさんが計算する所得は、「事業所得」です。つまり、以下で計算されます。 事業所得(事業の利益)=売上―経費 図にするとこのような感じです。 (2)「所得」「所得控除」「課税される所得金額」ってなに? 文字だけ見るとどれも似ていて面喰いますが、そんなに難しいことではないので見ていきましょう。 所得控除…...









 トップ
トップ



![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)

