MENU


 PICKUP
PICKUP
税務ニュース
【2025年度(令和7年度)税制改正(その1)】103万円の壁の引き上げは123万円に!いつから?大学生のバイト「103万円→150万円」の控除も解説
昨年12月20日に2025年度(令和7年度)税制改正大綱が公表されました。もっとも注目されたのは「103万円の壁の引き上げ」です。どうなったのでしょうか。いつから始まるのでしょうか。今回は、103万円の壁の引き上げと大学生のバイトの壁の引き上げを中心に解説します。 2025年度(令和7年度)税制改正①「103万円の壁」が「123万円の壁」に 個人向けの税制改正の1つ目は「103万円の壁の引き上げ」です。 103万円の壁とは、パート・バイトといった給与所得者の非課税枠を言います。「給与所得控除の下限55万円+基礎控除額48万円=給与年収の非課税の上限103万円」という内容です。 多くのパート・バイトはこの103万円の壁を気にするため、年末になると「働き控え」という現象が起きていました。そのため、企業は人手不足に悩み、家計は物価高が改善されないという状況に陥っていたのです。 そこで、与党から政策協力を求められた国民民主党が「103万円の壁を引き上げるべきだ」と提案しました。議論が重ねられた結果、今回の税制改正で103万円の壁が引き上げとなったの...

社会保険ワンポイントコラム
職場の離職率低下につながる効果が!治療と仕事の両立支援について
治療と仕事の両立についての社会的背景 近年、医療の進歩により、がんのように以前は不治とされていた病気でも生存率が向上し、長期にわたって仕事との両立が可能になりつつあります。病気になったらすぐに離職しなければならないという状況から、治療を行いながら仕事を続けられる社会的環境へと変化しています。 しかし、疾病や障害を抱える従業員を支援するための社内体制が整っていない場合、従業員は仕事を続けたくても離職を選択せざるを得ません。これは企業にとっても人材の大きな損失といえるでしょう。 両立支援の内容 治療と仕事の両立支援の内容ですが、具体的には次のような柔軟な働き方ができる制度を設けた上で、私傷病の治療や療養を目的とした利用ができるようにします。 時差出勤制度 短時間勤務制度 時間単位の休暇制度・半日休暇制度 フレックスタイム制度 在宅勤務(テレワーク)制度 休職制度 両立支援に取り組むことの効果 労働政策研究・研修機構(JILPT)の「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)2024年3月」によれば、上記のよう...

10件 1~10件を表示
-

2024.12.28 IT・ガジェット情報
中小企業のAI活用事例3選|課題・導入しやすいAIツールも紹介
中小企業におけるAI活用は、業務効率化や生産性向上、経営改善に大きな可能性を秘めています。しかし、「AI導入はコストがかかる」「専門知識が必要」などのハードルを感じる企業も多いのが現実です。 本記事では、実際にAIを導入し成果を挙げている中小企業の事例や、比較的始めやすいAI活用方法を紹介します。AIの活用がもたらす効果や導入ポイントを理解し、自社に適した形でAIを取り入れるヒントを見つけてください。 中小企業のAI活用事例3選 中小企業のAI活用事例を3つ紹介します。 図面をもとにAIが自動で見積りを作成 プラスチック・樹脂加工を手掛ける「プラポート」では、図面をもとに見積りを作成する業務が担当営業に依存し、属人化が課題となっていました。この状況を打開するため、図面から加工難易度を判断し、自動で見積り金額を算出するAIシステムを導入しました。 AIシステムの導入により、見積り業務は担当営業に限らず他の従業員でも対応可能となり、業務の属人化が解消されました。さらに、図面を受け取ってから見積り金額を回答するまでの時間が従来の約1/3に短縮され、わずか5分程度で見積りを作成でき...
-

2024.12.26 見逃し配信
【見逃し配信】ビジネスが劇的に変わる!生成AI実践テクニック
2024年12月18日(水)、ソリマチ株式会社はIT・ビジネスライター 柳谷 智宣 先生をお招きし、「ビジネスが劇的に変わる!生成AI実践テクニック」と題した無料のオンラインセミナーを開催いたしました。 セミナーレポート ビジネスを劇的に変えると言われる生成AIは、現在進行形で急速な進化を遂げています。しかし、日本企業ではまだまだ導入が進んでおらず、仕事に生かし切れていない方も多いのが実情です。 今回のセミナーでは、IT・ビジネスライター 柳谷 智宣 先生をお招きし、生成AIとは何か、どんなことができるのか、プロンプトの作り方などをお話いただきました。実際の生成AIのデモを豊富に交えているので、利用のイメージが湧きやすく、初心者の方にもわかりやすい内容となっています。 生成AIを仕事で使いたいけどどうすればいいかわからない。手探りで使ってみたけれど、いまいち上手くいかない。そんな方にオススメです。ぜひ、この機会に生成AIに触れてみてください。 [template id="4604"]
-

2024.07.31 IT・ガジェット情報
中小企業が活用すべきクラウドサービスとは?現状や選び方を解説
中小企業にとって、効率的かつ柔軟な業務運営を実現するための鍵となるのがクラウドサービスです。しかし、クラウドサービスの種類は多岐にわたり、どのサービスが自社に最適かを見極めるのは容易ではありません。本記事では、中小企業がクラウドサービスを活用する際の現状や、その選び方について詳しく解説します。 中小企業のクラウドサービスの利用状況 中小企業のクラウドサービスの利用状況について、総務省の「令和3年 情報通信白書」と「令和3年通信利用動向調査の結果」によると、2020年時点で全体の68.7%がクラウドサービスを利用しています。しかし、この数字は企業の規模や資本金によって大きく異なります。 具体的には、資本金1千万円未満の企業ではクラウド利用率が44.2%にとどまっています。これは、中小企業がクラウドサービスの導入に慎重であることを示しています。資本金1千万円~3千万円未満の企業では利用率が58.2%とやや高くなりますが、それでも半数程度です。 一方で、資本金1億円~5億円の企業ではクラウド利用率が77.3%に達し、50億円以上の大企業では95.0%と非常に高い利用率を示していま...
-

2024.05.14 IT・ガジェット情報
生成AI活用:AIのポテンシャルを引き出す5つの秘訣
生成AIは、私たちの創造性を大きく拡張する可能性を秘めた革新的なツールであり、今後、ビジネスにおいても、日常生活においても欠かせない存在となっていくでしょう。しかしながら、現状では、生成AIを十分に使いこなせていない人が多いのが実情ではないでしょうか。 本記事では、生成AI(ここでは主にテキスト生成を前提にお伝えします。)を業務や日常に効果的に取り入れるための5つのポイントを紹介します。生成AIの特性を理解し、その可能性を最大限に引き出すヒントを提供します。生成AIを単なるツールではなく、創造性を刺激する知的パートナーとして捉え直すことで、生成AIの活用がより一層楽しく実りあるものになるでしょう。 1、生成AIにはたくさん情報を与えよ 生成AIを活用する上で、AIに多くの情報を提供することは非常に重要です。理想的なアウトプットを求めているにもかかわらず、ユーザーが生成AIに与える情報が少ないケースをよく目にします。わずか数行のプロンプトしか書かず、AIからの回答に満足できない状況に陥ってしまうのです。 実際、筆者自身のプロンプトは数千字に及ぶことも珍しくありません。また、ひ...
-

2023.11.06 税務ニュース
NPO法人が経理業務の負担を軽減する方法
NPO法人は社会課題解決などのために重要な役割を果たしていますが、人材や資金などリソースをいかに活用するかが事業を継続する上で重要なポイントです。特に経理は、専任の経理スタッフを持たないNPO法人もあり、悩みを抱えている団体も多いでしょう。経理業務を効率化することで団体のリソースをより事業に投下できることにも繋がります。今回は、経理業務を軽減・効率化するための具体策を解説します。 ネットバンキングの活用 銀行口座を開設していても、インターネットバンキングを利用していないNPO法人も多くあります。特に小規模のNPO法人では専任の経理担当者を置いていないことも多いですが、経理の負担を減らす意味でもネットバンキングの開設は必要だと思います。ネットバンキングであれば時間に関わらず振込作業などが可能ですし、振込のために窓口やATMに並ぶ必要もなくなります。 また、ネットバンキングを活用することで経費削減に繋がる場合もあります。窓口やATMでの振り込みに比べてネットバンキングでの手数料の方が安いことが多いですし、ネット専業銀行では振込手数料がかなり安く抑えられています。 部門...
-
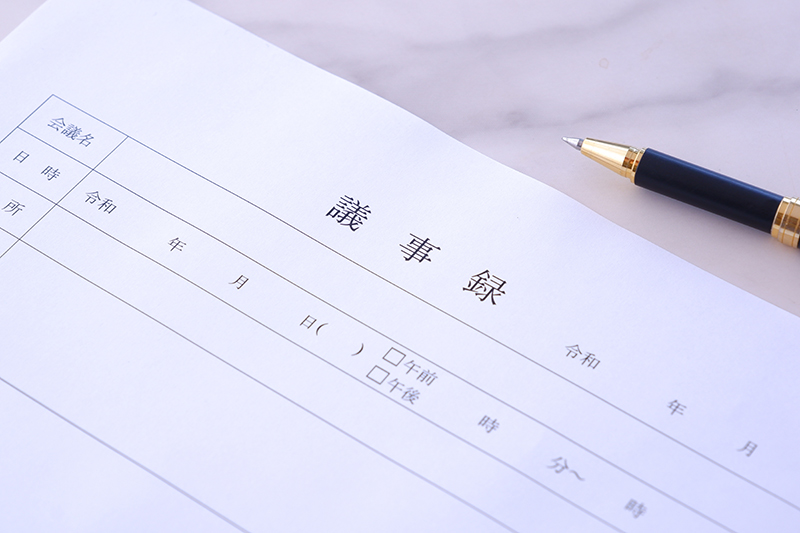
2023.10.06 中小企業おすすめ情報
コロナでここが変わった!~会社の議事録に印鑑を捺さなくなる?
はんこが押せないから、決済ができない! コロナ禍が始まったときに問題になったのは、「はんこが押せないから、決済ができない!」と言うものでした。会社の方針を決める決済は、すべてはんこが必要で、はんこを捺すためには、会社に行かなければならない。これは会社に限ったことではありません。町内会の回覧板も、学校の連絡帳も、みんなはんこに頼っていたんです。 考えてみれば、こんなに不確かな制度は無いように思います。はんこなど、珍しい名字でも、はんこ屋に行って、簡単に作れます。まして、珍しい名字でなければ、文房具屋でも、100円ショップでもはんこは売っています。「これは私のはんこで間違いありません」と証明できることができるでしょうか? 電子署名の出番 コロナ禍になり、急速にデジタル化が進みました。今やコロナに関わらず、テレワークが無くなれば、退職も考えるほどの影響を与えています。 はんこ制度も以前のように簡単に捺印ができなくなり、代わりに「電子署名」「電子証明書」という名前が聞かれるようになりました。電子署名についての法律が制定されたのは、平成12年、今から20年以上も前です。その...
-
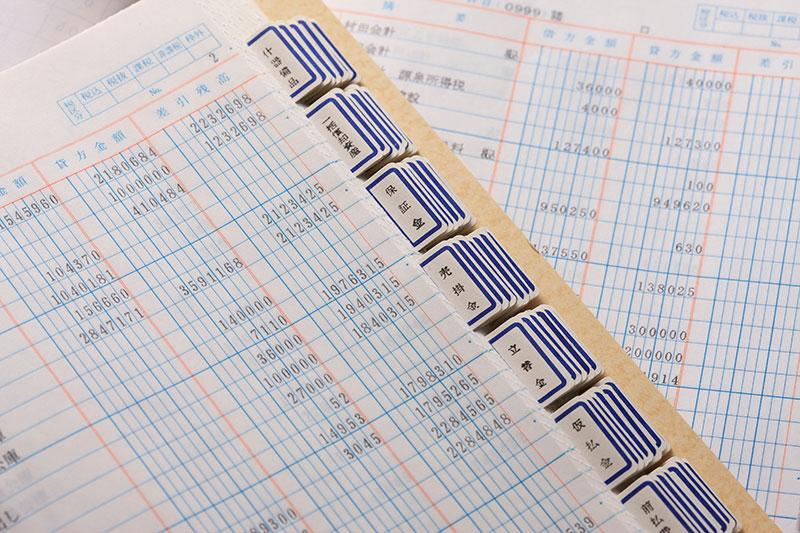
2023.08.16 税務ニュース
帳簿作成~頑張るばかりが能じゃない~
1.はじめに 突然ですが、会計帳簿はなぜ作成するのでしょうか。私が学生時代に買わされた教科書には、企業内外の利害関係者に提供する財務情報を作成するための大元の資料とすると言ったようなことが書いてあった気がします。しかし、個人事業主の目線からすると、青色申告特別控除55万円を獲得するための要件だから渋々作成している方も多いかと思います。そうであれば、事業主にとっては、青色申告特別控除が適用される必要十分な帳簿を作成したい。作成の手間は、少なければ少ないほど良いことになります。 では、必要十分な帳簿とは何かを把握しなければなりません。これは、すなわち発生主義の考え方で作成された複式簿記であるとされています。もう少し平たい表現にしますと、売上と必要経費を適切に計上した複式簿記ということです。と言うことは、青色申告特別控除の制度には、ご褒美(特別控除)を用意するから儲け(所得)の計算をちゃんとやって欲しいという意図が見えて来ます。 そうしますと、儲けの計算以外の部分は、多少簡略的な処理をしても許容される余地があると考えられます。無論、間違っていたり、やるべき事をマルっとやらないと言う...
-

2023.01.25 中小企業おすすめ情報
経理処理を効率化! 法人カードのメリットや導入時の注意点を解説
クレジットカードには個人の一般消費者向けに発行されているカード以外にも、企業や個人事業主が事業のために利用できる「法人カード」があります。ここでは経理事務の削減や資金繰りにも役に立つ法人カードの特徴を解説していきます。 事業の経費を支払うためのクレジットカード 法人カードとは企業などの法人や、個人事業主に対して発行されるクレジットカードです。基本的には、法人の代表者や個人事業主がクレジットカードの発行企業に申し込みを行い、カードの契約者となることで利用できます。 法人カードは、主に事業に関する経費を支払う目的で使用され、個人向けカードより利用限度額が大きい傾向があります。加えて特徴的なのが、契約した代表者だけではなく、従業員が利用するためのカードも複数枚発行できる点です。 また、個人向けのクレジットカードとは異なり、代金の引き落とし先として、法人が名義人となる銀行口座(法人口座)を指定することもできます。これにより、多数の従業員が複数枚の法人カードで支払いを行ったとしても、支払い元を1つの法人口座とすることが可能なのです。 経費精算や会計処理の手間を減らせる 企業などの法人...
-

2022.12.14 税務ニュース
クリニックが今取り組むべきDXとは?収益プロセスと人件費プロセスの重要性
新型コロナ・ウイルス感染症のパンデミック以降、我が国のクリニック(無床診療所)は、コロナ対策が徹底されたことで季節性感染症や風邪の発生が例年に比べて大幅に減少したことが響いたり、学校の休校や部活動の自粛でスポーツでのケガによる受診が減ったほか、外出自粛の影響で交通事故などによる外傷の受診も減少しています。結果的に、帝国データバンクが示しているように、実に8割のクリニックがコロナ前に比べて減収しているようです。 また、従来から問題視されている通り、2021年2月5日の医療制度改革関連法案の決定による2025年からの後期高齢者の医療費窓口負担の増加に端を発し、全世代の患者さんの医療費負担の増加→家計負担の増加→受診控え→クリニックの減収という予測される負のスパイラル(いわゆる2025年問題)への対応が急がれています。 今回はそのような環境変化において、クリニックがどのようにDXを試みるべきか、検討していきたいと思います。 クリニックの基本的なビジネス はじめに、クリニックの基本的なビジネスプロセスについて整理をしておきます。クリニックは、診療科や医薬処方の有無などの個別差はある...
-

2022.12.05 IT・ガジェット情報
2025年以降、DX化を推進しない企業が生き残っていくのは難しい時代になる
日本企業のDXが進まないと、2025年以降は毎年12兆円の経済損失が生じる 経済産業省は2018年に「DX(デジタルトランスフォーメーション)レポート」を発表し、これまでの非効率なビジネスのやりかたを続けた場合、2025年以降に毎年最大12兆円の経済損失が生じると予測しました。これを「2025年の崖」と呼び、経営者の中でも「DX」という言葉がバズりました。 経済産業省は企業が自己診断できる「DX推進指標」を2019年に策定したところ、日本のDXは諸外国と比べ想定以上に遅れていることがわかりました。その後コロナ禍に突入し、テレワークやビデオ会議などが普及しIT化が進んだように見えたのですが、2020年の自己診断でも9割以上の企業がDXに未着手でした。 [caption id="attachment_11017" align="aligncenter" width="1372"] DX推進指標自己診断結果。グラフは「DXレポート2」より[/caption] 2020年に経済産業省が発表した「デジタルガバナンス・コード2.0」ではDX化を推進するため、経営者に求め...









 トップ
トップ



![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)

