MENU


 PICKUP
PICKUP
税務ニュース
【2025年度(令和7年度)税制改正(その1)】103万円の壁の引き上げは123万円に!いつから?大学生のバイト「103万円→150万円」の控除も解説
昨年12月20日に2025年度(令和7年度)税制改正大綱が公表されました。もっとも注目されたのは「103万円の壁の引き上げ」です。どうなったのでしょうか。いつから始まるのでしょうか。今回は、103万円の壁の引き上げと大学生のバイトの壁の引き上げを中心に解説します。 2025年度(令和7年度)税制改正①「103万円の壁」が「123万円の壁」に 個人向けの税制改正の1つ目は「103万円の壁の引き上げ」です。 103万円の壁とは、パート・バイトといった給与所得者の非課税枠を言います。「給与所得控除の下限55万円+基礎控除額48万円=給与年収の非課税の上限103万円」という内容です。 多くのパート・バイトはこの103万円の壁を気にするため、年末になると「働き控え」という現象が起きていました。そのため、企業は人手不足に悩み、家計は物価高が改善されないという状況に陥っていたのです。 そこで、与党から政策協力を求められた国民民主党が「103万円の壁を引き上げるべきだ」と提案しました。議論が重ねられた結果、今回の税制改正で103万円の壁が引き上げとなったの...

社会保険ワンポイントコラム
職場の離職率低下につながる効果が!治療と仕事の両立支援について
治療と仕事の両立についての社会的背景 近年、医療の進歩により、がんのように以前は不治とされていた病気でも生存率が向上し、長期にわたって仕事との両立が可能になりつつあります。病気になったらすぐに離職しなければならないという状況から、治療を行いながら仕事を続けられる社会的環境へと変化しています。 しかし、疾病や障害を抱える従業員を支援するための社内体制が整っていない場合、従業員は仕事を続けたくても離職を選択せざるを得ません。これは企業にとっても人材の大きな損失といえるでしょう。 両立支援の内容 治療と仕事の両立支援の内容ですが、具体的には次のような柔軟な働き方ができる制度を設けた上で、私傷病の治療や療養を目的とした利用ができるようにします。 時差出勤制度 短時間勤務制度 時間単位の休暇制度・半日休暇制度 フレックスタイム制度 在宅勤務(テレワーク)制度 休職制度 両立支援に取り組むことの効果 労働政策研究・研修機構(JILPT)の「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)2024年3月」によれば、上記のよう...

43件 1~20件を表示
-

2025.01.20 起業応援・創業ガイド
【契約書の基本】トラブル防止のためのチェックポイント②不動産の賃貸借契約書
契約書の基本シリーズです。今回は多くの人がかかわる賃貸借契約書のチェックポイントを解説します。居住用や事業用としてアパートやマンションを借りようとしている方は必見です。 アパートやマンションを借りる時の「賃貸借契約書」とは アパートやマンションを借りるとき、必ず賃貸借契約書を作成します。なぜこのような書類が必要なのでしょうか。重要事項説明書とどう違うのでしょうか。最初に目的や内容を確認しましょう。 目的 そもそも、賃貸借契約とは「目的となる不動産などを有償で使用する」あるいは「不動産を活用して金銭を稼ぐ(経済的利益を得る)」といった行為のための契約です。一般に、賃貸借契約を締結すると、貸主・借主の双方に次のような義務が生じます。 【貸主】 物件を適切な状態で使用させる義務 修繕費用の支払い義務 改良費の支払い義務 【借主】 家賃を支払う義務 借りた物件を注意深く使用する義務(善管注意義務) 原状回復の義務 重要事項説明書との違い 重要事項説明書とは、契約内容の中でも特に重要な事項について説明を記した書面を言います。 重要事項説明は、宅...
-

2024.12.23 税務ニュース
【インボイス】「登録やめたい」「2割特例使えない」個人事業主が年内に知るべき消費税の届出とは?注意点も解説
インボイスに登録したものの、想定外の事態になった個人事業主の方は多いのではないでしょうか。そんなとき、知っておきたい届出書があります。しかし注意点も。今回は、インボイス登録ではじめて課税事業者となった個人事業主向けに、今年中に押さえておきたい消費税の届出と注意点をお伝えします。 インボイス登録後、小規模な個人事業主の事情は変わる 「私の売上規模は小さいし、2割特例で税金少ないから登録しようかな」 「インボイスを発行できないと、商売がやりにくくなるかもしれない」 こういった動機でインボイス(適格請求書)の発行事業者に登録した個人事業主の方は多いのではないでしょうか。しかし登録して時間が経過し、当初の予想と違うようになったケースもあるかと思います。 特に次の2つのケースです。 インボイス登録しなくてもよかった インボイス登録が必要なのは主にBtoBのビジネスです。美容院やネイルショップ、塾といったエンドユーザーが相手のBtoCビジネスならば、登録しなくても困りません。主婦や子どもといった一般消費者は、消費税の申告や仕入税額控除は関係ないからです。 【参考】【インボイス相談】イン...
-
![個人事業主も活用したいクラウドファンディングのしくみと税金[第5回]:寄付型クラウドファンディングと税金](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-97.jpg)
2024.12.20 起業応援・創業ガイド
個人事業主も活用したいクラウドファンディングのしくみと税金[第5回]:寄付型クラウドファンディングと税金
近年、フリーランスや個人事業主も活用できる資金調達手段として注目されているクラウドファンディング。何回かの連載で、フリーランスや個人事業主が知っておきたいクラウドファンディングのしくみと税金について解説します。第5回では個人が実施する寄付型クラウドファンディングにスポットをあててみましょう。 寄付型クラウドファンディングと税金 寄付型クラウドファンディングは、被災地や社会的弱者の支援など、社会貢献性の高いプロジェクトに利用されることが多い資金調達方法です。寄付型クラウドファンディングは、東日本大震災をきっかけに日本国内での普及が進みました。 寄付型クラウドファンディングの特徴は、支援者がクラウドファンディング実施者の社会貢献活動に対して資金を提供し、見返りを求めないというものです。したがって、寄付型クラウドファンディングにおいて、支援者が受け取るリターンの多くは、「お礼の手紙」「定期的な活動報告」「イベントへの参加」「プロジェクトのノベルティ」などとなっています。 寄付型クラウドファンディングには、寄付(寄附)に関する税金のルールが適用されます。しかし、寄付型クラウドファン...
-

2024.12.16 税務ニュース
【個人事業主の定額減税】定額減税のキホンから令和6年分所得税確定申告書への定額減税の記載方法まで税理士が解説!
早いもので今年も確定申告シーズン間近ですね。令和6年分の所得税確定申告は、定額減税に関する取扱いに注意が必要です。この記事では、個人事業主やフリーランスの方向けに、定額減税のキホンから令和6年分確定申告書への記載方法まで解説します。 1. 定額減税の対象者 定額減税は、次の1. 2.のどちらにも当てはまる方が対象です。 令和6年分所得税の納税者である居住者(※) 令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方 ※「居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。居住者以外の個人である「非居住者」は定額減税の対象とはなりません。 2. 定額減税額 定額減税の控除額は、次の合計額です。 対象者1人につき、所得税から3万円、住民税から1万円控されます。 ※所得金額等の要件があります。 ㊟青色事業専従者等は、定額減税の対象となる同一生計配偶者等には含まれないため、青色事業専従者等について定額減税の適用を受けることはできません。青色事業専従者等で一定以上の所得がある方は、ご自身で定額減税の適用を受けま...
-
![個人事業主も活用したいクラウドファンディングのしくみと税金[第4回]:購入型クラウドファンディングと消費税](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-108.jpg)
2024.11.25 起業応援・創業ガイド
個人事業主も活用したいクラウドファンディングのしくみと税金[第4回]:購入型クラウドファンディングと消費税
近年、フリーランスや個人事業主も活用できる資金調達手段として注目されているクラウドファンディング。何回かの連載で、フリーランスや個人事業主が知っておきたいクラウドファンディングのしくみと税金について解説します。第4回では購入型クラウドファンディングと消費税の関係にスポットをあててみましょう。 購入型クラウドファンディングは消費税課税が原則 クラウドファンディングサイトでは、一般的に「支援」や「応援」といった言葉が用いられるため、集めた資金には消費税が課税されないと考えている人も多いのではないでしょうか。 実は、購入型クラウドファンディングで集めた資金は、原則として、消費税の課税対象になります。なぜなら、第2回で解説したとおり、購入型クラウドファンディングの実態は、事業者が行う対価性のある通常の売買取引と同じだからです。 個人事業主も活用したいクラウドファンディングのしくみと税金[第2回]:購入型クラウドファンディングに係る税金① 一方、購入型クラウドファンディングであっても、消費税が課税されないケースもあります。消費税が課税されるケースと課税されないケースの違いは、どこにある...
-

2024.11.22 起業応援・創業ガイド
【契約書の基本】トラブル防止のためのチェックポイント①業務委託契約書(フリーランス向け)
今回から数回にわたって、契約書の基本を解説します。1回目の今回はフリーランスの方向けです。よく使われる業務委託契約書のポイントをわかりやすくお伝えします。 フリーランスに多い「業務委託契約書」とは?目的を確認 業務委託契約とは、企業が業務をフリーランスや法人などに外注する際に締結する契約形態のことです。コンテンツ制作やシステム管理などを中心に、幅広い業務委託で行われます。この契約を締結する際に作成するのが「業務委託契約書」です。 本来、口頭でも契約は成立します。それなのに、なぜわざわざ契約書という書面を作成するのでしょうか。これには次のような目的があるからです。 合意内容を明確にする 口頭での約束は、言った側と言われた側で解釈が異なることがあります。 例えば「納期は依頼日から2週間後が目安」という決め事です。言った側は2週間より前を期待しているかもしれません。一方言われた側は「2週間を多少過ぎてもいいや」と受け取っている可能性があります。双方の理解が食い違っていると、業務開始後にトラブルに発展するかもしれません。 契約事項からあいまいさをなくし、より具体的に決めるには、書...
-
![個人事業主も活用したいクラウドファンディングのしくみと税金[第3回]:購入型クラウドファンディングに係る税金②](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-134.jpg)
2024.09.24 税務ニュース
個人事業主も活用したいクラウドファンディングのしくみと税金[第3回]:購入型クラウドファンディングに係る税金②
近年、フリーランスや個人事業主も活用できる資金調達手段として注目されているクラウドファンディング。何回かの連載で、フリーランスや個人事業主が知っておきたいクラウドファンディングのしくみと税金について解説します。第3回では、購入型クラウドファンディングを実施するうえで知っておきたい節税対策や必要経費にスポットをあててみましょう。 購入型クラウドファンディングに係る税金 購入型クラウドファンディングで集めた資金に対しては、資金調達者が事業者であれば事業所得、それ以外の場合には雑所得として、所得税および住民税が課税されます。 購入型クラウドファンディングにおいては、「資金調達者を支援する」というかたちをとっているため「支援」や「応援」といった言葉が使われていますが、その実態は事業者が行う通常の売買取引と同じです。資金調達者はリターンという名目で商品やサービスを提供し、資金提供者は支援金という名目でその対価を支払っているにすぎません。そのため、資金調達者が事業を営んでいる場合、資金調達者が資金提供者から受け取った資金は、事業所得として所得税および住民税の課税対象となるのです。 なお...
-
![経営相談の現場から[シリーズ第3回]補助金の説明資料が難しすぎます](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-135.jpg)
2024.09.19 起業応援・創業ガイド
経営相談の現場から[シリーズ第3回]補助金の説明資料が難しすぎます
筆者は経営コンサルタントとして、日々経営者の方々のお悩みを伺っています。このシリーズは「経営相談の現場から」というテーマで、中小企業経営者や個人事業主の方から実際にあったご相談内容を取り上げます。今回は、大変多いご相談テーマのひとつである補助金のご相談を取り上げます。 魅力的な「補助金」。だけど分からないことだらけ! Cさん 「美容サロンを経営しています。3年前に自宅の一室を改装して開業しました。少しずつお客様が増えています。もっと売上を上げたいので、いろいろな取り組みを考えているところです。」 筆 者 「どんな取り組みを考えていますか?」 Cさん 「私のお店はヘアカットやヘアカラーが中心ですが、新メニューとして身体の脱毛やフェイシャルエステを始めようと考えています。」 筆 者 「なるほど。客数と客単価、両方を上げられそうな取り組みですね。」 Cさん 「そうなんです。それで脱毛機を導入したいのですがとても高価なので、何か補助金が使えたらいいなと思っています。でも補助金の内容が難しくて。」 筆 者 「どの補助金を調べましたか?どういうところが難しかったですか?」 Cさ...
-

2024.09.17 税務ニュース
法人成りとは?個人事業主が自分で手続きするときの流れを解説②税務・労務の届出・申請
登場人物 よっちゃん(以下「よ」):まゆこの夫。行政書士。仕事はできるが税金はくわしくない。特技は料理と釣り。夢は釣り三昧の日々。 まゆこ(以下「ま」):税理士・税務ライター。「こむずかしい税金をいかに分かりやすく表現するか」ばかり考えている。趣味は、よっちゃんのごはんを食べること。 「そろそろ法人成りしたい」。そんな風に感じるタイミングが個人事業主に訪れることがあります。個人事業主として行ってきた業務を法人に移す「法人成り」はどんな手続きが必要なのでしょうか。2回にわたって解説します。2回目の今回は税務・労務の手続きと注意点です。 登記したら税務・労務の手続きが必要…なぜ? よ「個人の事業を法人化したら、税務や労務の手続きも必要になるよね」 ま「そうなの」 よ「あらためて考えると面倒くさいよね。会社作って終わったら、そこで終わりにしてほしい」 ま「そうねぇ。でも会社も人間と同じく、経済活動をすればいろいろ社会的な責任が生じるから必要なのよ」 よ「?」 ま「ちょっと聞くけど、会社の経済活動にはどんなものがあると思う?」 よ「こんな感じかなぁ」 ま「こう...
-
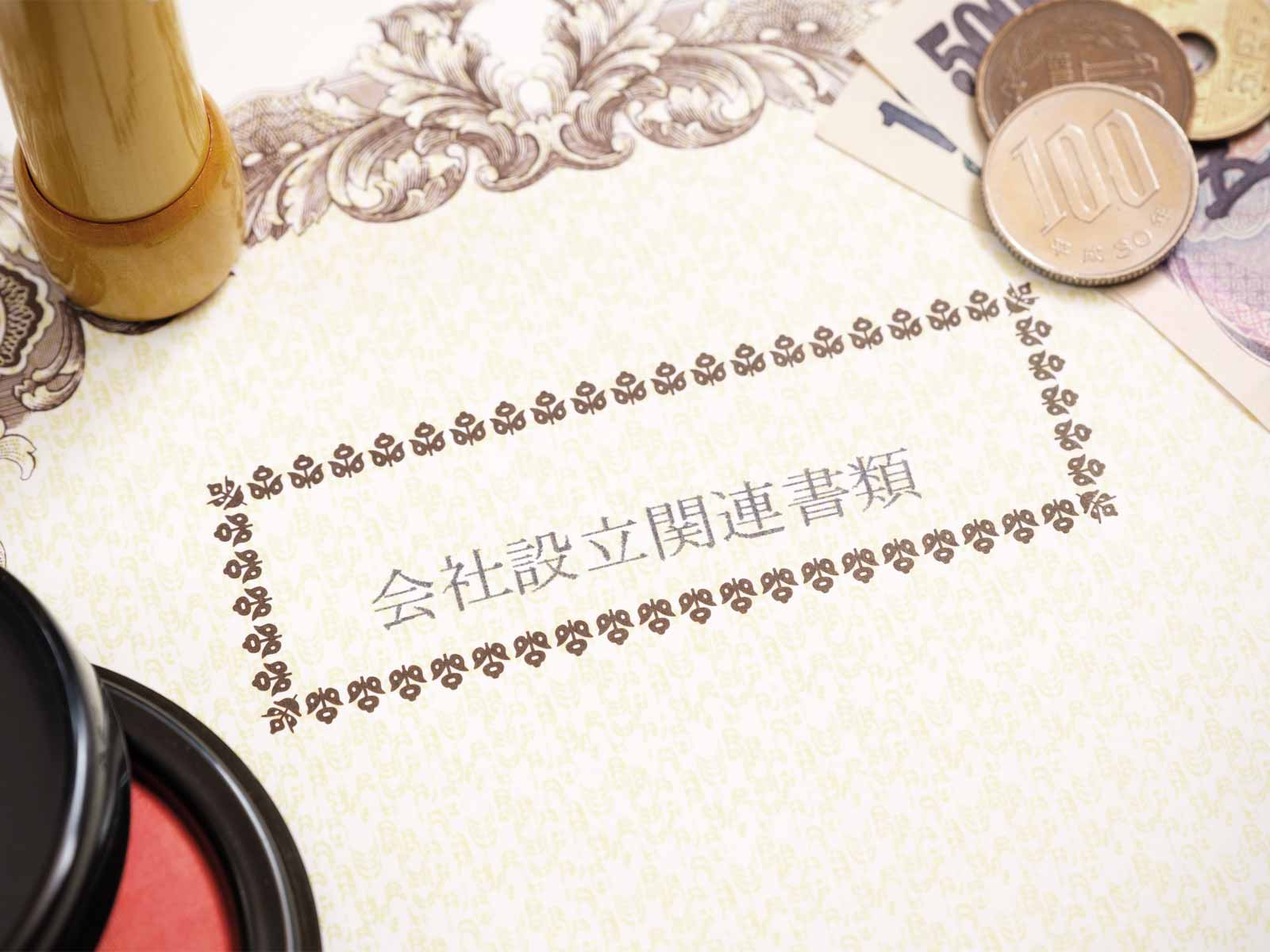
2024.09.13 起業応援・創業ガイド
法人成りとは?個人事業主が自分で手続きするときの流れを解説①概要決定~登記
「そろそろ法人成りしたい」。そんな風に感じるタイミングが個人事業主に訪れることがあります。個人事業主として行ってきた業務を法人に移す「法人成り」はどんな手続きが必要なのでしょうか。2回にわたって解説します。1回目の今回は登記までの流れです。 登場人物 よっちゃん(以下「よ」):まゆこの夫。行政書士。仕事はできるが税金はくわしくない。特技は料理と釣り。夢は釣り三昧の日々。 まゆこ(以下「ま」):税理士・税務ライター。「こむずかしい税金をいかに分かりやすく表現するか」ばかり考えている。趣味は、よっちゃんのごはんを食べること。 法人成りで多い「株式会社」「合同会社」の違いとは よ「わりと多い法人形態は2つ。株式会社と合同会社」 ま「どう違うの?」 よ「一言で言うと『所有と経営が分離されているかどうか』。株式会社は分離されている。『所有は株主、経営は取締役』という具合にね。合同会社は分離されていない。他にも、こんな違いがある」 法人成りの手続き よ「法人を作るときの手続きを株式会社の場合で説明していくね」 1.会社の概要を決める ...
-

2024.09.11 税務ニュース
【インボイス】登録したけどやめたい…どうしたらいい?個人事業主向けに手続きと注意点を解説
「インボイス、登録したけど消費税が重いから止めたい」そんな声を聞くようになりました。インボイス登録をやめるとき、どんな手続きをいつまでにしたらいいのでしょうか。今回は、手続きと注意点を個人事業主向けに解説します。 インボイスが必要な事業主、なくてもいい事業主 「インボイスに登録してたけれど、なくても困らない」と感じた事業主がいるかと思います。事実、インボイス登録が必要かどうかは、取引先次第です。次のように分かれます。 BtoBで大企業相手 デザイナーやライターなど、大企業から受注する事業主の多くは、インボイス登録をした方が無難です。大企業は原則課税で消費税の納税額を計算しています。原則課税だと、インボイスがないと仕入税額控除できません。つまり仮払いした消費税相当額分、損をするのです。 引用元:【インボイス制度】領収書はどう書くべき?手書きもOK?個人の飲食店・小売店に解説 昨年10月前後、得意先の大企業から登録をお願いされるケースが多数ありました。「登録しないなら10%分、取引額を下げてほしい」と交渉された人もいたかと思われます。 BtoBで中小規模の事業者相手 ビジネス客...
-
![個人事業主も活用したいクラウドファンディングのしくみと税金[第2回]:購入型クラウドファンディングに係る税金①](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-146.jpg)
2024.08.23 起業応援・創業ガイド
個人事業主も活用したいクラウドファンディングのしくみと税金[第2回]:購入型クラウドファンディングに係る税金①
近年、フリーランスや個人事業主も活用できる資金調達手段として注目されているクラウドファンディング。何回かの連載で、フリーランスや個人事業主が知っておきたいクラウドファンディングのしくみと税金について解説します。第2回では購入型クラウドファンディングに係る税金について、所得税と住民税にスポットをあててみましょう。 購入型クラウドファンディングとは 「購入型クラウドファンディング」は、資金調達者が商品やサービスをリターンとして設定し資金提供を募る方法です。資金調達者は集めた資金を活用して商品・サービスを開発し、プロジェクトに賛同し支援金を支払った資金提供者は、クラウドファンディングの成立後、完成した商品・サービスをリターンとして受け取ります。 このように、「購入型クラウドファンディング」は、商品などの開発資金を大人数で提供し完成品を受け取ることから、実態としては共同購入に近い性質があります。 購入型クラウドファンディングのメリットとデメリット クラウドファンディングの本来の目的は資金調達ですが、クラウドファンディングによって得られるメリットはそれだけではありません。 まず、資金...
-
![経営相談の現場から[シリーズ第2回]安い報酬で働き詰めの現状を打破したい](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-147.jpg)
2024.08.19 起業応援・創業ガイド
経営相談の現場から[シリーズ第2回]安い報酬で働き詰めの現状を打破したい
筆者は経営コンサルタントとして、日々経営者の方々のお悩みを伺っています。このシリーズは「経営相談の現場から」というテーマで、中小企業経営者や個人事業主の方から実際にあったご相談内容を取り上げます。今回はフリーランスとして動画編集を手掛けるBさんから、今後の事業方針についてのご相談を頂きました。 毎日遅くまで作業して、月の売上は15万円・・・。 Bさん 「事業者が動画再生サイトにアップする動画の編集を請け負っています。編集技術は独学で身につけました。クライアントがご自身で撮影した動画を、私が編集します。目を引くサムネイルを作ったり、効果音やテロップを入れたり、テンポよく話が展開するようにシーンをつなぎ合わせたり、といったことをしています。」 筆 者 「動画を活用する事業者は増えていますよね。受注はどのように獲得していますか?」 Bさん 「クリエイターと発注者をつなぐマッチングサイトを利用しています。私のホームページに過去実績やサンプル動画を載せているので、それを見た方からSNSで依頼が来ることもあります。」 筆 者 「そうですか。受注は順調ですか?」 Bさん 「はい。有難...
-

2024.08.15 起業応援・創業ガイド
個人事業主の小規模企業共済とiDeCo~違いとメリット・注意点は?
1. 小規模企業共済とは?税務上の取扱い、メリットと注意点は? ①小規模企業共済の概要 小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための、積み立てによる退職金制度です。国の機関である中小機構が運営しています。2023年3月末現在の加入者数は約162万人、資産運用残高は約11兆1,313億円です。(出所:中小機構ウェブサイト) 加入者は、月々1,000円~70,000円までの間(500円単位)で掛金を納付します。そして、退職や廃業時に積み立て金額に応じた共済金を受け取ります。この共済金の受け取り方は、「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。 ②小規模企業共済の税務上の取扱い 掛金払い込み時:掛金の全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。 共済金および解約手当金の受け取り時:受け取る際の年齢や一括または分割などの受取方法などで税法上の取扱いが異なります。 (基本的な取扱い) 個人事業主が廃業した場合や会社等の解散または会社役員の退任により共済金を受け取る場合の基本的な取り扱いは次の通りです。 一時金受け取りを選択した場合は「退職所得」 分...
-
![個人事業主も活用したいクラウドファンディングのしくみと税金[第1回]:クラウドファンディングのしくみ](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-171.jpg)
2024.06.24 起業応援・創業ガイド
個人事業主も活用したいクラウドファンディングのしくみと税金[第1回]:クラウドファンディングのしくみ
近年、フリーランスや個人事業主も活用できる資金調達手段として注目されているクラウドファンディング。何回かの連載で、フリーランスや個人事業主が知っておきたいクラウドファンディングのしくみと税金について解説します。第1回ではクラウドファンディングのしくみを概観してみましょう。 クラウドファンディングとは? クラウドファンディングは、近年、世界的に注目されている資金調達手段です。 Crowd(群衆) × Funding(資金調達)の造語で、一般的には「新規・成長企業等と資金提供者をインターネット経由で結び付け、多数の資金提供者(=crowds:群集)から少額ずつ資金を集める仕組み」と説明されています。 (参照)「金融審議会 新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ報告」(平成25年12月25日) 図表1は、近年のクラウドファンディング(購入型および寄付型)の市場規模の推移です。 クラウドファンディングの市場規模は急拡大しており、スモールビジネスの創業時や個人事業の開業時などにおける資金調達方法の一つとして浸透しつつあります。クラウドファンディングは、...
-

2024.06.10 税務ニュース
事業主に記帳や申告の知識はどこまで必要か
はじめに 近年、副業も含めると、かなり多くの方が事業を始めていらっしゃいます。開業を志す方は、営業の方法や収入を増やす方法については十分に検討され、ある程度の道筋を想定していらっしゃる一方で、経理や確定申告の準備は不十分であることが多いです。 そこで、本稿では、帳簿の作成や確定申告に関する知識を「どの程度持っていれば良いか」および「どんな方法で得れば良いか」についてご紹介いたします。 帳簿作成の目的 帳簿作成の目的について考えてみます。表向きには、財政状態の推移および残高の把握、経営成績の把握ということになっています。しかし、小規模な個人事業主の場合には、主に確定申告を見据えて帳簿を作成しているのが現実と言えるでしょう。もちろん、将来的に事業が大きくなって財政状態や経営成績の把握が重要となるフェーズが訪れる可能性もありますが、開業当初は取り敢えず税務上の要請に応えられれば、最低限の目的は達成できると考えられます。 税務上の要請とは 税務上の要請とは、本来は守備範囲の広い表現ですが、開業にあたっては適正な納税額の計算と、税制の優遇措置を受ける条件と割り切ってしまえます。税制優遇は...
-

2024.06.05 税務ニュース
漫画家・作曲家は確定申告のアフターケアが大事!予定納税の注意点と対策方法について解説。
確定申告が終わってひと安心。しかし、所得税の納税は確定申告時の年1回だけとは限りません。一定の税額が発生している場合には、年の途中に「予定納税」の義務が生じることがあるのです。 特に、漫画家・作曲家などのクリエイターが平均課税制度を利用した場合は要注意。本コラムでは、所得税の予定納税の注意点と対策方法について解説します。 所得税の予定納税とは? 予定納税とは、税金の前払いルールのことです。予定納税の対象者は、年の途中に所得税の前払いをしなければなりません。 予定納税をするかどうか、そして予定納税の時期や金額は、自分で自由に決めることはできません。予定納税の義務がある人には、おおむね6月15日頃までに税務署から通知が届きます。また、予定納税の時期は7月と11月、予定納税の金額は前年の所得税の3分の2(7月と11月にそれぞれ3分の1ずつ)と税金のルールで決められています。 予定納税の義務がある場合、納付期限を過ぎると延滞税という追加の負担が発生してしまうため注意しましょう。 予定納税の対象となる人は? 予定納税の対象者かどうかは、前年の確定申告の納税額で判定します。 具体的に...
-

2024.04.26 税務ニュース
【定額減税】個人事業主の定額減税はどうなる?
1. 定額減税とは? 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和等する観点から、令和6年分の所得税と令和6年度分の個人住民税について、一定額行われる減税です。 2. 定額減税の対象者 次の①②のいずれにも該当する方が対象です。 ①令和6年分所得税の納税者である居住者 ②令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方 …給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下の方。子ども・特別障害者等を有する者などの所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。 ※「居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。 !POINT・居住者以外の「非居住者」は定額減税の対象とはなりません。 ・合計所得金額1,805万円超の人は対象になりません。 3. 定額減税額 定額減税の控除額は、次の合計額です。 ※所得金額等の要件があります。 ※1 納税者本人の要件は、「2.定額減税の対象者」参照 ※2 「同一生計配偶者」とは、その年の12 月31 日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は...
-

2024.04.24 税務ニュース
個人事業主の年間納税スケジュールと納税対策
はじめに フリーランスで生活するならば、当然本業に力を入れたいわけですが、自分一人あるいは少人数で経営している場合には、なかなか理想通りには行かないものです。特に資金繰りは、事業の成長・存続のみならず自身の生活にも大きな影響を及ぼすもので、実は本業と同じくらい重要となります。 そこで、本稿では、資金繰りのうちでも特に煩わしい納税スケジュールについてまとめて見たいと思います。 年間スケジュール 図1 1月 2月 3月 4月 5月 6月 住民税(第4期) 源泉所得税納期特例 固定資産税(第4期) 所得税 消費税 自動車税 軽自動車税 &nbs...
-

2024.02.27 税務ニュース
確定申告をしなければならない人、した方が良い人
始めに 税理士になりますと、確定申告シーズンに各所で行なわれる税務相談会での相談員の当番が回ってきます。相談内容は多岐に渡りますが、頻繁に質問される内容の中に、「確定申告をしなければならないのか教えて欲しい」というものがあります。実はこの質問、案外に答え難い質問です。質問の文言では、申告義務の有無だけ答えれば良さそうですが、義務は無いが申告した方が良いケースもありますので、質問された方の立場を考えると単純な返答では不適当になりかねません。 そこで、本稿では、個人事業主、ダブルワーカー、並びに法人成りした経営者をターゲットに、確定申告をするかしないかについてまとめてみたいと思います。 確定申告をしなければならない人 (1) 給与を受け取っている人について サラリーマンであれば、源泉徴収と年末調整により原則的には所得税の計算は完了しますが、次のケースでは確定申告の義務があります。 ① 給与の収入金額が2,000万円超のケース *給与の収入金額=源泉徴収票の「支払金額」=各種天引き前の給与額 ② 1社から給与を受けていて 「給与以外の所得(事業所得・雑所得etc)」が20万円超 ...









 トップ
トップ



![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)

