MENU


896件 101~120件を表示
-

2024.06.14 中小企業おすすめ情報
パナソニック創業者が採用面接で聴いた質問とは?
誰もが知っているパナソニックという会社。この会社の創業者が松下幸之助さんです。筆者が就職する40年前は、松下電器産業という社名でした。当時は大阪府の門真市が拠点でした。松下翁は、会社経営にとどまらず、1946年には「Peace and Happiness through Prosperity」のスローガンを掲げてPHP研究所を創設したり、未来のリーダーを育成するため1979年に松下政経塾を設立されたりしました。特に、松下政経塾からは野田佳彦元首相をはじめとする国会議員や県知事など多くの政治家などを輩出しています。 松下翁は1894年(明治27年)和歌山県で生まれ、尋常小学校を4年生で中退して大阪の火鉢店や自転車店で丁稚奉公に出ています。その後、大阪電燈(現在の関西電力)に勤務。1918年(大正7年)23歳のときに松下電器器具製作所を創業されています。その後は、紆余曲折はあったにせよ、日本の経済成長と軌を一にして「天下の松下電器」へと成長させました。その松下翁の口癖は「成功したのは運が良かったから」「3つがなかったお陰」。3つとは「学歴がなかった」「家が貧しかった(落ちぶれた)...
-

2024.06.12 社会保険ワンポイントコラム
就業規則が分厚いと社員のモチベーションが高いワケ
人は予測できないことに不安を感じる 人の心理として、予測できないことに不安を感じます。たとえば、転職してきた人が、会社のルールが分からず不安というのも、この予測可能性が低いことが原因です。 そして、不安を感じると、社員のモチベーションにも影響を与えます。これはみなさん経験的に分かるのではないでしょうか。そのため、予測できないことをできるだけ少なくしていくことが社員のモチベーション維持や向上に必要です。 就業規則の周知が予測可能性を高める 会社には就業規則をはじめ、慣習的なものや暗黙知のようなルールが存在します。このようなルールはできるだけ周知して社員の予測可能性を高めましょう。 特に、就業規則は法令で周知が必要とされています。よく言われる例え話の中に、「就業規則を社長の机の中や社内の金庫にしまっているのはNG」というのがありますが、実際に私が関わった会社でも本当にあった話です。 周知の方法は、「社内に掲示」、「書面で交付」、「データで共有」などがあります。会社の規模などにもよりますが、クラウド上にデータで保存しておくのがベターでしょう。これだとテレワークで働いている社員も常...
-

2024.06.10 税務ニュース
事業主に記帳や申告の知識はどこまで必要か
はじめに 近年、副業も含めると、かなり多くの方が事業を始めていらっしゃいます。開業を志す方は、営業の方法や収入を増やす方法については十分に検討され、ある程度の道筋を想定していらっしゃる一方で、経理や確定申告の準備は不十分であることが多いです。 そこで、本稿では、帳簿の作成や確定申告に関する知識を「どの程度持っていれば良いか」および「どんな方法で得れば良いか」についてご紹介いたします。 帳簿作成の目的 帳簿作成の目的について考えてみます。表向きには、財政状態の推移および残高の把握、経営成績の把握ということになっています。しかし、小規模な個人事業主の場合には、主に確定申告を見据えて帳簿を作成しているのが現実と言えるでしょう。もちろん、将来的に事業が大きくなって財政状態や経営成績の把握が重要となるフェーズが訪れる可能性もありますが、開業当初は取り敢えず税務上の要請に応えられれば、最低限の目的は達成できると考えられます。 税務上の要請とは 税務上の要請とは、本来は守備範囲の広い表現ですが、開業にあたっては適正な納税額の計算と、税制の優遇措置を受ける条件と割り切ってしまえます。税制優遇は...
-

2024.06.07 IT・ガジェット情報
デジタルデトックスのススメ:ストレス軽減!デジタル依存の解放術
はじめに 現代社会において、デジタル機器は私たちの生活に欠かせない存在となっています。しかし、その過度な依存が問題視されるようになりました。常に情報を受け取り、即座に反応することを求められる環境は、ストレスを蓄積させ、心身の健康を脅かしています。 こうした背景から注目されているのが、「デジタルデトックス」という取り組みです。デジタルデトックスとは、一定期間意図的にデジタル機器から離れ、デジタル依存から解放されることを指します。ただし、デジタルそのものが悪だと決めつけるのではなく、デジタルとのバランスを保つことが大切です。(筆者はわかりやすくする為に、デジタルデトックスという言葉を選択していますが、デジタルの影響が必ずしも毒だとは思っていません。) 筆者自身、デジタル機器に囲まれた生活を送る中で、デジタルデトックスの必要性を強く感じるようになりました。そこで、2015年から毎年1回、自然豊かな千葉県香取市にて、2日間のデジタルデトックスを行っており、その効果を実感しまています。この記事では、筆者の体験を交えながら、デジタルデトックスの意義や方法についてお伝えして参ります。 デジ...
-

2024.06.05 税務ニュース
漫画家・作曲家は確定申告のアフターケアが大事!予定納税の注意点と対策方法について解説。
確定申告が終わってひと安心。しかし、所得税の納税は確定申告時の年1回だけとは限りません。一定の税額が発生している場合には、年の途中に「予定納税」の義務が生じることがあるのです。 特に、漫画家・作曲家などのクリエイターが平均課税制度を利用した場合は要注意。本コラムでは、所得税の予定納税の注意点と対策方法について解説します。 所得税の予定納税とは? 予定納税とは、税金の前払いルールのことです。予定納税の対象者は、年の途中に所得税の前払いをしなければなりません。 予定納税をするかどうか、そして予定納税の時期や金額は、自分で自由に決めることはできません。予定納税の義務がある人には、おおむね6月15日頃までに税務署から通知が届きます。また、予定納税の時期は7月と11月、予定納税の金額は前年の所得税の3分の2(7月と11月にそれぞれ3分の1ずつ)と税金のルールで決められています。 予定納税の義務がある場合、納付期限を過ぎると延滞税という追加の負担が発生してしまうため注意しましょう。 予定納税の対象となる人は? 予定納税の対象者かどうかは、前年の確定申告の納税額で判定します。 具体的に...
-

2024.06.04 見逃し配信
【見逃し配信】ファイナンシャルプランナーから学ぶ 新NISA 徹底解説
2024年5月29日(水)、ソリマチ株式会社はFPサテライト所属 ファイナンシャルプランナー 畑野 晃子 先生をお招きし、「ファイナンシャルプランナーから学ぶ 新NISA 徹底解説」と題した無料のオンラインセミナーを主催いたしました。 セミナーレポート NISAとは、株式や投資信託の配当金や分配金、売却益が非課税になる制度で、18歳以上なら誰でも利用でき、資産形成に役立てることができます。2024年から制度の一部が変わって「新NISA」が始まり、ますます注目が集まっています。 しかし、「投資」は難しそう、よくわからない、またはリスクがあるというイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。今回のセミナーでは、畑野先生がNISAとはどういう制度なのか、というところから解説し、運用の具体的な方法や、リスクとどのように向き合っていけばいいのかを、先生自身の運用例も交えて、わかりやすくご解説いただきました。 セミナーの録画は以下のURLでご視聴いただけます。NISAが気になる、もっと知りたいという方は、ぜひご覧ください。 [template id="4604"]
-

2024.06.03 税務ニュース
お酒の転売、シロウトがやると違法になる?法務・税務のリスクを解説②税務編
前回に引き続き、今回もお酒の転売に関する注意点です。今回は税務面についてお伝えします。 登場人物 よっちゃん(以下「よ」):まゆこの夫。行政書士。仕事はできるが税金はくわしくない。特技は料理と釣り。夢は釣り三昧の日々。 まゆこ(以下「ま」):税理士・税務ライター。「こむずかしい税金をいかに分かりやすく表現するか」ばかり考えている。趣味は、よっちゃんのごはんを食べること。 酒の繰り返し転売には税金がかかる ま「気になって調べたけど、前からお酒の転売は問題になっているのね」 よ「どれどれ…えっ!主婦も?」 ま「テーマは無免許販売による酒税法違反だけど…たぶん他の税金も納めていないんじゃないかしら」 【参考】酒類の無免許ネット転売が横行…大阪国税局、主婦や法人などに計188万円の納付通告 ま「『家にある不用品をたまに売る』程度だったら問題ないのよ。生活用動産の譲渡は所得税も住民税も非課税。消費税だってかからない。お酒は生活用動産とは言い難いけど、金額なんてたかが知れているから問題にならない。当然、酒販売の免許もなければ義務も果たさない」 よ「繰り返し転売だとどう...
-

2024.05.31 税務ニュース
お酒の転売、シロウトがやると違法になる?法務・税務のリスクを解説①法務編
コロナ以降、お酒の転売が急増しました。ネットのフリーマーケットで売り買いが行われているほか、街中でも買取業者の店舗を目にします。「飲まないお酒をたまに売る」くらいならいいのですが、頻繁に売買を繰り返すときは注意です。お酒の転売についての注意点を、2回にわたって解説します。今回は法務編です。 登場人物 よっちゃん(以下「よ」):まゆこの夫。行政書士。仕事はできるが税金はくわしくない。特技は料理と釣り。夢は釣り三昧の日々。 まゆこ(以下「ま」):税理士・税務ライター。「こむずかしい税金をいかに分かりやすく表現するか」ばかり考えている。趣味は、よっちゃんのごはんを食べること。 酒の繰り返し転売で行政処分が下る よ「まゆこ、このニュース知ってる?」 ま「どれどれ…えっ、酒の買取販売で逮捕されたの?びっくり」 よ「高級ウイスキー1500本、2500万円相当を繰り返し転売してたんだって」 【参考】高級酒を無免許で繰り返し転売か 20代男性行政処分 大阪国税局 ま「でもさ、最近、お酒の買取業者って増えているじゃない?一般人からウイスキーとか...
-
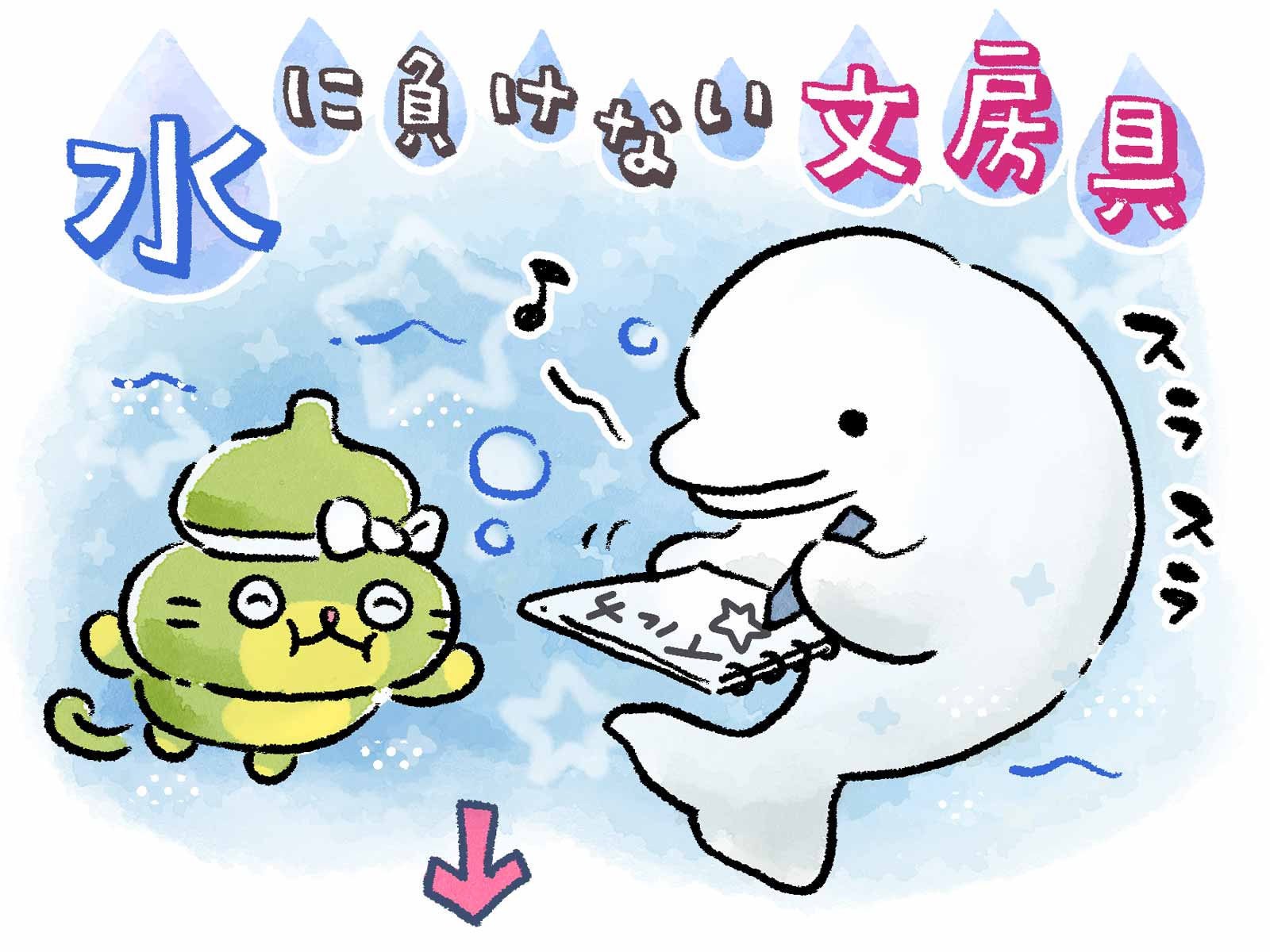
2024.05.30 IT・ガジェット情報
【文具ライター推薦】雨や屋外でもしっかり使える!水に負けない文房具
屋外でいざメモを取ろうと思った時に雨が降ってきてしまい、ペンのインクが滲んで文字が書けなかったり、紙が濡れてシワになって使えなくなってしまった…という経験はありませんか? そんな梅雨のシーズンや屋外作業、アウトドアなどの野外でも力を発揮してくれる、雨や水に負けない文房具をご紹介します。 濡れた紙にも書ける油性ボールペン「ウェットニー」 [caption id="attachment_17108" align="aligncenter" width="800"] メタルボディで耐久度も高くアウトドアでも大活躍[/caption] 屋外で打合せや電話をしているときに急に雨が降ってきてしまった時、メモを書いたら水で滲んで読めなくなったり、メモをとるのを諦めてしまい後から内容を確認する…といった経験はありませんか? 文房具は水に弱いイメージがある方も多いと思いますが、実は水に強く濡れても使える文房具もあるんです。 [caption id="attachment_17109" align="aligncenter" width="800"] ウェットニーは濡れた紙にもしっかり書けます...
-

2024.05.29 IT・ガジェット情報
事業に使える「電動自転車」!坂道も重い荷物もエコ・楽!
最近で電動自転車をよく見かけるようになりました。とくに印象的なのは、前後に子どもを乗せたお母さんが、颯爽と坂道を登っていくシーンです。とはいえそんなに楽々と坂道を登れるものなのか? 長距離を走れるのか? バイクのように素早く走れるのか? バッテリーはどのぐらい持つのか?など気になるところも多いでしょう。 ここでは通勤通学だけでなく、荷物を運んだり、拠点間を移動する手段として、仕事に事業に使えるのかを解説しましょう。 電動自転車って本当に便利?坂道は?最高速度は?疲れない? 電動自転車のメリットは、免許がなくても乗れる点です。バイクのようなアクセルはありませんが、べダルを漕ぐとモーターがアシストしてくれるので、普通の自転車よりペダルが軽くなります。 電動自転車で一番気になるのは坂道でしょう。事務所や自宅までの経路に坂道がある方は、絶対オススメします。緩やかな長い坂でも、ずっとモーターがアシストしてくれるので、ほぼ平地と変わりありません。またほとんどの電動自転車にはギアがついているので、べダルが重いと感じたらローギア(べダルは軽くなるが漕ぐ回数が増える)にチェンジすると、よ...
-
![アフターコロナの経営[シリーズ第5回]我が社はどれくらい借りられる?目安を知ろう](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-186.jpg)
2024.05.27 中小企業おすすめ情報
アフターコロナの経営[シリーズ第5回]我が社はどれくらい借りられる?目安を知ろう
このシリーズでは「アフターコロナの経営」というテーマで、この時代を生きる経営者が持っておきたい視点、知っておきたい情報を取り上げています。前回(第4回)のコラムでは、コロナ融資の返済に苦しむ事業者が多い現状を受け、返済が苦しいときの対応に関する基礎知識を取り上げました。今回のコラムでは、アフターコロナもまだまだ資金調達を必要とする事業者が多いことを受け、「自社はあとどれくらい借りられるのか」を考えるときの目安を解説します。 アフターコロナも資金需要は尽きない コロナ禍で大きなダメージを受けた事業者の多くが、徐々にお客様を取り戻して回復に向かっているのではないでしょうか。完全回復までの道のりで頼りの綱となるのは、やはり「手元資金」です。例えばコロナ禍で従業員が離れてしまった場合は、人材の採用・教育・定着に取り組む資金が必要です。施設設備の修繕やバリューアップが必要なケースもあるでしょう。アフターコロナに世の中に浸透したデジタルツールを導入するケースもあるでしょう。 コロナ禍の局面では主に「赤字の補填」という意味でコロナ融資が必要でしたが、アフターコロナに立ち直ろうとする局面では...
-

2024.05.22 中小企業おすすめ情報
備えあれば患いなし?災害発生時に企業が取るべき対応について
近年、パンデミックや紛争、そして大地震等の自然災害等により、企業の危機管理や事業継続の在り方が問われるような事態が続発しています。災害等が発生した場合、通常通り業務を実施することが困難になります。企業としてはどのように備えておけば良いのでしょうか。 1. BCP策定について 介護事業所では、3年の経過措置期間が終わり2024年4月より「BCP」の策定が完全義務化されました。「BCP」とは、「Business Continuity Plan」、「事業継続計画」と訳され、中小企業庁のホームページでは、「BCP(事業継続計画)とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと」と説明されています。 各種サービス提供が途絶えてしまうと、サポートを必要とする高齢者や障害者等へ大きな影響を与えてしまいますので、介護事業所にて義務化されましたが、近年の状況からすると、全ての企業におい...
-

2024.05.21 見逃し配信
【見逃し配信】給料王ユーザー様向け 定額減税対応セミナー
2024年5月15日(水)、弊社サポートセンターの給料王チームの定額減税担当が講師として登場し、『給料王』での定額減税の方法を解説する無料のオンラインセミナーを主催いたしました。 セミナーレポート 2024年6月から実施される「定額減税」では、従業員の賞与と給与に対する減税は、法人側が対応を行う必要があります。今回のセミナーでは、ソリマチサポートセンターの定額減税担当が、『給料王』を使用した定額減税への対応方法を解説しました。給与/賞与計算の流れを、テキストと『給料王』の画面を見ながら具体的に説明しています。 定額減税については、多くの方がご興味を持っているようで、たくさんのご質問をいただきました。「6月より前に定額減税の設定をしても大丈夫ですか」「間違った設定をした場合はどう修正したらよいですか」などの質問にお答えしています。 また、6/27(木)には、鈴木まゆ子税理士先生をお招きし、「定額減税どうしたらいい?毎月の給与・賞与 ~よせられた質問にお答えします~」というセミナーの開催を予定しています。 セミナーの録画は以下のURLでご視聴いただけます。ご興味をお持ちの方は、ぜ...
-

2024.05.20 中小企業おすすめ情報
中小企業が狙われているサイバー攻撃ってなに?~平均被害金額2,386万円から企業を守るために~
サイバー攻撃における被害の実態 特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)の「サイバー攻撃被害組織アンケート調査」により、ランサムウェア平均被害額は2,386 万円と発表されました。 国内のサイバー攻撃の被害組織で実際に生じたコストを調査するために、2017年1月から2022年6月までの5年半に報道のあった国内で発生したサイバー攻撃情報を収集し、被害組織の情報を調査し約1,300組織をリストアップし、アンケート調査を行ったものです。 また、ランサムウェア感染組織へのアンケート結果によると、データを復旧できた組織は50%で、全てバックアップデータからの復旧とのことで、アンケートに回答したランサムウェア被害組織すべてが「身代金は支払っていない」と回答しています。 警察庁の「令和5年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」では、2023年上半期に警察庁に報告のあった「企業・団体等におけるランサムウェア被害」の件数は103件に上り、そのうち約6割を中小企業が占めています。 被害種別 平均被害金額 サイバー攻撃の種別構成 ランサムウェア感染被害...
-

2024.05.17
(小規模事業者向け・障害福祉事業向け)令和6年度改正 処遇改善加算の基本理解
はじめに 福祉業界では、毎回大きく注目される3年に1度の報酬改定。今回も多岐にわたって報酬の改定が起きておりますが、とりわけ話題になっているテーマに「処遇改善加算1本化」が挙げられます。福祉事業者にとって、非常に馴染みのある「処遇改善加算」というキーワード。2009年の「介護職員処遇改善交付金」に始まり、その後数々の制度改正を繰り返し、「福祉・介護職員処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」という。)」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定処遇改善加算」という。)」「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「ベースアップ加算」という。)」の3つの加算に分かれて運用されてきました。 それぞれ申請要件、支払要件、支払対象者等が細かく規定されており、この3つの違いを理解するだけでも大変難解な制度となっておりました。今年はさらに令和6年2月からの「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(通称:臨時特例交付金)もありましたので、新規参入した障害福祉事業者や、初めて処遇改善加算を申請しようとする事業者にとっては、用語ひとつとっても、理解するのに苦労されたことと思います。 私の印...
-

2024.05.16 IT・ガジェット情報
オンライン会議で便利なガジェットとテクニック
コロナ渦で急激に普及し、超便利ツールとしていまだに幅を効かせる「オンライン会議」。昭和生まれの筆者としては、直接会ってその場の空気を感じて話し合いをしたいところだが、時短やコスパ重視のビジネスで、都内なのにオンライン会議なんてことも。 でも逆に便利なこともたくさんある。電話では伝わらないモノや資料を見せたり、相手の表情が見られるので、より情報を速く・正しく・理解でき、相手の感情も読み取れる。しかも移動時間が不要なので、時間の調整幅が広がり開催時間を合わせやすく、1日何本も打ち合わせできるようになった。 ただデメリットもある。マイクがまわりの音を拾ってしまい声が聞きづらかったり、移動中などは電波がカスれて途切れてしまったり、場所によっては回線がショボショボで画面がモザイクだらけになったりと、誰もが経験あるだろう。 今回は、オンライン会議をより便利に使えるアイテムなどをご紹介しよう。 パソコン内蔵のマイクとスピーカは相手をイラつかせる!? オンライン会議での禁じ手はパソコン内蔵のマイクとスピーカーで会議に望むこと。ヘッドホンやイヤホンをしていない相手を見ると「あ~↓↓」とそれ...
-

2024.05.15 社会保険ワンポイントコラム
新生活で感じるストレスは注意が必要! 五月病の症状と予防法を解説
春は入学や就職などで、たくさんの人が新生活を迎える季節です。新しい環境に早く慣れようと、はりきって頑張る人も多くいると思いますが、新生活開始から1ヵ月が経過する時期に増加する「五月病」に注意が必要です。 五月病にはどのような症状があるのか、また、どのように予防するべきかをみていきましょう。 五月病ってどんな病気? 気候が暖かく、貴重な大型連休があるため、毎年5月を心待ちにしている人は少なくないでしょう。しかし、楽しげなイメージと裏腹に、5月は体や心に不調をきたしやすい時期でもあります。この5月頃に多くみられる心と体の不調は、「五月病」と呼ばれます。 「五月病」という名称は、正式な病名ではなく俗称です。日本ではゴールデンウィーク明けの5月上旬の時期に、心身のバランスを崩す人が増加する傾向にあるため、この呼び方が定着したとされています。 五月病になると「やる気がでない」「不安になりやすい」「憂鬱な気分になる」「体がだるい」「食欲が低下する」「すぐに疲れる」「眠りが浅い」など、さまざまな症状が引き起こされます。 これらの症状は、風邪などのほかの要因でも見られるため、五月病だと...
-

2024.05.14 IT・ガジェット情報
生成AI活用:AIのポテンシャルを引き出す5つの秘訣
生成AIは、私たちの創造性を大きく拡張する可能性を秘めた革新的なツールであり、今後、ビジネスにおいても、日常生活においても欠かせない存在となっていくでしょう。しかしながら、現状では、生成AIを十分に使いこなせていない人が多いのが実情ではないでしょうか。 本記事では、生成AI(ここでは主にテキスト生成を前提にお伝えします。)を業務や日常に効果的に取り入れるための5つのポイントを紹介します。生成AIの特性を理解し、その可能性を最大限に引き出すヒントを提供します。生成AIを単なるツールではなく、創造性を刺激する知的パートナーとして捉え直すことで、生成AIの活用がより一層楽しく実りあるものになるでしょう。 1、生成AIにはたくさん情報を与えよ 生成AIを活用する上で、AIに多くの情報を提供することは非常に重要です。理想的なアウトプットを求めているにもかかわらず、ユーザーが生成AIに与える情報が少ないケースをよく目にします。わずか数行のプロンプトしか書かず、AIからの回答に満足できない状況に陥ってしまうのです。 実際、筆者自身のプロンプトは数千字に及ぶことも珍しくありません。また、ひ...
-

2024.05.14 農家おすすめ情報
スマート農業による特別償却制度の創設 令和6年度税制改正
はじめに スマート農業に関して特別償却制度が令和6年度税制改正により新設された。スマート農業技術等を活用した生産性の高い食料供給体制の確立に向けた税制上の所要措置について解説する。農業者はぜひ本稿を読んで参考にしていただきたい。記事の記載にあたり財務省及び農林水産省の公表資料をもとにわかりやすく説明している部分は、著者の個人的な見解も含むことをあらかじめお断りしておく。 背景 今後20年間で、現在の基幹的農業従事者の大宗を占める70歳以上の年齢層がリタイアした後、農業者数は現在から大きく減少することが見込まれる。従来の生産方式等を前提とした農業生産では農業の持続性を確保できない懸念が生じている。 基幹的農業従事者数と平均年齢 ここがポイント!今後20年間で、基幹的農業従事者は現在(2023年)の116万人から30 万人にまで減少することが見込まれる。 用語解説基幹的農業従事者とは、ふだん仕事として主に自営農業に従事している人。 スマート農業とは、ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用する農業のこと。 参考:スマート農業(水田作)スマート農業導入により農作業のハードルが下がり、...
-

2024.05.13 税務ニュース
NPO法人が役員に役員報酬や給与を支給する際の注意点
3月決算のNPO法人は、5、6月は社員総会や事業報告書の準備などで忙しくなる時期だと思います。役員報酬については社員総会または理事会で決定することになりますが、金額を変更するかなど検討されているNPO法人もあるでしょう。 特に収益事業を行っているNPO法人においては、NPO法の規定だけでなく法人税法など税務上の取り扱いも理解した上で役員報酬を決定する必要があります。税務上の取り扱いを正しく理解していないと、支給した役員報酬が損金(税務上の経費)として認められないといったことも起こり得ます。 今回は役員報酬に関するポイントをNPO法と税務の目線から解説します。 NPO法と役員報酬 まず、役員報酬を受けることができる役員は総数のうち1/3以下です。これはNPO法において定められているため、順守する必要があります。ここで言う役員とは、理事と監事のことを指します。ただ、NPOにおいては理事が従業員を兼務して現場の仕事に従事していることも珍しくありません。このような場合まで規制することは合理的ではないため、従業員を兼務する理事に対して従業員として支払った給与については対象とはなりませ...









 トップ
トップ



![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)

