MENU


896件 561~580件を表示
-

2021.12.23 税務ニュース
確定申告の準備、何をしたらいい?個人事業主が年内にやっておきたい4つのこと
「確定申告はまだまだ先」。12月、そう考える個人事業主は少なくありません。ですが、年明けから着手すると後が大変です。今回、年内にやっておきたい確定申告の準備についてお伝えします。 「確定申告は年明けから」がNGな理由 確定申告は年内に準備をしておくのが大事です。なぜでしょうか。次の2つの理由があるからです。 確定申告期間は1か月しかない 「年明けからでいい」と考えていても、実際の着手はもっと遅くなりがちです。1月は何かと忙しいため、締め切りが迫っていない確定申告は後回しになります。結果、2月に入ってから始めるパターンになります。 一方、申告できる期間は2月16日から3月15日までの1か月間です。2020年と2021年は4月15日が申告期限でしたが、これは「コロナ禍でやむを得ず」の措置でした。2022年は、原則通り3月15日が期限になると見られます。 たった1、2か月で所得を計算し、申告書をまとめるのは大変です。その間も日常業務はあります。短期間で申告作業を行うのは、かなり負担が大きいのです。 期限間際はトラブルが生じやすい 「取引が少ないから2月になってから...
-

2021.12.21 税務ニュース
来年1月からの電子帳簿保存法、2年猶予と聞いたけどホント?令和4年度税制改正を解説
2022年1月から始まる「改正電子帳簿保存法」。税制改正から1年後に施行される新制度は、今年の話題の中心となりました。そして「令和4年度税制改正で2年猶予された」とも聞きます。 なぜこんなに話題になったのか、そして何が猶予されたのか。今回、この2つに焦点を当てて解説します。 改正電子帳簿保存法とは何か 最初に改正電子帳簿保存法の内容を見ていきましょう。 20年以上あるけど使えない電子帳簿保存法 電子帳簿保存法とは「条件にのっとるなら、税法で定める証憑書類を電子媒体で保存できる」とするものです。 所得税法や法人税法などでは領収書や請求書などの証憑書類を紙で保存するのが原則です。一方、IT技術が発達するにつれ、デジタル媒体での保存のニーズが高まります。そこで平成10年、電子データでの帳簿や証憑書類の保存に関し、法律が定められたのでした。 法律自体は20年以上前から存在していたのですが、ほとんど活用されませんでした。要求される条件が非常に厳しい上、管轄の税務署の承認がなければいけなかったからです。しかし、紙媒体での保管は紛失リスクや管理コストの問題が伴います。 民間経済もどん...
-

2021.12.20 税務ニュース
あなたの会社の「強み」をアピール!国の認定を目指してみよう!
4種類の「国の認定制度」をご紹介します! 国は「若者雇用促進法」「障害者雇用促進法」「次世代育成支援対策推進法」「女性活躍推進法」などの法令に基づき、さまざまな方たちが働き続けることができる社会を目指しています。そして、雇用推進に優良な取り組みをしている事業主に対して、主に以下のA~Dにあるような国の認定制度があります。 今回は、各制度の「主な認定要件」についてご紹介します(詳細な要件につきましては厚生労働省ホームページでご確認ください)。 A.若者雇用を推進!「ユースエール認定」 若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小事業主が対象 【主な認定要件】 学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込みまたは募集を行っている 直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20%以下 前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員が1人もいない その他、所定要件を満たしている URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/...
-

2021.12.15 税務ニュース
災害が起きたら役員・従業員の税金はどうなる?救済策を確認しよう(2)
前回、役員・従業員向けに災害時の対応策を解説しました。今回は、会社の総務・経理向けにお伝えします。 会社の総務・経理も対策が必要 災害が生じると、勤務する個人だけでなく、会社そのものにも対策が求められます。次のような税務上の義務を負っているからです。 決算後の法人税や消費税、法人住民税や法人事業税の申告・納税 法人税・消費税の中間申告と納付 源泉所得税・復興特別所得税の納付 個人の住民税の徴収・納付 給与支払届出書など各種届出の提出 これらはすべて期限があります。頻繁に納期限が来る源泉所得税や住民税は、うっかりしていられません。しかし実際、災害で大きな被害を受ければ、申告・納税どころではなくなります。復旧に時間がかかりますし、修繕が必要なときもあります。いつも通りの経理はできないのです。 こういった状況を配慮し、税法では、会社そのものにも救済策を設けています。次のような制度を押さえておけば、不利益を被らずに済むかもしれません。 災害等による期限の延長 災害が生じた際、申告や納税、届出や申請の期限そのものを先延ばしにする制度です。具体的には次の3つが...
-

2021.12.10 税務ニュース
「本社」や「支店」は必要なの?
そもそも,本社は必要なの? コロナ禍で、上場会社が次々に本社を売却しているようです。テレワークを実施している会社にとっては、本社がなくても、会社を経営できると気付いたことは、大きな影響力を持ちますね。しかし、本社がどこにもない会社は存在できるのでしょうか? 本社、もっと言えば、「会社」という「場所」は、なんのためにあるのでしょうか? そもそも会社とは、社員が集まることにより、インスピレーションを得たり、社員同士のコミュニケーションをとったりする社交の場として、存在していたように思います。しかし、コロナ禍となり、社員同士のコミュニケーションをいかにとるか、会社が工夫を重ねた結果、社交の場としての機能は、オンラインで行う会社も増えました。商品開発のインスピレーションも、会社によっては、会議で報告を上げるだけになったところも多いようです。このようにオンラインでできるようになると、特に本社という「建物」を構えなくても会社としての利益をあげることに問題はないようにも思えます。 確かに、社員が集まるという意味での建物が無くても構わないのです。 しかし、会社の住所を特定する意味では、本社...
-
![[起業応援]植物の力はすごい!元作曲家が造園業を起業した理由とは?](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-632.jpg)
2021.12.09 起業応援・創業ガイド
[起業応援]植物の力はすごい!元作曲家が造園業を起業した理由とは?
起業応援インタビューの第6回は、関東近郊で造園業を営む『もちづき植木』です。音楽業界出身という異色の経歴を持つ代表の望月様に、起業に関するお話を伺いました! 現在起業を考えている方は、どのように起業したらよいか、どんな問題があるのか、など様々な不安があると思います。そこでこれから起業する人を応援するためプロジェクトを立ち上げました。起業したてのユーザー様にインタビューさせていただき、役立つ情報をお伝えしていきます。 起業の経緯を教えてください。 音楽業界で理想と現実に苦しむ 20代の頃は音楽業界にいて、作曲を担当したり、PA(音響)としてライブを手掛けたり、レコーディングでエンジニアをしていました。しかし、仕事となると自分が苦手な音楽も担当しなければいけないのが苦痛で、精神的に追い詰められてしまい、新しい仕事を探さなければいけなくなりました。 そんな折、アルバイトとして造園業の現場で働いた時に、「これだ」としっくりくる感覚があったんです。音楽と造園は無関係に見えますが、「お客様を感動させる」点は同じです。この仕事は自分に合っているかもしれない、その時、そう感じました。 造...
-
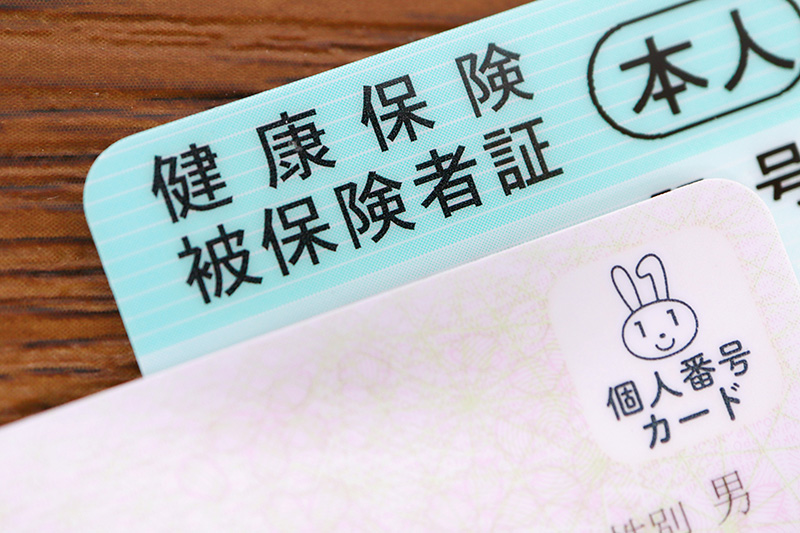
2021.12.06 税務ニュース
10月からマイナンバーカードが健康保険証代わりに?メリット・デメリットを解説
10月20日から、マイナンバーカードを健康保険証として使えるしくみが始まりました。現在、全国の医療機関や薬局で対応システムの導入が少しずつ進められているようです。今回は、このしくみが普及したときのメリット・デメリットを解説します。 「マイナンバーカードが健康保険証になる」メリット マイナンバーカードが健康保険証代わりになると、従来の健康保険証の提示が不要になります。つまり「持ち歩くカードが1枚減る」わけですが、それだけではありません。次のようなメリットがあります。 ●高額療養費の自己負担をしなくて済む もっとも大きいメリットは「高額療養費の自己負担をしなくて済む」という点です。高額療養費とは、病気やケガで医療費が高額になったとき、一定額以下に自己負担が抑えられる制度をいいます。高額な部分は国が負担してくれるのです。 「じゃあ今のままでも問題ないんじゃない?」と思うかもしれません。が、実は、そう簡単ではないのです。最終的に国が負担してくれるものの、一度は個人がすべて自己負担しなくてはなりません。 自分のお財布から高い医療費を払った後、市区町村や健康保険組合に高額療養費の支給申...
-

2021.12.03 中小企業おすすめ情報
中小企業のSNSの運用の注意点やトラブルの対処
中小企業がTwitterやフェイスブック、LINEなどのSNSを運用するとき、イメージダウンにつながる投稿や「炎上」には、くれぐれも注意しなければなりません。いったん炎上すると情報がまたたくまに拡散され、取り返しのつかない損失を被る可能性もあります。 今回は企業がツイッターやLinkedInなどのSNSを運用する際によくあるトラブルや炎上するパターン、実際にトラブルが起こってしまったときの対処方法をお伝えします。 1.企業SNSでよくあるトラブルのパターン 企業のSNS公式アカウントでは、以下のようなトラブルが起こるケースが多数見受けられます。 1-1.プライベートアカウントと間違えて投稿 企業アカウントを運営している従業員が、自分のプライベートアカウントと間違えて投稿してしまうパターンです。上司や評価制度への不満や自社商品に対する文句や愚痴を公式アカウントに載せてしまい、炎上してしまう事例もあります。 1-2.アカウント乗っ取り、なりすましの被害 企業のSNSアカウントが「乗っ取り被害」や「なりすまし被害」に遭う可能性もあります。 IDやパスワードが漏洩して、第三者...
-
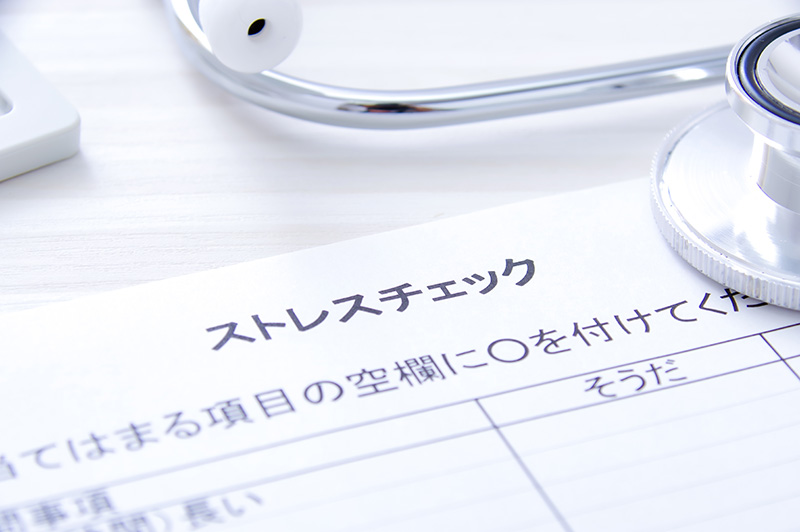
2021.12.01 社会保険ワンポイントコラム
コロナ禍だからこそ押さえておきたい!労働者へのストレスチェックの方法
ここ数年、メンタル不調者が増加しています。特にコロナ禍では、密を避けるために人とのコミュニケーションが希薄になったり、テレワークや時差出勤で働き方や生活スタイルが変わったりと、社会の大きな変化により、より多くの方のストレス増加に繋がっています。 そんな中でも、会社としては労働者のメンタル不調を未然に防止したいものです。そこで今回は、「ストレスチェック制度」について改めて確認しておきましょう。 労働者50人以上の事業場ではストレスチェックが義務 「ストレスチェック」とは労働安全衛生法に定められている制度で、ストレスに関する質問票に労働者が回答し、それを集計・分析することで、自分のストレス状態を調べる検査です。労働者が50人以上の事業場では、2015年12月より、毎年1回、労働者に対してストレスチェックを実施することが義務付けられていますので、ご存知の方も多いと思います。 実施手順は以下の通りです。 ① 労働者に質問票を配布し、記入してもらう 使用する質問票は、以下の3つが含まれていれば特に指定はありません。何を使えばよいかわからない場合には、国が推奨する質問票がありますし、専...
-

2021.11.26 税務ニュース
コロナ禍で高まった意識の一つが応援消費-年末までにふるさと納税を実施しましょう!
平成20年にスタートして、今年で14年目を迎えるふるさと納税ですが、利用者も着実に増え、令和元年には寄付金総額が4800億円を超えるほどになりました。ある調査によると国民の約2割がふるさと納税を利用したとも言われています。よって、今回はふるさと納税の制度や仕組みについて簡単にご紹介させていただきます。 各自治体の使い道のため寄附をしたい、地方支援をしたい、返礼品が欲しい等、ふるさと納税支援の理由は様々ですが、コロナ禍で高まった意識の一つが応援消費です。消費することで、困っている人たちを応援したい!ということです。なお、個人版ふるさと納税は年末までに実施しなければなりませんので、ご注意を! ふるさと納税は応援したい自治体を選んで寄付ができます 生まれ故郷ではなく、心の故郷に寄付ができます。要するにどこに寄付するかは自由です。また複数の地域に寄付することも可能です。 例えば、人気な返礼品として北海道白糠町「いくら醤油漬け」、北海道広尾町「岡嶋の生干ししゃも大メス」、奈良県王寺町「雪丸フライパン3点セット」、兵庫県新泉町「但馬牛 肩ロース(500g)」など選ぶだけでワクワクし...
-

2021.11.22 社会保険ワンポイントコラム
共働き夫婦の子供はどちらの扶養? 令和3年8月からの健康保険の新基準を解説します。
共働きの夫婦が子供を健康保険の扶養に入れる場合について、令和3年8月から取扱基準が一部変更になっていることをご存じだろうか。この変更は、夫婦の年収差が少ない場合に子供の被扶養者認定を円滑に行うため、従前よりも基準が明確化されたものである。今回は、この健康保険の新しい被扶養者認定基準を整理してみよう。 夫婦の年収差「1割」が認定の分かれ目に 夫婦の両方が健康保険の被保険者であり、2人で家族を扶養する状態を夫婦共同扶養という。この場合、その夫婦の子供は健康保険上、夫と妻のどちらの被扶養者になるのか。この点につき、令和3年8月1日からは夫婦の年間収入の差に応じ、次のとおりとされている。 「年間収入が多いほうの親の年収額」に対する「夫婦の年間収入の差額」の割合が、 “1割超”の場合 …『年間収入が多い親』の被扶養者とする。 “1割以内”の場合…『主として生計を維持する親』の被扶養者とする。 例えば、年間収入が夫は350万円、妻は400万円の夫婦の場合、年間収入の差額である50万円(=妻400万円-夫350万円)は、年間収入が多い妻の年収の12.5%(=50 万円÷妻4...
-

2021.11.15 税務ニュース
事業主・経理担当者必見!令和3年(2021年)の年末調整手続のチェックポイントを確認しましょう。
いよいよ年末調整の時期が近づきました。12月の調整計算に向け、すでに準備を始めている事業者の方々も多いと思います。すでに国税庁から2021年(令和3年)分の年調ソフト(Ver.2.0.0)もリリースされました。本年分については調整計算上の大きな変更点はありませんが、昨年から煩雑化した計算項目に対して、事業主は引き続き正確かつ効率的に調整を行うことが要求されています。 2021年(令和3年)分の変更点 年末調整申告書等(※)への押印義務が廃止されました! 年末調整申告書等(※)の電子化について税務署への承認申請が不要になりました! e-Taxによる申請等のイメージデータによる送信が可能になりました! ※「年末調整申告書等」とは、「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除申告書」、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」ならびに翌年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいいます(以下、同様)。 1. 様式の変更 (国税庁サイトより一部抜粋) 押印義務の廃止により、年末調整申告書等につ...
-

2021.11.12 税務ニュース
災害が起きたら役員・従業員の税金はどうなる?救済策を確認しよう(1)
近年、災害が増えています。夏から秋にかけて大雨や台風は、今や毎年恒例です。先日8日は、関東で直下型の大地震が起きました。思わぬ災害で会社や従業員の生活に支障が出たとき、給与や賞与などの税金はどうしたらいいのでしょうか。今回、会社の役員・従業員向けの救済策を解説します。 災害減免法による徴収の猶予及び還付 地震や台風といった災害に見舞われると、何かとお金が入用です。所得税や住民税を給料から天引きしてしまうと、その分自社の役員や従業員は生活の立て直しに困ってしまいます。そこで、災害減免法では、源泉所得税や復興特別所得税の徴収を先延ばしにしたり、天引き分を本人に戻したりすることを認めています。ただし、救済措置は一律ではありません。所得額や被害額によって、内容が変わります。なお、住民税にも同様の制度がありますが、地方自治体によって取扱いが異なります。 1.徴収の猶予と還付 所得がそれほど多くない役員や従業員については、源泉所得税や復興特別所得税の天引きを先延ばしにしたり、すでに引いてある税金を本人に戻したりできます。 ただし、次の3つの条件すべてに当てはまらなくてはなりません。 ...
-
![[起業応援]「大切なのは人と人のつながり」設計で人と地球環境に優しい未来をデザインする](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-640.jpg)
2021.11.10 起業応援・創業ガイド
[起業応援]「大切なのは人と人のつながり」設計で人と地球環境に優しい未来をデザインする
起業応援インタビューの第5回は『蘆田暢人(あしだ まさと)建築設計事務所』です。千葉大学の講師も務める代表の蘆田暢人様に、起業に関するお話を伺いました! 現在起業を考えている方は、どのように起業したらよいか、どんな問題があるのか、など様々な不安があると思います。そこでこれから起業する人を応援するためプロジェクトを立ち上げました。起業したてのユーザー様にインタビューさせていただき、役立つ情報をお伝えしていきます。 起業の経緯を教えてください。 「ものづくり」から設計士の道へ 子供の頃から図工やプラモデルが好きで、「将来はものづくりがやりたい」と考えていました。高校生の時に進路について考えた際、「建築設計」という職業を知りました。良いもの、面白いものを自分で考えて作り出す仕事は魅力的だし、人々の生活に密着する建物にも興味があった。よし、将来は設計士になろう、と考えて、京都大学の建築学科に進みました。 当初から起業を見据えて、就職先にはアトリエ事務所(建築家個人の作家性を強く反映した設計を行う設計事務所の通称)を選びました。2008年の建築士法改正で、設計事務所開設には一級建築...
-

2021.11.09 税務ニュース
インターネットバンキングとは?メリットや注意点を網羅的に解説
(1) はじめに インターネットバンキングは、インターネットを利用して銀行などの金融機関と取引ができるサービスです。パソコン、携帯電話・スマートフォン、タブレットなどから利用できるサービスで、メガバンク、地方銀行、信用金庫などがサービス提供しています。銀行の支店窓口や、ATMまで出向く必要がない利便性から、個人、法人いずれも利用が拡大しております。特に法人では、従来の経理処理(記帳、残高照会、振込、資金移動)をインターネット上で完結できることから、利用が拡大しています。 (2) インターネットバンキングの利用が増えている インターネットバンキングの利用は増加傾向にあり、中小企業や個人事業主の利用の増加が見込まれます。これまで、振込回数が少なく、インターネットバンキングの固定費が割に合わないため、導入を避けて来た企業も、安価な(無料の)サービスが増えていることや、キャッシュレス化、ペーパレス化、コロナ禍でのリモートワークの増加を理由に、導入に踏み切るケースが増えてきています。インターネットバンキングの振込手数料は、支店窓口やATMでの現金やキャッシュカードによる振込の手数料より安価...
-

2021.11.08 みんなの経営応援通信編集部
使ってる? 使ってない?「マイナンバーアンケート集計結果」
マイナンバーを活用していますか? ソリマチでは、ユーザー様宛にメールマガジン「会計・実務情報通信」を定期配信しています。「会計・実務情報通信」2021年10月1日号・2021年10月12日号にて、マイナンバーに関するアンケート調査を掲載し、延べ65名の方からご回答をいただきました。 以下では、その集計結果について、ご報告いたします。なお「複数回答可」とある設問は複数の選択肢を選択できる形式で、それ以外は一つの選択肢のみを選択する形式です。 総務省が発表している「マイナンバーカードの市区町村別交付枚数等について(令和3年10月1日現在)」を参照すると、日本全国でのマイナンバーカード普及率は38.4%です。この回答では「持っている」が六割弱ですから、平均よりも高い数字が出ています。マイナンバーにより関心の高い方が答えている傾向なのかもしれません。 第一位は「e-Taxなどの電子申請に使用するため」35.38%、第二位は「身分証として使用するため」26.15%でした。「身分証」はマイナンバーカードの用途の代表的なものですが、それ以上に電子申請へのニーズは高いようです。 ...
-

2021.11.05 税務ニュース
コロナ禍で企業のマーケティング戦略が変わり「広告代理店」はどのようにDXという生存戦略を考えれば良いのか?
この度のコロナ禍では、人々の生活様式が大きく変化し、消費行動も変わりました。消費行動の変化は、企業のマーケティング戦略を変え、その影響は当然に広告業界にも変化を与え、広告代理店の生存競争はより一層激しくなったようです。そんな環境において広告代理店は、どのようにDXという生存戦略を考えればよいのでしょうか。ビジネスモデルにおける財務的特徴から、顧客管理や案件管理という経営上の管理の目線で整理していきます。 広告代理店の基本的なビジネス構造 広告代理店は、メディアと言われる広告媒体が持っている広告枠を、広告代理店が仕入れて販売するモデルが主流です。顧客である広告主が広告代理店と付き合うメリットは、自社の戦略に沿った媒体の選定や広告運用など、マーケティング活動全般に対する支援が受けられることです。そのマーケティングを行う目的には、以下のようなものがあります。 販促広告:自社商品の市場への浸透や売上拡大 求人広告:自社の人材採用や定着のために、まずは求人への応募を獲得する コーポレート広告:自社のイメージ向上(多くの場合、自社社員や取引先等に対するイメージ戦略) 大...
-
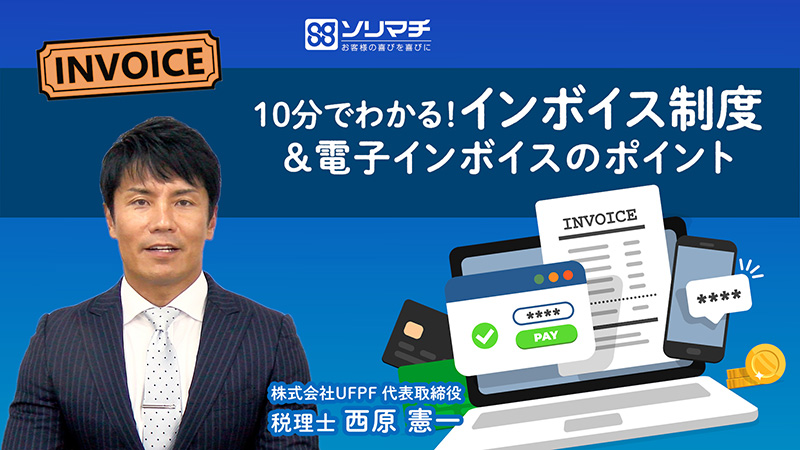
2021.11.04 見逃し配信
《解説動画》10分でわかる!インボイス制度&電子インボイスのポイント
インボイス制度とは何か? 具体的な対応方法は?登録事業者になるには? 人気税理士 西原 憲一 先生がインボイス制度をまるっと解説! [template id="4604"] [democracy id="152"]
-

2021.11.01 税務ニュース
リモート社員への手当・経費はどう支払えばいい?【社内ルールを決めておこう】
1.はじめに―リモートワークの普及で気になる手当や経費― 新型コロナウイルスの影響で、多くの企業がリモートワーク・テレワークを推奨するようになりました。このトレンドは、ウイルス感染が落ち着いても大きく変わらないことが予想されます。リモートワークの期間が長くなるにつれて、リモート社員への手当や経費の支給について気になってくるのではないでしょうか? 「リモートワーク・テレワークに伴う経費はどの範囲まで支給すればいいの?」 「在宅勤務手当はどんな扱いで支給すればいいの?」 このような疑問を持つ方に向けて、この記事ではリモート社員に手当や経費を支払う際の注意点について解説します。在宅勤務手当などの支給についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。 2.在宅勤務手当は給与として扱う 社員に在宅勤務手当を支給する場合、通常の給与と同じ扱いであり、社員は所得税の課税対象となります。というのも、通勤手当などと違い使途をはっきりと限定できないからです。手当の額は一律とするのが一般的です。また、パソコンなど在宅勤務に必要なものを現物で支給する場合も、「現物給与」として課税対象になります(ただ...
-

2021.10.25 社会保険ワンポイントコラム
2021年インフルエンザの予防接種-今年もワクチンを打つことが推奨されます。それはなぜでしょうか?
インフルエンザは直接死因になる場合があるほか、特に高齢者ではインフルエンザ罹患後に他の種類の肺炎にかかって死につながることも多く、決して侮ることのできない疾患です。新型コロナウイルス感染症対策が功を奏したのか、昨シーズンすなわち2020年終わりから2021年初めにかけてインフルエンザは全く流行しませんでした。今年も同様の可能性があります。でも、今年もワクチンを打つことが推奨されます。それはなぜでしょうか? インフルエンザ大流行の可能性は否定できません! インフルエンザは広い意味での風邪の一種ですが、急な高熱や関節痛等が特徴的な冬に起きる疾患です。多い年では日本人の約1割が感染すると考えられています。ワクチンはあるのですが効果は確実ではなく、誰も接種しなければ100人が感染するところを50人に抑える程度です。そのうえウイルスに型が多く、4種類くらいの型に合わせて混合して作られるのですが、それ以外の型が流行する場合もあります。さらに効果が持続せず、翌年にはまた打つ必要があります。三種混合ワクチンなどが一生に1~3回打てば強い予防効果を持つことを考えると、インフルエンザワクチンは"劣...









 トップ
トップ


