MENU


 PICKUP
PICKUP
税務ニュース
【2025年度(令和7年度)税制改正(その1)】103万円の壁の引き上げは123万円に!いつから?大学生のバイト「103万円→150万円」の控除も解説
昨年12月20日に2025年度(令和7年度)税制改正大綱が公表されました。もっとも注目されたのは「103万円の壁の引き上げ」です。どうなったのでしょうか。いつから始まるのでしょうか。今回は、103万円の壁の引き上げと大学生のバイトの壁の引き上げを中心に解説します。 2025年度(令和7年度)税制改正①「103万円の壁」が「123万円の壁」に 個人向けの税制改正の1つ目は「103万円の壁の引き上げ」です。 103万円の壁とは、パート・バイトといった給与所得者の非課税枠を言います。「給与所得控除の下限55万円+基礎控除額48万円=給与年収の非課税の上限103万円」という内容です。 多くのパート・バイトはこの103万円の壁を気にするため、年末になると「働き控え」という現象が起きていました。そのため、企業は人手不足に悩み、家計は物価高が改善されないという状況に陥っていたのです。 そこで、与党から政策協力を求められた国民民主党が「103万円の壁を引き上げるべきだ」と提案しました。議論が重ねられた結果、今回の税制改正で103万円の壁が引き上げとなったの...

社会保険ワンポイントコラム
職場の離職率低下につながる効果が!治療と仕事の両立支援について
治療と仕事の両立についての社会的背景 近年、医療の進歩により、がんのように以前は不治とされていた病気でも生存率が向上し、長期にわたって仕事との両立が可能になりつつあります。病気になったらすぐに離職しなければならないという状況から、治療を行いながら仕事を続けられる社会的環境へと変化しています。 しかし、疾病や障害を抱える従業員を支援するための社内体制が整っていない場合、従業員は仕事を続けたくても離職を選択せざるを得ません。これは企業にとっても人材の大きな損失といえるでしょう。 両立支援の内容 治療と仕事の両立支援の内容ですが、具体的には次のような柔軟な働き方ができる制度を設けた上で、私傷病の治療や療養を目的とした利用ができるようにします。 時差出勤制度 短時間勤務制度 時間単位の休暇制度・半日休暇制度 フレックスタイム制度 在宅勤務(テレワーク)制度 休職制度 両立支援に取り組むことの効果 労働政策研究・研修機構(JILPT)の「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)2024年3月」によれば、上記のよう...

4件 1~4件を表示
-
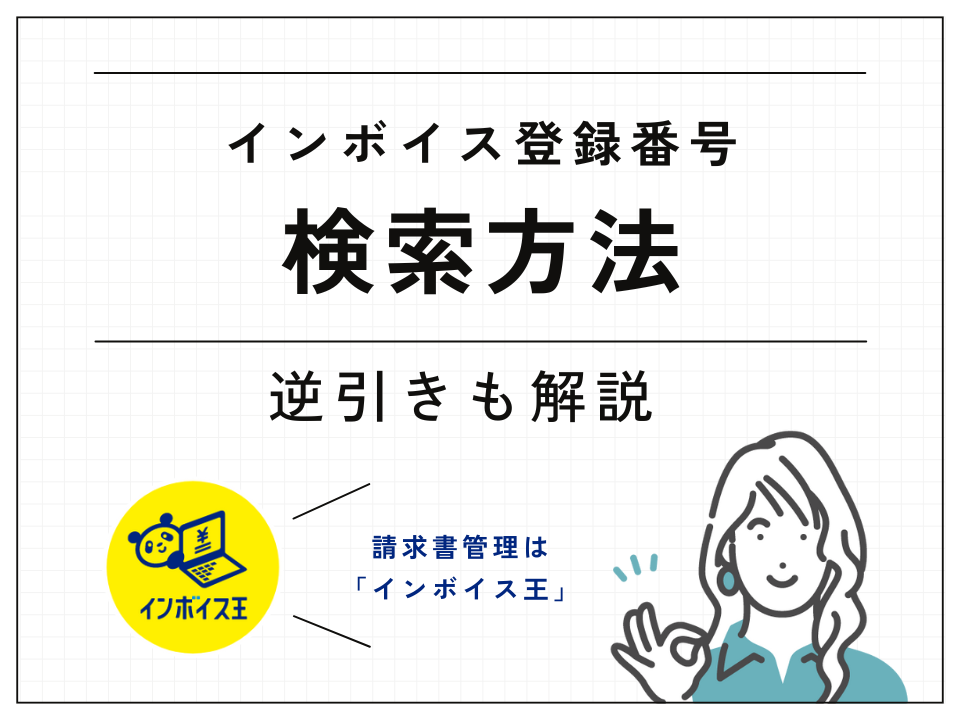
2024.08.08 税務ニュース
インボイス制度の登録番号を検索&確認する方法を解説|逆引きも
今回は、インボイス登録番号の確認方法を解説します。 インボイス制度の概要も含めて分かりやすく解説しているので、本制度についてよく分からないという人にもおすすめの記事です。 ソリマチ株式会社が手掛ける請求書発行サービス「インボイス王」も紹介しているので、ぜひご覧ください! インボイス制度の登録番号を効率的に管理するなら「インボイス王」 ソリマチ株式会社が提供する「インボイス王」は、インボイス制度に対応した請求書(適格請求書)をかんたんに発行・受領できるツールです。 インボイス王でできること ・請求書月10枚までの発行であれば無料で利用可能! ・年間5,500円で適格請求書が無制限で作成可能! ・項目が自動で取り込まれるOCR機能対応 ・取引先の情報は検索して簡単に登録・管理! ・ソリマチ製品「会計王」との連携で自動仕分化 インボイス王は取引先の登録番号もラクラク管理ができます。 一度登録した取引先の法人番号はインボイス王で確認ができ、法人ごとにまとめて請求書の管理も簡単です。。 また「インボイス王」は、月10枚までならインボイス制度対応の請求...
-
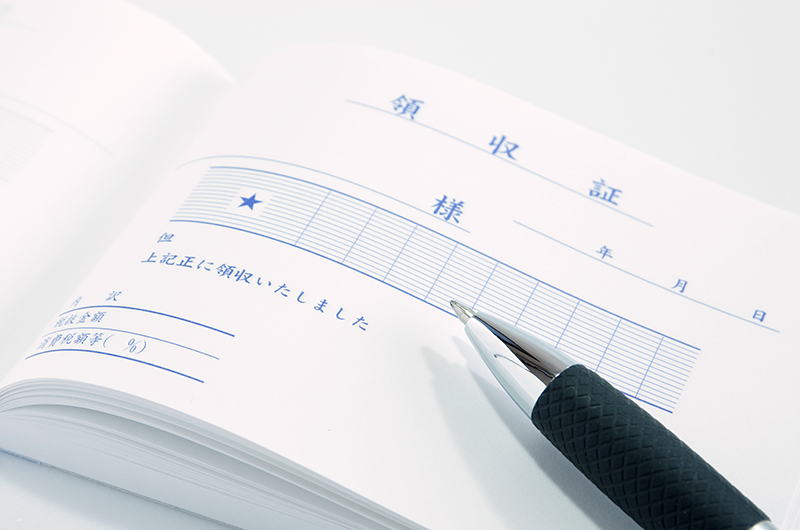
2023.09.27 税務ニュース
インボイス初年度!インボイス制度対応の請求書&領収書の注意点まとめ
2023年(令和5年)10月1日から始まるインボイス制度。 国税庁によると、7月末時点で約370万の事業者が登録事業者の申請をしたようです。インボイス制度の影響を受ける事業者はたくさんいらっしゃいますね。そこで、今回はインボイス制度対応の請求書・領収書の注意点をお伝えしていきます。 注意点1:「6つの記載事項」がないとNG! 発行する書類が「適格請求書(インボイス)」として認められるためには、一定の事項を記載する必要があります。インボイスとして必要な事項を記載していれば、インボイスは請求書に限られず、領収書や納品書などでもインボイスに該当します。 具体的にインボイスに記載が必要となるのは、次の6点です。 ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 ②取引年月日 ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率 ⑤税率ごとに区分した消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに一回ずつ) ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 ※下線部分が、インボイス制度導入により追加される事項です。 なお、不特定多数の...
-

2023.08.13 税務ニュース
【インボイス制度】領収書はどう書くべき?手書きもOK?個人の飲食店・小売店に解説
「領収書=インボイス」はなぜ必要?ポイント3つを解説 なぜ、領収書をインボイスにしたほうがいいのでしょうか。それは、納める消費税の計算ルールが10月から変わるからです。この計算ルールにインボイスが関係します。 インボイスがないと「-仮払消費税」ができなくなる 納める消費税は原則、次の式で計算します。 納める消費税=預かり消費税-仮払消費税 預かり消費税というのは一般消費者や他の事業者から預かった消費税、仮払消費税というのは他の事業者に支払った消費税のことです。現在、必要書類さえあれば、仮払消費税は誰に支払ったものでも差し引けます。 しかし今年の10月以降、インボイスがなければ差し引けなくなります。買手が消費税を納める事業者なら、売り手がインボイスを発行してくれるかどうかが重要になります。インボイスがなければ、その分、納める消費税が高くなるからです。売手にとっては、インボイスが発行できないことで売上が下がるリスクが生じます。 だから「10月から領収書はインボイスにしたほうがいい」と言われるのです。 インボイスの発行事業者になれるのは「消費税を納めている事業者だけ」 インボイスは...
-

2023.02.20 税務ニュース
あなたの知らない領収書の世界(インボイス編)
税理士は知っているけれども、一般の人には知られていない領収書をテーマにした「あなたの知らない領収書の世界」。読者の皆様のおかげで回数を重ねることができ、今回も取り上げていただくことになりました。読者の皆様には、大変、感謝しております。 さて、今回の領収書の世界は、インボイス制度が導入された後の世界についてです。しかし、インボイスの世界は、私たち税理士にとっても未知の世界です。そういう意味では、“だれも知らないインボイスの世界”ともいえるのです。 インボイス制度の簡単な内容 インボイス制度につきましては、新聞報道やネット上の記事でかなり詳しく取り上げられており、ここでは簡単な内容を見ていきます。インボイス制度は、令和5年10月1日より実際の取り扱いが始まります。今までの領収書、請求書と取り扱いが異なる部分がいくつかありますがそれは消費税の取り扱いに限られます。つまり、そのほかの取り扱いについては、従来のそれとは異ならないということを理解しておくとよいでしょう。 例えば、品物の料金を支払った際にもらった領収書は、インボイス発行事業者かどうかは関係なく、その代金を支払った証拠には...









 トップ
トップ



![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)

