MENU


 PICKUP
PICKUP
税務ニュース
【2025年度(令和7年度)税制改正(その1)】103万円の壁の引き上げは123万円に!いつから?大学生のバイト「103万円→150万円」の控除も解説
昨年12月20日に2025年度(令和7年度)税制改正大綱が公表されました。もっとも注目されたのは「103万円の壁の引き上げ」です。どうなったのでしょうか。いつから始まるのでしょうか。今回は、103万円の壁の引き上げと大学生のバイトの壁の引き上げを中心に解説します。 2025年度(令和7年度)税制改正①「103万円の壁」が「123万円の壁」に 個人向けの税制改正の1つ目は「103万円の壁の引き上げ」です。 103万円の壁とは、パート・バイトといった給与所得者の非課税枠を言います。「給与所得控除の下限55万円+基礎控除額48万円=給与年収の非課税の上限103万円」という内容です。 多くのパート・バイトはこの103万円の壁を気にするため、年末になると「働き控え」という現象が起きていました。そのため、企業は人手不足に悩み、家計は物価高が改善されないという状況に陥っていたのです。 そこで、与党から政策協力を求められた国民民主党が「103万円の壁を引き上げるべきだ」と提案しました。議論が重ねられた結果、今回の税制改正で103万円の壁が引き上げとなったの...

社会保険ワンポイントコラム
職場の離職率低下につながる効果が!治療と仕事の両立支援について
治療と仕事の両立についての社会的背景 近年、医療の進歩により、がんのように以前は不治とされていた病気でも生存率が向上し、長期にわたって仕事との両立が可能になりつつあります。病気になったらすぐに離職しなければならないという状況から、治療を行いながら仕事を続けられる社会的環境へと変化しています。 しかし、疾病や障害を抱える従業員を支援するための社内体制が整っていない場合、従業員は仕事を続けたくても離職を選択せざるを得ません。これは企業にとっても人材の大きな損失といえるでしょう。 両立支援の内容 治療と仕事の両立支援の内容ですが、具体的には次のような柔軟な働き方ができる制度を設けた上で、私傷病の治療や療養を目的とした利用ができるようにします。 時差出勤制度 短時間勤務制度 時間単位の休暇制度・半日休暇制度 フレックスタイム制度 在宅勤務(テレワーク)制度 休職制度 両立支援に取り組むことの効果 労働政策研究・研修機構(JILPT)の「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)2024年3月」によれば、上記のよう...

3件 1~3件を表示
-
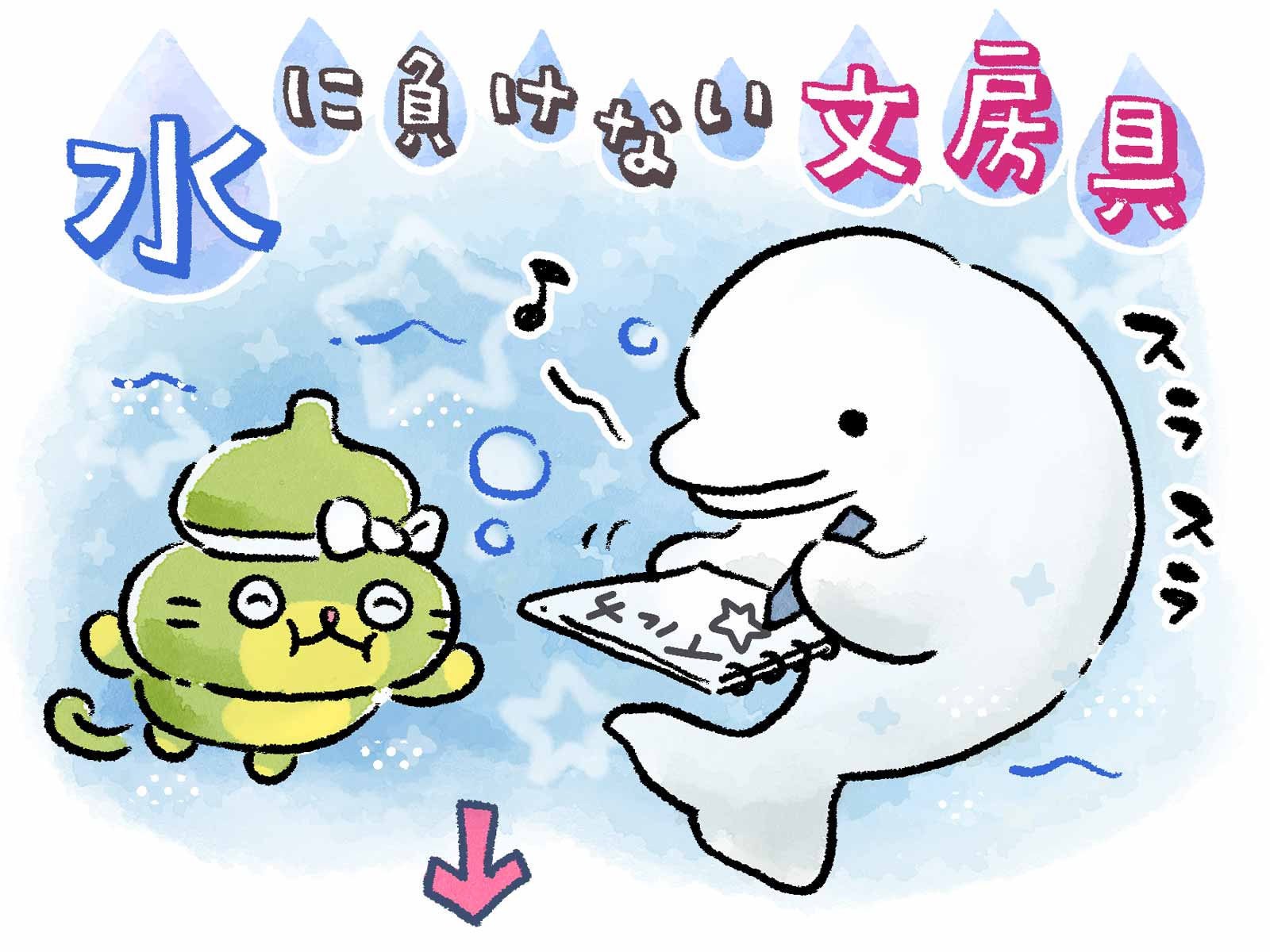
2024.05.30 IT・ガジェット情報
【文具ライター推薦】雨や屋外でもしっかり使える!水に負けない文房具
屋外でいざメモを取ろうと思った時に雨が降ってきてしまい、ペンのインクが滲んで文字が書けなかったり、紙が濡れてシワになって使えなくなってしまった…という経験はありませんか? そんな梅雨のシーズンや屋外作業、アウトドアなどの野外でも力を発揮してくれる、雨や水に負けない文房具をご紹介します。 濡れた紙にも書ける油性ボールペン「ウェットニー」 [caption id="attachment_17108" align="aligncenter" width="800"] メタルボディで耐久度も高くアウトドアでも大活躍[/caption] 屋外で打合せや電話をしているときに急に雨が降ってきてしまった時、メモを書いたら水で滲んで読めなくなったり、メモをとるのを諦めてしまい後から内容を確認する…といった経験はありませんか? 文房具は水に弱いイメージがある方も多いと思いますが、実は水に強く濡れても使える文房具もあるんです。 [caption id="attachment_17109" align="aligncenter" width="800"] ウェットニーは濡れた紙にもしっかり書けます...
-

2023.10.20 IT・ガジェット情報
関東大震災から100年目に当たる2023年 会社に備えておきたい防災グッズ
このところ異常気象が恒常化しています。2023年も例外ではなく、いくつもの台風が同時に日本を襲ったり、線状降水帯が頻繁に発生し被害をもたらしました。さらにはゲリラ豪雨で日本各地に洪水災害をもたらしたことは記憶に新しいでしょう。 今年は関東大震災から100年目に当たる年。いやがおうにも防災について考えさせられる機会が多くなっています。私たちも過去には阪神淡路大震災、新潟中越地震、そして東日本大震災でいろいろなことを学びました。いつ来てもおかしくない南海トラフ地震をはじめ、さまざまな災害にも対応できるよう、防災対策に有効なグッズをご紹介します。 単1から単4電池までどれか1本あれば使える懐中電灯 防災グッズの基本中の基本と言えば懐中電灯です。おそらくどの事務所にも備え付けられていますが、その懐中電灯は点灯しますか? 電池は使わなければ、いつまでも電気を蓄えていられるように思われていますが、時間が経つと自然に放電しカラになります。それ以前に最近は電池が別売の懐中電灯が多くあるので、電池が入っていないなんてことはありませんか? 過去の災害からも明らかなように、コンビニやスーパーから...
-

2023.03.10 IT・ガジェット情報
東日本大震災から12年。社員の安全確保や事業継続に役立つ「防災アプリ」とは
企業の経営においては、災害時の対応を考えることも大切です。防災マニュアルの整備など着手すべき施策はいくつも考えられますが、まずは社員ひとりひとりに「防災アプリ」の利用を勧めてみてはいかがでしょうか。この記事では社員の安全確保に役立つ防災アプリの基本や、用途別に代表的なアプリを紹介していきます。 防災アプリは「通知」と「位置情報」を必ず設定! 防災アプリとは一般的に、災害時の情報収集や、家族など身近な人の安否確認などができるスマートフォンアプリのことを指します。災害はいつ、何時起きるか予想がつきません。そのため、どこでも持ち運べるスマートフォンに防災アプリを入れておけば、迅速な災害対応につながるのです。 防災アプリは種類によって、利用できる機能が大きく異なります。また個人向けのほか、企業が社員の安否確認などに活用できる法人向けも提供されています。 このように様々な種類がある防災アプリですが、どのサービスにおいてもあらかじめ行うべき、スマートフォンの設定が2つあります。いずれもiPhone向けの「iOS」では、歯車のアイコンがついた「設定」アプリから設定することができます。 ...









 トップ
トップ



![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)

