MENU


 PICKUP
PICKUP
税務ニュース
【2025年度(令和7年度)税制改正(その1)】103万円の壁の引き上げは123万円に!いつから?大学生のバイト「103万円→150万円」の控除も解説
昨年12月20日に2025年度(令和7年度)税制改正大綱が公表されました。もっとも注目されたのは「103万円の壁の引き上げ」です。どうなったのでしょうか。いつから始まるのでしょうか。今回は、103万円の壁の引き上げと大学生のバイトの壁の引き上げを中心に解説します。 2025年度(令和7年度)税制改正①「103万円の壁」が「123万円の壁」に 個人向けの税制改正の1つ目は「103万円の壁の引き上げ」です。 103万円の壁とは、パート・バイトといった給与所得者の非課税枠を言います。「給与所得控除の下限55万円+基礎控除額48万円=給与年収の非課税の上限103万円」という内容です。 多くのパート・バイトはこの103万円の壁を気にするため、年末になると「働き控え」という現象が起きていました。そのため、企業は人手不足に悩み、家計は物価高が改善されないという状況に陥っていたのです。 そこで、与党から政策協力を求められた国民民主党が「103万円の壁を引き上げるべきだ」と提案しました。議論が重ねられた結果、今回の税制改正で103万円の壁が引き上げとなったの...

社会保険ワンポイントコラム
職場の離職率低下につながる効果が!治療と仕事の両立支援について
治療と仕事の両立についての社会的背景 近年、医療の進歩により、がんのように以前は不治とされていた病気でも生存率が向上し、長期にわたって仕事との両立が可能になりつつあります。病気になったらすぐに離職しなければならないという状況から、治療を行いながら仕事を続けられる社会的環境へと変化しています。 しかし、疾病や障害を抱える従業員を支援するための社内体制が整っていない場合、従業員は仕事を続けたくても離職を選択せざるを得ません。これは企業にとっても人材の大きな損失といえるでしょう。 両立支援の内容 治療と仕事の両立支援の内容ですが、具体的には次のような柔軟な働き方ができる制度を設けた上で、私傷病の治療や療養を目的とした利用ができるようにします。 時差出勤制度 短時間勤務制度 時間単位の休暇制度・半日休暇制度 フレックスタイム制度 在宅勤務(テレワーク)制度 休職制度 両立支援に取り組むことの効果 労働政策研究・研修機構(JILPT)の「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)2024年3月」によれば、上記のよう...

6件 1~6件を表示
-

2024.06.07 IT・ガジェット情報
デジタルデトックスのススメ:ストレス軽減!デジタル依存の解放術
はじめに 現代社会において、デジタル機器は私たちの生活に欠かせない存在となっています。しかし、その過度な依存が問題視されるようになりました。常に情報を受け取り、即座に反応することを求められる環境は、ストレスを蓄積させ、心身の健康を脅かしています。 こうした背景から注目されているのが、「デジタルデトックス」という取り組みです。デジタルデトックスとは、一定期間意図的にデジタル機器から離れ、デジタル依存から解放されることを指します。ただし、デジタルそのものが悪だと決めつけるのではなく、デジタルとのバランスを保つことが大切です。(筆者はわかりやすくする為に、デジタルデトックスという言葉を選択していますが、デジタルの影響が必ずしも毒だとは思っていません。) 筆者自身、デジタル機器に囲まれた生活を送る中で、デジタルデトックスの必要性を強く感じるようになりました。そこで、2015年から毎年1回、自然豊かな千葉県香取市にて、2日間のデジタルデトックスを行っており、その効果を実感しまています。この記事では、筆者の体験を交えながら、デジタルデトックスの意義や方法についてお伝えして参ります。 デジ...
-

2024.05.15 社会保険ワンポイントコラム
新生活で感じるストレスは注意が必要! 五月病の症状と予防法を解説
春は入学や就職などで、たくさんの人が新生活を迎える季節です。新しい環境に早く慣れようと、はりきって頑張る人も多くいると思いますが、新生活開始から1ヵ月が経過する時期に増加する「五月病」に注意が必要です。 五月病にはどのような症状があるのか、また、どのように予防するべきかをみていきましょう。 五月病ってどんな病気? 気候が暖かく、貴重な大型連休があるため、毎年5月を心待ちにしている人は少なくないでしょう。しかし、楽しげなイメージと裏腹に、5月は体や心に不調をきたしやすい時期でもあります。この5月頃に多くみられる心と体の不調は、「五月病」と呼ばれます。 「五月病」という名称は、正式な病名ではなく俗称です。日本ではゴールデンウィーク明けの5月上旬の時期に、心身のバランスを崩す人が増加する傾向にあるため、この呼び方が定着したとされています。 五月病になると「やる気がでない」「不安になりやすい」「憂鬱な気分になる」「体がだるい」「食欲が低下する」「すぐに疲れる」「眠りが浅い」など、さまざまな症状が引き起こされます。 これらの症状は、風邪などのほかの要因でも見られるため、五月病だと...
-

2024.03.18 社会保険ワンポイントコラム
職場でとるべき基本的なメンタルヘルス対策について
職場のメンタルヘルス問題が大きく取り上げられるようになって10年以上たちますが、いぜんとしてメンタルヘルス問題による休職は大きな問題であり、労災申請、労災認定件数も年々増加の一方です。今回は職場でとるべき基本的なメンタルヘルス対策についてお話しします。 休職は発生する前から会社に損失を与えている 産業保健はILO(国際労働機関)とWHO(世界保健機関)により「すべての職業における労働者の身体的、精神的及び社会的健康を最高度に維持、増進させること、労働者のうちで労働条件に起因する健康からの逸脱を予防すること、雇用中の労働者を健康に不利な条件に起因する危険から保護すること、労働者の生理学的、心理学的能力に適合する職業環境に労働者を配置し、維持すること、以上を要約すれば作業を人に、また、人をその仕事に適合させること」を目的とするとされています(1995年)。 もちろん、これは理想論です。すべての社員にそれぞれの心理学的能力に適合した作業を配置することは無理で、職場や作業と本人の特性との不適合はある程度発生せざるを得ず、中にはメンタルヘルス不調を起こし休職する社員も現れま...
-

2023.04.12 中小企業おすすめ情報
従業員数50人以上の会社の”人事労務担当者”が知っておくべき5つのポイント
はじめに 従業員規模が拡大するにつれ、企業として対応すべき労務管理上の義務が新たに発生します。人数規模による企業の義務は、幾度となく法改正を繰り返して基準も変化しており、実務対応に頭を悩ませている人事労務担当者も多いのではないでしょうか。 本記事では、従業員数が50人以上になった場合に発生する5つの義務について、人事労務担当者が知っておくべきポイントを解説していきます。 そもそも従業員数50人とは? 従業員数50人には、フルタイムの常勤社員のみならず、パートタイマーも含むものとされています。また、労働安全衛生法令では、事業場を場所的観念によって考えます。つまり、営業所や工場、施設等、拠点を複数持つ企業においては、会社全体で50人の判定をするのではなく、拠点ごとに50人の判定をする必要があります。 (1)産業医の選任 従業員の健康管理を適切に行う為に「産業医」を選任しなければならないことになっています。「産業医」は、医師の中でも特別な研修を受けた者が有する認定資格であり、医師であれば誰でもよいわけではありません。この「産業医」探しになかなか苦労することがありま...
-

2022.08.11 社会保険ワンポイントコラム
メンタルヘルス不調の社員を早期発見するコツと対策
1960年代に日本は第3次産業が最も多い割合を占める国となりました。以来第3次産業の割合は増え続け、それとともに労働者のメンタルヘルス不調が産業衛生の大きな問題となっています。今回はメンタルヘルス不調の社員を早期発見するコツについてお話しします。 ストレスチェックは目的が違う 最初に強調しておきたいのは、ストレスチェック制度はメンタルヘルス不調の早期発見のためにあるわけではないということです。同制度の目的は二つです。まず受検した方が自分自身にストレスが溜まっているかどうかを確認すること。ストレスは自分自身で気づいていないことも多いからです。第二に、ストレスの高い従業員が多く存在する部署等があれば、これをきっかけに原因の解明や改善につなげることです。 着目点はKAPEや「2週間ルール」 ではどうやって早期発見すればいいのでしょうか。産業保健の世界ではKAPEを重視するべきだとされています。 K:勤怠=欠勤、突発休み、遅刻、早退など勤怠の乱れ A:安全=職場で安全行動をとっているか P:パフォーマンス=パフォーマンスが低下していないか E:影響=周囲への悪影響を及ぼしていないか 勤...
-
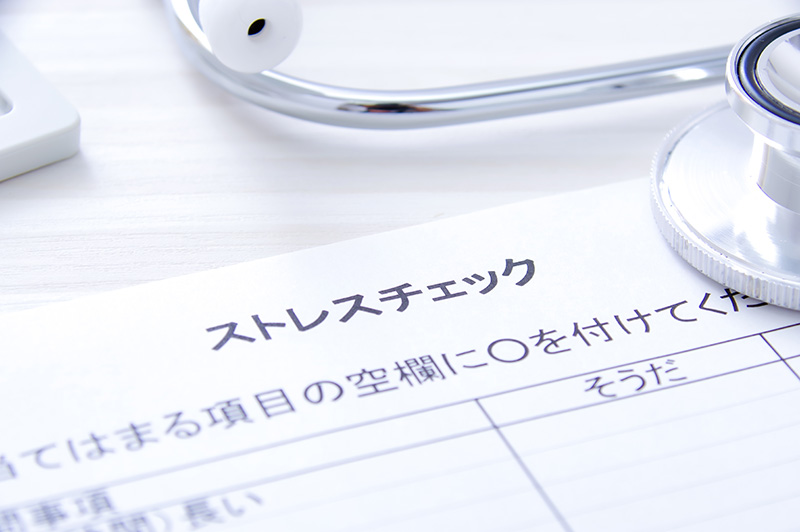
2021.12.01 社会保険ワンポイントコラム
コロナ禍だからこそ押さえておきたい!労働者へのストレスチェックの方法
ここ数年、メンタル不調者が増加しています。特にコロナ禍では、密を避けるために人とのコミュニケーションが希薄になったり、テレワークや時差出勤で働き方や生活スタイルが変わったりと、社会の大きな変化により、より多くの方のストレス増加に繋がっています。 そんな中でも、会社としては労働者のメンタル不調を未然に防止したいものです。そこで今回は、「ストレスチェック制度」について改めて確認しておきましょう。 労働者50人以上の事業場ではストレスチェックが義務 「ストレスチェック」とは労働安全衛生法に定められている制度で、ストレスに関する質問票に労働者が回答し、それを集計・分析することで、自分のストレス状態を調べる検査です。労働者が50人以上の事業場では、2015年12月より、毎年1回、労働者に対してストレスチェックを実施することが義務付けられていますので、ご存知の方も多いと思います。 実施手順は以下の通りです。 ① 労働者に質問票を配布し、記入してもらう 使用する質問票は、以下の3つが含まれていれば特に指定はありません。何を使えばよいかわからない場合には、国が推奨する質問票がありますし、専...









 トップ
トップ



![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)

