MENU


 PICKUP
PICKUP
税務ニュース
【2025年度(令和7年度)税制改正(その1)】103万円の壁の引き上げは123万円に!いつから?大学生のバイト「103万円→150万円」の控除も解説
昨年12月20日に2025年度(令和7年度)税制改正大綱が公表されました。もっとも注目されたのは「103万円の壁の引き上げ」です。どうなったのでしょうか。いつから始まるのでしょうか。今回は、103万円の壁の引き上げと大学生のバイトの壁の引き上げを中心に解説します。 2025年度(令和7年度)税制改正①「103万円の壁」が「123万円の壁」に 個人向けの税制改正の1つ目は「103万円の壁の引き上げ」です。 103万円の壁とは、パート・バイトといった給与所得者の非課税枠を言います。「給与所得控除の下限55万円+基礎控除額48万円=給与年収の非課税の上限103万円」という内容です。 多くのパート・バイトはこの103万円の壁を気にするため、年末になると「働き控え」という現象が起きていました。そのため、企業は人手不足に悩み、家計は物価高が改善されないという状況に陥っていたのです。 そこで、与党から政策協力を求められた国民民主党が「103万円の壁を引き上げるべきだ」と提案しました。議論が重ねられた結果、今回の税制改正で103万円の壁が引き上げとなったの...

社会保険ワンポイントコラム
職場の離職率低下につながる効果が!治療と仕事の両立支援について
治療と仕事の両立についての社会的背景 近年、医療の進歩により、がんのように以前は不治とされていた病気でも生存率が向上し、長期にわたって仕事との両立が可能になりつつあります。病気になったらすぐに離職しなければならないという状況から、治療を行いながら仕事を続けられる社会的環境へと変化しています。 しかし、疾病や障害を抱える従業員を支援するための社内体制が整っていない場合、従業員は仕事を続けたくても離職を選択せざるを得ません。これは企業にとっても人材の大きな損失といえるでしょう。 両立支援の内容 治療と仕事の両立支援の内容ですが、具体的には次のような柔軟な働き方ができる制度を設けた上で、私傷病の治療や療養を目的とした利用ができるようにします。 時差出勤制度 短時間勤務制度 時間単位の休暇制度・半日休暇制度 フレックスタイム制度 在宅勤務(テレワーク)制度 休職制度 両立支援に取り組むことの効果 労働政策研究・研修機構(JILPT)の「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)2024年3月」によれば、上記のよう...

14件 1~14件を表示
-

2024.02.21 起業応援・創業ガイド
<連載>副業をはじめよう!【第6回】副業で法人化するのはいつ?メリットデメリットは?
副業を個人事業から法人化? 会社員が副業として独自のビジネスを始めるとき、多くの場合は、小規模で始まりますが、時間とともに成長する可能性があります。 「法人化」とは、個人が運営するビジネスを、設立した会社に引き継ぐことです。法人化は、ビジネスの成長と発展に伴うリスクと責任を管理するための一つの方法として広く利用されています。 副業を行う個人にとって、法人化を選ぶ最大の理由は、個人事業主としてのリスクや税負担を軽減しつつ、事業の信頼性や拡大の可能性を高めることができる点にあります。 この回では、副業で個人事業主→法人へステップアップする際のポイントやメリット/デメリットを詳しくみていきましょう。 法人化をするタイミングは? 法人化は、いつするのがいいのでしょうか?副業を個人事業で進めてきた場合、具体的にどのような状態になったら、法人化をするべきなのか。 個人事業主は、所得(売上から経費を控除したもの)の金額に応じて所得税がかかります。一方、会社設立をした場合は会社でのもうけ(所得)の金額に応じて法人税が課税されます。 個人事業主の所得税の税率は累進課税となっています。※1税率の...
-

2024.01.31 税務ニュース
給与所得と、副業の事業所得がある場合のはじめての確定申告
終身雇用制度の縮小や非正規雇用の増加など、労働市場の変化に伴い、多くの労働者が安定した収入を確保するために副業に取り組むようになっています。副業は、異なる分野でのスキルや経験を積む機会となり、キャリアの多様化に貢献するといわれています。また、個人の成長や新たなキャリアパスの開拓にも役立っていることでしょう。 従来は副業を禁止または制限する企業が多かったですが、最近では副業を許可する企業が増えています。これは従業員のワークライフバランスの向上や、多様な経験を通じた人材の成長を促すためなどといわれます。 今回は、給与所得と事業所得の両方がある場合の確定申告について、はじめての方に知っておいていただきたいことについてふれていきます。 事業所得の計算の概要 まず、事業に関連して得たすべての収入を集計します。これには、販売収入、サービス提供による収入、事業に関連するその他の収入が含まれます。必要経費について、事業運営にかかった費用(必要経費)を計上します。主には、材料費、仕入、交通費、交際費、通信費(電話、インターネット等)、家賃や水道光熱費(事業用の部分)、機器、備品の購入費や修理...
-

2024.01.29 起業応援・創業ガイド
<連載>副業をはじめよう!【第5回】副業はどこまで経費にできる?初心者向けの明確なルールとヒント
副業をご検討されている方、すでに開始されている方、副業の経費計上の基本について知っておくことは大切です。この記事では、副業における経費の計上方法と、その重要性について分かりやすく解説します。※ ※副業が事業所得や雑所得の区分で行う方を前提とします。副業がパートアルバイトの場合は、給与所得に該当しますので、ご自身で経費を計上することはありませんのでご注意ください。 副業の経費の基本 副業での経費とは、その活動に直接関連する必要経費のことを指します。これには、仕事で使用する機器の購入費、通信費、事務用品の購入費などが含まれます。経費を正しく計上することは、「節税」という意味で大きな役割を果たします。ただし、経費が多ければいいというものでは決してなく、適切に経費を使っていて、事業として利益を出せているのかが重要です。 しかし、副業の経費として計上できるものとできないものがあるため、その区別を理解することが重要です。ここからは、副業での経費計上の明確なルールとヒントをお伝えしていきます。 計上できる副業の経費 副業で計上できる経費には、様々なものがあります。 旅費交通費 ...
-

2023.12.24 起業応援・創業ガイド
<連載>副業をはじめよう!【第4回】副業のお金の管理_売上編
副業のお金の管理_売上編 近年、多くの会社員が副業やフリーランスとして働く機会を持つ時代になりました。しかし、このような働き方の中では、従来の雇用形態とは異なる「管理」が求められます。自己責任で収入や経費を管理し、税金を計算すること。これは、副業やフリーランスの成功において重要な要素です。自分自身の副業における価値を正確に把握し、その収益を最大化するためには、効果的なお金の管理が必要となります。 今回は、お金の管理、特に「売上・収入の管理」を中心にまとめています。 お金の流れを把握するから、将来の経済的不安が軽減する 副業をする方の中には、将来の経済的不安をなくしたいという理由から副業をされる方が多くいらっしゃいます。でも、実は副業でお金を稼ぐだけでは、将来の漠然とした経済的な不安はなくなりません。なぜならば、お金を稼ぐこととお金を残すことは別のことだからです。不安を払拭したければ、「お金の流れ」を把握することが必要となります。 副業でのお金の流れを簡単に説明すると下記のようになります。 1:副業でお金を稼ぐ 2:経費としてお金を使い 3:お金が手元に残る 1から3を繰り返し...
-

2023.11.24 起業応援・創業ガイド
<連載>副業をはじめよう!【第3回】副業と確定申告を初心者向けに徹底解説!
近年、副業を解禁する企業も増え、また副業をきっかけに新たなキャリアを描こうとする方も増加傾向にあります。副業で収入を得たら必ず関係してくるお金のコト。今回は副業の確定申告を中心に詳しく解説していきます。 副業の確定申告について初心者向けに徹底解説! 確定申告とは1年間(1月1日から12月31日まで)に所得がある方が、所得税と復興所得特別所得税の金額を申告して納税する制度です。もし、納めすぎた所得税等がある場合は還付申告を行うことで、お金が戻ってきます。本業での勤務のみの会社員は年末調整があるので、基本的には確定申告が不要です。 しかし、会社員で副業を始めたら本業の会社で年末調整をしていても別で確定申告が必要になることがあります。 副業での収入はいくらから確定申告が必要か 副業での収入があれば、下記の場合に確定申告が必要になります。 ①副業が給与所得に該当:パートアルバイトの年間の給与収入が20万円を超えた場合 ②副業が雑所得や事業所得に該当:年間の所得が20万円を超えた場合 副業での収入があるが確定申告が不要な場合とは? 上記の説明の裏返しになりますが、以下の場合には、確定申...
-

2023.09.06 起業応援・創業ガイド
<連載>副業をはじめよう!【第2回】リスクなく堅実に!副業の始め方
会社員としての副業:現状と可能性 近年、多様化する働き方の中で、「副業」が注目されています。 経済の変動やライフスタイルの多様性が求められる現代において、多くの会社員が本業だけでなく、副業を持つことで収入を増やす動きが活発化しています。従業員の副業・兼業を禁止または制限する企業は減少傾向にあり、多くの企業が副業を許可する方向へとシフトしています。 副業を持つ会社員のメリット 副業を持つことで得られるメリットは数多く存在します。まず第一に、収入の増加です。月収だけでなく、年収も格段にアップする可能性が広がります。また、異なる職種や業界での経験は、スキルや視野の拡張、ネットワークの拡大にも繋がります。これは、将来的なキャリアチェンジや独立を考える際の大きな武器となります。 前回の記事「副業をはじめよう!キャリアの選択肢に副業を!」では、副業のメリットや広がる可能性について更に詳しく書いてますので、是非お読みください。 副業における最初のステップ:情報収集 安心安全な副業の見極め方 副業を始めるにあたり、最も重要なのは「安心安全な副業」を行うことです。副業でお金が稼げるという甘い言葉...
-

2023.08.10 起業応援・創業ガイド
<連載>副業をはじめよう!【第1回】キャリアの選択肢に副業を!
"副業の時代を極める” 稼ぐ&キャリアの可能性を広げる確実な方法 副業時代の到来ですね!国策として、副業・兼業が推進される時代です。日本経済の衰退、終身雇用性も崩壊し、会社に定年まで勤めるということが難く、「国」が自ら主導して副業を推す時代が来るなんて、10年前には、全く予想しなかったことではないでしょうか。 そんな流れで、最近、以前にもまして会社員の方からの副業のご相談をたくさんいただくようになっています。私は、税理士として起業副業の専門家として、支援をする中で、年間100名以上の副業のご相談を頂いていますが、その中で1番多いのは、 副業はやってみたいけれど、何をすればよいかわからない。 自分には、売る商品がない! などの「副業の始め方がわからない」というご相談です。 また、副業に興味がありご相談にはきてくださるものの、実際に副業のスタートをきる方は、本当に一握りです。その位、副業を始めることのハードルは一般の会社員の方にとっては、意外と高いものだと実感しています。 しかし、副業は、追加の収入を得るだけでなく、キャリアの柔軟性と多様性を高める機会を提供して...
-

2023.07.17 社会保険ワンポイントコラム
他社でも社保加入中の副業・兼業社員 給料にかかる社会保険料額はどう決まる?
働き方改革に伴う副業・兼業の解禁により、他社でも厚生年金・健康保険に加入しながら働く社員が増えている。そこで今回は、複数の企業で社会保険に加入する社員の社会保険料額決定の仕組みを整理しよう。 他社の給料を合算して決める社会保険料 社会保険では、同時に複数の企業で厚生年金・健康保険に加入する勤務形態を二以上事業所勤務という。二以上事業所勤務をする社員の月々の給料にかかる社会保険料額は、他社でも加入中であることを踏まえて額が決定される。 保険料額を決める具体的な手順は、次のとおりである。 ① 各企業の給料額を合算する。 ② 合算した給料額に対応した標準報酬月額を求める。 ③ 求めた標準報酬月額に保険料率を乗じ、保険料額を算出する。 ④ 算出された保険料額を各社の給料額で按分し、企業ごとの保険料額を割り出す。 ① 給料額を合算する 厚生年金の保険料額を例にとり、具体例で考えてみよう。例えば、A社で社会保険に加入中の社員が、B社でも社会保険に加入して働くことになったとする。 この場合に合算する給料額は、食事を提供するなど現金以外で支給するものもあるケースでは、それらも金額換算して加...
-

2023.01.05 社会保険ワンポイントコラム
労災はどちらの会社で手続きする?副業・兼業における労務管理のポイント
はじめに 新型コロナウイルスの影響も相まって、副業・兼業への関心が一気に高まっています。従業員が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由という考え方がありますので、原則的には副業・兼業を認める方向での検討が望ましいとされています。 しかし、企業には副業・兼業を認めるうえで本業にどのような支障をもたらすかを精査し、副業・兼業を一切認めない、あるいは条件付きで認める等の判断を入れる必要があります。 厚生労働省が公開している統計によると、正社員の副業を容認する企業は増加している一方、全面禁止としている企業も多く存在していることがわかります。 (出典)厚生労働省『副業・兼業の促進に関するガイドラインの改定案について』P5 今回は、企業が副業・兼業を検討するときに知っておくべき、労働時間管理や健康管理のポイントについてお伝えします。 判断を入れる際のポイント 副業・兼業を希望する人が年々増加傾向にある中で、企業としてどのような方針を採るべきか悩むところです。 判断を入れる際のポイントは以下のとおりです。 ① 本業の仕事への支障 ② 働きすぎによる心身の健康...
-
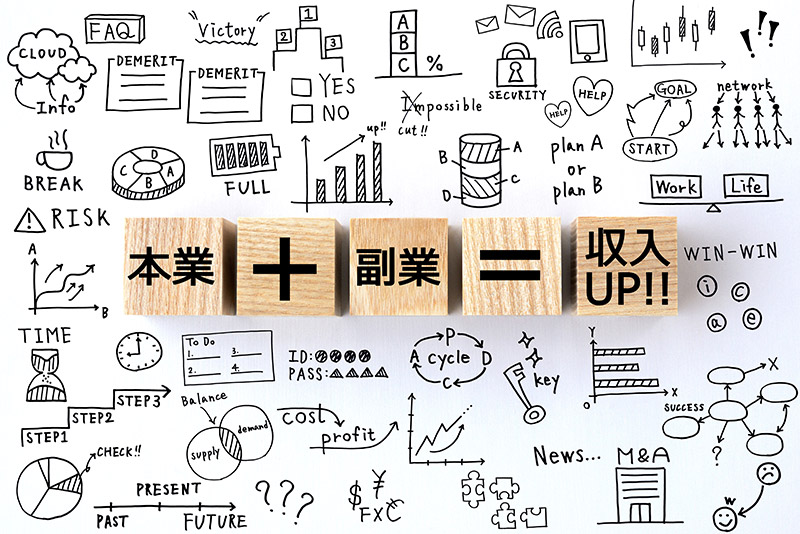
2023.01.03 起業応援・創業ガイド
副業で20万円以下は確定申告はしなくていい?
会社員で副業・兼業をしている方、これからしようかなと検討中の方は多いのではないでしょうか?副業・兼業で収入を得たら、知っておく必要がある確定申告について、しなければいけない場合、確定申告不要となる場合について詳しく解説しています。 ①会社員の副業と確定申告 国策を挙げて、副業が推進される時代です。副業解禁も進み、副業に本気で取り組む会社員の方も増えています。総務省による調査によれば、下記のように副業を希望する雇用者は年々増加傾向にあることが分かっています。 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」P22から引用 副業で収入を得たら、自分で1年間の税金を計算し、申告と納付を行う「確定申告」についても知っておく必要があります。会社員の方は、特殊なケースに該当しない限り、1年間の税金の精算として会社が行うおなじみの「年末調整」で税金の計算は完了しています。 でも、副業で収入を得た場合は、会社員が副業で得た合計額が、年間で20万円を超えた場合には、確定申告を行う必要があります。この20万円の判定は、副業が給料なのか、その他の事業所得や雑所得かによって異なります。 副業がパートアル...
-
![クリエイターと税金[第1回]:人も税も中身が肝心?クリエイターが独立前に稼ぐ「お金の性質の違い」について解説](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-514.jpg)
2022.09.15 おんすけと学ぶ税務情報
クリエイターと税金[第1回]:人も税も中身が肝心?クリエイターが独立前に稼ぐ「お金の性質の違い」について解説
フリーランス・クリエイターが知っておきたいお金と税金のしくみ クリエイターが独立しようとすると、さまざまな疑問や悩みがでてきます。 本コラムでは、これから独立しようと考えている駆け出しクリエイターが知っておきたいお金と税金のしくみを、独立前・開業準備・開業1年後などのステップごとに、やさしく解説します。 第1回では、「独立前」にスポットを当てて、稼いだ「お金の性質」の違いについて考えてみましょう。 クリエイターが稼いだ「お金の性質」とは? 多様化するクリエイターの収入源 SNSなどのプラットフォームの発展により、個人が自分の作品を広める機会が増えました。今まで消費者の立場だけだった人でも、誰もがクリエイティブ領域に飛び込み、コンテンツの生産者・販売者になれるチャンスがあります。 クリエイティブ領域で利用されるプラットフォームは、YouTubeやInstagramなどのSNSをはじめとして、Shopify、NFTなど多岐にわたります。クリエイターはこれらのツールを活用して、デザイン・動画・音声・文字などの「コンテンツ」の提供、広告掲載、オリジ...
-

2022.06.21 税務ニュース
従業員の副業がバレる?会社が住民税の決定通知書で確認すべき3つのポイント
「住民税の決定通知書で従業員の副業がバレる」と言われます。それはなぜでしょうか。また、通知書のどこを見たら副業が分かるでしょうか。今回は、会社の経理や総務の方向けに、住民税のしくみと決定通知書のチェックポイントをお伝えします。 なぜ副業バレ?住民税のしくみを確認しよう 住民税の決定通知書で副業がバレるしくみを見る前に、住民税の計算や徴収の仕方を確認しましょう。 住民税は地方自治体が計算・徴収する「賦課徴収方式」 住民税は市町村(東京都23区は東京都)が賦課徴収する地方税です。課税されるのは、その年の1月1日時点で自治体内に住所のある人となります。 納税者自ら所得額と税額を計算して国に納める所得税と違い、住民税は各自治体が所得額と税額を計算します。納付書(住民税の決定通知書)が送付されたら、個人はこれを使って住民税を住んでいる自治体に納めるのです 住民税は「均等割」「所得割」が中心 税額計算も、所得税と異なります。所得税は「所得額×税率」で計算するのみです。一方、住民税は次の2つが中心です。 均等割:所得が一定額以上だと定額で課される住民税。2022年現在、一律5,00...
-

2022.03.01 税務ニュース
副業収入が減る??事業者も会社員も必見!副業による「インボイス制度」の影響について詳しく解説!
副業解禁・副業推進のニュースが当たり前にみられる時代になりました。今回は、2023年10月から始まるインボイス制度が及ぼす副業をされている方への影響を解説していきます。 この記事を読むと以下が分かるようになります。 インボイス制度が始まると、副業に影響があるのか?売上が減少するかも・・と言われている理由 副業の方のインボイス制度への対策 インボイス制度の概要 https://revision.sorimachi.biz/taxnews/20210927_01 https://revision.sorimachi.biz/taxnews/20210811_01 2023年10月1日(令和5年10月1日)から「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が導入されます。今回は、副業の方に、インボイス制度がどのように影響があるのかを中心にお話しますので、制度の詳細については、大枠を説明させて頂きます。 インボイス制度とは「企業と企業(または個人)の取引における消費税額や適用税率を正確に把握することを目的とした制度」で、消費税の仕入税額控除を受ける際に「適格請求書(...
-

2021.09.20 社会保険ワンポイントコラム
中小企業でも副業・兼業は活用できる!大切なポイントを押さえておきましょう。
政府が推進する働き方改革を受け、厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を2020年9月に改定しました。象徴的なのが、それまでは「許可制」としていたものを「届出制」とする、複雑となる労働時間の管理を「管理モデル」という手法で簡素化する、などでしょうか。先進的な大手企業では、このような環境変化に伴い自社の戦略的な人材開発として「副業・兼業」を積極的に活用し始めています。いわば、禁断の果実だったものを成長の果実へと発想の転換をしているわけです。 ただ、緩和されたとはいえ、多くの企業では「副業・兼業」の制度化に二の足を踏んでいるのが実情です。それは、経営者から見れば人材の流出や長時間労働を助長するのではないか、働く人の視点では賃金カットやリストラにつなげるステップとなるのではないか、といった予断があるからでしょう。 「副業・兼業」の2つの方法 ここで、「副業・兼業」制度を感覚的に一括りで捉えるのではなく、二つに分解してみると分かりやすくなります。一つは、「副業・兼業」元として、自社の社員を「副業・兼業」先へ送り出す方法です。二つ目は、逆に「副業・兼業」先として、外部の「...









 トップ
トップ



![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)

