MENU


 PICKUP
PICKUP
税務ニュース
【2025年度(令和7年度)税制改正(その1)】103万円の壁の引き上げは123万円に!いつから?大学生のバイト「103万円→150万円」の控除も解説
昨年12月20日に2025年度(令和7年度)税制改正大綱が公表されました。もっとも注目されたのは「103万円の壁の引き上げ」です。どうなったのでしょうか。いつから始まるのでしょうか。今回は、103万円の壁の引き上げと大学生のバイトの壁の引き上げを中心に解説します。 2025年度(令和7年度)税制改正①「103万円の壁」が「123万円の壁」に 個人向けの税制改正の1つ目は「103万円の壁の引き上げ」です。 103万円の壁とは、パート・バイトといった給与所得者の非課税枠を言います。「給与所得控除の下限55万円+基礎控除額48万円=給与年収の非課税の上限103万円」という内容です。 多くのパート・バイトはこの103万円の壁を気にするため、年末になると「働き控え」という現象が起きていました。そのため、企業は人手不足に悩み、家計は物価高が改善されないという状況に陥っていたのです。 そこで、与党から政策協力を求められた国民民主党が「103万円の壁を引き上げるべきだ」と提案しました。議論が重ねられた結果、今回の税制改正で103万円の壁が引き上げとなったの...

社会保険ワンポイントコラム
職場の離職率低下につながる効果が!治療と仕事の両立支援について
治療と仕事の両立についての社会的背景 近年、医療の進歩により、がんのように以前は不治とされていた病気でも生存率が向上し、長期にわたって仕事との両立が可能になりつつあります。病気になったらすぐに離職しなければならないという状況から、治療を行いながら仕事を続けられる社会的環境へと変化しています。 しかし、疾病や障害を抱える従業員を支援するための社内体制が整っていない場合、従業員は仕事を続けたくても離職を選択せざるを得ません。これは企業にとっても人材の大きな損失といえるでしょう。 両立支援の内容 治療と仕事の両立支援の内容ですが、具体的には次のような柔軟な働き方ができる制度を設けた上で、私傷病の治療や療養を目的とした利用ができるようにします。 時差出勤制度 短時間勤務制度 時間単位の休暇制度・半日休暇制度 フレックスタイム制度 在宅勤務(テレワーク)制度 休職制度 両立支援に取り組むことの効果 労働政策研究・研修機構(JILPT)の「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)2024年3月」によれば、上記のよう...

12件 1~12件を表示
-
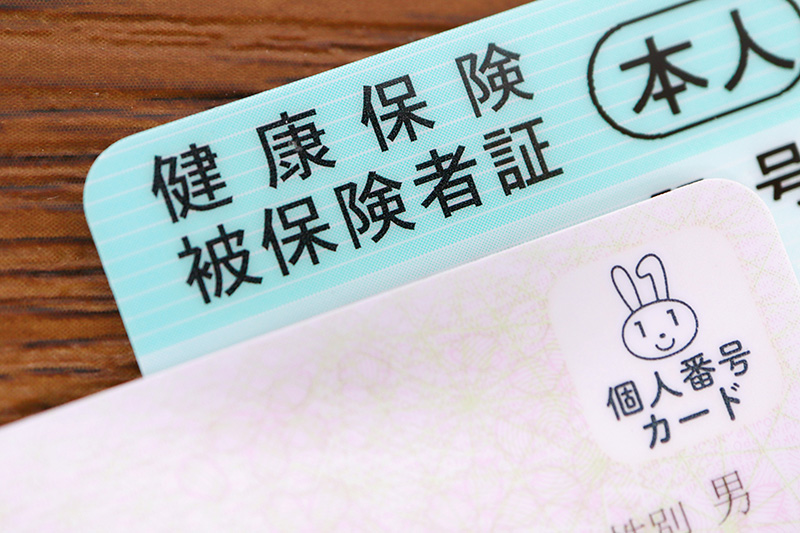
2022.10.26 社会保険ワンポイントコラム
2024年秋、健康保険証がマイナンバーカードに!知っておきたいメリット・デメリット
河野デジタル相は10月13日、記者会見にて「現在の健康保険証を廃止し、マイナカードと一体化した『マイナ保険証』を原則とする」という政府の方針を発表しました。2024年秋以降、病院での診療や薬局での薬の購入は原則、健康保険証と一体化したマイナンバーカードで行われることになります。現行の健康保険証は使えなくなるのです。 マイナンバーカード一体化の背景 健康保険証とマイナンバーカードの一体化を言い換えると「マイナンバーカード所持の義務化」です。日本は国民皆保険制度を採用しており、健康保険への加入は義務付けられています。加入の事実を示すのが健康保険証なのですが、「健康保険証=マイナンバーカード」になれば、健康保険に加入している人全員、マイナンバーカードを持つ必要が生じるのです。 なぜ政府は、このような方針を打ち出したのでしょうか。背景には次の2つがあります。 ポイント事業をしても取得率が50%未満 1つ目の理由は「マイナンバーカードがなかなか普及しないから」です。2016年1月にマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がスタート、同時にマイナンバーカードの交付が始まりました。6年超が...
-

2022.10.20 税務ニュース
節電ポイントやマイナポイントには税金がかかる?ポイントと税金の関係について解説。
ポイントをもらったり使ったりした場合、税金がかかるのでしょうか? 本コラムでは、企業ポイントと税金の関係について、やさしく解説します。 ポイントと税金の関係は「値引き」かどうかで判断 近年の電力不足問題の深刻化を受けて「節電ポイント」の導入が進められています。 電力需要の逼迫が懸念されるため、各家庭に節電を促すのが目的です。電力会社が開催する節電キャンペーンや省エネプログラムに参加し、その内容に応じて節電ポイントが付与されます。 政府が実施する「ポイント政策」は、ほかにマイナポイントや消費税の増税に伴うキャッシュレス決済のポイント還元などが記憶に新しいところです。 この「ポイント」には税金がかかるのでしょうか? その判断の要点は「値引き」かどうかです。 この点について、国税庁は、個人が商品を購入するときに付与されるポイントで、「通常の商取引における値引き」と同様の行為が行われたものと考えられる場合には、所得税の課税対象にならないものとして取り扱うと説明しています。 マイナポイントや節電ポイントは「通常の商取引における値引き」とは同視できないため、課税対象になるのです。 ...
-

2022.06.16 税務ニュース
6月30日からスタートするマイナポイント第2弾。マイナンバーカード申請のメリット・注意点は?マイナポイントには所得税が課税される?
総務省は、マイナンバーカードの取得者に対して1人あたり最大2万円相当のポイントを付与するマイナポイント事業(第2弾)の申込受付を2022年6月30日から開始することを発表しました。このマイナポイント第2弾は、マイナンバーカードの普及の促進、消費喚起や生活の質の向上などが目的で、2021年11月19日に閣議決定した経済対策にその実施が盛り込まれていました。 本コラムでは、マイナポイント第2弾の概要やメリット・注意点を確認しながら、気になるマイナポイントの課税関係について、やさしく解説していきます。 参照:首相官邸「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)」 マイナポイント第2弾の内容 以下①〜③の3つをあわせて最大2万円相当のポイントが付与されるというのが、マイナポイント第2弾の内容です。 ポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限は2022年9月末まで、マイナポイント第2弾の申込期限は2023年2月末までです。 参照:総務省「マイナポイント事業」 ①マイナンバーカードの新規取得等で最大5,000円相当のポイント付与 マイナン...
-

2022.01.21 みんなの経営応援通信編集部
【DXの基礎知識】マイナポータル&マイナンバー制度の現在と未来
平成27年10月以降に通知されたマイナンバー(個人番号)は認知度も上がってきており、「全く聞いたことがない」「知らない」という方は少ないかと思います。 ですが、「マイナンバーを使って何ができるのか」については、よくわからない方もいるかもしれません。マイナンバー制度の目的、マイナンバーによって現在できること、将来的にできることについて解説していきます。 マイナンバーって何だろう? マイナンバー(個人番号)は住民票を持つ全ての人に付番される12桁の番号です。一人につき一番号で、他人と重複することはなく、原則として一生同じ番号を使用することになります。 また、法人には13桁の法人番号が付番されています。こちらは個人番号とは異なり原則として公表され、どなたでも利用できます。 マイナンバーの目的としては、次の三つがあります。 国民の利便性の向上 社会保障・税関系の申請などの事務手続きの効率化を図ります。 行政の効率化 国や地方公共団体の間で情報連携し、情報の照合や転記等の効率化を図ります。 公平・公正な社...
-
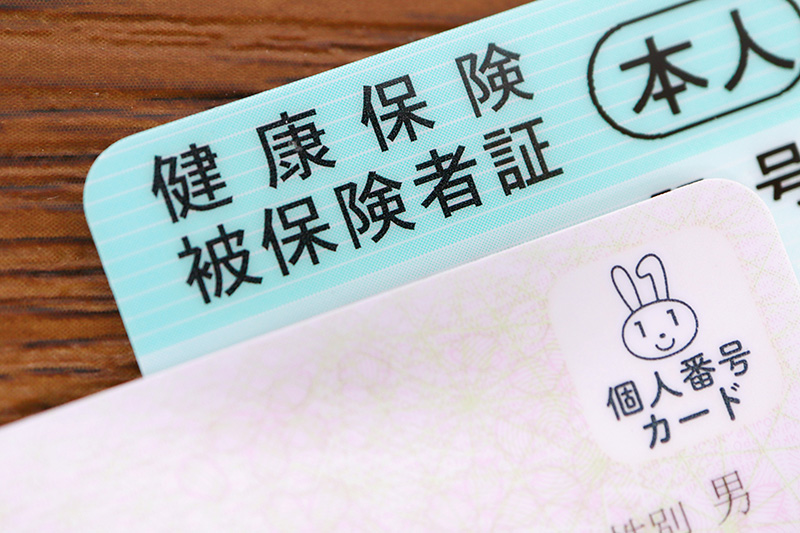
2021.12.06 税務ニュース
10月からマイナンバーカードが健康保険証代わりに?メリット・デメリットを解説
10月20日から、マイナンバーカードを健康保険証として使えるしくみが始まりました。現在、全国の医療機関や薬局で対応システムの導入が少しずつ進められているようです。今回は、このしくみが普及したときのメリット・デメリットを解説します。 「マイナンバーカードが健康保険証になる」メリット マイナンバーカードが健康保険証代わりになると、従来の健康保険証の提示が不要になります。つまり「持ち歩くカードが1枚減る」わけですが、それだけではありません。次のようなメリットがあります。 ●高額療養費の自己負担をしなくて済む もっとも大きいメリットは「高額療養費の自己負担をしなくて済む」という点です。高額療養費とは、病気やケガで医療費が高額になったとき、一定額以下に自己負担が抑えられる制度をいいます。高額な部分は国が負担してくれるのです。 「じゃあ今のままでも問題ないんじゃない?」と思うかもしれません。が、実は、そう簡単ではないのです。最終的に国が負担してくれるものの、一度は個人がすべて自己負担しなくてはなりません。 自分のお財布から高い医療費を払った後、市区町村や健康保険組合に高額療養費の支給申...
-

2021.11.08 みんなの経営応援通信編集部
使ってる? 使ってない?「マイナンバーアンケート集計結果」
マイナンバーを活用していますか? ソリマチでは、ユーザー様宛にメールマガジン「会計・実務情報通信」を定期配信しています。「会計・実務情報通信」2021年10月1日号・2021年10月12日号にて、マイナンバーに関するアンケート調査を掲載し、延べ65名の方からご回答をいただきました。 以下では、その集計結果について、ご報告いたします。なお「複数回答可」とある設問は複数の選択肢を選択できる形式で、それ以外は一つの選択肢のみを選択する形式です。 総務省が発表している「マイナンバーカードの市区町村別交付枚数等について(令和3年10月1日現在)」を参照すると、日本全国でのマイナンバーカード普及率は38.4%です。この回答では「持っている」が六割弱ですから、平均よりも高い数字が出ています。マイナンバーにより関心の高い方が答えている傾向なのかもしれません。 第一位は「e-Taxなどの電子申請に使用するため」35.38%、第二位は「身分証として使用するため」26.15%でした。「身分証」はマイナンバーカードの用途の代表的なものですが、それ以上に電子申請へのニーズは高いようです。 ...
-

2021.10.15 税務ニュース
スマホで確定申告してみよう!!マイナポータル連携で確定申告がかんたんに
電車に乗ると、乗車しているほとんどの人が行っている“あること”に気付きます。90%以上の人がスマートフォンの画面を眺めているのです。メール、インターネット、SNS、動画、電子書籍などそれぞれが自分の好きなことをしています。いわゆる携帯電話としての通話機能を使うことはあまりありません。 実は、税金の世界でもスマートフォンの利用は進んでいます。なかでも、個人の確定申告についてはスマートフォンの利用が拡大しています。スマホ申告というとハードルが高いように感じますが、手続き自体はかなり簡便化されており、ぜひ利用してほしい手続きです。まずは、スマホ申告を行うためのふたつの方法について説明していきます。個人所得税の確定申告は、どちらでも申告することはできますが、最初にどちらで申告するかを決めなければなりません。申告方法によって手順が若干異なりますので注意が必要です。 スマホ申告を行うためのふたつの方法 マイナンバーカード方式 マイナンバーカードを利用してe-Taxを行う方法です。 この方法はマイナンバーカードに収納されている個人情報を申告書データに添付することによって、個人を特定できる...
-
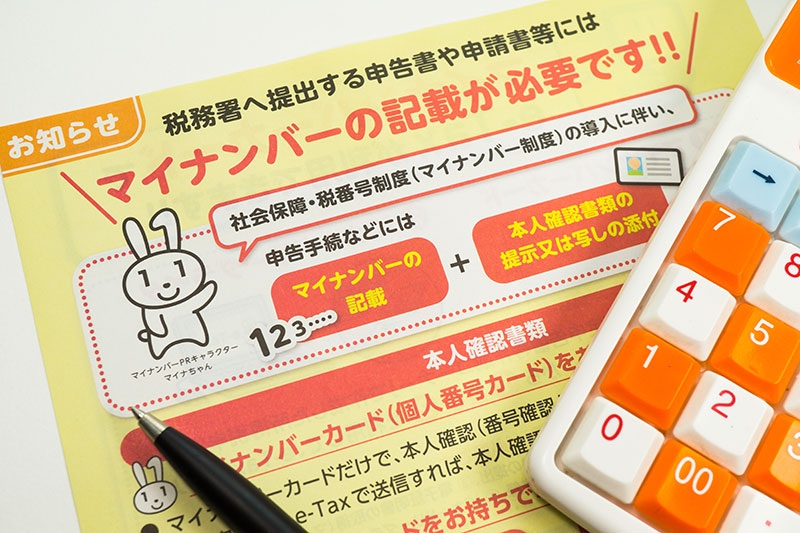
2021.09.10 税務ニュース
税務でマイナンバーを求められるのはどんな時? e-Taxなども併せて税務手続きを効率的に!
マイナンバーが導入されたことにより、税金関係の手続きがスムーズにできるようになりました。 「でも、具体的にどんな税務手続きでマイナンバーが必要なの?」 こんな疑問を持たれている方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、マイナンバーが必要な税務手続きについて解説していきます。 1.確定申告 マイナンバーは確定申告の際に必要になります。平成28年の運用開始以降、確定申告書にマイナンバーを記載して提出することになりました。例えば所得税等の確定申告書B様式第一表には、以下のように本人のマイナンバー記載欄があります。 国税庁HP:「マイナンバーの申告書への記載について:令和2年分 確定申告特集 (nta.go.jp)」参照 また、所得税等の確定申告書B様式第二表には、下の図のように配偶者・扶養親族・事業専従者のマイナンバーを記載する必要があります。 国税庁HP:「マイナンバーの申告書への記載について:令和2年分 確定申告特集 (nta.go.jp)」参照 従来、年末調整や確定申告などで控除を受けるためには、さまざまな書類を揃えなければなりま...
-

2020.03.01 税務ニュース
マイナポイント事業<25%還元の制度徹底解説>
2019年10月より消費税率の引上げとそれに伴う消費の落ち込みを防ぐためにキャッシュレス・ポイント還元事業が開始されました。制度開始の10月1日から12月16日までに対象決済額は約2.9兆円、還元額は1,190億円となり、キャッシュレス決済の利用が拡大しました。ただし、この制度は2020年6月までの期間限定の施策です。そのため、還元事業の終了と東京オリンピックの終了後の景気の落ち込みへの懸念から、マイナポイントを活用した事業が予定されています。 マイナポイント事業は、消費税率引き上げに伴う需要平準化策として、消費の活性化を図ると同時に、カード普及率が全国平均で15.0%(令和2年1月20日現在)と低迷しているマイナンバーカードの普及促進、キャッシュレス決済基盤の構築を目的としています。2020年9月1日から7ヵ月の期間限定で、自ら選択したキャッシュレス決済サービスを用いてキャッシュレスでチャージ又は買い物をするとマイナポイントが25%貰えます。例えばキャッシュレスで2万円のチャージ又は買い物をすると1人あたり5000円分のマイナポイントが貰え、マイナポイントは選択したキャッシ...
-

2018.05.01 税務ニュース
住民税のマイナンバー記載と電子化
個人の住民税は、企業にお勤めの給与所得者の場合、6月から翌年5月まで、毎月の給与から会社が給与天引きし、市区町村に納付します。 天引きされる税額は、市区町村が特別徴収税額通知書を企業に宛てて通知しており、通知書は特別徴収義務者である企業が保管するものと、納税義務者である本人に渡されるものとがあります。 平成30年度税制改正大綱に、この通知書に記載されるマイナンバーの取扱いを一部見直すことが明記され、昨年12月26日に、地方税法施行規則が一部改正されました。この改正により、各地方団体が書面により特別徴収税額通知を送付する場合には、当分の間、マイナンバーは記載しないこととされました。その一方、eLTAXや光ディスク等、電子的に特別徴収税額通知を送付する場合には、マイナンバーは記載することとされています。よって、平成30年度からは、特別徴収税額通知が書面により通知されるか、電子媒体により通知されるかにより、マイナンバーの記載が異なることになります。特別徴収税額通知の電子化は、平成28年度分の個人住民税から可能となり、行政事務の電子化を推進する政府は電子化を奨励していますが、平成29...
-

2016.04.01 税務ニュース
新入社員にかかる税務とマイナンバー
4月は多くの企業で新入社員を迎える季節です。 総務や人事、経理を担当する管理部門では、新入社員にかかる事務に気を使うことになります。例えば、新入社員の方には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいますが、それは扶養状況等を把握し、月々の給与から源泉徴収される所得税を、扶養家族等の数に応じて計算する必要があるからです。 た、前職がある方や、新卒の方でも1月から3月までの間にアルバイト等による給与収入がある場合には、源泉徴収票を提出してもらう必要もあります。これらのほか、今年はマイナンバー制度が開始されてから初めて新入社員を迎える企業が多いことから、マイナンバーにかかる事務手続き等にも気を付ける必要があります。新入社員の入社時には、その社員となる方のマイナンバーを取得し、本人確認が必要となります。本人の顔写真の入った「個人番号カード」なら、本人確認をすることも可能ですが、「通知カード」で本人確認を行う場合には、「通知カード」と「写真付身分証明書」等により確認します。 なお、マイナンバーの取得の際には、「給与所得源泉徴収票」の作成事務、「健康保険・厚生年金保険」の届...
-

2015.04.01 税務ニュース
平成28年1月から開始されるマイナンバー制度
平成28年1月から、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の利用が開始され、法人には法人番号、個人には個人番号が、平成27年10月から通知される予定です。国税庁長官が書面で通知する法人番号は数字のみの13桁で構成され、平成28年1月以降に開始する事業年度にかかる申告から、申告書等に法人番号を記載することになります。一方、12桁の番号で構成される個人番号(マイナンバー)は、市区町村から住民票の住所に「通知カード」で通知され、住民票を持つ者(外国人を含む)全員に付番されます。事業主は社会保障分野(雇用保険、健康保険、年金など)において書面の提出が必要となる場合に、また税分野において税務署に提出する法定調書等に、従業員等のマイナンバーを記載します。 また、所得税の確定申告においては、平成28年分の確定申告から申告書にマイナンバーを記載することになります。 番号が利用できる範囲は、法律や自治体の条例で定められた、社会保障・税、災害対策に制限され、事業主は、必要とされる従業員やその家族のマイナンバーを収集しなければなりません。例えば、平成28年分の扶養控除等申告書を提出してもらう場合には...









 トップ
トップ



![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)

